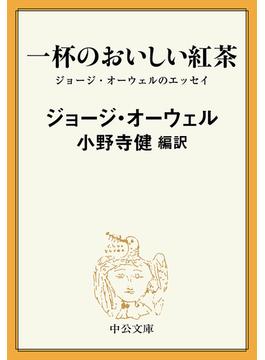- みんなの評価
 3件
3件
一杯のおいしい紅茶 ジョージ・オーウェルのエッセイ
著者 ジョージ・オーウェル 著 , 小野寺健 編訳
鋭利で辛辣、政治一辺倒――
そんなオーウェルのイメージは
本書を読めば心地よく裏切られる
「人間はぬくもりと、交際と、余暇と、
慰安と、安全を必要とするのである」
自然に親しむ心を、困窮生活の悲哀を、
暖炉の火やイギリス的な食べ物、
失われゆく庶民的なことごとへの愛着を記して、
作家の意外な素顔を映す上質の随筆集
文庫化に当たり「『動物農場』ウクライナ版への序文」を収録
一杯のおいしい紅茶 ジョージ・オーウェルのエッセイ
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
一杯のおいしい紅茶 ジョージ・オーウェルのエッセイ
2020/12/06 13:36
ジョージ・オーウェル氏のエッセイと手紙を集めた作品集です!
5人中、5人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ちこ - この投稿者のレビュー一覧を見る
本書は、1900年代前半に活躍されたイギリス植民地時代のインド生まれのイギリスの作家であり、ジャーナリストのジョージ・オーウェル氏の作品です。同氏は、全体主義的ディストピアの世界を描いた『1984年』の作者として有名で、『1984年』で描かれたような監視管理社会を「オーウェリアン」と呼んでいます。同書は、その同氏が残したエッセイと手紙の数々は今なお新鮮に私たちに語りかけるということからそういったものを集めた作品集です。紅茶のいれ方から書くことまで、ジュラ島での生活、流行歌、子どもの本についてなど、くつろいだ楽しいエッセイが中心に収録されています。ぜひ、オーウェル氏を懐かしむ意味でも読んでみてください。
2024/11/17 21:03
エッセイと書簡集
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:りら - この投稿者のレビュー一覧を見る
特に前半のエッセイの視点が興味深い。
食べ物、暮らし、自然などへの目線やこだわりが当時のイギリスの時代の雰囲気をよく捉えている様子で、その時を生きた者ならではという感性なのかもしれないし、オーウェルだからこその感性で紡いでいる文章なのかもしれない。
随分と賢い人であったようだが、学歴にこだわらず、実地で見て考える、表現することで、広く社会に問題提起をした人なのだなと思った。
が、ガチガチでもなく、エッセイ、特にカエルの話や紅茶やパブへのこだわりなどは、いかにもイギリスの人らしく、微笑ましい。
一転、後半のいろいろな文章や書評などに関する記述は近代英米文学に詳しくないとわからないところがある。
作家のものの考え方が窺い知れるのは興味深い。
2024/11/17 22:25
第二次大戦頃の「未来のユートピア」とはこうだったのかと面白くもある
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:大阪の北国ファン - この投稿者のレビュー一覧を見る
以前にこの著者のパリ・ロンドン放浪記を読み、どん底の暮らしをする庶民たちの生々しいルポルタージュに驚いた。その中で英国では中・上流階級の人々のみならず庶民やそれ以下の最下層の人々の暮らしにまで如何に紅茶が重要な役割を占めているかを知り、私自身も紅茶に魅了され、朝・昼・午後と茶葉を変えてそれぞれの香りと味を楽しむようになった。
その紅茶が本のタイトルになっているのだから読まない手はないと思って読み始めた。ところが紅茶についてのは冒頭5ページで終わってしまい、あとは著者による書評や新聞・雑誌への寄稿類、そしてジュラ島で過ごした際に知人に宛てた手紙類、そのあとに同時代への評論と続くいわば「随筆集」だった。数ページ単位の短いエッセイがつなっていき、読みにくくはないが、淡々と綴られる文章には抑揚がないためところによっては少々退屈なところもあった。
当時まだ暖炉やラジオが全盛だった時代に予想された「近未来」、いわゆる「ユートピア」での暮らし、例えば自動食器洗い機や電子レンジなどがある生活の功罪についても真面目に語られる。さらに進んで、今やテレビ電話やテレビ会議が当然となった時代に生きるわれわれから見ると、なるほどその心配は少しばかり杞憂に終わると結果論で楽しめる文もあった。しかしながら著者は近未来の物質至上主義を別の大著で警告的に描いた人であり、その主義主張の端緒はこの本からも充分感じとれた。
出色なのは巻末に付されている「編訳者あとがき」と著者自身による「『動物農場』ウクライナ版への序文」である。この両方を読むと、著者が何を悪として社会に警句を鳴らそうとしたのか、その原点はどこにあるのかがよくわかる。著者は言う。「私の見るところ、ロシアは社会主義国であって、その支配者のすることはすべて許されるという信念くらい、本来の社会主義の概念を堕落させるのに役立ったものはない。社会主義運動を蘇生させたければまずソヴィエト神話を打破することが根本だと固く信じてきた」。この文が書かれてから既に70年以上経過している。近時の例をひくまでもなく、著者の述べるロシアの忌避されるべき本質はこの時から何も進化・改善されていない。
そして慧眼の持ち主である著者のこの序文は、何と「ウクライナ版」の序文であるのだ!