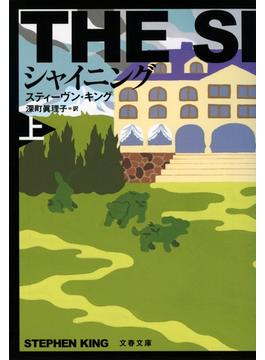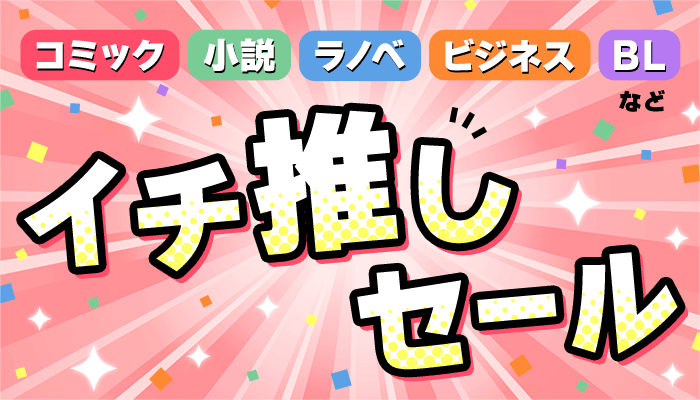- みんなの評価
 13件
13件
シャイニング
著者 スティーヴン・キング , 白石 朗・訳
鬼才スタンリー・キューブリック監督による映画化作品でも有名な、世界最高の「恐怖の物語」
雪に閉ざされたホテルに棲む悪霊が、管理人一家を襲う。天才キングが圧倒的筆力で描き出す恐怖! これこそ幽霊屋敷もの、そして20世紀ホラー小説の金字塔
ドクター・スリープ 下
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは


この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
シャイニング 新装版 上
2017/01/01 18:04
読んでいる最中、頭の中で「ゴゴゴゴゴゴッ」と音が鳴ってました。
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:テトラ - この投稿者のレビュー一覧を見る
もはやキングの代名詞とも云える本書。スタンリー・キューブリックで映画化され、世界中で大ヒットしたのはもう誰もが知っている事実だろう。
とにかく読み終えた今、思わず大きな息を吐いてしまった。何とも息詰まる恐怖の物語であった。これぞキング!と思わず云わずにいられないほどの濃密な読書体験だった。
物語は訪れるべきカタストロフィへ徐々に向かうよう、恐怖の片鱗を覗かせながら進むが、冒頭からいきなりキングは“その兆候”を仄めかす。
誰もが『シャイニング』という題名を観て連想するのは狂えるジャック・ニコルスンが斧で扉を叩き割り、その隙間から狂人の顔を差し入れ「ハロー」と呟くシーンだろう。とうとうジャックは悪霊たちに支配され、ダニーを手に入れるのに障害となるウェンディへと襲い掛かる。それがまさにあの有名なシーンであった。従ってこの緊迫した恐ろしい一部始終では頭の中にキューブリックの映画が渦巻いていた。そして本書を私の脳裏に映像として浮かび上がらせたキューブリックの映画もまた観たいと思った。この恐ろしい怪奇譚がどのように味付けされているのか非常に興味深い。キング本人はその出来栄えに不満があるようだが、それを判った上で観るのもまた一興だろう。
映画ではジャックの武器は斧だったが原作ではロークという球技に使われる木槌である。またウィキペディアによれば映画はかなり原作の改編が成されているとも書かれている。
≪オーバールック≫という忌まわしい歴史を持つ、屋敷それ自体が何らかの意思を持ってトランス一家の精神を脅かす。それもじわりじわりと。特に禁断の間217号室でジャックが第3者の存在を暴こうとする件は既視感を覚えた。この得体のしれない何かを探ろうとする感覚はそう、荒木飛呂彦のマンガを、『ジョジョの奇妙な冒険』を読んでいるような感覚だ。頭の中で何度「ゴゴゴゴゴゴッ」というあの擬音が鳴っていたことか。荒木飛呂彦氏は自著でキングのファンでキングの影響を受けていると述べているが、まさにこの『シャイニング』は荒木氏のスタイルを決定づけた作品であると云えるだろう。
幽霊屋敷と超能力者とホラーとしては実に典型的で普遍的なテーマを扱いながらそれを見事に現代風にアレンジしているキング。本書もまた癇癪もちで大酒呑みの性癖を持つ父親という現代的なテーマを絡めて単なる幽霊屋敷の物語にしていない。怪物は屋敷の中のみならず人の心にもいる、そんな恐怖感を煽るのが実に上手い。つまり誰もが“怪物”を抱えていると知らしめることで空想物語を読者の身近な恐怖にしているところがキングの素晴らしさだろう。
本書が怖いのは古いホテルに住まう悪霊たちではない。父親という家族の一員が突然憑りつかれて狂気の殺人鬼となるのが怖いのだ。
それまではちょっとお酒にだらしなく、時々癇癪も起こすけど、それでも大好きな父親が、大好きな夫だった存在が一転して狂人と化し、凶器を持って家族を殺そうとする存在に変わってしまう。そのことが本書における最大の恐怖なのだ。
やはりキングのもたらす怖さというのは読者にいつ起きてもおかしくない恐怖を描いているところだろう。上下巻合わせて830ページは決して長く感じない。それだけの物語が、恐怖が本書には詰まっている。
ドクター・スリープ 上
2018/05/04 04:29
『シャイニング』に続編が!
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:かしこん - この投稿者のレビュー一覧を見る
『シャイニング』の36年後の続編。
とはいえ、私が『シャイニング』を読んだのはかなり前のことで・・・しかも映画版のほうを先に観てしまったという(映画にいまいち納得がいかないところがあったので、それを埋め合わせたくて読んだのだが、結構違う話だったので衝撃を受けた。古典的ゴーストストーリー×超能力だった)。『ドクター・スリープ』単独でも楽しめる(でも深くしみるのは『シャイニング』を読んでいる人)という評判を受け・・・昔読んでるんだから、これを読んでいるうちに思い出すのでは?、とローティーンだったころに自分の記憶力に期待してあえて復習はしなかった(映画もあの頃、一回観た限りだが・・・意外と覚えていたりするから)。
<オーバールック>ホテルでの惨劇をからくも逃れたダニーとその母ウェンディのその後の暮らしから始まる。序章に当たる「その日まで」を読むことで、読んだことのある人は『シャイニング』の記憶がよみがえる(読んだことのない人は、ここで必要最低限に知識を得られる)。
そして物語は一気に30年後に。少年だったダニーはすっかり大人になり、あの頃恐れていたはずの<父親>と同じ道を辿っている。ひとところに落ち着けず、ついにティーニータウンに流れ着いたダニー(正確にはダン・トランス)は不思議とこの土地に落ち着けるような気がして、そしてダンに手を差し伸べる理解者とも出会い、彼の人生はようやく一ヶ所に立ち止まる。<かがやき>の能力は年齢とともに弱まってはいたが、完全に失われたわけではなく、ホスピスの職員として働きながら旅立つ人々の手助けをするように。
そんなダンの静かな生活はすぐに終わりを告げる。ダン以上の<かがやき>を持つ少女アブラからの接触があり、<かがやき>を持つ子供たちを長年の間餌食にしている<真結族>という存在がアブラを狙っているという。ダンはアブラを救うことができるのか!、という話。
→ 続きは下巻に。
ドクター・スリープ 下
2018/05/04 04:31
表紙の意味がわかってくるまで読むとこみ上げる感慨
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:かしこん - この投稿者のレビュー一覧を見る
→ 上巻から続き。
前作が<ゴーストストーリー×超能力>ならば、今回は<吸血鬼(のようなもの)×超能力>。
ダンが大人になっている場面には衝撃を受けた! というか、どん底にいるある人のくだりを読んでいて、それが少年ダニーののちの姿であるとわかったときの驚きときたら!勿論、作者はその効果をわかったうえで書いているんだろうけど、まんまとやられました・・・。その物語はひとまず終わりを告げるかもしれないけれど、そのあとは読者が思う以上にハッピーとは限らない、という哀しさを見せつけられ。だからダンが立ち直っていく様、彼が自分が思うところのそれなりの人に近づいていくのがうれしかった。
この物語的にはアブラの存在が結構大きく、ダンの出番が少ないのでは?、と思える部分もあるものの、かつてジャック・ハローランがダニーを導いてくれたように、今度はダンがアブラのメンターになる番。人生はそういう順送りですよ、というのがしみじみと感じられ、時間の経過と読者である自分も年をとったという感慨があります。
今回の敵<真結族>は<かがやき>を持つ子供たちを極限まで痛めつけ、最後に吐き出される<命気>をエネルギー源とする種族。勿論、そうされた子供たちは死んでしまうので(場合によっては被害者は子供でないこともあるが、命気の純度は子供のほうが強いから)、吸血鬼的なイメージで。上巻のはじめのほうで<真結族>がある人間を自分たちの仲間にする儀式の様子が、あまりにも邪悪すぎるポーの一族という感じで心底ぞっとした(そう思うとキング・ポーは優しかった)。が、そんな<真結族>も物語が進むにつれて無敵ではないことがわかってくることで、逆に悪役として魅力的に見えてくる面白さ。
ダンとアブラの出会いが偶然にしてはできすぎていると感じても、本編では「偶然と呼べることは何もない」と繰り返され、すべてが必然であったかのように読者も感じてしまう。
キングの初期作品にあったものにくらべ、中期以降の作品は<語り>の勢いが強くなって、「ときにはちょっと無駄な部分もあるんじゃないの?」と思ったりもするんだけど・・・本書『ドクター・スリープ』にもその傾向は多々あるんだけど、その無駄にも見える過剰な語りが独特のリズムを産み、結果的に読まされてしまうという。多分、それは私が慣れてしまったからで、これからスティーヴン・キングを読む人はそれこそ『シャイニング』や『デッド・ゾーン』あたりから入ったほうがいいかもしれない。
実際、私は子供の頃はキングが苦手だったのだが(理不尽に子供が死ぬから、という理由で。子供の頃の私はまともだった)、高校生で映画『デッド・ゾーン』を観て感銘を受け、原作を手に取って苦手意識がなくなった。キング作品の映像化には当たりはずれが多いが、きっかけとタイミングにはなるので・・・キューブリック版の『シャイニング』をキングは今も許してないみたいですが、まぁ映像化を許してしまったのだからそういう部分はあきらめるしかないかと。
で、今回は普通に読んでいたのですが・・・エピローグに当たる「眠りにつくまで」でまさか泣かされるとは!
電車の中で読んでいたのにあふれ出る涙を抑えられず、大変でしたわ。
ちなみに『ドクター・スリープ』も連続ドラマ化決定だという話・・・確かにおいしいキャラクターが多いから、ドラマのほうが描きやすいとは思うんだけど、バトルシーンは映像化が難しいと思う。
やっぱりこれは、小説だからこそ成り立つ物語。

実施中のおすすめキャンペーン