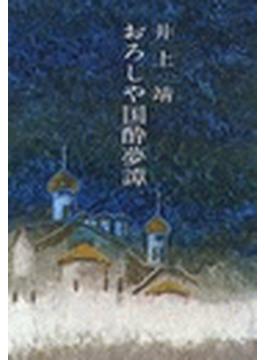- みんなの評価
 4件
4件
おろしや国酔夢譚
著者 井上靖 (著)
天明二年(1782)の暮、伊勢を出帆し江戸へ向かった大黒屋光太夫率いる神昌丸は、強風に運ばれアリューシャン列島に漂着した。帰国の途を求めて光太夫はシベリアを横断し、モスクワを経由してぺテルブルグを越え、ついにロシア女帝エカチェリーナ二世の謁見を受ける。風雪十年ののち対日使節とともに故国に帰った光太夫に、幕府は終身幽閉を命じた……。鎖国の時代、運命に操られるままに世界を見た漂民の波瀾と感動の生涯を十八世紀日露交渉史、漂民史等を駆使して描いた哀切の大作。
おろしや国酔夢譚
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
おろしや国酔夢譚
2012/02/18 18:46
『おろしや国酔夢譚』は冬に読むがいい
4人中、4人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:saihikarunogo - この投稿者のレビュー一覧を見る
まず、寒さである。大黒屋光太夫と16人の船乗りが漂着した、アレウト(アリューシャン)列島のアムチトカ島でも、そこからロシア人たちと船を仕立ててたどりついたカムチャツカ半島東岸の町ニジネカムチャツクでも、そこから陸路で横断して西岸から渡航したオホーツクでも、更にそこからずっと内陸の、世界中で一番寒い町ヤクーツクでも、そして、ヤクーツクからずっと西南の、清との国境に近い、バイカル湖南岸の町イルクーツクでも、冬は地面が凍って墓穴が掘れない。
16人の船乗りは、アムチトカ島漂着寸前に1人死に、アムチトカ島で一年目に6人死に、二年目にまた1人死に、ニジネカムチャツクで冬に町全体が食料不足に陥り、それまで牛乳・牛肉を拒否していた光太夫たちも受け入れるようになるが、その冬はなんとかしのいだのに、結局、壊血病でまた3人死に、ヤクーツクからイルクーツクへ向かう途中で、庄蔵が凍傷にかかり、イルクーツクで悪化して片脚を失い、ために彼はロシア正教に改宗し、イルクーツクで三年目にまた1人死に、ロシア女性と恋仲になった新蔵がロシア正教に改宗し、大黒屋光太夫1+{16-(1+6+1+3+1)-2}=3人で日本に帰って来たが根室でまた1人死に、結局、光太夫と磯吉の2人だけが、漂流してから十年目に生きて江戸まで戻り、そこで七十余歳と六十余歳まで生きた。漂流したときは三十歳代と二十歳代だった。
亡くなった人々は、皆が冬に命を落としたわけではないが、彼らの気力体力を萎えさせた大きな原因に、北緯50度の気候があったのは間違いない。
作者の井上靖の死後に研究が進んだ分子人類学によれば、日本人の祖先は多様な地域から列島に流れ込んで構成されており、なかにはバイカル湖あたりから来た人々もいるそうだが、その人々は寒さに強い遺伝子を持っているのに、南方から来た人々は寒さに弱い遺伝子しか持っていない。そういう違いが、大黒屋光太夫の一行にも、あったのかもしれない。
光太夫は、ヤクーツクからイルクーツクへ移動するとき、自分を含めてここまで生き残った6人は、もうめったなことでは死ぬまい、と考えた。それだけの気力体力知力を持っていると考えた。この6人は確かにそれだけの強い個性を持って描かれている。読んでいるうちに、私は、ある懐かしさを覚えた。それというのも、私は、高校生の頃、井上靖の『夏草冬濤』を愛読しており、主人公洪作少年や友人たちと似通うものを感じたのだ。なぜか本来的に寂しく、それでいてどこかのんびりした暖かさ。また、洪作が、何かを期待して希望を持ったり失望したりと輾転する場面があったように、光太夫もまた、日本へ帰国できるかどうか、希望と絶望とに輾転する場面があり、それも似ていた。
『おろしや国酔夢譚』では、その序章において、江戸時代の初期から大黒屋光太夫たちの前までの、ロシアに漂着した日本人たちを紹介している。彼らは日本語教師として国に雇われて一生を終わった。それは一つには、物理的技術的に彼らを日本に送還するのが困難だったせいもあるが、もう一つには、将来、日本と国交を開き、貿易をするための布石とする、という政策のゆえもあった。それゆえ、大黒屋光太夫たちがロシアに来たとき、物理的技術的には、日本に送還することは簡単とはいかないまでも不可能ではなくなっていたのに、彼らもまた日本語教師として働かせようとする国の意志が、帰国をむずかしくした。光太夫たちは、先に漂着した日本人の子孫にイルクーツクで出逢ったとき、塩を撒きたくなるほどの厭な感じを持ってしまった。
しかし幸運にも、光太夫たちが同じくイルクーツクで出逢った、キリル・ラックスマンが、彼らを日本に送還することを突破口として国交を開くことを、エカチェリーナ女帝に勧めた。エカチェリーナ女帝は、結局、日本人漂民たちを、日本語教師組と、帰国組とに分ける決定を下した。
キリル・ラックスマンは、本人が日本に興味津々で是非共出かけて行って研究したいという強い情熱があったからでもあるが、夫人と共に実に親切に家族同様に光太夫たちの世話をした。磯吉はラックスマンに心酔し、彼の研究助手を熱心に務めた。
光太夫たち帰国組が、庄蔵と新蔵とに涙のわかれをする場面で、磯吉は、日本とロシアとの国交が開けたらまた再会できる、という希望を語った。私も、是非そうなってほしい、ラックスマンに日本に来てもらいたい、と思った。
だけど、毛皮商人のシェリホフには来てほしくないわ、と思った。裕福な毛皮商人たちのなかでも最も有力な人物で、ラックスマンとともに大黒屋光太夫たちの支援もしてくれたが、アレウト列島やシベリアで、現地の人々を搾取している商人の筆頭でもあるのだ。もっとも、シェリホフ自身も、楽観的なラックスマンとはちがい、日本に漂民を送還したからといって国交が開けるとは期待していなかった。シェリホフは非常に現実的な冷めた眼を持っていた。
この『おろしや国酔夢譚』では、アレウト列島やシベリアの先住民が、かつては激しい抵抗運動をしたのに、大黒屋光太夫たちが来た頃にはすっかり温順になってしまっており、それは、諦めによるもので、かつてのコサック兵たちのようなむちゃくちゃ残酷な支配から比べれば、毛皮商人や役人たちは穏健になったものの、本質的には搾取が続き、苦しさは変わらないと述べている。また、先住民のなかには、徴税を請け負って非常に裕福になっている人々もいた。
『おろしや国酔夢譚』には登場しないが、大黒屋光太夫たちと同時代に蝦夷地を探検した最上徳内の一行は、松前藩の請負商人たちによる搾取の実態を知り、怒り、アイヌに同情している。
案外、ロシアの毛皮商人と松前藩の請負商人となら、うまく交渉するかもしれないが、どのみち、北緯50度の先住民の苦しさは変わらない。
キリル・ラックスマンは、博物学者であり、鉱山師でもあった。日本の平賀源内を思わせる。源内は、大黒屋光太夫たちが漂流するよりも前に死んでいるのでこの小説に出てこないが、もし、生きて、ラックスマンに会ったなら、意気投合したかもしれない。源内と同時代の学者で彼より20歳若い桂川甫周は、恩師ツンベルクの書物によってヨーロッパの知識人にその名を知られていた。光太夫は、ラックスマンから桂川甫周を知っているかときかれたときには答えられなかったが、日本へ帰ってから彼に会い、聞き書き『北槎聞略』が作られた。不思議な縁である。
だが、光太夫は、見てはならぬものを見、知ってはならぬものを知ってしまい、それは桂川甫周や他の蘭学者たちとも分かち合えないものだった。磯吉が望んだようにラックスマンが日本に来ることもできなかった。文字通りの「鎖国」が、制度的に精神的に、光太夫たちと他の日本人たちとを隔ててしまった。とても寂しく、残念である。ただ、光太夫も磯吉も、帰国後に妻子を得て、長命を保ったことに、たくましさと救いを感じた。
おろしや国酔夢譚
2011/11/02 15:44
旅路の果てに見えるもの
3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ががんぼ - この投稿者のレビュー一覧を見る
壮大な旅の物語である。それは同時に精神の旅の軌跡でもある。
大黒屋光太夫。江戸時代、一介の伊勢の海商にすぎなかったこの男は、運命の針が振れなかったら、歴史の表舞台に上ることもなかっただろう。だが彼と仲間たちを乗せた船は嵐で遠く北へと流され、そこから予想だにしなかった人生が展開する。難破して仲間たちとともに流れ着いたシベリアで転々、やがてロシア人に拾われて、女帝エカテリーナ2世が率いる帝政ロシアの首都ペテルブルクまで、実に往復2万キロの旅をすることになるのである。何という壮大、かつ数奇な運命であることか。そしてそれは辛い運命である。苦難の果てに仲間を次々に失いながらも、しかし光太夫の強靭な精神と知恵はこの苛烈な現実に耐え抜く。圧倒的な人生。そして想像を絶する十年の後、帰国した光太夫待ちうけるものは…
しかし名匠井上靖は、あまり人物の内面に立ち入ろうとはしない。それは我々が「歴史」に立ち会う形に似ているかもしれない。結局はたしかには知り得ない遠い過去の出来事である。それでもそこに生きた人間たちの胸中にはるかに思いをめぐらせること。それこそが歴史というものではないか。
2016/02/29 08:56
胸がつぶれる
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:プロビデンス - この投稿者のレビュー一覧を見る
米原万里の、マイナス50Cの世界からの紹介で。
インターネットがあり、英語も多少勉強した後でも外国生活で辛い思いをする人は多い。それと比べて鎖国真っ只中の江戸末期、紀伊から江戸に行こうとしたのに、嵐のせいで8ヶ月も海をさまよい、ロシアの存在する知らぬ者がロシアにようやく漂着する。仲間がいたせいかもしれないが、貪欲に言葉を学び知恵を絞って生きて行く光太夫のその強さに心打たれる。しかし生き延びていくためには当地に溶け込むこと、つまり、日本人らしさを封印することにもなるという皮肉。調べたら最初の漂着地は今はアメリカ領のようで驚いた。