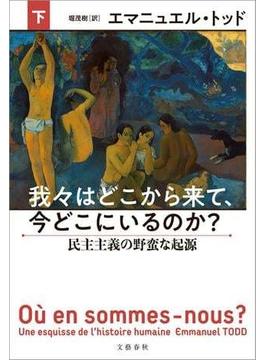- みんなの評価
 2件
2件
我々はどこから来て、今どこにいるのか? 下 民主主義の野蛮な起源
著者 エマニュエル・トッド , 堀茂樹・訳
ホモ・サピエンス誕生からトランプ登場までの全人類史を「家族」という視点から書き換える革命の書!
人類は、「産業革命」よりも「新石器革命」に匹敵する「人類学的な革命」の時代を生きている。「通常の人類学」は、「途上国」を対象とするが、「トッド人類学」は「先進国」を対象としている。世界史の趨勢を決定づけているのは、米国、欧州、日本という「トリアード(三極)」であり、「現在の世界的危機」と「我々の生きづらさ」の正体は、政治学、経済学ではなく、人類学によってこそ捉えられるからだ。
下巻では、「民主制」が元来、「野蛮」で「排外的」なものであることが明らかにされ、「家族」から主要国の現状とありうる未来が分析される。
「核家族」――高学歴エリートの「左派」が「体制順応派」となり、先進国の社会は分断されているが、英国のEU離脱、米国のトランプ政権誕生のように、「民主主義」の失地回復は、学歴社会から取り残された「右派」において生じている。
「共同体家族」――西側諸国は自らの利害から中国経済を過大評価し、ロシア経済を過小評価しているが、人口学的に見れば、少子高齢化が急速に進む中国の未来は暗く、ロシアの未来は明るい。
「直系家族」――「経済」を優先して「人口」を犠牲にしている日本とドイツ。東欧から人口を吸収し、国力増強を図かるドイツに対し、少子化を放置して移民も拒む日本は、国力の維持を諦め、世界から引きこもろうとしている。
我々はどこから来て、今どこにいるのか? 下 民主主義の野蛮な起源
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
我々はどこから来て、今どこにいるのか? 下 民主主義の野蛮な起源
2023/02/22 09:42
人口学・人類学をベースに現状を理解する
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:とらとら - この投稿者のレビュー一覧を見る
家族の形態をベースにして、教育・宗教、人の指向などを類型化しつつ、すぐには変わらなさそうなポイントと変化してゆく部分をとらえて、現在の世界の解釈や理解を進める。
高等教育が各国の分断を進めている、日本は国力の維持を諦めている、現在の民主主義は一定の範囲の人の中で外部を排除して成り立っているなど、いろいろな刺激のある論が展開されている。
それらの理解や解釈の上で、ではどうしてゆくべきなのかは、価値中立の立場で論じる著者の直接の言及範囲ではなく、各人が考えるべきこととなっている。
日本語版のあとがき部分は、上巻のはじめの部分同様、2022年に書かれているので、原著版にはない、2017年以降のうごきへの補足がされている。
我々はどこから来て、今どこにいるのか? 下 民主主義の野蛮な起源
2023/09/02 17:54
ポスト民主制の起源とゆくすえ
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:かばおじさん - この投稿者のレビュー一覧を見る
難しい内容が難しい言葉で書かれているので、わかったようなわからないような、ストンと腹に落ちる感覚に乏しい読後感だった。
フランス人らしくフランスに関する記述は詳細だが、フランスに詳しくないのでイマイチピンと来ない。ドイツ、アメリカに対しては結構辛辣(そんなところもフランス人らしいと言えるのか)。ただ、アメリカ社会の本質は原初のホモサピエンスモデルと言いながら、その太古的な普遍性に(人々は)惹かれるとも書いており、ダイナミックに進むアメリカ社会に対する羨望が垣間見える。
ヨーロッパにおける高等教育の普及や家族形態(意外と直系家族が多い)、宗教の影響といった観点から、「自由で平等な自由主義的民主制」の「権威と不平等の階層秩序構造」への変容を指摘している点が興味深い。ドイツ封じ込めが設立目的の1つとしたEUが、「ドイツ」的な価値観に飲み込まれてしまった形である。ただ、この傾向はアメリカや日本でも同様であり、いわゆる西側諸国の変容でもある。ポスト民主制の将来について、不安定化を懸念する著者の意見には同調したい。
一方でロシア・中国についてはあまり詳述されていない。中国の将来は「不安定化の極となる」と悲観的であるが、ポストコロナの景況感を見る限り(近視眼的だが)実現しそうな感じである。
ロシアについて著者はロシア国内で女性のステータスが相対的に高くフランスと同じ平等主義という点で「買って」いるフシがあるが、統合性の強い国家概念と平等性の強い国民性なんだとすれば、やはり不安定さは拭えないのではないか。