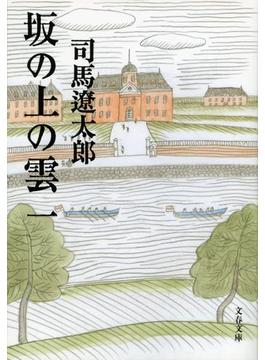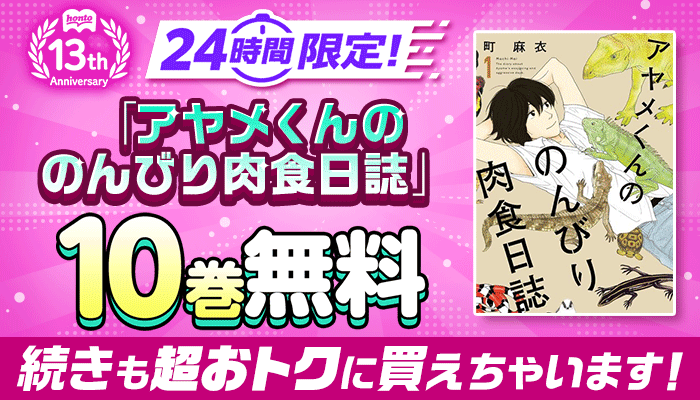- みんなの評価
 67件
67件
坂の上の雲
著者 司馬遼太郎
維新で賊軍とされた伊予・松山に、三人の若者がいた。貧乏士族の長男で風呂焚きまでした信さん(後の秋山好古)、弟で札付きのガキ大将の淳さん(真之)、その竹馬の友で怖がりの升さん(正岡子規)である。三人はやがて、固陋なる故郷を離れ、学問・天下を目指して東京に向かう。しかし、誰が彼らの将来を予見できただろうか。一人は日本陸軍の騎兵の礎をつくり、一人は日本海大海戦を勝利にみちびき、さらに一人は日本の文学に革命を起こすことになるのである。
坂の上の雲(八)
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
坂の上の雲 新装版 1
2011/12/21 01:25
一身独立して一国独立す
9人中、8人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:yjisan - この投稿者のレビュー一覧を見る
NHKでドラマ化されたことを契機に、再び話題を呼んでいるようだ。
戦争賛美の作品と誤解される恐れから、生前の作者は本作の映像化・ドラマ化等の2次使用を許諾しないという立場をとっていた。
そのためかドラマ化にあたっては種々の「政治的配慮」が見られるので、ドラマから入った人は、ぜひ原作も読んで、比較していただきたい。色々な発見があって、より楽しめると思う。
明治維新と相前後して伊予松山に生を享けた正岡子規と秋山真之。そして真之の兄の好古。
本作は、この3人の明治人を軸に、明治という時代の精神を描いた大河小説である。
ただし正岡子規死後の日露戦争の記述が非常に詳細で、「小説日露戦争」の趣がある。
おそらく作者自身が執筆しているうちにノッてきてしまい、当初の構想よりも拡大したのだろう。
そういう意味では、日露戦争の描写を圧縮して3人の青年期を丁寧に描いたドラマ版の方が、全体としてのバランスは良いかもしれない。
本作の主題は日露戦争ではなく、あくまで明治の時代精神である。
作者は、近代国家日本の揺籃期と己の青春期が重なった、すなわち国家の勃興と自らの栄達が何の葛藤もなく共存し得た幸運な時代を駆け抜けた男たちの楽天的な刻苦勉励を通して、ひたすら前のみを見て上昇し続ける明治日本の「明るさ」を感動的に叙述している。
自主独立、立身出世主義、無邪気な愛国心、武士道精神。
これらを手放しに称揚するのはノスタルジーに傾斜しすぎている、という批判はもちろん成り立つとは思う。
しかしそれでもなお、私は本作に限りない共感を寄せるのである。
坂の上の雲 新装版 1
2003/03/07 19:10
自信をなくしかけている日本人へ
7人中、7人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:佐伯洋一 - この投稿者のレビュー一覧を見る
この本の主人公は日露戦争で活躍した秋山兄弟と正岡子規、、と最初はそれでも別段不自然さは感じない。しかし、後半になるにつれて、物語は連合艦隊を指揮した東郷平八郎と旅順で陸軍を指揮した乃木希典を中心に回っていく。あえていえば、主人公は日露戦争そのものではないか、とさえ思う。
乃木将軍とともに旅順でロシア軍と戦った経験のある人々は、旅順と聞いただけで、同胞のことを想起し、涙が止まらなくなってしまう人が昔は多かったらしい。しかし、現在ではそれらの人々はもはやこの世にいないであろう。だが、司馬先生の本を読むことによって、追体験することは現代でも可能なのです。文学の普遍性はまさにここにあると、感じざるを得ない。
クライマックスは世界最大の領土を誇るロシア軍に立ち向かう弱小国日本の勝利を描く対バルチック艦隊戦。東郷平八郎の将帥としての器量、当時の日本人の優秀さ、どれひとつを書いても勝利はありえなかった。本当に、よく勝ったもんだ、と何度見ても不思議に思ってしまう。いったい、どのようにして勝利を得たか? それはいくつもの選択肢を逐一取捨選択していった、男たちの決断の積み重ねである。
司馬先生はそれを克明に再現なさる。
中東の国々には、坂の上の雲に登場する乃木将軍と東郷元帥、そして有色人に唯一挑戦しそして勝利した日本人への尊敬をこめて、未だに名前に「ノギ」や「トウゴウ」とつける人がいるという。海外の国でも知っているわが国の誇るべき歴史を是非、坂の上の雲を通して知っていただきたいと思います。
坂の上の雲 新装版 1
2014/09/13 09:26
戦後史観へのアンチテーゼ
7人中、5人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:コーチャン - この投稿者のレビュー一覧を見る
戦争というものに、正義の戦争、悪の戦争があるとしたら、日露戦争は間違いなく正義の戦争であった。これは、ロシアの侵略に対峙した日本が、生き残るか滅びる(あるいは植民地化される)かの瀬戸際を乗り切るために何としても戦わねばならなかった、またそれに勝利したことで西洋列強の植民地支配に苦しむアジアの諸国民に希望と勇気をあたえ、世界史を大きく前進させた、そういう戦争であった。
しかし残念なことに、我が国が世界に誇るべきこの戦争を、戦後の日本では、日本が列強の仲間入りをし、近隣諸国をいじめ、ついには太平洋戦争と敗戦という悲劇を生むきっかけとなった悪の戦争と教えられてきた。われわれは国のために尊い命を捨てた祖先を敬うこともなく、反対に彼らを恥じるよう教えられてきた。すべては戦後日本の教育界、学問界、マスコミにはびこる反日左翼勢力の仕業である。
『坂の上の雲』は、そんな史観が蔓延していた1960年代終わりから70年代初めにかけて発表され、当時の社会に大きな衝撃をあたえた司馬遼太郎のベストセラー小説である。当初、日露戦争で陸軍騎兵隊を指揮した秋山好古と、その弟で日本海海戦の参謀秋山真之、そしてその友人で俳人の正岡子規という愛媛出身の3人の物語という体裁ではじまった本書は、巻が進むにつれ、日露戦争記という様相を呈するようになった。それも、旅順戦、日本海海戦などのメジャーな戦いについてだけでなく、たとえば、ロシアを国内からかく乱させるために、明石元二郎がおこなったボルシェヴィキへの支援活動、小村寿太郎らによる外交交渉、極寒のロシアから灼熱のアフリカ沿岸、インド洋を通って極東へ向かうロシア艦隊に対して日本の同盟国イギリスがおこなった執拗な嫌がらせ等々、日本がこの戦争を有利に進めるためにあらゆる面から画策した努力のすべてが描かれる、壮大で多面的な歴史ドラマとなっている。
何といっても感動的なのは、明治の軍人がもっていた徳の高さである。どんな危機的な状況にあっても冷静さを失わない東郷平八郎元帥の器の大きさ、旅順攻略にてこずる最中に届く次男戦死の報せを淡々と受け入れる乃木希典大将の悲壮、己の戦略による旅順攻略を乃木の功労に帰した児玉源太郎陸軍参謀長の深慮、またいずれの将も敗軍の敵将に対しては敬意といたわりをもって接したことなど、どれも感涙なしには読めないものばかりである。
歴史小説である以上、本書には史実と異なる部分も数多く見受けられることは認めるべきである。しかしそれでも、日本の近代史を最初から悪と決めつける戦後史観へのアンチテーゼともいえるこの作品は、司馬史観の原点として、今も燦然と輝き続けている。