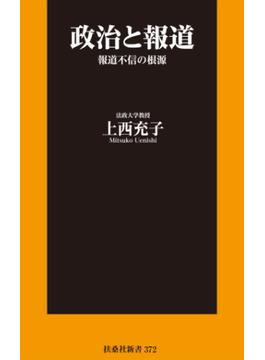- みんなの評価
 1件
1件
政治と報道 報道不信の根源
著者 上西充子
「野党は“反発“、政権側は“反論“」「決定打を欠いた」「笑われる野党にも責任」……。
政策論争に沿った報道ではなく、対戦ゲームのような政局報道に終始するのはなぜなのか?
統治のための報道ではない、市民のための報道に向けて、政治報道への違和感を検証。
「市民の問題意識と個々の記者の問題意識、組織の上層部の問題意識がかみ合っていく中で、より適切に報道は、権力監視の役割を果たしていくことができるだろう」(本文より)
「ご飯論法」「国会パブリックビューイング」の上西充子・法政大学教授が、不誠実な政府答弁とその報じ方への「違和感」を具体的事例をベースに徹底検証。
・権力者と報道機関の距離感はどうあるべきなのか?
・政府の「お決まり答弁」を生み出す、記者の質問方法の問題点。
・なぜ「桜を見る会」の問題を大手メディア記者は見抜けなかったのか?
・政権与党による「世論誘導」に、知ってかしらずか加担する大手新聞社
・新聞社はどのように変わろうとしているのか?
政治と報道 報道不信の根源
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
政治と報道 報道不信の根源
2022/09/08 11:37
政治報道の言葉と記者の感覚
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:かずさん - この投稿者のレビュー一覧を見る
「ご飯論法」で有名な著者が政治報道への不信感から著した一冊。前半は大手新聞社の記事から言葉の使い方や見出しの付け方に疑問を提示し、それを読んだ一読者の反応と書いた記者への使い方を論じている。後半は新聞の在り方や「桜を見る会」の国会質疑を通じて政治報道を専門とする政治部記者の感覚について論じている。後半の部分には一段と興味をそそられて読んだ。行政・国会での質疑に対する内閣や与党の応じ方に多いに疑問もあるし、政治部記者の取材感覚にも慣れがあるのでは。前半での引用の記事が大手2社中心になっているのは何か理由があるのだろうか。メデイアの今後の報道方法や姿勢に一石を投じている。