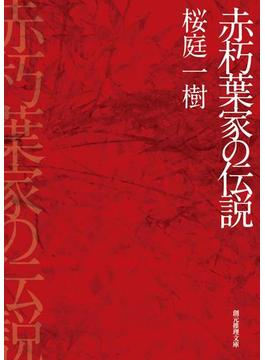- みんなの評価
 7件
7件
赤朽葉家の伝説
著者 桜庭一樹
「辺境の人」に置き去られた幼子。この子は村の若夫婦に引き取られ、長じて製鉄業で財を成した旧家赤朽葉家に望まれ輿入れし、赤朽葉家の「千里眼奥様」と呼ばれることになる。これが、わたしの祖母である赤朽葉万葉だ。――千里眼の祖母、漫画家の母、そして何者でもないわたし。高度経済成長、バブル景気を経て平成の世に至る現代史を背景に、鳥取の旧家に生きる三代の女たち、そして彼女らを取り巻く不思議な一族の姿を、比類ない筆致で鮮やかに描き上げた渾身の雄編。第60回日本推理作家協会賞受賞作。ようこそ、ビューティフル・ワールドへ。
製鉄天使
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
赤朽葉家の伝説
2011/08/29 15:58
圧巻の大作、全身に震えが走りました…
5人中、5人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ジーナフウガ - この投稿者のレビュー一覧を見る
頁を繰る、とそこには『赤朽葉万葉(まんよう)が空を飛ぶ男を見たのは、十歳になったある夏のことだった』
冒頭の一文が、ピタリ決まっている。そういった作品に駄作なし!と信じている僕にとっては、
これはただ事ならぬ傑作であるに違いないぞとの予感が全身を駆け巡りました。
女三代の孫娘である赤朽葉瞳子(とうこ)の語りによって、山陰地方の小さな山村、紅緑(べにみどり)村にて、
戦後日本を必死に生き、死んで行った祖母万葉、母毛毬(けまり)の人生と
伝説が鮮やかに描き出されて行きます。【第一部・最後の神話の時代・一九五三年~一九七五年】
万葉が山陰地方の、更に辺境に住み暮らすと伝えられている【山の人】達から
紅緑村に置き去りにされた事から伝説は始まります。村の若夫婦によって拾われ育てられた
十歳前後からの生活。それはタイトルにも在る様に、戦後の日本が、それまではまだ辛うじて残って居た、
前近代的な風習や土着思想を凪ぎ払い、急激に画一化する中で、日本人としては、
何か大切な物を無意識的に捨て去った、大変な時代だったんだなぁ、と追体験する様な不思議な感覚に
震えたです。万葉の、と言うか、物語の舞台となる紅緑村は、だんだんに区切られていて、
下から見上げると、天上界に位置している様な赤朽葉本家。そして、その力を誇示するかの様に聳え立つ製鉄所。
村では【上の赤】と呼ばれ畏れと親しみのない混ぜになった想いで見られています。
反対に戦後に勃興した造船成金【下の黒】こと、黒菱家、ここの長女である、【出目金】黒菱みどり、
普段はいじめっ子で子分を侍らせている彼女は、万葉とは常日頃から、『いじめっ子』『拾われっ子』と、
言い争っていますが、本音の深い部分で互いを認めあう関係になって行きます。
みどりは終戦から十年近くを経た今もシベリヤにて抑留中の美しい兄じゃの帰還を待ち侘びて、
ただ一人泣きじゃくっています。この兄じゃを巡っての万葉の【予見】と、痛ましい事件、結果として、
みどりの流行歌に乗せた裸の恋心の告白には、フィクションを超えた圧倒的なリアリズムを感じました。
さて、その後、赤朽葉の【恵比寿さま】と崇められている大奥さま、タツに見初められた万葉は赤朽葉の
【千里眼奥様】としての人生を過ごし、次の世代の毛毬が激烈に登場してくる
【第二部・巨と虚の時代一九七九年~一九九八年】(彼女の短い生涯に関してはスピンオフ作品が出ているので、
そこで触れます)、赤朽葉の伝説や謎が孫娘瞳子の手によって丹念に解き明かされていく
【第三部・殺人者・二〇〇〇年~未来】へ綿々と継承されて行くのですが、
最終的な謎が解けた時に瞳子の胸に去来した『せかいは、そう、すこしでも美しくなければ。』という想いに、
この本が読めて心から良かったと思いました。是非機会を見つけて読んで頂きたい、大オススメの一冊です。
赤朽葉家の伝説
2010/10/07 20:15
一気読み必至なので、時間の余裕をみて読み始めてくださいm(__)m
4人中、4人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:mayumi - この投稿者のレビュー一覧を見る
山陰の旧家を舞台に、祖母、母、娘の三代にわたる物語。
面白かった。
続きが気になって気になって、手をとめることができなかった。
祖母は千里眼、母は漫画家、そして何者でもない孫、と孫は語るが、ようするに時代がそういう人物を望んでいたのだろうと、感じた。
そう、ただ女たちの三代を描いたのではなく、そこ根底には戦後から現代にいたるまでの社会があり、山陰の旧家であってもその荒波は容赦なく押し寄せてくるのだ。
と、同時に、祖母の悲しいまでに純粋な心の物語なのだと思った。
飛ぶ男を幻視したのが始まりで、結局は物語はそこに着地していく。
自分の気持ちも、相手の気持ちにも、気づくことも察することもできない程に純粋だった恋だったからこそ、祖母は孫娘にその結末を託したのだろう。
孫娘が自分で歩き始められるように…。
薄ら怖くて、優しくて、美しい物語だった。
赤朽葉家の伝説
2011/08/25 10:39
生き生き生きて、死に死に死んで。
3人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ひろし - この投稿者のレビュー一覧を見る
物語は1950年代の山陰地方、地元の名家赤朽葉家が舞台となって始まる。読み口は何ともおどろおどろしく、世界観も独特な物を感じる。登場人物の様相や奇妙な名前や一種異様な描写から、少々オカルトチックな物を感じてしまうが、それは決してコケ脅しの世界で終始せず、重厚な物語展開と作者の類まれなる筆致ががっちりと支えている。あえて言うなら文豪と言われた作家の作品に感覚が似ているだろうか。例えば芥川龍之介の「鼻」や「羅生門」を彷彿とさせないでもない。そこに独特の世界観やSF的なエッセンスを加えてあると表現したら、この作品のテイストを想像頂けるであろうか。
紅緑村という名の村落に、一人の少女が置き去りにされる。浅黒い肌をしたその少女は「辺境の人」と呼ばれる、山奥に住む人々に置き去りにされたらしい。良心的な夫婦に引き取られたその少女は万葉と名付けられ成長し、やがて村一番の名家、赤朽葉家に嫁ぐことになるのだが。そこで生まれる命、出会う命別れる命。そして去りゆく命、消える命。たくさんの命の物語が展開される。どの命も大変な存在感を持ち輝いて、そしてロウソクの火がふと消えるように、消えて行ってしまう。でもそこから立ち上る白い煙がまた後の世界に影響を及ぼし、命の物語は過去から近代、現代へと親子3代の物語へ連綿と続いていくのだ。そして物語終盤には、悲しいひとごろしのエピソードが、展開される。
非常に読みごたえがあり、最近出会っていなかった感じの文体・物語に読書心をリフレッシュさせられた。本好き物語好きには堪らない一冊ではなかろうか。でも少々読み手を選ぶかもしれない。中学生が「夏休みに読む一冊」にはちょっとオススメ出来ないけれど、どんな本好きもうなずく、力作である事は間違いないと思います。