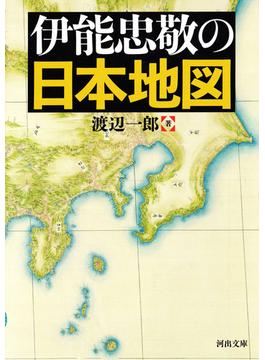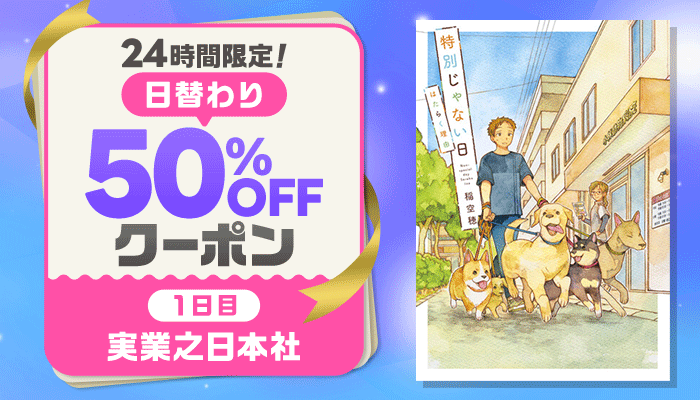- みんなの評価
 1件
1件
伊能忠敬の日本地図
著者 渡辺一郎
16年にわたって艱難辛苦のすえ日本全国を測量した成果の伊能図は、『大日本沿海輿地全図』として江戸幕府に献呈された。それからちょうど200年。伊能図を知るための最良の入門書。
伊能忠敬の日本地図
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
伊能忠敬の日本地図
2022/09/11 17:14
地図作成の全貌はわからない
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:つばめ - この投稿者のレビュー一覧を見る
著者は電電公社勤務を経て会社経営、65歳で引退後伊能忠敬研究に専念、伊能忠敬を彷彿とさせる生き方である。本書は『図説 伊能忠敬の地図をよむ』(ふくろうの本 2000)を低本に再編集、一部加筆したものである。本書は、伊能忠敬の生涯・測量の方法・日本全国を測量した足取りなど伊能忠敬に焦点を当てた前半と、伊能図が世界各国に散在する実態を著者自身が探訪して調査する後半の大きく2部構成となっている。測量の方法で、各測点間の距離の測定は歩測、その後縄や鉄鎖を使用、あわせて各測点間の方位角・勾配を測量することを繰り返し地図を作成したようである。経度の測定では、太陽の正中時刻を起点として、垂揺球儀という振り子時計により時刻を確定し、異なった地点の日月食の開始時刻と終了時刻を測定することで求めたようである。ただし、測量作業のすべてを本書で理解できるわけではない。例えば、地上で行う距離測定が不可能な海上、伊豆諸島の測量をどのように行ったのか。島が近接していれば三角測量も可能であろうが。御蔵島と八丈島のように離れている場合は、どのようにしたのであろうか? 地図作図(内業)では三角関数表を利用して各測点の位置を確定させたであろうが、当時の三角関数表はどのようなものであったのだろうか?また、内業は測量作業と同時並行で行ったのか、測量作業終了後に行ったのか?その作業時間にどの程度要したのか?後半の世界各国に散在する伊能図を求めて、著者自身が米国や欧州に調査に赴く執念には脱帽させられるが、伊能図作成の詳細を知りたい読者には、若干不満の残る内容ではなかろうか。