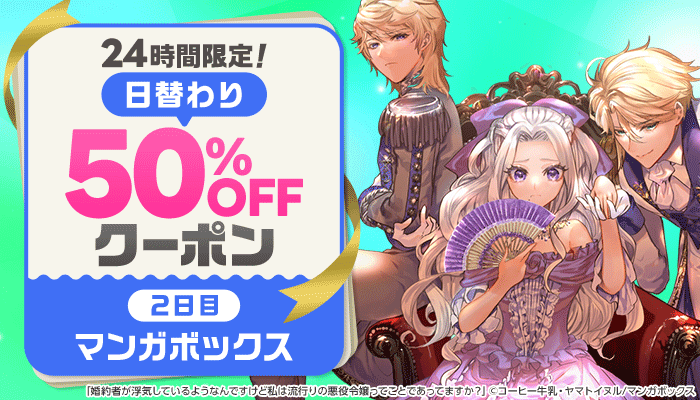- みんなの評価
 11件
11件
鶴見俊輔コレクション
「専門哲学の外にいる哲学者が人類の中にいると考え、むしろそこから、その哲学を考えてみたい。」先人の生き方を知ることで、ものの見方を日々更新し続けてきた鶴見がつむぐ、オーウェル、花田清輝、ミヤコ蝶々、武谷三男…らの思想と肖像。みずみずしい小伝のなかから、人物を通じて鶴見の哲学の根本に触れる作品を精選した、文庫オリジナル・コレクション。
ことばと創造
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは


この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
鶴見俊輔コレクション 4 ことばと創造
2017/03/07 00:42
ことばの守り人
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:親譲りの無鉄砲 - この投稿者のレビュー一覧を見る
鶴見俊輔は、ことばを大切にする思想家であり、行動家である。ここでいう「ことば」とは文章言語のそれのみではなく身振りや映画、まんがといった「映像的」表現などの別の表現手段を持ちうるものも含む。些細な表現であっても、それ以前の誰もがやらなかったものなら、創造的な部分が必ずある。だから、あまり一般には見向きもされない、カウンターカルチャーあるいはサブカルチャー的なまんが作品、多くの評論家たちによって芸術作品としての価値を認められなかった表面的には「大衆映画的手法」を採った「振袖狂女」のような映画の批評等において鶴見俊輔は時代の先端を切って走った。先端表現者としての行動家・鶴見の矜持があったのであろう。本書にもいくつかのエッセイが収録されている「限界芸術論」はそんな鶴見の面目躍如たる著作である。いまでこそ、サブカル論等は華やかであるが、鶴見が挑んだ時は未踏の荒野の分野だったはずである。そんな彼の「ことばと創造」を切り口としたアンソロジーが本書である。編者は黒川創。
本書以外にも、「文章心得帖」等の著作を通じて、彼のことばに対する感性の鋭さは、世によく知られている。彼の論壇デビュー作といってよい「ことばのおまもり的使用法」は、鶴見を語る上では必須文献である。戦後間もなくの時代背景があっての論文ではあるが、時間を経た今でも色あせることがない。何度でも読み返したい。
彼の論考の守備範囲は極めて広い。守備範囲の広さは彼の好奇心のありかによるものだろう。ゆえに、あえて意図的に「鶴見哲学」と呼ばれるようなものを構築しなかったように思われる。「普通」の評論家・哲学者が思いもつかないようなかたちで、日本文学の胎動を一つの方法で刺激したエトランゼ・小泉八雲を藤田省三、横光利一、木下順二、谷川雁、中野重治らを縦横に引いて疾走するかのごとく語ることによって、これに対比させる形で、戦中の「勅語」を中心にした共通言語の貧しさを自覚しえなかった日本人の言語空間における幼稚さをあぶりだした。
そして、その奔流はとどまるところを知らず、身体表現を含む漫才、円朝、「アメノウズメ」一条さゆりにまで及ぶ。なお、「鞍馬天狗の進化」を読むとわかるが、戦中の貧しく息苦しい言語空間に閉ざされた文学者の中で、鶴見の視点からすれば、唯一に近い例外が大佛次郎であったようだ。大佛の「阿片戦争」や「乞食大将」、特に後者は、時代小説の姿を借りた自由主義者が言わば白昼を闊歩して行った、とまで書く。
所収の「かるた」は、本人の少年期の記憶を頼りにその時の思いをその時味わった感性に忠実に日常的な言葉で再現する実践的な作品である。そこには、自然に形成されたみずみずしい少年の世界が平易な言葉で語られている。何よりもある一個の人間を成立させる思想、レーゾンデートルは、皆の心の中にある言語単位である多数枚の「かるた」というユニットで構成されており、その言葉のカードに呼応する形でイメージや記憶の単位が想起されるようになっている、そういうことを示そうとした意欲作であった。表現者・鶴見の一側面を表す作品であろう。「誤解権」という著作も、行動家・鶴見の基盤となっている思想の表れなのであろう。必読文献の一つである。そして、鶴見の著作のほぼ最後を飾る90歳のときの作品が「意思表示」という行動であった。末尾に全文引用して本レビューを終わることにする。
―今の私にどれだけの力があるかどうか、分かりません。しかしはっきりと、憲法九条を守る意思表示をしたいと思います。―
鶴見俊輔コレクション 1 思想をつむぐ人たち
2016/09/29 18:15
共鳴によって繋がっていく思想
2人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:親譲りの無鉄砲 - この投稿者のレビュー一覧を見る
黒川創編による鶴見俊輔コレクション1。表面的には、鶴見による人物評伝を集めたもの、という感じ。ただし、巻末の坪内祐三の解説にもあるように、金子ふみ子から末尾のホワイトヘッドへの連環の妙は、黒川に帰される作品性がみられる。ただのアンソロジーと侮ってはいけない。一冊の本として通して読むことによって、個別のエッセイをそれぞれ読むのとは明らかに異なる、鶴見の思想を立体的に把握できるような読後感を持つことになる。そこに編集の意義があるといえる。
鶴見の長編の評伝には、本書には収まりきらないような「高野長英」といった長編作品もあるが、個人的には、短めのものの方が鶴見の良さが出ている、と感じる。何よりも、圧巻は、「金子ふみ子―無籍者として生きる」である。朴烈大逆事件で不当検挙され獄中縊死した金子ふみ子には、「何が私をこうさせたか」という自伝がある。(鈴木重吉監督の映画の原作でプロレタリア作家・藤森成吉著「何が彼女をそうさせたか」はこれにインスパイアされたものと思われる。)これは、獄中で書かれた。この(自伝に書かれた)彼女の苛烈な前半生が、彼女の精神を強靭にし、そして抵抗者としての人生を選択させた。そこには鶴見が信頼するクロポトキンの思想と共鳴した彼女の哲学がある。鶴見はその点に共鳴(彼の言葉で言えば同情)した。
普通の人はあまり思いつかないのだが、「亡命」という言葉から、新島襄の生涯を考える。それと似たパターンで、エイケンの「ウシャント」を読み、石原吉郎のシベリア抑留体験に思いを致す。石原は語っている。「苦痛そのものより、苦痛の記憶を取りもどして行く過程の方が、はるかに重く苦しい・・・」だから、似たパターンを繰り返しつつ、同じ場所に戻ってくることはない。記憶の暴力性は鶴見自身も体験した事である。そこで、難破が次の難破に繋がる人生として、鶴見はさらに田中正造を思い出す。その中で、自らの精神の中に、繰り返し抵抗するものを見出す。ただし、鶴見は安易にカルマというような言葉を使わない。個人のなかでの繰り返しだけでなく、人から人への共鳴によって、歴史的に、空間的につながっていく部分があるからだ。ただ、金子ふみ子とホワイトヘッドを結び付けられるのは鶴見ぐらいのものだろう。そう思ってこの本を読むと、バラバラの人物評伝が、鶴見を媒介として、大きな思想の流れの中で生き生きと立ち上がってくるのを感じる。鶴見の視座を通して、一般の人は哲学者とはみなさないであろう金子ふみ子、加藤芳郎、南伸坊や、知名度のあまり高くないであろう、仁木靖武、ヤング夫人、能登恵美子らの生き様を、かけがえのない哲学そのものとしてみる。鶴見は、彼らの生き様の系譜を、読者が受け継ぐことを期待しているのかもしれない。(内村鑑三がいうように、人の生き様こそ後世への最大遺物なのである。)ここに、自身が共感した有名無名の人々の評伝を鶴見が書き続けた真の意味があるのであろう。
蛇足だが、鶴見がゲーリー・スナイダーとの仁義上、彼の導きでLSDによる幻覚体験をしたことがあることを、本書を読んで初めて知った。ただし、鶴見は、クエイカーとは別流の霊震の経験を既にしていたはずである。だからかもしれない。かような神秘的体験を絶対視しないで相対化できる心の余裕度を感じる。葬式仏教から得るものは少ないだろうが、ティク・ナット・ハンの唱える上座部仏教や、ゲーリー・スナイダーの仏教に向き合う姿勢に対する共鳴は十分あるものとみた。
鶴見俊輔コレクション 2 身ぶりとしての抵抗
2016/08/20 19:42
抵抗者・鶴見俊輔
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:親譲りの無鉄砲 - この投稿者のレビュー一覧を見る
鶴見俊輔は、行動する思想家だった。本書は、社会的発言の一環としての「行動」、とくに抵抗運動にまつわる鶴見のエッセイを集めたものである。特に「五十年・九十年・五千年」は、鶴見自身が自身の業績としてあまり言及することがなかったハンセン病回復者の社会復帰への思いを語った重要なエッセイとして、我々は認識するべきである。ハンセン病回復者の社会復帰は、病気に対する無知や偏見によって維持されてしまった「らい予防法」の1996年の廃止まで、長らく妨げられてきた。鶴見がその問題を最初に自覚したトロチェフさんとの出会いからみても、実に50年の年月が過ぎていた。もちろん、このような件で国が自発的に法律を改定することはない。多数の理解者が寄せた善意にもとづく「むすびの家」のような、外の人間の人との交流の場を作るための努力が営々と積み重ねられてきた背景があってのことだ。また、鶴見がすべてを仕切ったわけではない。彼の教え子たちが自主的に行動に移したことを、見守ってきた部分が大きいのかもしれない。さらに、この運動には各方面から思わぬ協力が集まったり、出会いがあった。鶴見にとって忘れられないのは、柴地則之、白石芳弘、那須正尚、矢追日聖、大江満雄、杉山龍丸、谷川雁、といった面々である。不思議なことに、鶴見の周りには有能な実務家がよく集まる。天の配剤というべきか。
鶴見は、60年安保での運動以降、ベトナム戦争反対運動などで、中核的な役割を果たした。それも、組織至上主義ではない、一つ一つの案件ごとに緩くつながり、終わったら自然解散するような形で時の権力に対峙してきた。それがべ平連であり、米兵脱走支援活動である。それは昨今のSEALDsのような若者の運動の先取りであり、彼らがお手本にしたであろう台湾の「ひまわり運動」の学生たちが採った戦略のひな形ともなっていた。この歴史的事実は我々もきっちり押さえておく必要はあると思う。「日付を帯びた行動」、「脱走者たちの横顔」の章には、鶴見の視点から見た当時の運動の様子がよくわかるエッセイが並ぶ。
もうひとつ、鶴見の評論家としての特徴がよく表れているのが、「隣人としてのコリアン」の章において示される、金石範、金時鐘、金芝河ら「抵抗文学者」たちに寄せる共感であり、共振である。それは戦後の韓国、朴正煕軍事政権下における金芝河解放運動の行動への協力という形になっても現れる。一方、日本人の被統治国・朝鮮人に対する気まずきコンプレックスを吐露した田中英光の小説に対し高い評価を与える。その両側面を、鶴見自身の内部に有していた。
鶴見の抵抗の精神の源流には、足尾鉱毒事件において、国会議員を辞し、在野の運動家として生涯を貫いた田中正造、そして木下尚江の系譜があった。田中正造の価値観は、江戸時代の庄屋のせがれとしての精神基盤の上にすでに形成されていた。つまりそれは西洋の思想家に習わなくても、自発的に日本人が獲得できるはずのものである。そこには鶴見が指摘するように、「大勢はきまったと判断され、その判断が現状にあたっていると思われる時に、その後は大勢に身をまかせるのではなく、いくらかの原則をたてて異議申したてをつづけることには意味がある」、と、内省しながら行動に移す習慣があった。しかし鶴見は、明治以降の日本に欠けているのはこの習慣である、とも指摘する。足尾鉱毒事件は、昔の過ぎ去りし事件ではない。表面的な体裁は違うが、水俣病、森永ヒ素ミルク事件、在沖米軍に関わる暴行事件や基地問題、今もなくならない多数の冤罪事件などの形として執拗に日本人に気づきを迫ってくるのである。

実施中のおすすめキャンペーン