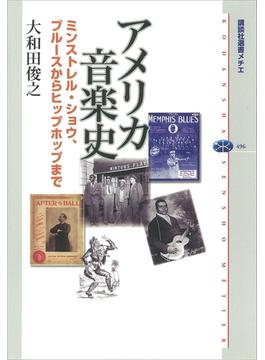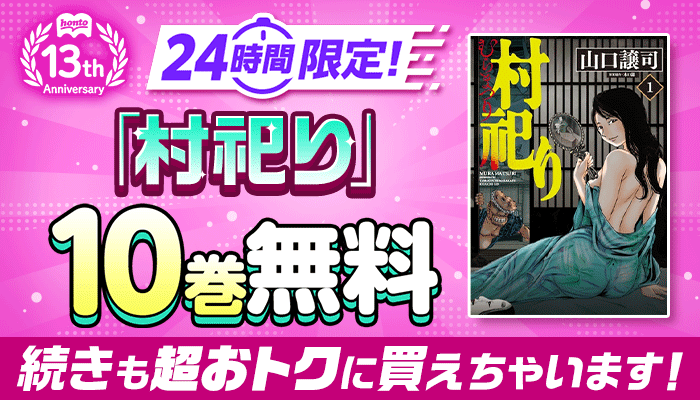- みんなの評価
 2件
2件
アメリカ音楽史 ミンストレル・ショウ、ブルースからヒップホップまで
著者 大和田俊之
【2011年サントリー学芸賞[芸術・文学部門]受賞】そのサウンドと〈歴史〉はいかなる欲望がつくったか。ロック、ジャズ、ブルース、ファンク、ヒップホップ……音楽シーンの中心であり続けたそれらのサウンドは、十九世紀以来の、他者を擬装するという欲望のもとに奏でられ、語られてきた。アメリカ近現代における政治・社会・文化のダイナミズムのもと、その〈歴史〉をとらえなおし、白人/黒人という枠組みをも乗り越えようとする、真摯にして挑戦的な論考。(講談社選書メチエ)
アメリカ音楽史 ミンストレル・ショウ、ブルースからヒップホップまで
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
アメリカ音楽史 ミンストレル・ショウ、ブルースからヒップホップまで
2012/03/26 03:46
アメリカの音楽史を駆け足で眺める
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:かねたん - この投稿者のレビュー一覧を見る
「はじめに」には、「本書はアメリカのポピュラー音楽史を(擬装)というテーマで読み解くものである」と書かれている。
「擬装」とは、他人になりすますことであり、アメリカのポピュラー音楽を駆動してきたのは他人になりすます欲望であるという。そして、その代表としてマイケル・ジャクソンを挙げている。
筆者は、慶應義塾大学法学部准教授で、専攻はアメリカ文学とポピュラー音楽研究であると、見返しに書かれている。
「あとがき」によれば、本書は2006年度から2008年度にかけて慶應義塾大学法学部(地域文化論)、同大文学部(米文学)、青山学院大学文学部(米文学特講)で担当した講義をもとに執筆したということである。
本文を読み終わったあとに、あとがきを読んで、すぐに納得した。
それは、本書がアメリカのポピュラー音楽史を駆け足で眺めていると感じたからだ。
大学での限られた回数の講義で、アメリカのポピュラー音楽史を概観しようとすれば、駆け足になってしまうことはやむを得ないと思う。
ただ、この駆け足が読者にとってどう作用するかは、読者が何を求めて本書を読むかによって異なるだろう。
細部はともかく、アメリカのポピュラー音楽全体を概観したいと思っているなら、オススメできる本である。
一方、例えば、特定のジャンルについて詳しく知りたいと思っているなら、それぞれのジャンルについて詳しく説明している本を読むべきだろう。
しかし、細部に目を向けるにしても、事前に概観しておくことは有益だと思う。
では、具体的な内容に目を向けてみよう。
本書では、アメリカのポピュラー音楽における唯一の革命として「ビバップ革命」を挙げている。チャーリー・パーカーやディジー・ガレスピーらによって起こされた革命は、黒人文化の解放/抵抗を表しているという従来の見解に対し、芸術性の獲得を表していると筆者は主張する。
そして、ジャズ史上最も影響力のあるアルバムとしてマイルス・デイヴィスのカインド・オブ・ブルーを挙げ、このアルバムで用いられた「モード」という奏法について、こう評している。
「西洋クラシック音楽の呪縛から逃れ、コードの重力から解放された『モード奏法』こそが<黒人音楽>としてのジャズを決定づけるもっと重要な断絶だとはいえないだろうか。」
これらの考え方に対して、仮に100%の肯定はできなくても、反論するのは容易でないと思う。筆者の考え方は、アメリカで急速に進んでいるジャズなどについてのアカデミックな研究に基づいており、最近の研究成果の一部を知るための資料としても、本書は有効だと思う。
ただし、次の記述には、少々違和感が残った。
「少しでも音楽活動を経験したことがあるものは、たとえばペンタトニック・スケールが即座にブルースを連想させる音階であることを憶いだしてほしい。」
ペンタトニック・スケールで作られている曲というと、「蛍の光」がとっさに思いつく。
しかし、蛍の光を聞いても、残念ながらブルースは連想しない。
あるいは、日本の民謡などで使われる陽旋法もペンタトニック・スケールと同じ構成音であるが、こちらもブルースは連想しない。
ブルースを連想するスケールとして筆頭に挙げるべきなのは、ブルーノート・スケールではないかと思うがいかがだろう。長調と比較した場合に、第3音と第7音、場合によってはさらに第6音が半音低いブルーノート・スケールを聞けば、即座にブルースを連想する。
まあ、これは主観によって違いがあることだし、重箱の隅をつつくような話でもあるので、本書の価値を揺るがすものではないが。
アメリカ音楽史 ミンストレル・ショウ、ブルースからヒップホップまで
2024/04/27 16:07
「偽装」を切り口にアメリカ音楽史を描いていく
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ichikawan - この投稿者のレビュー一覧を見る
「偽装」を切り口にアメリカ音楽史を描いていく。音楽史を論じるのに国ごとの区分けに意味があるのかという疑問を抱く人もいるだろうが、本書を読むとやはりアメリカ音楽史はアメリカ音楽史という形でしか論じられないのだと思う。