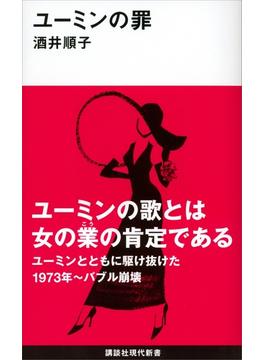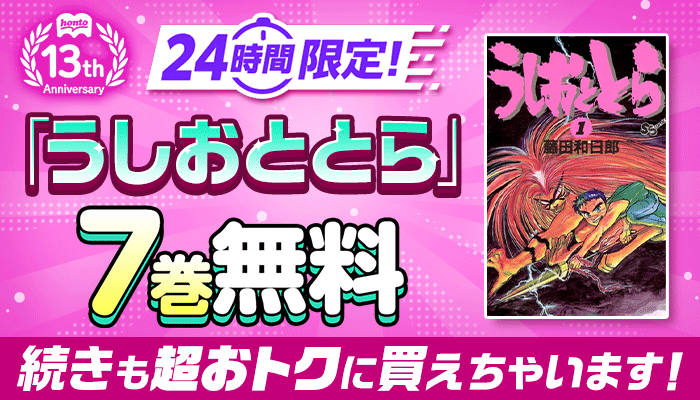- みんなの評価
 3件
3件
ユーミンの罪
著者 酒井順子
ユーミンの歌とは女の業の肯定である――ユーミンとともに駆け抜けた1973年からバブル期の時代と女性達を辿る、著者初の新書。ユーミンが私達に遺した「甘い傷痕」とは? キラキラと輝いたあの時代、世の中に与えた影響を検証する。 ※本書は「小説現代」2012年1月号~2013年8月号に連載された「文学としてのユーミン」を改題、大幅に加筆したものです。
ユーミンの罪
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
ユーミンの罪
2022/06/12 22:36
由実とみゆき
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:うーよー - この投稿者のレビュー一覧を見る
今朝NHKラジオで取り上げられ、酒井順子さんの話が聞けた。ユーミンのデビューから50周年だそうだ。ポップス界には唯一無二の存在と言っていたが、ユーミンがひなたの存在なら、陰の様に女の業をストレートに描き、その後人間賛歌にまで昇華させた中島みゆきという存在も忘れてはいけない。
ユーミンの罪
2021/08/07 13:43
中高年の思い出
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ぶたたぬき - この投稿者のレビュー一覧を見る
だいぶん前に上梓された本で、本棚に埋もれていたところを引っ張り出して読んだ。
改めて読むと著者と、ほぼ同世代のせいか、当時の思い出と共に共感するところが多く、面白くまた、少し感慨深めに読めた。
荒井由美時代の若者と死の影の話、曲にかくれた助手席心理の話、横浜のおしゃれと影の話、バブル時代のリゾートスポーツ(苗場など)の話、ダイヤモンドダストの泡とバブル崩壊の予兆の話、宴が終わって女性も自立しなければならない時代の到来の話など昭和後期から平成の時代までをそのヒットアルバム内の曲と共に、著者らしい感想と共に話は進みます。
その時々の世相を感じさせるユーミンの曲の数々。特に女性は共感を呼ぶことが多いのではないかと。
最初はそのタイトルにある何が罪なのかと疑問だったのです。
そして、バブル期のスキー場にかつてこのユーミンの曲ばかりが流れていたことを思い出させてくれます。
時代時代によって人生観は変わるものです。バブル期当時に青春期を迎えた者は時代と共に浮かれていたのかもしれません。今の時代とは大違いです。
この著書の内容は今の若者には、たぶん共感できないだろうと推察します。
時代背景をリアルに経験していないと、感想は違うだろうと思われるから。
時代とは年々発展して住み良くて、改善されてゆくものだと勝手に思っていました。
しかし、今の状況はどうでしょう? コロナを差し引いても、決して20年前、30年前よりも良くなったと云えるだろうか?私にはそうは思えません。
そういった意味からも、ユーミンというより中高年の罪といった方がしっくりとくるなぁと感じさせられて一冊でした。
ユーミンの罪
2016/03/02 19:59
ユーミンの罪なのか功罪なのか。
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:更夜 - この投稿者のレビュー一覧を見る
私は著者、酒井順子さんと松任谷由美さんの丁度真ん中くらいの年齢です。
ユーミンのアルバム『LOVE WARS』で卒業したと勝手に思っているし、このアルバムでずいぶんと方向転換したな、と思った覚えがありますから、それまでのユーミンのアルバムはずいぶんと聞き込みました。
ユーミンのレコードを「DISK UNION」のビニール袋に入れず、ジャケットを堂々と見せて登校してきた同級生(放送部の子で、おしゃれだった)をよく覚えています。
ユーミンとサザンは、おしゃれだけれど嫌味のないおしゃれだったと思いますね。
まぁ、もう、平成になって26年、サザンとユーミンは卒業してしまったというか、ばっちり愚かだった思い出したくない自分の10~20代の黒歴史がぞろぞろと思い出されるので、意識的にもう聞かないです。
音楽についての本や文章というのは、難しくて普通の人が書くと大体、曲にまつわる思い出になってしまいます。
私は見ざる言わざる聞かざるの黒歴史なので自分がどうだったかを書く気はありません。
しかし、1973年の『ひこうき雲』から1991年の『DAWN PURPLE』まで、酒井さん、10代~20代にのめり込んだ背景には日本のバブル経済と女性学的見地からみた女性の立場や社会進出、晩婚化、少子化をユーミンは常に先取りしていた。
だから、「ニュー」ミュージックと呼ばれたのです。
常に新しい先を見る事ができた天才。そして
「ユーミンは、「湿度を抜く」ということにかけて天才的才能を持っています。」
確かに、私は、一人で池袋文芸地下の大島渚監督特集に通うような学生でしたが、そんなマイナーな女の子にも共感と幻想(夢というより幻想)を大きく持たせるくらい懐が広い歌を歌っていました。
スキーとサーフィン、助手席の女の子、ラグビーと山手のドルフィン、ソーダ水の中を貨物船が通る・・・おしゃれでありながら、好き、聞いてると公言しても恥ずかしくない数少ないミュージシャンだったと思います。
音楽というのは本や映画よりも、漫画やアニメに近くて個人的こだわりがひどくあるもので、ジャンルも幅広い。
だから個人的好き嫌いが非常に分かれているなか、男性にも女性にも受け入れられたのがユーミンとサザンでした。
そして、「男ユーミン」と言われた大江千里も同世代で、千里君も湿度を抜く天才でしたね。最初はアイドル風でしたが、だんだんユーミン化していき、今はまったく違うジャンルの世界にいます。
歌人の穂村弘さんが、やはりユーミンが好きで(穂村弘さんと私は同世代)「お互いを高めあう恋」に男の子も憧れていた、と知ったとき、さすがユーミンと思ったのです。
演歌の女たちが「ひたすら受け身に待つ。泣く女」であるのに対してユーミンの歌の女の子たちは「ダサいから泣かない」
今でもなぜか日本酒の宣伝は、熟女っぽいきれいな和服の奥さんが「おかえりなさい」とにっこり微笑むのは変わらないけれど、ユーミンはどんどん進化して、恋は戦だ!勝つんだ!と宣言しました。
恨み事は中島みゆきにまかせて、愛は勝つ!と『LOVE WARS』でたからかに宣言した時、私はユーミンを卒業しました。
今でも、かわいい若い女の子たち、男の子たちがたくさん、夢を振りまいているけれど、作られた感じが全くしなかったユーミン。(もちろん、夫の松任谷正隆さんの存在は大きい)
ただ、私は思うのです。
所詮それは幻想だ、と後で気づいても、夢見る一瞬、夢見る刹那というのは若い人に必要なものではないかと、そしてそれは卒業していくものだと、思うのです。