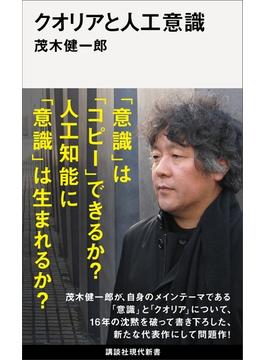- みんなの評価
 2件
2件
クオリアと人工意識
著者 茂木 健一郎
「意識」は「コピー」できるか?
人工知能に「意識」は生まれるか?
茂木健一郎が、自身のメインテーマである「意識」と「クオリア」について、
16年の沈黙を破って書き下ろした、新たな代表作にして問題作!
人工知能の研究の進展が目覚ましい。
だが、人間は、なぜ人工知能を生み出すのだろうか?
その根底にあるのは、自分の「似姿」をつくろうとする本能である気がしてならない。
人間は、その知性を通して、「万物の霊長」たる地位を確立してきた。
そのような人間の知性の一つの究極の応用として、人工知能の研究、開発がある。人工知能の研究には、もちろん、実用的な意義も大きいが、それに加えて人間が自分自身の成り立ちを理解するという意義もある。
人工知能は、私たちの「鏡」なのだ。
その「鏡」の中には、果たして、「クオリア」に満ちた私たちの「意識」もまた、映っているのだろうか?
人工知能をつくることは、「人工意識」を生み出すことにつながっていくのだろうか。
<本文より>
☆本書で考察するテーマの一部
〇眠る前の「私」と、目覚めた後の「私」はなぜ同じなのか?
〇私たちは、「ホモサピエンス」(知性を持つ人間)である以上に「ホモコンシャス」(意識を持つ人間)である。
〇物質に過ぎない脳から、「意識」や「クオリア」が生まれてくる不思議。
〇「意識」は「コピー」できるか?
〇「人工意識」をつくることは可能か?
〇人工知能が生成した文章は、「どこにもたどり着かない」?
〇統計的アプローチでは、「意識の謎」の解明はできない。
〇人工知能をめぐる議論に、ときに驚くほど終末感が漂うのはどうしてなのか?
〇記憶を「外套」だとすると、脳は、その外套を引っ掛けておくための壁に打たれた「釘」に過ぎないという考え方。
〇「私」という「意識」は、この宇宙の全歴史の中で一回だけのものであり、一度死んでしまえば二度と戻らないという「セントラルドグマ」は正しいのか?
クオリアと人工意識
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
クオリアと人工意識
2021/12/02 18:24
脳科学者の茂木氏が人工知能について語る、新書にしては内容充実の1冊
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:YK - この投稿者のレビュー一覧を見る
人工知能が発達した先に、いつの日にか人間を超える能力を獲得し(シンギュラリティ)さらに自我が芽生える瞬間が来るのではないかと考えられる程に人工知能の開発は進んできました。本書は脳科学者の茂木氏が、人工知能研究の最前線で議論されている概念について、様々な思考実験の例を挙げつつ述べられている1冊です。
「人工知能が将棋などで圧倒的に強化されていくのは、人間と違ってそのことだけに1日24時間没頭し続けることができるからで、(気分転換を必要としないような)バランスを考慮しない尖り方は反生命的といえる」、「与えられた状況判断で生命は絶滅の可能性を避けるために敢えて80%程度の正答率に抑えることで想定外、予想外の事態に対応する余裕を持たせている」、「人間とスムーズに会話を交わす人工知能は、統計的に単語や動詞がどう続くかを処理しているに過ぎず、文章の意味自体を理解しているわけではない”言語ゾンビ”といえる」、「川端康成の”雪国”冒頭の一節を与えれば、現在の人工知能はそれに続く自然なフレーズを生成することができるが、その最初のフレーズを発話することは意識のある人間にしか不可能」、「眠る前の”私”と目覚めた後の”私”が同じであるという事は、(眠る前と目覚めた時の風景など)様々な状況から脳が推定して”同じ”と判断している」、「ある人の脳を完全に計算機でシミュレーションできたとしても、そこにその人の意識が存在するわけではない。なぜなら、計算機で完全に地球の気候をシミュレーションできたとしても、計算機の中に実態のある地球の気候が存在しないのと同じことだから」、「自動運転を司る人工知能の評価関数(もし事故が想定される状況で何を優先するか。子供と大人、男性と女性、有名人と一般人など)がブラックボックスのままでは不安だが、それを全てオープンにすると人間関係に深刻な問題が発生する(この車の人工知能は”乗員の安全を優先します”と謳われた場合、歩行者の安全をないがしろにしても良いという印象を持たれてしまう)ため、自動運転への人工知能の実装は難しい」等々、様々な切り口から実例を挙げつつ議論が展開されています。
400ページ弱という新書にしては多い目のボリュームに「人口知能と人工意識」、「知性とは何か」、「意識とは何か」、「私と自己意識の連続性」など興味深い視点で述べられており、内容の半分以上は科学と言うよりは哲学に近い印象です。私自身は本書で茂木氏が述べられている議論の半分ぐらいはあまりに哲学的、抽象的過ぎて理解やイメージが追い付かない印象でした。しかし、簡略化し過ぎれば茂木氏の伝えたい事が十分に表現できなかっただろうし、難解になり過ぎないように茂木氏なりに”攻めた”結果が本書ではないかと思います。理解できた(ような気がする)半分だけでも、何かとんでもなく深淵な世界の一端を見せてもらったような、不思議な読後感が得られました。
2024/12/04 18:14
脳科学者の茂木氏が人工知能について語る、新書にしては内容充実の1冊
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:YK - この投稿者のレビュー一覧を見る
人工知能が発達した先に、いつの日にか人間を超える能力を獲得し(シンギュラリティ)さらに自我が芽生える瞬間が来るのではないかと考えられる程に人工知能の開発は進んできました。本書は脳科学者の茂木氏が、人工知能研究の最前線で議論されている概念について、様々な思考実験の例を挙げつつ述べられている1冊です。
「人工知能が将棋などで圧倒的に強化されていくのは、人間と違ってそのことだけに1日24時間没頭し続けることができるからで、(気分転換を必要としないような)バランスを考慮しない尖り方は反生命的といえる」、「与えられた状況判断で生命は絶滅の可能性を避けるために敢えて80%程度の正答率に抑えることで想定外、予想外の事態に対応する余裕を持たせている」、「人間とスムーズに会話を交わす人工知能は、統計的に単語や動詞がどう続くかを処理しているに過ぎず、文章の意味自体を理解しているわけではない”言語ゾンビ”といえる」、「川端康成の”雪国”冒頭の一節を与えれば、現在の人工知能はそれに続く自然なフレーズを生成することができるが、その最初のフレーズを発話することは意識のある人間にしか不可能」、「眠る前の”私”と目覚めた後の”私”が同じであるという事は、(眠る前と目覚めた時の風景など)様々な状況から脳が推定して”同じ”と判断している」、「ある人の脳を完全に計算機でシミュレーションできたとしても、そこにその人の意識が存在するわけではない。なぜなら、計算機で完全に地球の気候をシミュレーションできたとしても、計算機の中に実態のある地球の気候が存在しないのと同じことだから」、「自動運転を司る人工知能の評価関数(もし事故が想定される状況で何を優先するか。子供と大人、男性と女性、有名人と一般人など)がブラックボックスのままでは不安だが、それを全てオープンにすると人間関係に深刻な問題が発生する(この車の人工知能は”乗員の安全を優先します”と謳われた場合、歩行者の安全をないがしろにしても良いという印象を持たれてしまう)ため、自動運転への人工知能の実装は難しい」等々、様々な切り口から実例を挙げつつ議論が展開されています。
400ページ弱という新書にしては多い目のボリュームに「人口知能と人工意識」、「知性とは何か」、「意識とは何か」、「私と自己意識の連続性」など興味深い視点で述べられており、内容の半分以上は科学と言うよりは哲学に近い印象です。私自身は本書で茂木氏が述べられている議論の半分ぐらいはあまりに哲学的、抽象的過ぎて理解やイメージが追い付かない印象でした。しかし、簡略化し過ぎれば茂木氏の伝えたい事が十分に表現できなかっただろうし、難解になり過ぎないように茂木氏なりに”攻めた”結果が本書ではないかと思います。理解できた(ような気がする)半分だけでも、何かとんでもなく深淵な世界の一端を見せてもらったような、不思議な読後感が得られました。