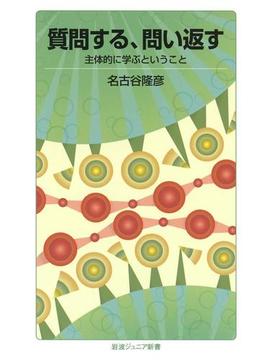- みんなの評価
 2件
2件
質問する,問い返す-主体的に学ぶということ
著者 名古谷隆彦著
さまざまな学校でアクティブラーニングが積極的に導入されるなど,教育現場では「主体的・対話的な学び」の在り方に注目が集まっている.一方通行の学びではなく,自ら問いを立て主体的に学ぶためには何が必要なのか,そもそも「考える」とはどういうことなのか? 多くの学校現場を歩いてきた経験をもとに,主体的に学ぶことの意味を探る.
質問する,問い返す-主体的に学ぶということ
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
質問する、問い返す 主体的に学ぶということ
2019/10/31 17:58
今、聞かないでいつ聞くのか。記者らしい。
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ノッポ - この投稿者のレビュー一覧を見る
ひとつひとつ語られる言葉から相手の深層心理に迫っていく問いかけ方は日常生活にも使えそう。例えば職場の人間関係や思春期を迎えた子供に対してなど、応用できそうです。相手がなぜそういう行動を起こすのか、相手の価値観や判断基準を丁寧に掘り下げて聞いていくには、こちらも問い返すだけの知識や豊かさが必要だということが分かってきます。自己啓発につながる本です。
2018/12/04 21:21
記者らしい
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:あ - この投稿者のレビュー一覧を見る
著者は共同通信の記者であり、全体を通して、取材によって日本の教育に潜む欠点を炙り出し、問題を投げかける内容となっている。日本の教育によってどういった人間が育つのか、ハッとさせられる実例が多く盛り込まれている。フランスの大学入学試験「バカロレア」の話も興味深かったし、「子どものための哲学対話」=p4c(philosophy for children)を取り入れた自治体の子ども達の成長なども面白かった。
興味を失わずに途中まで読めていたのだが、最後の8章で雲行きが怪しくなった。冒頭から、東日本大震災に伴った福島の原発のトピックになる。このトピックを扱うことそれ自体が悪いとは言わないが、どうも著者のイデオロギーが巧妙に仕込まれているように感じた。感傷的なストーリーを道具にして、"被害者"の「悲痛な叫び」「心が引き裂かれるような思い」、"政府や権力者"が「〜と突き放した」「〜と言い放った」「取り合わなかった」などの表現を多用するのは印象操作の常套手段である(この辺のことは『「読む」技術』(光文社新書)に書いてあったと思う)ため、こういった表現が目につくと警戒する。
著者は本書の読者に中学生から大学生を想定したというが、そういった層にこういう刷り込みを行うことは罪深いのではないか。
読者を引き込む文章力があるが、裏を返せば恣意的であり、良くも悪くも記者らしいと思った。