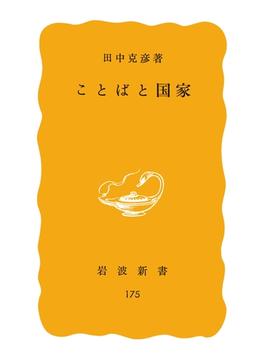- みんなの評価
 4件
4件
ことばと国家
著者 田中克彦
だれしも母を選ぶことができないように、生まれてくる子どもにはことばを選ぶ権利はない。その母語が、あるものは野卑な方言とされ、あるいは権威ある国家語とされるのはなぜか。国家語成立の過程で作り出されることばの差別の諸相を明らかにし、ユダヤ人や植民地住民など、無国籍の雑種言語を母語とする人びとのたたかいを描き出す。
ことばと国家
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
ことばと国家
2004/12/04 14:45
私のことばに国家がどうかかわっているのかを考えさせられる
11人中、11人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:yukkiebeer - この投稿者のレビュー一覧を見る
日本語というひとつの言語で用が足りてしまい、隣の国の言葉と日常的に接する機会もない日本人にとっては、言語というのは空気のように身近で透明な存在です。しかしこうした言語状況は世界的にはまれなことです。ひとつの国家が自国内の多数の言語をある方向に統御していくという、海外では常に目の当たりにさせられる事がこの本では具体的な例とともにわかりやすく提示されています。
この本が出版されるまで日本全国の国語の教科書には「最後の授業」というフランスの小説が掲載されていたものです。ドイツとの戦争に敗れたためにフランスから割譲されるアルザス・ロレーヌ地域でフランス語の授業が明日から禁止される、そんな最後のフランス語の授業を描いた名作短編と言われていました。私も子供のころ、自分の国の言葉を愛することの大切さ、自分の言葉を奪われることの理不尽さを、この小説を通して教えられた憶えがあります。
しかしこの「ことばと国家」が世に出たことで日本の国語の教科書から「最後の授業」が一斉に姿を消しました。「フランス語万歳!」と叫んだ「最後の授業」の舞台となった地域で多くの人々が実は日常的にはフランス語ではなくドイツ語の一方言を話していたということがこの本で明らかにされたためです。<名作>とされた小説の裏に、実は民衆を省みないフランス政府による言語統制があった。その事実に愕然とさせられました。
翻ってみると、この私の使う日本語ひとつとっても、国家の意図とは無縁ではないはずです。自分が話していることばが国家のどういう意図によって成り立っているのか、この本はそのことに目を向けさせてくれます。より主体的に「ことば」にかかわっていくきっかけになる一冊として、多くの人に読んでもらいたいと思います。
ことばと国家
2011/04/23 11:29
偏見を逃れる端緒としての相対的立場
5人中、4人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:Genpyon - この投稿者のレビュー一覧を見る
相対的な立場から「ことば」について論じた著書で、特に、相対的立場から絶対的立場を批判する迫力が小気味よい。
絶対的立場として取り上げられるのは、題名にも「国家」とあるとおり、国家語・標準語といった国家による制度的構築物で、それらの成立過程が多くの興味深い例を交えながらわかりやすく語られる。
相対的立場としては、標準語に対する方言はもちろん、国家語に対しては、国家を持たない雑種言語としてのピジン語・クレオール語など、日本のような国にいると思いもつかないような言語もとりあげられる。
たとえば標準語話者が方言話者を差別したり、標準語からの文法の逸脱を嘲笑したりするような事実が、本著では、標準語や方言の言語的差異によって引き起こされるものではなく、たとえば標準語に与えられた国家の威信といった、言語外の理由によって引き起こされるものと説明される。
ことばに限らず、ある事実についての差別は、事実そのものが持つ性質ではなく、事実外の理由、特に権威的なものがもたらす偏見が原因となって引き起こされると考えられるが、本著は、相対的な立場こそがそういった偏見から逃れる端緒となることを教えてくれる。
ことばと国家
2021/11/08 14:39
国を持たない言語は母国語とは呼べないってか・・・
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:719h - この投稿者のレビュー一覧を見る
本書は言語学に興味を持った頃に手に取り、
そのせいかと言うべきか、
そのお蔭でと言うべきか、
とにかく社会における言語の在り方について
考える上で、現在にまで尾を引くほどの影響を
受けました。
母語と母国語との区別とか。
フランスの言語政策の独善性を
突いているくだりなどは実に痛快です。