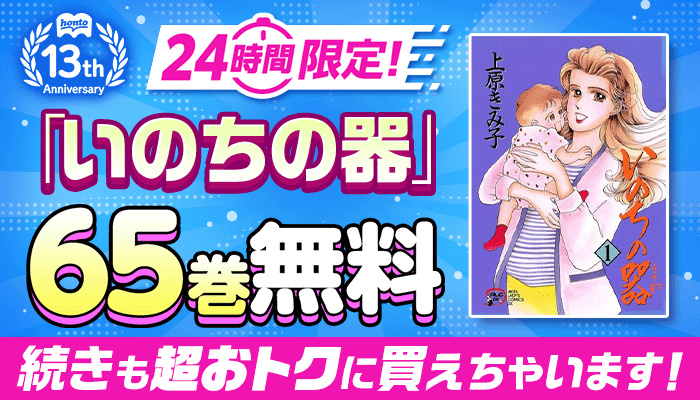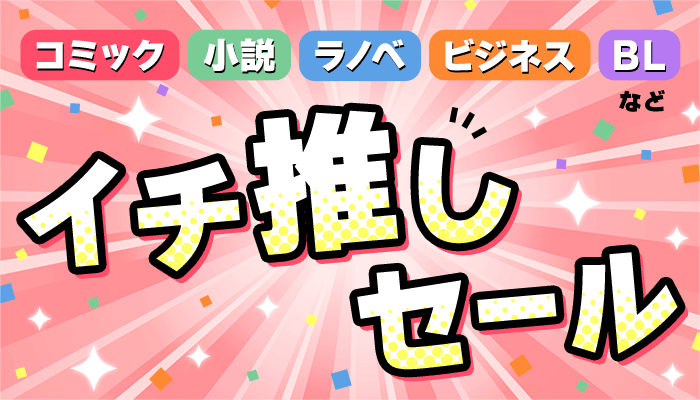- みんなの評価
 2件
2件
モチベーション脳 「やる気」が起きるメカニズム
著者 大黒 達也(著)
気鋭の脳神経科学者が、”飽きない脳”の仕組みを解説
やる気のある人や状態は、やる気のない状態から意識的にやる気を出したわけでなく、脳が「ワクワク」した結果、身体が勝手に動いてノリノリになっている場合がほとんどです。無意識であるという意味では、本来やる気などは存在しません。そのような思い込みが作り出した「モチベーションの壁」を壊すには、脳の喜びを心身に伝えるしかないのです。
モチベーションアップの行動を起こすためには、誰もが生まれつき持っている脳の「統計学習」の機能が有効な手段となります。統計学習とは、脳の潜在的(無意識的)な学習機能です。統計学習によって、脳はさまざまな事柄に対して「次にどんなことがどのくらいの確率で起こるか」を予測し、社会環境の中で何に注意を向けるべきかを適切に察知できます。統計学習において、知っていることばかり起きると脳は「飽きて」しまいます。逆に、脳がワクワクするような適度に新しい出来事が起こると脳のモチベーションが維持され、やる気が身体に伝わるのです。
はじめに
第1章 脳は勝手に判断する――脳の予測とモチベーション
第2章 「脳の壁」を壊す――変化と維持のせめぎあい
第3章 脳と思考の関係――意欲をコントロールする仕組み
第4章 脳の「思い込み」――不満を減らすか、満足感を増やすか
第5章 最高のモチベーションのために――自ら意欲を高める
おわりに
モチベーション脳 「やる気」が起きるメカニズム
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
2023/04/16 18:35
より深く理解する
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:tatenushi - この投稿者のレビュー一覧を見る
統計学習は本能ともいうべき元々ヒトあるいはある程度高度な生物にそなわった機能である。無知な状態から繰り返し同じようなを刺激を受けることで学習し、連続的な刺激は予測ができるようになる。
ヒトの場合、刺激の連続体があまりに変化がなければ退屈を覚える。そこに刺激の変化があると、不安になるが、新しく学習の深度があがる。その新しさへの興味がさらなる学習意欲に繋がり、より高度な学習が始まる。
初めは他者から刺激を与えらるが、次第に自分で発見できるようになり、その興味に従って勝手に学習を深めていく。
モチベーション脳 「やる気」が起きるメカニズム
2023/03/27 17:36
ドーパミン
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:とめ - この投稿者のレビュー一覧を見る
思考と意欲のバランス、不確実性の増減など、脳の統計学習という潜在的な学習機能の観点からモチベーション向上のためのメカニズムを解説している。マグレガーやマズローなど懐かしの名前も出てくる。