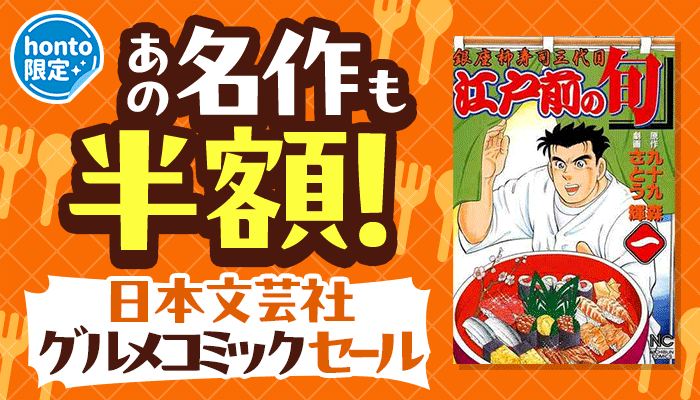- みんなの評価
 89件
89件
三体
尊敬する物理学者の父・哲泰を文化大革命で亡くし、人類に絶望した中国人エリート女性科学者・葉文潔。彼女が宇宙に向けて秘密裏に発信した電波は惑星〈三体〉の異星人に届き、驚くべき結果をもたらす。現代中国最大のヒット小説にして《三体》三部作の第一作
三体0 球状閃電
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
三体 1
2020/08/05 23:49
圧倒的スケールで描かれるSFの原点。
12人中、12人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ゲイリーゲイリー - この投稿者のレビュー一覧を見る
本作は、アメリカ最高のSF賞とも言えるヒューゴ賞を受賞している。
しかもアジア人初受賞であり、そもそも翻訳小説としてヒューゴ賞を受賞すること自体が初快挙なのである。
そんな大注目作品である本作、結論からいうと前評判に劣らない見事な作品だった。
本作のコンセプトは異星文明とのファーストコンタクトである。
これだけを聞くと今まで何度も使い古されてきた題材であると思われるかもしれないが、本作はそのシンプルさが強みとなっている。
最近のSF作品は身近な出来事や日常生活に焦点を当てた、こじんまりとした作品が多いと思われる。
そんな中、本作は圧倒的なスケールで話が展開されていく。
それはまるでSFの原点に立ち返ったかのようで、誰もが宇宙規模の「未知」の世界や科学技術に魅せられることだろう。
また、そのシンプルさに併せてSF要素以外のエンタメ要素をうまく取り入れているのも、本作の魅力の一つだ。
主人公であるワン・ミャオが撮影する写真に映る謎のカウントダウン。
科学者たちの相次ぐ自殺。
そして物語の中盤でワン・ミャオの身に起こる事件。
これらのミステリー要素やサスペンス要素を盛り込むことでページを繰る手が止まらない。
個人的に最も素晴らしいアイデアだと思ったのは、物語内で出てくるVRゲーム「三体」である。
これを用いることで三体世界の説明を登場人物に理解させつつ、読者にも物語の世界観を説明する構造が非常に上手いと思った。
またVRゲームのパートは世界観の説明ではあるのだが、このゲーム内の描写もとても面白い。
そしてもう一人の主人公である葉文潔の過去も本作の欠かせない要素である。
彼女が経験してきた辛い出来事の至る所に政治的問題が描かれており、彼女の下した決断について非常に考えさせられた。
彼女を通して人間に対する「絶望」を描き、ワン・ミャオや史強を通して人間に対する「希望」を描いている。
この人間に対するそれぞれの考え方や、三体協会の内部分裂などが物語に奥行を与えていた。
本作はSF好きな方は勿論のこと、今までSFを遠ざけていた方にも是非読んで頂きたい。
ジャンルに囚われることなく、ただひたすらに面白い小説として本作は素晴らしい作品なのである。
しかもこれがまだ三部作の一作目というのが恐ろしい・・。
二作目以降にも大いに期待したい。
三体 1
2024/04/28 19:31
三体
4人中、4人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ムギ - この投稿者のレビュー一覧を見る
とにかく話題になった本だということで読んでみた。普段SFはほとんど読まないし映画も見ない。どちらかというと苦手であったが、この作品は抵抗感なく読み進められた。三体という名前のゲーム世界の話と現実世界の物語、登場人物の過去の物語に最後には異星人の物語まで、次々と展開が進むが、章立てが細かく、置いてきぼりにならずに読みやすい。キーとなる三体問題についてはイマイチ理解できたかといわれると微妙だが、それで投げ出さないくらい物語として魅力的だった。
三体 2 黒暗森林 下
2020/08/12 16:32
副題に込められた意味。
4人中、4人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ゲイリーゲイリー - この投稿者のレビュー一覧を見る
フェルミのパラドックス
ーー物理学者エンリコ・フェルミが指摘した地球外生命体の文明の存在の可能性の
高さと、その様な文明との接触の証拠が皆無である事実間の矛盾を指す。
本作の副題である「黒暗森林」はフェルミのパラドックスに対する解釈となっている。
下巻では、上巻の冒頭で葉文潔がルオ・ジーに提案した「宇宙社会学」が物語の鍵となる。
「宇宙社会学」の二つの公理と概念を駆使して導き出される結論に驚きを禁じ得ないと同時に、とても納得できる内容となっていた。
下巻では上巻の伏線回収は勿論のこと、アッと思わず声を出してしまう驚きの展開の連続である。
ミステリーと言ってしまっても差し支えないのではと思ってしまうぐらいの、見事な伏線回収と展開なのだ。
第一部以上にハードSFとしてエンタメ小説としてパワーアップした本作は、もう非の打ち所がない。
難解な技術的描写でさえもエンタメに昇華してしまう著者の筆力に感服した。
そして「黒暗森林」や「猜疑心連鎖」といった学説は、現代社会のメタファーなのではないかと考えてしまう。
恐怖から相手への理解よりも攻撃を最優先してしまう姿勢は、未だに我々がとりうる行動である。
そういった目で本作を見るとただのエンタメ小説ではなく、危機に面した時に我々がどのような行動を取るべきかを記しているように解釈できるのではないだろうか。