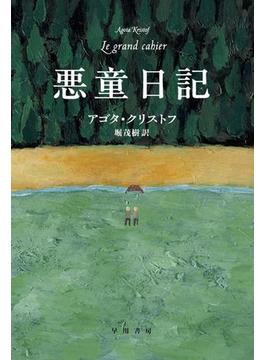- みんなの評価
 21件
21件
悪童日記
戦火の中で彼らはしたたかに生き抜いた――大都会から国境ぞいの田舎のおばあちゃんの家に疎開した双子の天才少年。人間の醜さ、哀しさ、世の不条理――非情な現実に出あうたびに、彼らはそれをノートに克明に記す。独創的な手法と衝撃的な内容で全世界に感動と絶賛の嵐を巻き起した女性亡命作家のデビュー作。
第三の嘘
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
悪童日記
2009/07/14 12:13
愛すべき双子の日々
16人中、14人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:k** - この投稿者のレビュー一覧を見る
第二次大戦のさなか、戦火を逃れるために田舎のおばあちゃんのもとに預けられた天才の双子。しかもそのおばあちゃんは夫を毒殺したと噂され<魔女>と呼ばれる怖い人だった。
けれども二人はそこで農家の仕事を覚え、読み書きを覚え、痛みに耐えることを覚え、たくましくなっていく。
この双子はとても残酷なことを平気でする。だけどその双子がそういうことをするのにはいつだって理由があって常に筋が通っている。二人は二人でいるからこそどんなことも乗り越える。
彼らは絶対に人を差別しない。彼らのものさしでことの善悪を判断し、対応する。たとえ周りからその人が蔑まれていようが、守るときめたら守り通す。
同情はしない。相手が飢えて苦しんでいたら彼らも断食してその気持ちを理解するし、目が見えない人をみたら黒い三角の布を目にあててその状態を理解する。何もごまかさない。
この双子から私たちが学ぶべきことはあまりにも多すぎる。
すべて文章はその双子の視点で描かれていて、シニカルで、そこでは一切の主観も入らないように細心の注意が払われている。
彼らは一見すごく大人にみえるけれど、たまに子どもらしさが垣間見え、又、子どもだからこそ物事を先入観なくとらえられる純粋さがうかがえる。
特に印象に残っているのは、周りからの言葉の暴力に耐えるために二人で訓練するところ。
「ぼくらはもう、赤くなったり、震えたりしたくない。罵詈雑言に、思いやりのない言葉に慣れてしまいたい。ぼくらは台所で、テーブルを挟んで向かい合わせに席に着き、真っ向から睨み合って、だんだんと惨さを増す言葉を浴びせあう。(中略)そして、とうとうどんな言葉にも動じないでいられるようになったことを確認する。しかし、以前に聞いて記憶に残っている言葉もある。おかあさんは、ぼくらに言ったものだ。『私の愛しい子!最愛の子!私の大切な、可愛い赤ちゃん!』これらの言葉を思い出すと、ぼくらの目に涙が溢れる。これらの言葉をぼくらは忘れなくてはならない。なぜなら、今では誰一人、同じたぐいの言葉はかけてくれないし、それに、これらの言葉の思い出は切なすぎて、この先、とうてい胸に秘めてはいけないからだ。」
子どもが子どもでいられないのは社会がそれを許さないからだ。なぜこの双子がこの涙を乗り越えなければならないほど強くならなければいけないのか…それは、なんて悲しくて残酷なことだろう。
私はこの双子を思い切り抱きしめてあげたい。
ふたりの証拠
2011/08/03 10:57
言わない事、言えない事
11人中、11人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:muneyuki - この投稿者のレビュー一覧を見る
2011年7月27日、日にちは微妙に違いますが、レイハラカミ、小松左京の訃報と共に彼女が亡くなった事を知りました。
そういえば買ったのに読んでなかったな、と思って、
『ふたりの証拠』を読み始めました。
『悪童日記』『ふたりの証拠』『第三の嘘』という彼女の代表三部作の内の真ん中が本書。
悪童日記だけ大分前に読了しており、すっかり話の筋を忘れていましたが、『ふたりの証拠』は十分に一冊の本として独立して面白い本でした。
『悪童日記』においては、主人公達を含め周囲の人間は固有名詞を持たず、
一人称は「ぼくら」という複数形で語られます。
この作品のラストで二人は自分達ではっきりとそれぞれの思いを固め、
別れる・分かれることとなります。
そして、『ふたりの証拠』の開始時、
「ぼくら」は初めて「リュカ」と「クラウス」という名前を獲得して、
別々の人間である事が自覚的・客観的に示されます。
国境の向こう側へと「行った」クラウスと、
そのまま其処へ「残った」リュカ。
本作では残ったリュカについての物語が語られます。
「ぼくら」であることを失ったリュカには、もう何もない。
美しい青年に育ったリュカではありましたが、
彼には目指すべき将来も、愛すべき家族も、人間的な欲望も、
何も持たない街の影の様な存在として人々に「白痴」と呼ばれながら、
家に暮らし、農業を営み、それでも何とかギリギリに人間的な生活を送っています。
しかし、突然の闖入者によって、リュカにも一つの希望が示されます。
其処から始まるのは、リュカの、人間としての再生の物語。
戦争によって色んなモノが歪められた街の中で、
色んなモノを失った人間達と共にリュカの、リュカ個人としての物語が漸く幕を開けます。
けれども「正確ではない言葉」を、「甘っちょろい言葉」を排した
アゴタ・クリストフがそんなに甘甘なストーリーを描く筈も無く。
僕達人間には、「美しい」とか「楽しい」とか、
うまく完全には言葉で表せない感覚的なモノがいつも心の中に存在しています。
うまく言い表せないモノだから、色んな言葉を借りて来て
「天上の如き至福」とか「ヴィーナスの嬰児のように美しき」とか
色んな思いを言葉に託します。
しかし、その過程で何かをサボってないか。
本当にその感覚を心に刻みつけたか。
言葉選びに耽溺しているだけではないか。
クリストフの描く『ふたりの証拠』は、全く感情表現が排されているにも拘わらず、読者の心に揺さぶりをかけてきます。
何故こんなに「カッコいい言葉」を使わないのに、心を締め付けられるのか。
『悪童日記』においては、感情表現が排される事で、子どもの子どもならではの残忍さ・冷酷さが強調され、衝撃的な印象をより強めていました。
しかし、本作『ふたりの証拠』においては、その技法は喪失感や悲しみを強調する為のワザとして作用しています。
そういった感覚は、完全に人と共有する事は出来ない為、ついつい私達は「カッコいい言葉」を使って、より自分だけのものとして大事に大事に心の中にとっておこうとします。
甘い。
この本の最後で、今までの物語が一気に引っくり返されます。
それでは今まで描かれてきたモノは何だったのか?一体誰の語りだったのか?
早いとこ『第三の嘘』も読まなければ…。
悪童日記
2011/07/17 09:32
決して癒えない傷が書かせる物語
6人中、6人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:SlowBird - この投稿者のレビュー一覧を見る
戦争において子供達が被る被害は理不尽なものだろう。もっとも、その理不尽さなど問題にせず、もっとも早く状況に適応するのも子供かもしれない。もちろんそんな適応がいいこととは言えず、人格の奥底に暗い記憶として残り、消えない怨嗟の連環を生み出すのではないだろうか。
ナチス占領下にあったハンガリーと思しき舞台で、祖母の元に疎開させられてくる双子の少年。直接戦火を受けるわけではないが、それまでの暮らしから一転する物資の不足、弱者にいっそう辛くあたる人々、その背景にある思想統制が、子供達を圧迫する。
それでも子供達は表面上は元気を失わずに成長するのだが、大人になってみて消しがたい人間不信か硬直性かなにか、自分の人格の歪みに気づくだろう。あの頃に自分を抑圧したもの達に反抗し、あるいは貝のように自我を閉ざして守ることが出来たらと夢想するだろう。
双子の少年達は、町では魔女と呼ばれて孤独に生きる祖母と暮らすうちに、彼女が純真で一途さを貫いているがゆえにそう呼ばれていることを感じ取り、その生き方をロールモデルとして取り入れることで自分たちの世界を守り通す。
彼らは当時の大人達から見ればどうしようもない悪たれ小僧であり、反社会的な存在ですらある。しかし子供が本来の自分として成長するためには、それが必要だった。なにより大人達の裏をかき、鼻を明かし、翻弄する彼らの姿こそは、かつて虐げられた者による大人への復讐なのだ。この双子の存在は、戦争に流され、民族イデオロギーに加担した大人達への糾弾だ。だからこそクールで痛快。時には彼らなりの純粋さでひそかな懲罰を与えもする。戦禍を生き延びることで精一杯だった、彼らのもっとも愛した両親さえも、距離を置いて見るようになっていく。
支配者はナチスからソ連へと移って行くが、子供達にとっては何も好転するわけでもなく、支配者に摺り寄る大人が入れ替わるだけで、そのことも彼らは冷徹に見ている。
日本の戦争末期から戦後にかけてでも、やはり疎開したり親を失ったりした子供達は同じような境遇にあったのだろうし、周囲の大人の欺瞞に目をつぶって生き延びて来たのだろう。そしてたぶん、復讐などする余裕も無かったのだ。大人達に十分な庇護を受けた子供達には分からないことで、同じ世代の中でも「悪童」の側とその反対の立場がいることだろう。
この作品は、作中での復讐と同時に、作者のように時代を経て理解者の少ない境遇の者から、当時から現代までその罪を忘れて来た人々への復讐でもある。この自分が撃ち抜かれた者であることに気づかない人々を、僕らは目撃する。