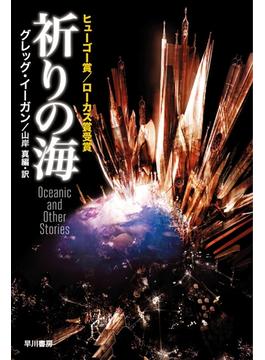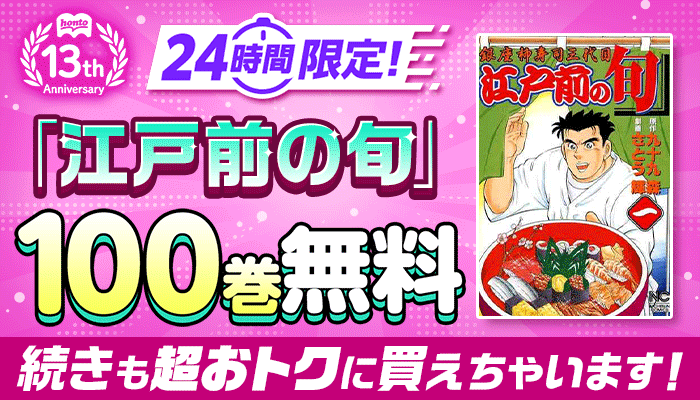- みんなの評価
 6件
6件
祈りの海
二万年前に惑星コブナントに移住し、聖ベアトリスを信奉する社会を築いた人類の子孫たち。そこで微小生物の研究を始めた敬虔な信者マーティンが知った真実とは? ヒューゴー賞・ローカス賞を受賞した表題作、バックアップ用の宝石を頭のなかに持った人類の姿を描いた「ぼくになることを」ほか、遙かな未来世界や、仮想現実における人間の意志の可能性を描く作品までヴァラエティにとむ全十一篇を収録。
祈りの海
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
祈りの海
2001/04/24 21:42
不死社会の中の死?
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:キュバン - この投稿者のレビュー一覧を見る
これは中短編集だが中でも特に「ぼくになるために」に焦点をあてる。
脳の情報をそっくり全てコンピューターや他の脳に写すことで肉体は死んでも意識の不死性を獲得する、という設定のSFは数多い。だがこれは真の不死性の獲得だろうか?
生き残るのはあくまでもコピーであり、自分自身の意識ではないことは明らかに思える。−−−命題1
一方この技術が実現し普及した社会を考えてみよう。本体が死んだ後に生き残ったコピーにとって自分は本体が物心ついてからの全ての記憶を持つ本体自身としか感じられない。そしてその記憶には死んだはずなのに生き返った経験も含まれている。このコピーにとってはもう一度死んで別のコピーが生き残ることは真の不死としか感じられないだろう。まして他人にとってはコピーと死んだ本人の区別はできない。
結果として命題1を正しいと考える人はいなくなり、この技術は不死を実現する素晴らしい科学の勝利ということになり、この社会は存続する。その影で何億もの意識が殺されていることは誰にもわからない。本体が死ぬのが寿命なら良いが「本体の性能が落ちる前に」処置されるとなると事は深刻である。
この状況は相当リアルで深刻な恐怖だが、命題1の恐怖を正面切って描いたSFを私が読んだのは本書「ぼくになるために」が初めてである。他の作家がよほど脳天気なのか?イーガンが鋭いのか?
本作品は一応はハッピーエンド?なのだが。
実は脳のハードウェアを少しずつ置き換えた場合を想定すると命題1も必ずしも正しくないかも知れない点は付記しておこう。
他の作品にも触れると、「キューティ」「繭」は社会派作品と言えるが極近未来に、いやもう既に実現しうる状況を描いている点で衝撃が大きい。この2作は既に未来小説ではなく現代小説である。
「誘拐」も考えさせられる作品だ。見方によっては人形に魂を感じる感性は昔からあるじゃないかとも言えるのだが。
「イェユーカ」は社会悪との対決の物語でラストは感動的。奇しくも現実の世界でもエイズ治療薬のゾロ品問題が起きたが。
「祈りの海」のテーマは「月があばただらけの岩の塊とわかったらロマンがなくなるのでは?」というのと同じテーマに思えて新鮮味は感じない。設定された社会と人々の描写はおもしろく読める。
祈りの海
2017/04/29 14:34
これが本当のハードSFなのかもしれない
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:コスモス - この投稿者のレビュー一覧を見る
前々から気になっていたハードSFの作家グレッグ・イーガン。
一回読んだだけでは、内容が全く理解できないかもしれませんが、そこであきらめてはいけません。僕は二回読んで内容を理解することが出来ました。
内容を理解できた時に感じられるセンス・オブ・ワンダー、それでいて徹底的に科学的な厳密性を追求し、なおかつ人間のアイデンティティーを問う内容に、読者はいろいろなことを考えさせられるでしょう。
2015/03/30 21:34
すこしふしぎ
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:えむ - この投稿者のレビュー一覧を見る
難しかったけれど、面白かったです。
間抜けな感想ですみません・・・。
どの話も近未来のありえそうな状況に主人公が悩む、というものです。
個人的には“キューティ”のお父さんと“繭”の捜査官?さんが好きです。
宗教や思想が絡むものはちょっと理解が追いつきませんでしたか、
また読み返して噛み砕こうと思います。