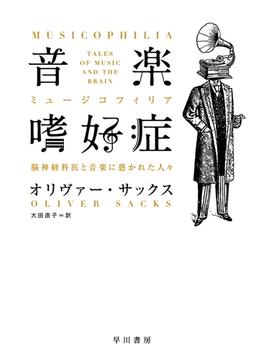- みんなの評価
 3件
3件
音楽嗜好症(ミュージコフィリア)
著者 オリヴァー・サックス , 大田 直子
雷に打たれ蘇生したとたん音楽を渇望するようになった医師、ナポリ民謡を聴くと発作を起こす女性、フランク・シナトラの歌声が頭から離れず悩む男性、数秒しか記憶がもたなくてもバッハを演奏できる音楽家……。音楽と精神や行動が摩訶不思議に関係する人々を、脳神経科医が豊富な臨床経験をもとに温かくユーモラスに描く。医学知識満載のエッセイは、あなたの音楽観や日常生活さえも一変させてしまうかも?
音楽嗜好症(ミュージコフィリア)
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
2015/10/24 23:25
オイ、ヴェイ、ヴェイ。・・・・
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:okadata - この投稿者のレビュー一覧を見る
雷に打たれ命を取り留めた替わりにいきなり音楽に取り憑かれた男、金管楽器の低音に反応しててんかん発作を起こす船乗りと言った様々な症例を紹介するオリバー・サックスは「レナードの朝」の原作で有名な神経学者だ。
歌手がよく音楽の力を口にするがどうも一定の条件では本当に力を持つ。言葉を話せなくなった失語症の患者が音楽にのせると会話ができるようになる事がある。なんと話しかけても「オイ、ヴェイ、ヴェイ。・・・」を繰り返す自動症の患者に音楽に乗せて問いかけると答えが帰ってくるようになった。「コーヒー、それとも紅茶?」「コーヒー」・・・「デイヴィッドは治っている!」彼の食事を持って帰りこう告げた。「デイヴィッド、朝食だよ」「オイ、ヴェイ、ヴェイ。・・・」
絶対音感を持つ者がいれば、音楽を認識できない人もいる。4~5歳で音楽の訓練を始めた場合ちなみに中国人の6割は絶対音感の基準を満たしたのに対し、普通のアメリカ人の場合わずか14%に留まった。声の高低を使う声調言語が音感を鍛える様なのだ。絶対音感のある音楽家の脳は側頭平面の大きさが、左右で大きく違っており、赤ん坊の方が絶対音感に頼るところが大きいことから「大部分の人間は絶対音感をなくし、音楽能力が縮小した」のかも知れない。とは言え絶対音感と美しい音楽を作る能力は別物だ。
生まれつきの視力障害の場合に聴力が発達するのは使われない視神経を聴覚に割り当てるからで、感覚神経は融通が効くものらしい。音色や言葉や数字に色を感じる共感覚はなんだか電話が混戦しているような話だ。特定の才能だけが飛び抜けている知的障害のサヴァン、「なぜ私たちみんなにサヴァンの才能がないのだろうか?」、胎児や乳幼児で弱い左脳が損傷を受けた場合、右脳が対照的に過剰発達をしてしまうのか。左脳が発達すると右脳機能の一部を抑制したり阻止したりするのだが左脳の損傷で変則的に右脳優位になる場合がある。
脳神経に起きているのはおそらく物理的な現象だがそれにしてもいろんなことが起こる。オリバー・サックスの新作は「見てしまう人々 幻覚の脳科学」すでにiPadの中で積ん読状態でこちらも楽しみだ。
音楽嗜好症 脳神経科医と音楽に憑かれた人々
2016/03/21 00:20
音楽は言葉の代替手段なんだろうか
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:タヌ様 - この投稿者のレビュー一覧を見る
絶対音感は4,5歳までにトレーニングすると身につく、最初はある人が多い。実際にそういう実例を見てきた。
なんとも、この音を捉える力は、不思議なのである。
音楽専門の人に言葉が通じないと言うか、聞こえていても理解していない。コミュニケーション不可だと思う一方で、日本語以外の言語をいともたやすく身につけている。苦もなくなのだ。そう、聞いているうちになんか身につけているのである。
本書でそういう不思議な外界世界と関わり方をする人の脳はMRIでたやすく変異が確認されるとある。作家や数学者はできないんだそうで。
脳という未知なる世界が創り出す人間像をサックス氏は語っている。なんとも驚きではあるのだが。
音楽嗜好症 脳神経科医と音楽に憑かれた人々
2015/04/26 17:38
音楽の力
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:Tucker - この投稿者のレビュー一覧を見る
映画「レナードの朝」の原作者としても有名な脳神経科医オリヴァー・サックスによる医学エッセイ。
著者の他の作品でもそうだが、長い脚注が玉にキズ。
「音楽嗜好症」という名前の病気があるわけではなく、音楽に関連する症例と、その考察となっている。
また、症例だけでなく、音楽に関するサヴァン症候群の話や、音と色の共感覚の話などもあり、実に盛りだくさん。
音楽を聴いたり、演奏したり、歌ったりするする事は、脳の様々な部位に関わり、かつ深い部分に根ざしているらしい。
病気やケガで、脳の機能の多くが破壊されてしまったとしても、音楽を認識する機能は、なかなか損なわれない。
歌う事ができる失語症患者がいるかと思えば、リズムをつけて歌うように話す事で意思の疎通ができる認知症患者もいるし、記憶が数秒しか持続しない元音楽家の患者は演奏する事ができる。
そういえば、映画「レナードの朝」でも、指一本動かせない患者が音楽に反応するシーンがある。
自分の事を振り返ってみても、Youtubeなどで、子供の頃、見たアニメや特撮番組の主題歌を聴いたりすると、ストーリーは、さっぱり覚えていなくても、自分でもビックリするほど、正確に歌えたりする事がある。
それに音楽ではないが、「イイクニ作ろう」と言われたら、未だに「鎌倉幕府」と反射的に答えてしまう。
(今は、鎌倉幕府の成立は「1192年(イイクニ)」ではないらしいが・・・)
つくづく思うのは、人間の脳の働きの不思議さ。
チェスや将棋など特定のルール下で行われるものなら、人工知能が人間に勝つ時もあるが、「故障」に対する「冗長性」では、人間の脳の方がはるかに進んでいると思える。
本書で紹介された患者達は、「故障」した機能の代わりに動き出した部分が、過剰に活動してしまっているが・・・。
ところで、実際に音楽を治療に用いる「音楽療法」というものも、あるらしい。
薬も効かない症状に対して、音楽が効く、というのも、不思議と言えば、不思議な話。
(ただ、音楽によって、発作が起きる、あるいは症状が悪化するケースもあるので、音楽は決して「万能薬」ではない。)
一体、人間にとって、音楽とは何なのか?という疑問も湧いてくる。
音楽も作曲者や演奏者との「触れあい」と考えれば、映画「レナードの朝」のラスト近くのセリフが頭をよぎる。
「一番の"薬"は"人の心"(=人との触れあい)だった。」