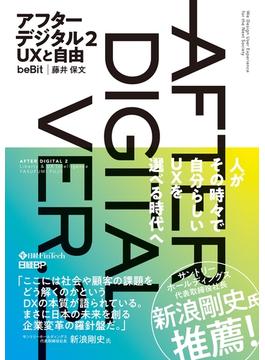- みんなの評価
 4件
4件
アフターデジタル2 UXと自由
著者 藤井 保文
デジタルが隅々まで浸透した「アフターデジタル」社会。日本はその社会に向けてゆっくりと進んでいましたが、コロナ禍で状況は一変し、速度を上げてアフターデジタル社会に突き進んでいます。
多くの日本企業は「DX戦略」で活路を見いだそうとしていますが、実はその立脚点が危ういケースは少なくありません。すべてがオンラインになるという前提に立っていないのです。
本書ではアフターデジタル先進国に注目し、特に中国のアリババやテンセントといった巨大デジタル企業の「戦略」、表面的な取り組みの奥にある「本質」に迫ります。事実として、アフターデジタル社会では産業構造がひっくり返ってしまいます。これは予測ではなく、実際の中国市場がそうなっており、こうした世界が広がれば、日本のお家芸ともいえる製造業は最下層に位置づけられてしまうのです。
いわゆるデジタル企業だけでなく、デジタルビジネスとは直接関係ないと思っているビジネスパーソンにも、本書を読んでほしい。なぜなら、アフターデジタルでは、リアルがなくなるのではなく、リアルの役割が大きく変わると言われているからです。
アフターデジタル社会になると、市場のルールが変わると考えたほうがいい。キーワードは「UX」。そして、アフターデジタル社会において成功企業が共通で持っている思考法を「OMO」(Online Merges with Offline)と呼びます。社会の変革は避けようがないなら、こうした新たなルールをいち早く学び、自社の立ち位置を決めて戦略を練らねば負けてしまいます。既に新たな成果を出し始めている日本企業もあります。デジタルを強みにするには必読の書です。
アフターデジタル2 UXと自由
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
2023/04/20 17:43
UXの重要性を再確認できる
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:八朔 - この投稿者のレビュー一覧を見る
書籍内に登場するOMOという考え方はいままで知らなかった考え方で、DXを誤った方向で自分は捉えていたんだなと感じました。
顧客接点をどのように作るかという、マーケティングの学びもあり、読んで損がない書籍です。
実例も様々登場し、読みすすめやすい書籍です。
アフターデジタル 2 UXと自由
2021/08/11 00:36
DXの目的は「新しいUXの提供」
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:しょひょう - この投稿者のレビュー一覧を見る
薦められて購読。前著「アフターデジタル」も読んでおり、さほどの感想もなかったのであまり気が進まなかったのだが、本書は読んでよかった。
前著は「進んでいる中国の事例紹介」程度の印象だったが、本書では、「デジタル」により管理社会・監視社会に陥らず、むしろ社会・顧客の多様性を発展させていく、満足させていくためにどういたらよいか、を理念と実践を説いている。
読んだからと言ってすぐに実践できるわけではないが、アフターデジタル、OMOとは何か、に少し近づいた気がした。とてもおすすめ。
本書の構成(まえがきより)
第1章 「アフターデジタルを凝縮し、最新状況にアップデートする」章
第2章 「新しい産業構造での生き残り方、勝ち方を事例から学ぶ」章
・製品販売型 → 体験提供型
第3章 「自らの視点を補正する」章
・日本にありがちなアフターデジタルの誤解・妄想・幻想
第4章 「アフターデジタル社会の在り方を考える」章
・「精神」と「ケイパビリティ(能力・方法論)」
第5章 「日本企業の取り組みから学ぶ」章
・流通と接点
2020/08/30 02:04
とても面白く、興味深く、共感できるところがすごく多くて、大変勉強になり、気持ち良く読めた。
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:matsuzaka - この投稿者のレビュー一覧を見る
昔から、ユーザーインターフェースやコミュニケーション、メディアが、あらゆるサービスにとって最重要なんじゃないかと思っていて、本書というかアフターデジタルがUIというかUXにさらにフォーカスしていくのは、読む前から楽しみだったし、読んでさらに意識が高まった。
もちろん、アフターデジタルは、単にUIの話ではなくて、もっと高次だけど当たり前のこととして、ユーザーが欲しい物を欲しいタイミングで提供すれば、ユーザーは喜ぶ、という、至極当たり前のことを言っていて、それを、飛躍的に進化するデジタルテクノロジーを存分に活用しながら、実行する、デジタルとリアルを組み合わせれば、それは非常にやりやすくなっている、可能性が高まっている、という感じがする。
ビフォアデジタルでも、カーディーラーとかの優秀な営業マンというのは、ベタだけど、車そのものにとどまらず、顧客の心を掴むあらゆる小技を、顧客の生活に浸透していたりして、成功のコツが属人的に詰まっていることがある。それをテクノロジーで汎用化しようという試みがアフターデジタルの一部なのかも知れない。
「ジャーニー」という考え方で思い出されたのは、いい意味で一昔前のソニーの商品群で、ハードウェア技術・製品オリエントなところではあるけど、必ずソフトウェアそのものと、ユーザーの利用シーンを提案していたことはすごく当時好感を持っていたことを思い出した。
また、アフターデジタルのプロセスの中では、やはり既存事業は稼ぐ大事なコアで、そこに高頻度なデジタル顧客接点(インターフェース)を組み合わせていく、というのは、なんか、アナログな既存事業をやっている身としては、勇気づけられたようにも感じた。
アフターデジタル、好きな分野だから、会社の中でも、好きな人の方が熱量があると思うから、自ら、率先して牽引できるように頑張りたい。
あと、アフターデジタル&UXという観点は、UXを通してユーザーがサービスの使い方を学んで成長することは大事だし期待されるし、そこでサービス寄りに染まっていけば、エコシステムや自社経済圏としてすごく有利になると思う。
もちろん初期は寄り添うことも重要だけど、慣れればリテラシーとして獲得されることはすごく大きいと思う。