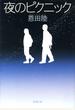しょひょうさんのレビュー一覧
投稿者:しょひょう
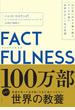
FACTFULNESS 10の思い込みを乗り越え、データを基に世界を正しく見る習慣
2019/03/09 23:46
評判通りの名著!
38人中、35人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
書店で平積みになっていて、あちこちで取り上げられていたことから購入して通読。
さまざまな本能(むしろ思い込み)に惑わされず、事実(データ)を基に世界を正しく捉えることの重要性とそのためのポイントを、平易な言葉で明るく、かつ豊富な具体例を交えながら説得力・熱意をもって伝える。
本文だけでも300ページを超える本だが、グラフや写真も多いし、冒頭にあるクイズに代表されるように、読者を引き付ける工夫に満ちているので、色々考えさせられながらも、飽きることなく最後まで読める。
また、この手の本にありがちな「これが正しい唯一の方法論だ」みたいな断定的・強硬な主張はなく、本書は、どんなことにも限界があることを素直にかつ明るく認め、極端に偏らず、バランス感覚を保っている点も非常に好感が持て、気持ちよく読めた。
ここ数年で読んだ本の中では、全然ジャンルは違うが「サピエンス全史」以来の満足感。同書よりも気軽に楽しく読めるので、幅広い方にお薦め。

忘れられた日本人
2017/12/17 23:15
知らなかった日本
7人中、6人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
書名に惹かれて、何となく手に取った本だが、読む前とは少し違った自分を感じる。
民俗学者の宮本常一が昭和前半に西日本を中心に旅をして、各地の老人から聞いた話をまとめたもの。昭和前半に老人だった者の子供の頃(すなわち明治頃)の山里の村々の風習、風俗、日々の暮らしが語られている。
寄り合い、夜這い、隠居、本家・分家、今となっては昔話の民話のような暮らしが、今から100年あまり前まで、確かに日本にあったのだ、ということを感じさせられる。
21世紀の都会で暮らす身からすると、「忘れられた日本」というよりも「知らなかった日本」であった。
その頃が良かった、というような懐古主義ではないが、何か大事なものを忘れてきてしまったのではないか、という気にさせられる。私たちの数世代前の先祖の暮らしぶりを語り継ぐ本として、今後も多くの人に読み続けられて欲しいと思う話だった。
お薦め。

ホモ・デウス テクノロジーとサピエンスの未来 上
2018/12/13 00:47
人間至上主義の先のデータ至上主義は必然か
4人中、4人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
サピエンス全史に大きな感銘を受けたので、続編である本書も購読。
「過去」の物語であった前作に比べると、「現在と将来」を論じているだけに、多少抽象的・概念的な部分が多く、読むのに苦労したが、予想通り満足。
著者は、人間至上主義の先は「データ至上主義」とし、人間は宇宙の中心からただのデータになる、と未来を予測しつつ、読者に対して未来は変えられる、と訴えるのだが、(逆説的になるが)あまりに説得力のある論理展開に、未来は必然なのではないか、とも感じてしまった。
必ずしも明るい結末の本ではないが、前作同様にいろいろ考えさせられた。
折に触れ繰り返し読んでみたい一冊。
また、前作も同様だが翻訳本とは思えないほどに、こなれて読みやすい日本語訳もありがたい。
2017/11/19 23:31
分かりやすく面白い
4人中、4人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
書名に惹かれて電子書籍で購読。
知的財産権については、何となくの興味はあったが、しっかり勉強したことはなかったが、本書で(もちろん入り口だけだが)楽しく学ぶことができた。
著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権など、言葉は聞いたことがあっても、それぞれの違いはよく分からない諸権利について、法律をもとに解説しているほか、実際に起きた事案紹介もあって、最後まで興味を持続できた。
図表や実際の写真も多く掲載されているのも、素人にとってはありがたい。
もちろん、一読しただけで全体像が把握できるわけではないのだが、専門書に行く前の入門書として、単純に知的好奇心を満たす書籍として非常にお薦め。
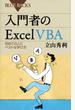
入門者のExcel VBA 初めての人にベストな学び方
2017/03/12 22:43
分かりやすい
3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
VBAは、記録マクロ+αでウロウロしているレベルなので、一度基礎をしっかり学びたいと考えて購読。
新書一冊と分量は少なく、紹介されている例も少ないが、著者が言っているように、初心者が躓くポイントをしっかり押さえて記載されている。
特に、変数についての記載は、これまで読んだ類書のどれよりも分かりやすく、本書に記載されていない機能についても、独力で学んでいけそうな気がした。
1~2日で読める量だし、分厚い本に手を出す前にまず一読ための本として、実際にプログラムを書きながら、ふと根本のところに不安を覚えたときに立ち戻るための本としてお薦め。
2017/02/05 22:21
経済・社会を考えるのにお薦め
3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
20世紀アメリカの経済学者ガルブレイス(1908-2006)の生涯・思想を解説。
現代資本主義の分析をもとに、政府の適切な関与の必要性を主張した。
グローバル資本主義の限界が明らかになり、格差の問題がクローズアップされる今、経済学に止まらず、社会全般について考えさせられる一冊。
文章は平易で、経済学についての深い知識は不要。
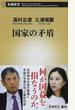
国家の矛盾
2017/02/26 21:11
一読の価値あり
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
書店で興味を持ち、電子書籍化されたので購読。
自民党の高村副総裁と国際政治学者の三浦瑠麗氏の対談録。
平和安全法制をメインに外交、政治について語っている。
基本は高村氏が話し手、三浦氏が聞き手だが、三浦氏の見解も随所に示される。
新書の対談録なので、非常に読みやすく、特に平和安全法制についての高村氏の考え方、および他の考え方がが平易に語られている。
その他のテーマは深く掘り下げられてはいないが、高村氏の現実に真摯に向き合う姿勢は、とかく耳障りのよい話に飛びつきがちな風潮のなかだからこそ、妙に安心させられる。
二時間ほどで読み終えたが、読んでよかったと思う一冊。
モチベーション3.0 持続する「やる気!」をいかに引き出すか
2019/12/04 01:15
読みやすく説得力あり。お薦め。ただし、実現は難しい・・・
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
書店で見つけ、面白そうだったので電子書籍で購入して通読。
アメとムチ、金銭的報酬によるモチベーションは長続きせず、自律・内発的な本来人間に備わっている欲求によるモチベーションが必要、というのが主張。
「金銭的な報酬は、その活動への本心からの興味を失わせる」と。
(以下の2から3への移行の必要性を訴える)
モチベ―ション1 生存欲求
モチベーション2 報酬と処罰(アメとムチ)による欲求
モチベーション3 自律・内発的欲求
多くのビジネス書(最近だと「ティール組織」などもこの系譜か)が同じような主張を述べているが、本書は著名人の語録を豊富に用い、論理的にかつ平易、説得力を持って語られている。読んでいて楽しい。良書。
後半にはモチベーション3になるためのヒントや参考図書も掲載されている。「そんな理想を言っても実際にはアメとムチだよ」とか「成果主義にも課題はあるが、それを否定すると年功序列の悪平等だし」などと思いつつも、本書が提示する第三の道を試してみたくなる。
電子書籍で読んだが、紙の本の方が読み返しやすかったかもしれない。お薦め。
2017/05/27 00:13
読んでよかった。勉強になった。
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
タックスヘイブンについては、テレビや新聞で一通りのことは理解しているつもりだったが、ほんの表面しか知らなかった、ということが良く分かった。
タックスヘイブンは、先進国・大国も含めたさまざまな「国益」が絡み合っていること、なにより、その本質が税率が低いことではなく、情報の非開示性にある、ということは、言われてみればその通りだが、本書により良く理解できた。
タックスヘイブンを使っての資金洗浄などの事例も紹介されている。その核心は本書を読んでも分からないが、グローバルに国境を超えるマネーと国境に縛られる租税、の根本的な不整合がある限り、その解決は容易ではないと感じた。
表現の端々に著者の自慢・アピールが入るので、気に障る人もいるかもしれないが、総じて読みやすかった。お薦め。
2022/05/08 20:55
誠実なレポルタージュ
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
みずほ銀行のシステム障害についてのレポート。
金融機関のシステムに係わった経験があったのと、システム障害が起きていた頃に前作(MINORIをかなり持ち上げた内容)を複雑な思いで読んでいたのだが、その日経コンピュータが障害をどう評価しているのかにも興味があって通読。
読了した感想としては、かなり良かった。
事実を事実とし、原因分析もステレオタイプを排して地に足が着いていると感じた。
誠実な叙述に好感を持てた。読んでよかった。

アフターデジタル 2 UXと自由
2021/08/11 00:36
DXの目的は「新しいUXの提供」
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
薦められて購読。前著「アフターデジタル」も読んでおり、さほどの感想もなかったのであまり気が進まなかったのだが、本書は読んでよかった。
前著は「進んでいる中国の事例紹介」程度の印象だったが、本書では、「デジタル」により管理社会・監視社会に陥らず、むしろ社会・顧客の多様性を発展させていく、満足させていくためにどういたらよいか、を理念と実践を説いている。
読んだからと言ってすぐに実践できるわけではないが、アフターデジタル、OMOとは何か、に少し近づいた気がした。とてもおすすめ。
本書の構成(まえがきより)
第1章 「アフターデジタルを凝縮し、最新状況にアップデートする」章
第2章 「新しい産業構造での生き残り方、勝ち方を事例から学ぶ」章
・製品販売型 → 体験提供型
第3章 「自らの視点を補正する」章
・日本にありがちなアフターデジタルの誤解・妄想・幻想
第4章 「アフターデジタル社会の在り方を考える」章
・「精神」と「ケイパビリティ(能力・方法論)」
第5章 「日本企業の取り組みから学ぶ」章
・流通と接点

両利きの経営 「二兎を追う」戦略が未来を切り拓く
2021/08/01 23:01
「深化」と「探索」を両立するのはリーダーシップ
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
本屋で気にはなっていたものの読む機会がなかったが、とある研修課題となっていて購読。
成熟した大企業が「イノベーションのジレンマ」を超えて成長していくためには「深化」と「探索」の二兎を追う(=両利きの経営)」ことが必要。
この二兎を追い続けるためのリーダーシップ5原則が以下。
1.心に訴えかける戦略的抱負を示して、幹部チームを巻き込む。
2.どこに探索と深化との緊張関係を持たせるかを明確に測定する。
3.幹部チーム間の対立に向き合い、葛藤から学び、事業間のバランスを図る。
4.「一貫して矛盾する」リーダーシップ行動を実践する。
5.探索事業や深化事業についての議論や意思決定の実践に時間を割く。
豊富な事例(成功事例だけでなく失敗事例)を挙げた本文での説明に加え、巻頭の解説も分かりやすくおすすめ。
それにしても、「両利きの経営」とはかくも難しいものか。。。と実感。

イノベーションのジレンマ 技術革新が巨大企業を滅ぼすとき 増補改訂版
2021/05/03 22:08
現代の古典という形容がぴったり
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
さまざまなビジネス書や論考で引用されていて、いつかは読まねばと思っていたので一念発起して購読。
大まかな内容は知っていたので驚きはないが、実証的なデータ・研究に基づく丁寧な論理展開に圧倒される。
「大企業が正しく行動することにより新興企業にとってかわられる。」
原書が出版されてからもうすぐ四半世紀だが、まさしく現在のIT新興企業の勃興と既存大企業の苦境を予言しているかのよう。
本書を四半世紀前に読んでおけば、と思う反面、読んでいてもやはり「正しく敗れる」道を進んでしまうような気もする。
要旨はすでに人口に膾炙するところだが、腰を落ち着けて精読したことで本書の価値を実感できた。今更だが、読んでよかった。
2020/08/30 20:46
心地よい読後感
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
新潮文庫の100冊の中からチョイスして電子書籍で購読。
学校行事の歩行祭(丸一日歩く)に様々な思いを持って臨む高校生の物語。
ネタバレになるので、内容は控えるが、生徒たちが歩行祭のゴールに近づいていくなかで感じる寂しさのような気持ちと、この物語が終わりに近づいているという気持ちが妙に響きあうところがあって、心地よい読了感だった。
高校生活なんてもう数十年も前のことになってしまったが、たまには青春小説もいいな、と思った。

現代経済学 ゲーム理論・行動経済学・制度論
2019/02/28 22:32
経済学の「今」を俯瞰するのに適した好著
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
書店で惹かれて購入。
書名の通り、現代の経済学(20世紀後半以降)の研究テーマをノーベル経済学賞などとともに解説。
経済学については昔ながらの「ミクロ経済学」と「マクロ経済学」を数十年前に勉強しただけで、行動経済学やゲーム理論などは表面的な知識しかなかったが、本書で大きな流れや関係性が理解できた。
300ページにも満たない新書に広範な内容が詰め込まれているので、1つ1つについて深く学べるわけではないが、教養として経済学を捉える読者にとってはありがたい一冊であり、かなりお薦め。
序章:経済学の展開
第1章:市場メカニズムの理論
第2章:ゲーム理論のインパクト
第3章:マクロ経済学の展開
第4章:行動経済学のアプローチ
第5章:実験アプローチが教えてくれること
第6章:制度の経済学
第7章:経済史と経済理論との対話から
終章:経済学の現在とこれから