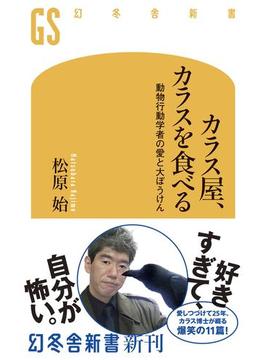- みんなの評価
 2件
2件
カラス屋、カラスを食べる 動物行動学者の愛と大ぼうけん
著者 松原始
カラス屋の朝は早い。日が昇る前に動き出し、カラスの朝飯(=新宿歌舞伎町の生ゴミ)を観察する。気づけば半径10mに19羽ものカラス。餌を投げれば一斉に頭をこちらに向ける。俺はまるでカラス使いだ。学会でハンガリーに行っても頭の中はカラス一色。地方のカフェに「ワタリガラス(世界一大きく稀少)がいる」と聞けば道も店の名も聞かずに飛び出していく。餓死したカラスの冷凍肉を研究室で食らい、もっと旨く食うにはと調理法を考える。生物学者のクレイジーな日常から、動物の愛らしい生き方が見えてくる!
カラス屋、カラスを食べる 動物行動学者の愛と大ぼうけん
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
評価内訳
- 星 5 (0件)
- 星 4 (0件)
- 星 3 (0件)
- 星 2 (0件)
- 星 1 (0件)
カラス屋、カラスを食べる 動物行動学者の愛と大ぼうけん
2024/03/11 20:36
研究者の日常
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:DB - この投稿者のレビュー一覧を見る
カラス屋ことカラスの研究者である松原始のエッセイです。
「カラスを食べる」というタイトルはインパクトありますが、最初は違うタイトルをつけていたのが出版社側の意向でキャッチ―なタイトルになったようです。
食材として認識したことはないカラスですが、もしこれが美味しかったら都会のカラス問題は起きなかっただろうからその味も推して知るべし。
実食したところ、胸肉がレバーとかハツのような内臓っぽい味でモツ系のねっとりした匂いがするそうです。
肉質は硬くて噛むと血の味がするそうですが、京都の神社で凍死したハシボソガラスの若いオスの死体を拾ってきて、解剖の後に余った肉を食べたようなので血抜きしなかったせいかもとは著者の談。
ちなみにこのカラスの焼き鳥パーティーで一緒に供されたのはハクビシンの肉のスープだったそうで、山でソロキャンプしてワイルドな気分に浸っている人たちに食べさせてみたい代物だ。
研究者の対象物への愛は食べるところまで行くのかと思ったエピソードでしたが、研究対象としてどんな行動をしているんだろう、何を食べているんだろう、骨格や筋肉はどうなっているんだろうといった好奇心の一端としてどんな味なんだろうというのが出てくるのかなとも思った。
もちろんこのカラスを食べた話はいろんなエピソードがつまった本書のごく一部で、研究者の日常が面白く語られています。
院生時代に冠島という無人島でミズナギドリの調査をしたエピソードでは、ミズナギドリの繁殖地となっているため島全体が鳥臭い場所を天国と評していた。
生態調査のためにひたすらミズナギドリを捕まえてリングをつけるか、すでにリングをつけている個体のナンバーを確認していくという作業の手伝いとして呼ばれたそうです。
そこで出会った個体が二十四年前に環境庁によってリングをつけられたミズナギドリだったそうで、こういったフィールドワークのスパンの長さがわかる話でもあった。
鳥の話だけでなく同じく手伝いで行ったウミガメの産卵調査の話や、屋久島のサル調査の話も出てきます。
このサル調査の時には、マムシを食べたり肉屋に食材を買いに行ったはずが生きたヤギを渡されて解体して食べたという。
どんな環境でもサバイバルできそうな研究室ですね。
他にも笑ってしまうエピソードが満載の面白いエッセイでした。
2019/09/02 15:56
愛が
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ぽぽ - この投稿者のレビュー一覧を見る
ものすごく愛情は感じましたが、読んでいる途中で、もうついていけなくなってきます。若干変態気質ですかね。