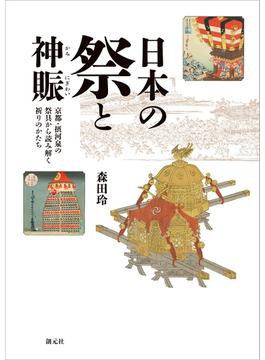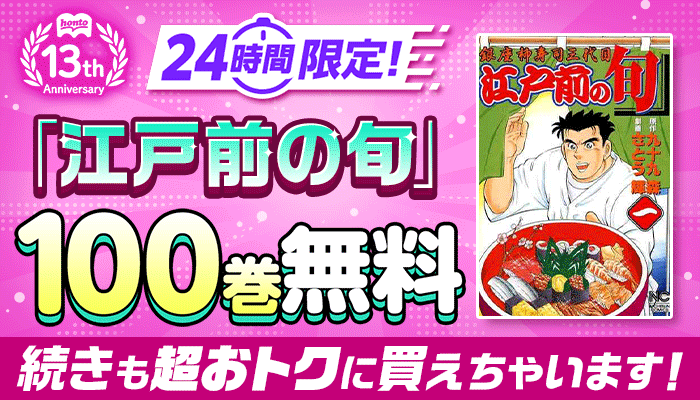- みんなの評価
 1件
1件
日本の祭と神賑
著者 森田玲
多彩に展開する現代日本の祭を、まず神事と神賑行事に分類し、カミとヒトが織りなす基本構造から図解。神輿・提灯・太鼓台・地車・唐獅子などの祭具が、神事と密接に関係しながらも、人々の楽しみに応えて発達してきた歴史を明らかにする。京都と大阪(摂津・河内・和泉)を中心に日本各地を旺盛にフィールドワークした成果から、人々が熱狂する祭の本質と新たな魅力を描き出す。オリジナル図版、写真、貴重史料も多数収載。
日本の祭と神賑
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
2017/12/21 15:07
海外在住邦人たちに推薦したい一冊
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:かわぽん - この投稿者のレビュー一覧を見る
海外在住の者です。
恥ずかしながら日本の祭をまともに見たこともないまま海外へ出てしまい、外国人の友人から日本の祭について聞かれて初めて「祭とは何なのか」を考えるようになりました。
本書はそんな祭について何も知らなかった時に勧められて読んだ本です。
祭初心者にとって一番ありがたかったのは、まえがきの後の序章「図説・祭のかたちを読み解く」で、これから本編で読み進めていく内容をダイジェスト版で説明しているところです。豊富な資料と図解がカラー13ページにわたって掲載されていて、これらのページを読むだけでも後で学ぶ祭についての大枠の知識と祭に使用される祭具(神輿、御迎提灯、太鼓台、地車、唐獅子)を視覚情報から学ぶことが出来ます。
ところで、本書には「ミアレ型」「ミソギ型」「ミアレ型」といった様々な聞き慣れない用語が登場します。(著者による造語)
これはそもそも祭を論じる時、「祭についての基礎知識や共通言語がな」かった故、氏がある事象を他のものと区別できるように言葉で明確に限定した(つまり定義づけた)ことによります。
著者の独自の、しかし非常に的を射た切り口で造られたこれらの用語は、時代の移り変わりと共に複数の要素が重なり合い、また地域によっても多様性を見せる複雑な日本の祭に、共通点を見つけ出し、祭を体系的に理解する大きな手助けになります。著者の言葉選びのセンスも良く、初めて目にする用語でも容易に頭に入ってきます。この点がすごい。
個人的には第7章「祭のフィールドワーク」と巻末の「祭事日程・内容一覧」がお勧めです。
本書を読み進めると、近日行われる祭はいつ・どこだ?!と思わず日程をチェックしたくなるはずです。
近畿圏を中心に開催される祭の日程、場所、目的、起源、主な祭具を一目で確認できる表が巻末に掲載されていて大変便利です。日本に一時帰国する際、本書は必ず携帯しています。
最終章では祭の土日開催化、祭のイベント化への危惧が語られています。
祭の土日開催、つまり「神事」と「神賑行事」の日程を分離することは「カミとヒトとの乖離」に等しく「異常事態」であり、カミ不在の祭はただの賑い行事(イベント)に過ぎないと著者は言います。
私が住む国は多民族国家で、西暦とは別にそれぞれの民族が独自の暦を持ち、新年や宗教行事はその暦に沿って祝うことが当たり前とされています。個々の民族、宗教にとっての大切な日を西暦に合わせたり、ましてや土日にずらすなんてことはありえません。
祭の土日開催の採用が進められている主な理由が、「土日の方が多くの人が仕事を休めるから」というのも病んでいる日本を表していて哀しいです。日本人のカミとは何なのでしょう。会社?お客様?
祭の本質を無視してたくさんの人が、ただワーワー賑やかにやる傾向は、日本におけるクリスマスやハロウィンを彷彿させます。西洋から入ってきた宗教行事が日本でイベントと化すのは百歩譲って理解できるとして、日本の祭がハロウィン化したとしたら本当に笑えない冗談です。
祭の入門書として気軽に手に取った本書でしたが、読後は「日本人とは何か」を強く考えるようになり、海外在住者の私にとってなくてはならない本となりました。
日本在住にとどまらず、海外在住邦人にも推薦したい一冊です。