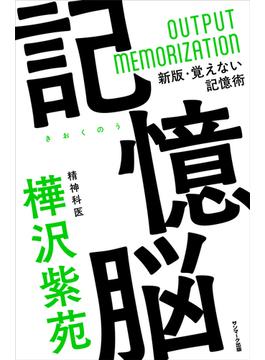- みんなの評価
 1件
1件
記憶脳
著者 樺沢紫苑
記憶ポテンシャル、無限化。
“記憶の概念”が根底から変わる本。
脳の仕組みから精神科医がひもといた「新時代の記憶術」。
情報は「脳に蓄える」より、「外化(自分の外側に記録)」することで
記憶のポテンシャルは無限に広がる!
脳の仕組みを研究した精神科医が、
AI時代の新しい記憶術について伝授します。
試験勉強、うっかりミス、物忘れ、効率UP、「無限記憶」ですべて解決します!
記憶の入口の「インプット」と出口の「アウトプット」を上手に回して、
人間の脳とデシタル脳を一体化させた「記憶脳」を手に入れることができれば、
仕事や学びの効率は、10倍、いや100倍以上も変わってくるでしょう。
ぜひ、日々の学びや仕事、暮らしにお役立てください!
※本書は、2016年1月に小社より刊行された『覚えない記憶術』を加筆・再編集したものです。
記憶脳
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
記憶脳
2024/02/16 19:53
とにかく、書こう
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:あお - この投稿者のレビュー一覧を見る
「覚えられないのなら、覚えなければいいじゃない」
…というのは、本書読了後の自分の脳内をしばらく駆け巡っていた言葉です(どこの王妃様ですかとツッコみつつ)。
本書には「情報を闇雲に頭に詰め込むのではなく、脳科学的な事実に基づいて工夫を凝らしつつ、可能な部分はアウトソーシングして、うまく活用する」ためのノウハウが書かれていると理解しているので、自分の中で本書の言いたいことを端的にまとめるとこういう言葉になってしまった、という感じです。
自分の記憶力のピークは中学生くらいだったなあ…と過去の栄光(?)に半ばすがりつつ、20代の頃はまだ良かったものの30代に入ってから格段に記憶力が落ちたと感じていました。
それはおそらく、ストレスコントロールができずにコルチゾールが海馬を萎縮させにかかっていたこと、睡眠の質と量が圧倒的にダメダメだったこと、何より自分の悪い癖で「TO DOリスト」を作らず(なぜか紙にタスクを書き出すということに大きな抵抗がありましたし、スケジュールを書くことすら、何だか苦手なのです)、脳内を常に未完了タスクで覆いつくしては取りこぼすを繰り返していたことが原因ではないかと思っています。
数年前にメンタル不調を起こし休職となりましたが、復職の目処がついてきたので、現状自分の中での一番の目標は「その日1日のタスクを紙に書き出す」、すなわち作業記憶をショートさせないようにすることです。
樺沢先生の勧める睡眠・運動・朝散歩はできる範囲で続けてきたつもりで(精度を上げる余地はまだまだあり過ぎますが)、ストレスコーピングの土台であるこの3つは継続していきたいと思います。
そう言えば昔、職場の上司の1人が≪すぐに忘れる≫人だったという印象があります。例えば、すでに何度か相談していた案件について相談する度、必ずと言っていいほど「何だっけ?」と訊き返してくるのです。しかし仕事するうえでの分析力、決断力、実行力はすさまじく、今にして思えばその人はもしかしたら常に作業記憶=「脳メモリ」をまっさらにしていたのかもしれません。
作業記憶をすっきりさせる目的も含め、本書は全体を通して「書く」ことの重要性を説いていると思います。
記憶定着のため、五感を鍛えるため、自己理解のため、他者との間で理解・共感を呼び覚ますため。
自分にとって≪書く≫ものの筆頭は、こうした本の感想で、細々と続けられていますが、以前『読書脳』(サンマーク出版)のレビューで「本に書き込みなんてとてもできやしない」という主旨の内容を書きました。
ですが最近、すごくページ数の多い難解な本に当たってしまって以来、いわゆる「HOW TO本」限定ですがラインマーカーを引く勇気がつきました(むしろ引きたいまであります)。また、再読しながら小さなノートに自分なりのまとめを書いて作る習慣ができました。学生の頃、授業で配られたハンドアウトや参考書をまとめたノートを自作して試験対策していたのを思い出しつつ、時間はかかりますがそこそこ楽しい時間を過ごしています。自分の中で理解し、整理した言葉は、自分だけのものであり、達成感も相まって見返すことが多くなるような気がします。
もっと言えば1、3、7日後に少しずつ見直すように習慣づけたいですね。そして、小出しでも行動を。
とにかく「書く」。書いたら一旦、そこに「預ける」。何でも頭にとどめておこうと頑張るような無理をせず、頭の中も軽々として、毎日を過ごせたらいいなと思っています。