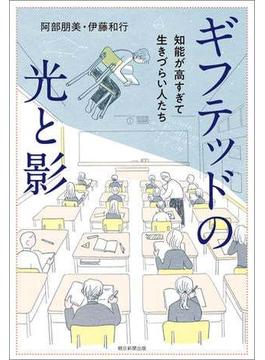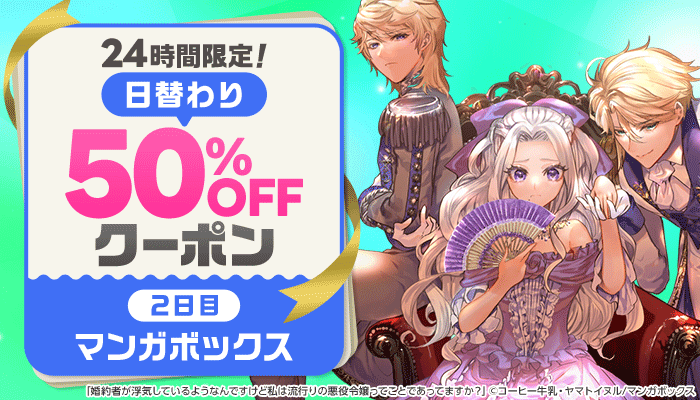- みんなの評価
 3件
3件
ギフテッドの光と影 知能が高すぎて生きづらい人たち
「同級生と話が合わない。なじめたことは一度もない。授業はクソつまらない」……IQ130以上がひとつの基準ともされるギフテッド。強い個性ゆえに周囲になじめない現実を描く。朝日新聞の人気連載「ギフテッド 才能の光と影」を加筆。
ギフテッドの光と影 知能が高すぎて生きづらい人たち
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
2024/12/22 09:30
定義
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:sas - この投稿者のレビュー一覧を見る
ギフテッドに該当する人の基準・定義を設けることが難しいのだと思いました。
「生きづらさがある」ことが前提となるのでしょうが、これを測るのも難しいです。
ギフテッドの光と影 知能が高すぎて生きづらい人たち
2024/05/26 01:03
☆ギフテッド☆
5人中、4人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ACE - この投稿者のレビュー一覧を見る
ギフテッド(intellectual giftedness)は、平均より著しく高い知的能力を指す用語だ。
傍から見ると、生まれつき才能が与えられたとして、周囲の羨望の眼差しがある。光の部分である。
ただし、社会、とりわけ集団生活を好む日本などでは、ギフテッドは「他と違う存在」であり、「異分子」として見られる。その結果、周囲の雰囲気を感じ取りやすいギフテッドは、周りになじめなくなる。影の部分である。
私は、MENSA会員だ。これは、職場等の周囲には公言している。こうすることで、敢えて周囲に特徴づけ、居場所を確保している。
第1章で紹介されている方たちの吐露を読み、共感できるとことがあった。
うろ覚えではあるが、私も学校というものがあまり好きではなかった。というか、あまり当時の思い出がない。寧ろ記憶に蓋をしているのかもしれない。
確かに、学校の授業は退屈だったように覚えている。私の場合は、全て復習の場として切り替えていたかもしれないが、第1章で紹介されている方たちは、もっと繊細な方たちだったのだろうと、勝手に解釈する。
現在、職場では職員の色々な相談を受け、それに助言するような職責を負っている。新入社員から管理職まで、相談に来る人は様々だ。しかし、相談を受けている中で既に解決策がみえてしまい、「こうすればいいのに、何故悩んでいるのかなぁ?」と疑問に思いつつも、助言をしている。解決策を模索している過程は楽しいのだが、やはり職場の雰囲気には、未だになじむことが難しいかもしれない。
寧ろ、放課後や業後といった団体から解放された時間が、凄く落ち着く。自由に勉強ができる。ピアノができる。自分の興味あることが色々とできる。
とまぁ、自分語りをしてしまったが、やはり、ギフテッドの悩みは共感できる。さすがに心を病むまでには幸いにもならなかったが、周囲とのギャップに変に悩んでしまったことは、同じだなぁ、と思った。
そんなギフテッドに明るい未来はあるのか。答えは、ある、と言える。ただし、今の日本では正直言って無理だと考える。
才能を伸ばす場を企業やNPO団体が提供する試みがあり、一時的にはギフテッドに寄り添ってはいると思う。しかし、本当にギフテッドにとって明るい未来はなにか、と問われると、ギフテッドと呼ばれるほうも、そうでないほうも、お互い変に意識しない社会が構築されることだと思う。これは、ジェンダー論とか他の分野でも同じことなのだろう。
取材を受けたある女性の即答した「ほっといてほしいですね」がド正論だと思った。全く無視する、ではなく、変に特別視せず、1つの個性として普通に過ごす、という意味での願いの言葉であると、私はそう解釈した。
2024/05/26 01:05
☆ギフテッド☆
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ACE - この投稿者のレビュー一覧を見る
ギフテッド(intellectual giftedness)は、平均より著しく高い知的能力を指す用語だ。
傍から見ると、生まれつき才能が与えられたとして、周囲の羨望の眼差しがある。光の部分である。
ただし、社会、とりわけ集団生活を好む日本などでは、ギフテッドは「他と違う存在」であり、「異分子」として見られる。その結果、周囲の雰囲気を感じ取りやすいギフテッドは、周りになじめなくなる。影の部分である。
私は、MENSA会員だ。これは、職場等の周囲には公言している。こうすることで、敢えて周囲に特徴づけ、居場所を確保している。
第1章で紹介されている方たちの吐露を読み、共感できるとことがあった。
うろ覚えではあるが、私も学校というものがあまり好きではなかった。というか、あまり当時の思い出がない。寧ろ記憶に蓋をしているのかもしれない。
確かに、学校の授業は退屈だったように覚えている。私の場合は、全て復習の場として切り替えていたかもしれないが、第1章で紹介されている方たちは、もっと繊細な方たちだったのだろうと、勝手に解釈する。
現在、職場では職員の色々な相談を受け、それに助言するような職責を負っている。新入社員から管理職まで、相談に来る人は様々だ。しかし、相談を受けている中で既に解決策がみえてしまい、「こうすればいいのに、何故悩んでいるのかなぁ?」と疑問に思いつつも、助言をしている。解決策を模索している過程は楽しいのだが、やはり職場の雰囲気には、未だになじむことが難しいかもしれない。
寧ろ、放課後や業後といった団体から解放された時間が、凄く落ち着く。自由に勉強ができる。ピアノができる。自分の興味あることが色々とできる。
とまぁ、自分語りをしてしまったが、やはり、ギフテッドの悩みは共感できる。さすがに心を病むまでには幸いにもならなかったが、周囲とのギャップに変に悩んでしまったことは、同じだなぁ、と思った。
そんなギフテッドに明るい未来はあるのか。答えは、ある、と言える。ただし、今の日本では正直言って無理だと考える。
才能を伸ばす場を企業やNPO団体が提供する試みがあり、一時的にはギフテッドに寄り添ってはいると思う。しかし、本当にギフテッドにとって明るい未来はなにか、と問われると、ギフテッドと呼ばれるほうも、そうでないほうも、お互い変に意識しない社会が構築されることだと思う。これは、ジェンダー論とか他の分野でも同じことなのだろう。
取材を受けたある女性の即答した「ほっといてほしいですね」がド正論だと思った。全く無視する、ではなく、変に特別視せず、1つの個性として普通に過ごす、という意味での願いの言葉であると、私はそう解釈した。