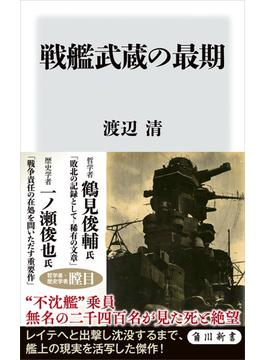- みんなの評価
 2件
2件
戦艦武蔵の最期
著者 渡辺清(著者)
「おれたちをここまで追いつめたやつは、一体誰だ、誰だ、誰なんだ・・・・・・。」 “不沈艦” 神話を信じ、乗り組んだ船で見たのはあまりに悲惨な戦場の現実だった――全長250m超の大和型2番艦「武蔵」は1944年10月、日本の存亡をかけたレイテ沖海戦へと出航する。アメリカの航空戦力を前になすすべなく、主砲も沈黙するなか、「おれ」が選んだ道とは? 組織内暴力や上官の不条理、無差別に訪れる死。実際の乗艦経験をもとに、戦場の現実を描いた戦記文学の傑作。鶴見俊輔氏の論考も再録。 解説・一ノ瀬俊也◆主砲の制御装置が魚雷一本の振動で故障、航空機には通用せずあえなく廃棄◆「鬼」と恐れられていた上官が戦闘では遁走◆元小学校教師は爆弾に吹き飛ばされ、十六歳で志願した少年は足を失い息を引き取る◆沈没時は乗員よりも天皇の肖像写真の退避が優先された
戦艦武蔵の最期
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
戦艦武蔵の最期
2024/02/17 22:55
『戦艦大和ノ最期』と対をなす、凄惨な戦闘現場を描いた一書
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:Haserumio - この投稿者のレビュー一覧を見る
書店でたまたま見つけ、『戦艦大和ノ最期』を読んだ評者としては、読み比べてみようと思い、昨日購入して本日読了。一気読みというか、怒涛の二日読みでした。
「直撃弾を受けたというならまだしも、水線下にくった魚雷一本の振動ぐらいで、あっけなく故障するような方位盤を、どうしていままでそのままにしておいたのか。」(142頁)
「自分の着たいものを自由に着られるっていうのが本当の世の中よ」(151頁)
「武蔵はもともとトン数の大きさだけが目的で造られたではなかった。これは大和の場合もそうだが、まだ外国にもその例のない口径四十六サンチ(十八インチ)の主砲九門を搭載するために、ただそれだけの目的のために、その大きさ(満載排水量七万二千八百トン)を必要としたのである。つまり日本の海軍が欲しかったのは、大きな艦ではなく、どこまでも大きな大砲だった。」(204頁)
「いまは死もおれにとってひとつの安らぎだった。おれは死ぬことによって、一刻も早くこの地獄の戦慄を脱したいと思った。」(223頁)
『戦艦大和ノ最期』は美文で、内容的にいかにも将校が書くべき作品であるのに対し、本書は文章は荒削りだが現場の厳しさ・悲惨さが伝わる一冊。両方合わせて一書であると思うこと大。
戦艦武蔵の最期
2024/05/29 23:05
夫人公認「ノンフィクション・ノベル」第一弾
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:オタク。 - この投稿者のレビュー一覧を見る
勢古浩爾の「大和よ武蔵よ」によると「砕かれた神」なる偽日記は昭和50年頃に書かれたとあり、「渡辺清の自伝的三部作を、夫人は「ノンフィクション・ノベル」といっている」とある。渡辺の妻が嘘つきか勢古浩爾が無意識に筆を曲げてなければ昭和天皇と海軍を批判しているはずの渡辺の本はフィクションという事になる。
この本に出て来る人物の「経歴」で昭和19年当時の短現は短期現役士官を指して師範卒が入団する短期現役兵制度は昭和14年に廃止されたそうだ。29歳で戦死した事になっている上級兵曹は「十二年にわたった」とあるので17歳で入団した事になるが、これは陸軍の志願兵の話だ。「日本陸海軍総合事典第二版」によると海軍が海軍年少兵制度を導入して15歳以上なら水兵として志願出来るようになったのは大正14年生まれの渡辺が入団した事になっている「昭和16年5月1日」より後の7月5日。何でも水兵団教育を終えた渡辺「四等水兵」は何と砲術学校で3か月学んだとか武蔵の前に沈められた駆逐艦で終戦を迎えたとか称しているので実は海軍の軍歴自体がないのではないか?「大和よ武蔵よ」には渡辺の水兵姿の写真が掲載されているが自称グリーンベレー大尉の柘植久慶が「ザ・グリンベレー」などに掲載した安っぽい軍装品で決めた「グリーンベレー姿」みたいに見えてくる。
「軍艦武蔵」の著者の手塚正巳は講演で渡辺について質問されると強い口調で批判していたが「『軍艦武蔵』取材記」には実際に武蔵に乗り込んでいた元水兵の遺族から送られた「どれも「武蔵」本としては広く出回っているもので」、「多くの個所に赤線が引かれていて、余白には訂正の文字が踊っていた」、「何気なく裏表紙を見ると、そこにはこれも赤色の太いマジックペンで、『ウソばっかりだ!これでは死んだ者も、戦った者も、浮かばれない!』と、大書してあった」とある。多分、渡辺の「海の城」や「戦艦武蔵の最期」もあるだろう。
さて旧軍の専門家らしい埼玉大の一ノ瀬俊也と担当編集者は手塚正巳の著書や「大和よ武蔵よ」を読んでいないのか?一ノ瀬さん、あなたの同僚の岡崎勝世氏が「皇軍兵士の日常生活」なるものと同じ講談社現代新書から刊行した「聖書vs.世界史」のような何度も読み返したくなる本を書かれたらいかがでしょうか?夫人公認の「ノンフィクション・ノベル」だろうと昭和天皇や海軍を批判すればよしなら「キメラ」の著者が児島襄の「満州帝国」に書かれている熱河省の悲惨な農村光景を読んで設定上、チチハル郊外という事にしてそっくり引き写した「聞き書き ある憲兵の記録」を鵜呑みにしたのと同じだ。
7月に「海の城」が出るそうなので多分、偽日記「砕かれた神」も出るだろう。軍歴詐称者が書いた「ノンフィクション・ノベル」三部作を楽しく読ませてもらいます。