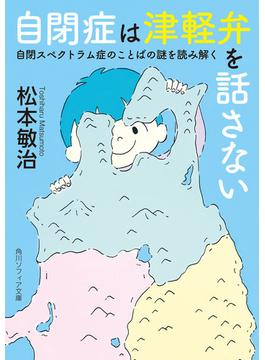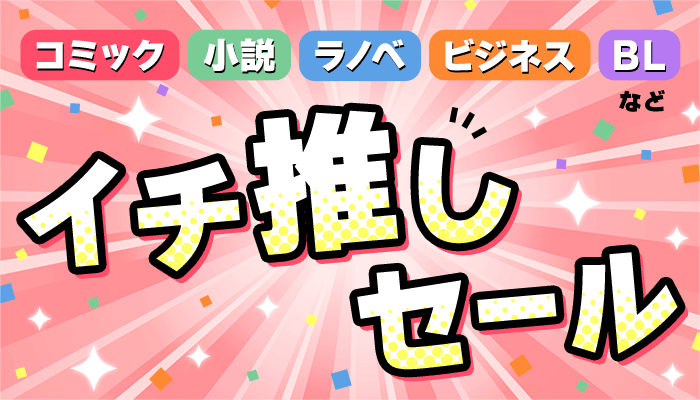- みんなの評価
 6件
6件
自閉症は津軽弁を話さない 自閉スペクトラム症のことばの謎を読み解く
著者 著者:松本 敏治
自閉症児者が方言をしゃべらないという噂は本当なのか? 方言の社会的機能説、意図理解、自閉症児者の言語習得、自閉症児者のコミュニケーションの特異性等、筆者の飽くなき探究心から見えてきた真相とは。
自閉症は津軽弁を話さない 自閉スペクトラム症のことばの謎を読み解く
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
自閉症は津軽弁を話さない 自閉スペクトラム症のことばの謎を読み解く
2021/05/22 21:31
発見の種はどこにでもある
5人中、5人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:第一楽章 - この投稿者のレビュー一覧を見る
「あのさぁ、自閉症の子どもって津軽弁しゃべんねっきゃ(話さないよねぇ)」という、臨床発達心理士の妻の一言に、大学で特別支援教育を教え障害児心理を専門とする筆者は反発します。自閉スペクトラム症(ASD)の独特の音声的特徴ゆえに津軽弁に聞こえないだけではないか、安易なレッテル貼り・診断につながりかねないのではないか、と。ここは研究者らしく、調べて白黒つけようじゃないか、と。
そこから10年余り、夫婦喧嘩に端を発した研究は、津軽地方だけではなく全国的な調査へ、そして方言の持つ社会的役割を考察し、ASDとそうではない子どもの言葉の学習の仕方の違いといったところまで、拡大・飛躍し、ひとつの推論にたどり着きます。
子どもは、相手の意図を読み意図を理解すると言った社会・認知的スキルを通して、周囲で交わされている自然言語(方言が使われている地域ではその方言)からことばを学習していく。そのスキルに困難を抱えるASDの子どもは自然言語の学習が難しく、代わりにテレビやビデオといった繰り返される決まり文句やセリフなどを利用して言葉を学習しているのではないか。そして成長した後も、方言が持つ帰属意識や連帯意識の表明といった社会的機能を捉えることができず、方言と共通語の使い分けに困難があるのではないか。
結論も興味深いのですが、むしろそこに至る調査や考察を追体験できる内容で、学術的な研究の醍醐味を筆者と共有できるという点が、この本の魅力だと思います。
そう、結論を行ってしまえば、夫婦喧嘩は妻の勝ちでした。「この夫婦喧嘩は、私の完敗。妻は、ホタテを肴に勝利の美酒に酔っている。地酒の田酒だ。『したはんで、言ったべさ』」(P.274 おわりに)
自閉症は津軽弁を話さない 自閉スペクトラム症のことばの謎を読み解く
2021/03/29 21:28
最近話題の本
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:Kei - この投稿者のレビュー一覧を見る
最近話題の本です。数々の新聞やメディアでも取り上げられています。
内容は、自閉症の子供がどうして津軽弁をしゃべらないか、実証的に
研究した成果です。
とはいえ一般読者にも分かりやすく書いてありますのでご安心を。
自閉症は津軽弁を話さない 自閉スペクトラム症のことばの謎を読み解く
2021/01/05 13:54
松本敏治氏による長年の自閉症と方言の研究成果です!
3人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ちこ - この投稿者のレビュー一覧を見る
本書は、公認心理師、特別支援教育士スーパーバイザー、臨床発達心理士などの肩書をもたれ活躍されている松本敏治氏による作品です。同書では、「今日の健診でみた自閉症の子も、お母さんバリバリの津軽弁なのに、本人は津軽弁しゃべんないのさ」という不思議な一文で始まります。これは、津軽地域で乳幼児健診にかかわる妻が語った一言なのですが、著者をこれをきっかけにして、じゃあ、ちゃんと調べてやろうと、「自閉症と方言」の研究に10年以上も費やした成果の集大成です。同書における方言の社会的機能を「意図」というキーワードで整理するなかで見えてきた、自閉症児のコミュニケーションの特異性に迫った画期的な書です!