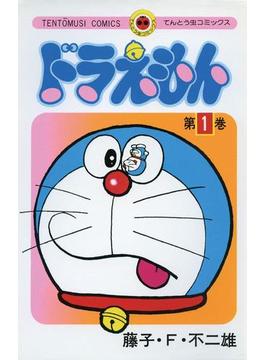- みんなの評価
 349件
349件
ドラえもん
著者 藤子・F・不二雄
●日本を代表する漫画家藤子・F・不二雄先生の傑作作品『ドラえもん』。未来の国からやってきたごぞんじ、ネコ型ロボットのドラえもんが親友のび太とともにくりひろげる生活ギャグまんが。四次元ポケットから取りだされる不思議な道具で日本中を笑いに包みこむ。しずかちゃんやスネ夫、それにジャイアンも元気いっぱい。ワクワクドキドキ、キミを心温まるドラえもんワールドにご案内!
▼第1話/未来の国からはるばると▼第2話/ドラえもんの大予言▼第3話/変身ビスケット▼第4話/秘(丸囲み)スパイ大作戦▼第5話/コベアベ▼第6話/古道具きょう争▼第7話/ペコペコバッタ▼第8話/ご先祖さまがんばれ▼第9話/かげがり▼第10話おせじ口べに▼第11話/一生に一度は百点を▼第12話/プロポーズ大作戦▼第13話/◯◯が××と△△する▼第14話/雪でアッチッチ▼第15話/ランプのけむりオバケ▼第16話/走れ! ウマタケ
ドラえもん 45
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
ドラえもん 1 (てんとう虫コミックス)
2010/01/24 22:16
親子でドラえもん
14人中、13人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:marekuro - この投稿者のレビュー一覧を見る
言わずと知れた名作、ドラえもんである。
ストーリーは説明するまでもないだろう。
自分も子供の頃はドラえもんに夢中だった。
そんなドラえもんに夢中だった自分も大人になり
いつしか人の子の親になっていた。
最近になって子供がテレビ版のドラえもんを見るようになった。
自然、我が家ではテレビにDVDにドラえもんが映っている事が
多くなっている。
先にも述べたが、自分も幼少期よりドラえもんに親しんできた。
今のドラえもんの声が大山のぶ代さんではないことに違和感を
感じつつも、やはり子供に付き合って目に耳にする機会が多く
なってきた。ドラえもん再入門状態である。
ドラえもんは国民的アニメと称されることがある。
親子2代に渡ってお世話になっている事から考えても
やはり、国民的アニメなのだろう。
ところで、2009年7月より藤子不二雄全集が発売開始になった。
ドラえもんはもちろんの事、藤子不二雄作品に影響を受け育ってきた
自分は、この全集を記念に購入しようかと思ったが、ふと思い返すと
自分が幼少期~少年時代に近所の小さい小さい個人経営の本屋さんで
親にせがんで買ってもらった、あるいは、おこづかいを握りしめて買いに
行った本は、このてんとう虫コミックス版のドラえもんだった。
このドラえもんシリーズ。一度は全巻そろえていたものの、長い年月を経て
引越しの度に、ひとつまたひとつと紛失していき、気づけば本棚には
ボロボロになった、てんとう虫コミックス版ドラえもんが数冊残っているだけに
なっていた。
先にも述べたが、ドラえもんを見て育ってきた感のある自分は、本棚に残った
数冊のドラえもんを見ている内になんだか寂しくなってきた。
それは、幼少期~少年時代が年月と共に遠くなっていき、忘れられていく事と
コミックスが欠けている事を重ねたからなのかもしれない。
いずれにしても、いい大人になった自分がドラえもんのコミックスをきっかけに
感傷的になっているさまが少々滑稽に感じられた。
しかしだ。その一方で「大人には大人の買い方があるじゃないか!」と
妙な蛮勇を奮い立たせている自分もいたわけで、思い立ったその数日後には
妻の顔色をうかがう…前に全巻を注文してしまった。
そんな訳で届いたドラえもん全45巻を妻の視線を気にしつつも、ご満悦
で眺めながら、さっそく第1巻を手にしてみた。
奥付を見ると初版は1974年とある。あらためて歴史を感じた一瞬だった。
長い年月を経て再読した感想は
・教育的な要素が入りつつファンタジーと子ども向けのギャグがバランスよく
混ざっている
というものだった。
それは「走れ!タケウマ」で登場する秘密道具の「ウマタケ」や
「一生に一度は百点を・・・」で登場する秘密道具の「コンピューターペンシル」
の使い方をめぐる、のび太の葛藤と選択に色濃く表れている。それは
のび太が22世紀の便利な道具を用いて、うまく事をなしとげる誘惑に
惑わされつつも、最後は失敗しつつも自力で頑張り抜く姿が印象的だ。
また、SFギャグ漫画だと思い気を抜きながら読んでいると思わぬ名言に
遭遇するから気が抜けない。どのような名言が飛び出てくるかについては
inbookというサービスに@marekuroとしてドラえもんの
名言をいくつか投稿しているので参照してみてほしい。
なお、一部では不評も多いこの漫画。特にのび太がドラえもんに依存する
姿は海外でのドラえもんの人気がいまひとつなのと関連があるとかないとか
という話を聞いたことがある。その他にもジャイアンのいじめる姿が槍玉に
あがったこともあった。はっきりと「子供を堕落させる」と言っている人を見た
事もある。
しかし、自分はそうは思わない。
本作の中では不器用ながらに一進一退しつつ成長しようとする少年(のび太)
の姿と、同じく不器用ながらに一進一退しつつ、のび太を支援しようとしている
ドラえもんの姿がある。
その双方向性の支援のあり方は、友人というもののあり方をあますことなく
表現してくれていると言っても過言ではない。そして、のび太をとりまく友人ら
(ジャイアン、スネ夫、しずかちゃん)の関係も、綺麗事を抜きにした現実の
社会のいくらかを表していると思う。
子どもにとって良い意味でも悪い意味でも学ぶ所は多いであろう。
自分は少年時代にドラえもんに想像する事の楽しさを育ませてもらい、今は
大人として、親としてドラえもんの世界を子どもと共に楽しませてもらっている。
子供とドラえもんの事を話すという、この上なく楽しい時間と共に、想像すること
という、この上ない秘密道具を与えてくれたドラえもんに感謝の念は絶えない。
いつまでもいつまでも、受け継いでいってほしい作品である。
ドラえもん 2 (てんとう虫コミックス)
2010/01/31 18:50
白黒テレビや2層式洗濯機の描写に歴史を感じつつ、名作と呼ばれる事になる「ぼくの生まれた日」や「オオカミ一家」という収録作品を楽しむ。そして再びアンキパンが欲しくなる。
8人中、8人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:marekuro - この投稿者のレビュー一覧を見る
ドラえもんの第2巻です。
奥付を見ると初版は1974年。
手元にある第2巻は20年以上も前に購入した物で
ボロボロになって、紙は黄ばんでいます。
この第2巻の特徴ですが
経済評論家の勝間和代さんも著作の中で、その存在に触れている
秘密道具の「暗記パン」や、後々のエピソードにも頻出する「タイムふろしき」
の初登場。
特別編として映像化もされている有名なエピソード
「僕の生まれた日」「オオカミ一家」が収録されている事でしょう。
※「オオカミ一家」は「オオカミ一家を救え」というタイトルでTVスペシャルに
なっています
※「ぼくの生まれた日」は08年にTV版でリメイクされています。
上記はいずれもyoutubeやニコニコ動画で閲覧することが可能です。
以下、目次
・テストにアンキパン
・ロボ子が愛している
・怪談ランプ
・ゆめふうりん
・ぼくの生まれた日
・正直太郎
・しずちゃんのはごろも
・うそつき
・うそつきかがみ
・タイムふろしき
・かならず当たる手相セット
・オオカミ一家
・N・Sワッペン
・地下鉄をつくっちゃえ
・タタミのたんぼ
・このかぜうつします
・勉強部屋の大なだれ
・恐竜ハンター
第2巻で見ることの出来る秘密道具の中で一番の
目玉はやはり「アンキパン」だと思います。
以下はwikipediaからの引用
アンキパンは、『テストにアンキパン』
(てんとう虫コミックス2巻に収録)に登場する。
スライスした食パンを模した道具。
ノートや本のページに重ね、内容をパンにコピーして食べる
とその内容が確実に暗記できるが、スライス1切れにつき
暗記できる量(せいぜい1切れに教科書1ページ程度)が限られ
大量のページを暗記できないことや、暗記した内容が体内に取り
こまれることはなく、排泄によって効果がなくなるという欠点がある。
タカラ(現タカラトミー)からアンキパンをモチーフとした学習用小型
端末を発売予定。
テレビ朝日版アニメでは、1979年放送「テストにアンキパン」で
登場し、1992年にも「アンキパン」のタイトルで再制作された。
子供のころ、本気でこのアンキパンが欲しかった自分ですが、大人になった
今も資格試験などが近づいてくると、脳裏をよぎる「アンキパン」の
存在。人間、そうそう変わらないという事でしょうか。
このアンキパンについて、他力本願を戒める意味からか
作中ではしっかりとオチがついていますが、いつかアンキパンのように
簡単に暗記できるようになる製品が実用化するのではないかと密かに
心待ちにしています。
実はこの2巻を再読するのは15年~20年ぶりなのですが
改めて気づいたことが幾つかあります。
それは「タイムふろしき」のエピソード中で野比家のテレビが不調に
なる箇所で写らなくなったテレビの事をのび太ママ(野比たまこ)
にドラえもんとのび太が報告するコマで
「このチャンスにカラーに買いかえましょう」 (p86)
と言う場面です。
しかし、のび太ママは約60度の角度でテレビの上部を叩くことで
テレビの不調を直してしまうのですが、そういえば今の電化製品は
ものすごい精密機械化していて、不調になったら叩いて直すなどという
荒技は使えないなぁなどと、しばし考えてしまいました。
今日、テレビという主語のない状態で「カラーに買い換えましょう」と
言われてもなんの事かすぐにはわからないと思います。
プリンターですらカラーが当たり前ですし、今テレビの事をあえて
「カラーテレビ」と呼ぶ人はいないでしょう。
電気屋で「カラーテレビを探しているのですけど・・・」と店員に尋ねている
自分を想像したら、やはりとても不自然なんです。
同じような流れで今は液晶モニターのテレビの事を
「薄型テレビ」や「液晶テレビ」などと呼びますが、そのうち
"薄型”や"液晶”であることが当たり前になって、あえて「薄型テレビ」
「液晶テレビ」などとは呼ばなくなるのではないかと思います。
そしてカラー放送が開始になったのは1960年。本書の出版が74年
作中の時間の流れをリアルでの時間の流れと同期させて考えるなら
なんと野比家はカラー放送開始から14年の時間が経過した後も
白黒テレビを使用していたことになります。
もっとも野比家のテレビについて指摘している私自身はどうかというと
正月位しかテレビを見ないという事もあるのですが、未だに14インチの
ブラウン管テレビを置いています。しかも絶滅機種のテレビデオです。
自分を基準に"庶民”を語るのは他の家庭に対して失礼に当たるので
自粛しますが、野比家の庶民っぷりには共感できる事然りです。
なお、同ページに洗濯機が描かれているのですが、これも
やはり2層式の洗濯機です。このように細かい設定、描写の
ひとつひとつを見ても時間の経過、歴史を感じます。
そして「ぼくの生まれた日」においては「のび太」という名前の由来
が語られます。
すこやかに大きく、どこまでも、のびてほしいという
ねがいをこめた名まえだよ。
(p56)
とは、のび太パパの弁。
自分は長年、のんびりしているから「のび太」だと思ってたのですが
思わぬ発見でした。
第2巻ということで、物語としては始まったばかりの頃のエピソードを
収録していますが、後々の長編映画の元ネタかなと思われる「恐竜ハンター」
や、以降も頻出する「タイムふろしき」の存在など、この後のドラえもんの世界に
欠かせない重要なアイテム・エピソードなどが盛り込まれています。
ドラえもんが好きな人には改めて読んでもらいたい一作です。
ドラえもん 3 (てんとう虫コミックス)
2010/02/15 16:21
ストーリーテラーとしての作者の実力を知る事の出来る1作。幅広く色々なタイプの物語が収録されている。
5人中、5人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:marekuro - この投稿者のレビュー一覧を見る
ドラえもんの3巻です。
本巻にも前巻のようにTVスペシャル版として
放送されたエピソードや名作として評価の高い作品が
収録されています。
そして特筆すべきは、現在のTV版ドラえもんの
記念すべき第1話「ゆめのまち ノビタランド」が収録
されている事でしょう。
以下、目次
************************************
・あやうし!ライオン仮面
・日付を変更カレンダー
・ママをとりかえっこ
・シャーロック ホームズセット
・スケジュールどけい
・うそつ機
・スーパーダン
・ボーナス1024倍
・ミチビキエンゼル
・そっくりクレヨン
・きせかえカメラ
・ああ、好き、好き、好き!
・ゆめの町、ノビタランド
・ソウナルじょう
・ぼくを、ぼくの先生に
・白ゆりのような女の子
・おはなしバッジ
・ペロ!生きかえって
**************************************
先に述べたTVスペシャル版にもなっていて、かつ名作の呼び声も
高い作品といえば、「白ゆりのような女の子」と「ペロ!いきかえって」
が挙げられます。
「白ゆりのような女の子」のストーリーの概要は、のび太パパの子どもの
頃にまで遡ります。
なんと設定は昭和20年代という事になっており、のび太パパは学童疎開
中です。
そこで出会った女の子のエピソードなのですが、それを聞いたドラえもんと
のび太がタイムマシンで女の子の写真を撮りに行こうとするのですが・・・
という感じです。タイムマシンによるタイムパラドックスが楽しめる佳作だと
思います。それにしても、のび太パパの少年時代が昭和20年という設定には
驚きました。
もう一つのエピソードである「ペロいきかえって」のストーリーの概要ですが
これは、しずかちゃんの飼っていた犬が死んでしまう所から物語が始まります。
空き地で泣いているしずかちゃんに対して、事情を知らないのび太は
「秋晴れの気持ちの良い一日だね」と声をかけて皆に批難されます。
事情を知り、しずかちゃんとペロ(犬)とのエピソードを知ったのび太は
思わず「ペロを生き返らせよう!!」と息巻きます。
しかし、言ってはみたものの、それを聞いたドラえもんは困惑するのですが・・
そんなドラえもんとのび太はタイムマシンでペロがしぬ前の夜にまで遡り
動物の病気に効く薬を与えます。
結果的にペロは生き返るのですが、そのような感動的なエピソードの中に
その雰囲気を壊さないように上手にギャグ的要素が盛り込まれています。
夜中にしずかちゃんの家の前をうろつくドラえもんとのび太に対して
職務質問をする警官がラストにどのように登場するのか、その点は
読む機会があれば確認してみてください。
作者のさりげない遊び心に、思わずニヤリとしてしまう瞬間です。
記念すべきTV版第一話についてですが、TV版のドラえもんには
色々と事情があるそうで、その辺りに関してはwikipediaにて詳しく説明されています。
「ゆめの町、ノビタランド」に関しては、このキーワードで検索すると
動画共有サイトなどで閲覧、参照する事が出来ます。
久々に見たのですが、やはり時代を感じるというのが正直な感想です。
色々と問題がありそうなので、リンクを貼る事はしませんが、興味のある方は
検索して参照してみると面白いかもしれません。
本書の初版は1974年です。30年以上昔の作品が収録されています。
気になったのはp80でドラえもんが「定期預金だと10年で倍くらいになる」
と述べている事です。
読んだときに「!?」となりました。そんなに金利が高かったのかと。
現在の国内の銀行の定期預金なら
今から預けて元金を倍にするには気の遠くなるような年月が必要です。
定期預金はまだしも、普通預金にいたっては200年たっても倍にならない
でしょう。
自分は1974年にはまだ生まれていません。そんな金利の高い時代も
あったのだと、理屈では知っていましたが、ドラえもんという作品を通して
知ることで妙に驚きました。
本書の特徴はドラえもんにおけるストーリーの幅の広さを伺い知る事の
出来る1冊です。
それは、作者も公言しているようなギャグマンガ的要素であったり
一方では感動・名作系の作品が収録されている事からも理解できます。
さらには歴史的要素が含まれた作品であったり、とてもシュールな内容の
エピソードも見受けられます。中にはその時々の世相を取り込んだエピソード
もあり、ストーリーテラーとしての作者の実力を知ることが出来る一冊です。
ドラえもん好きはもちろんのこと、あまりドラえもんと縁のなかった
人にもおすすめしたい一冊です。