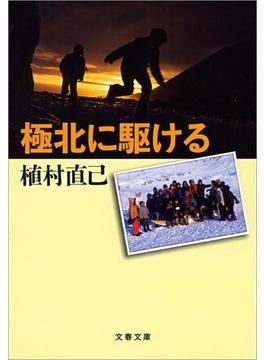0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:つよし - この投稿者のレビュー一覧を見る
いや~、面白かった。「青春を山に賭けて」に続いて2冊目の植村直己。文章が格段にうまくなっている。読んでいると、植村直己とともに犬ぞり旅をしているかのようだ。グリーンランドの厳しくも美しい自然、生肉を中心とした食、飾らず人懐っこい人々。巻末の解説には、それが時代とともに、利便性と引き換えに失われつつあることが書かれていて、何とも寂しい気持ちになる。
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:エムチャン - この投稿者のレビュー一覧を見る
この著書中で、一番、印象的だったのは、昨日まで犬ぞりを引いていた犬を食料とすること。これは、知らなかったです。彼らにとっては、犬は、人間のための道具なんですね。ペットではなく。それが、植村直己さんに出来なかったと。
投稿元:
レビューを見る
極北グリーンランドのイヌイットの人たちの氷に閉ざされた自然の生活を、作者自身もイヌイットの村民となって体験する様子がいきいきと伝わってきてさくさくと読み進めました。数ヶ月たらずで犬ぞりで数千キロの旅なんて、やっぱり植村直己さんは偉大だ。
衝撃だったのが「学校に行ったってなんの意味があるんだい、本を読んだって目が悪くなると狩りができなくなって生活に困るじゃないか」という村の人の言葉。ここでは生きることとは狩りをすること。本で得た知識で家族を養っているわけではない。本物の狩人は純粋に自然の生態系の一部だから、存在自体がすごく文明とはかけ離れた存在なのかも。そう考えると自然に生きる人と文明を築く人はもしかしたら相容れないものなのかな。
絶妙なバランスで成り立っていたイヌイットの人々と狩りの関係が、温暖化や入植民の影響であれこれ劇的に変わっていることは初めて知った。ヒマラヤのシェルパの村が溶けた氷河に流されそうな今の危機的な状況と、なにか重なるものがあります。世界のあちこちでこういう状況にあることをもっと知って、広めるのも大事なのかな。
投稿元:
レビューを見る
北極圏を犬ぞりで走り抜ける探検を記録した本作。
実際に犬ぞりで走っているところも面白いけれど、それ以上に準備期間が面白い。
言葉も通じないイヌイットと交流し、犬ぞりなど極北を生き抜くのに必要な技術を身につけて行く様子がいきいきと描かれている。
探検は征服ではなく順応なのかもしれない。
投稿元:
レビューを見る
偉大なる冒険家の偉大なる挑戦の一編。
しかし日々の思考は泥臭く至って普通の感性を持っていると感じる。
周りから無茶だと言われていたことに挑戦する姿勢は素晴らしいが目的地をあえて周りの人達に言わずにいつでも予定を変更できるようにすることなどはいかにも人間臭いと思う。
投稿元:
レビューを見る
「部屋に置いたバケツへ排泄し、その傍に吊るしたアザラシ肉を削いで食う」というエスキモーのビックリな風習を聞いて興味半分で手に取った本。恥ずかしながら植村氏のこともよく知らなかったのだが、活き活きした筆致で書かれる彼の強い意志にすっかり心を打たれてしまった。揺れる海氷の上を渡る犬ぞり旅の記録にはハラハラしたし、旅を支えてくれた素朴で親切なエスキモーとの触れ合いには涙が出てしまう。植村氏が数十年前にマッキンリーで消息を絶たれたことを読後に知った時は少し暗い気持ちになった。兵庫県に氏の記念館があるというので近く訪ねたいと思う。
投稿元:
レビューを見る
僕が敬愛する人物のひとり、植村直己さん。その魅力は、世界で初めて5大陸最高峰に登頂した冒険心と、アマゾンの原住民とでもイヌイットとでも、すぐに打ちとけてしまう愛嬌という、矛盾しそうな2つの性格をあわせ持っているところだと思います。
グリーンランドを犬ぞりで3,000キロ走った冒険を記録した『極北に駆ける』でも、その魅力を遺憾なく発揮。犬ぞりの訓練のために突然訪れたイヌイットの村に、植村さんはすぐに溶け込んで、言葉も風貌もすっかりイヌイットの仲間になってしまうからすごい。
それだけに、この本は冒険の記録であると同時に、文化人類学にもイヌイットの生活に入り込みくわしく記述したフィールドワークの記録になっています。特に、イヌイットの超開放的なSEX感や、海鳥をアザラシの皮下脂肪に詰めた強烈な料理「キビヤック」などの食事文化を知ると、「世界って広いな…」と思わずにはいられません。
投稿元:
レビューを見る
とても軽く楽しめる。冒険そのものよりも、土地の文化や風習、人々の暮らしが瑞々しく描かれた部分に引き込まれてしまう。単独で冒険に行っているように見えても、冒険の場所にはいつも暖かな人々との交流があるようだ。
投稿元:
レビューを見る
犬ぞりでの旅が如何に厳しいものであるかを理解できた。
現在はどうやって北極点や南極点へ行っているのだろうか?
投稿元:
レビューを見る
すごい、の一言しかない。極北での生活の在り方や、植村直己の冒険に向けたまっすぐな意志、そして極北の驚異にはっとさせられることばかりだった。
投稿元:
レビューを見る
文章もうまくて言うことなし。現代の冒険家はこのような豊穣な冒険が残されていないことを充分に認識してそれでもやらずにはいられないのだな、と切ない気持ちになった。
投稿元:
レビューを見る
いやー、やはり植村さんの文章力はすごい。読み手はどんどん引き込まれる。
本書は、植村さんが南極大陸横断にあたっての試験的な、訓練的なグリーンランド物語りであり、その際に関わったエスキモーとの文化の違いなどを、大変な文章力で綴る。しかしながら、冒険書は冒険書であり、内容も非常に興味深い。エスキモーは、犬橇を引く犬を、用に足さなくなると、皮を剥いで食べてしまうが、植村さんは、どうしてもそれができなかった。エスキモー部落から単独3000キロの特訓旅行に出て、危うく遭難しかけて、飢えかけても食べることはできなかったという。こんなとこにも植村さんの人柄がよく現れているといえよう。
投稿元:
レビューを見る
【いちぶん】
どこにも文明の光ひとつない、孤立した極北のエスキモー部落にたったひとりはいりこみ、生肉を食べたこと、犬橇技術を憶えたこと、太陽のない真暗闇のなかを橇で走ったこと、三千キロの単独旅行をやったこと、いずれも私には十分満足できるものだった。
(p.262)
投稿元:
レビューを見る
植村直巳と言えば、日本を代表する偉大な冒険家。その植村直巳のグリーンランドでのエスキモー(イヌイット)と一緒に住み、犬橇の扱い方・極地の寒さに慣れた過程を記した伝記。「青春を山に賭けて」に比べれば、グリーンランドでの生活だけに絞っているため、少し弱いが、それでも十分過ぎるほど植村直巳の凄さ、そのバイタリティ、熱気、人の良さが伝わってくる。
現代社会で日々悶々としている人たちに是非読んで欲しい作品。
冒険に出かけたくなる作品であり、より植村直巳が好きになり、尊敬する作品だった。電子書籍化されている。
投稿元:
レビューを見る
本を読み始めるまで上村直己という方の存在を知りませんでした。この小説はグリーンランド、イヌイットで過ごした日々を日記を基に物語として記述されています。当時の北極圏での生活は食文化、俗文化ともに日本とはかなり違う文化で新鮮感の塊です。またそこに住む犬も日本の飼い犬とは違い、犬橇用の動物として想像以上にキツく調教されていることも知りカルチャーショックを受けましたが生きる為には仕方がない事だと思います。素敵な本でした。