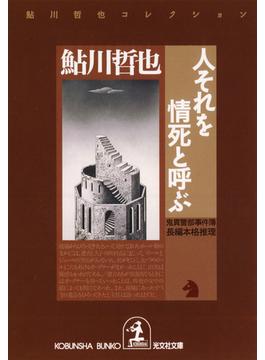病みつきになる快感
2002/04/08 20:05
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ピエロ - この投稿者のレビュー一覧を見る
A省汚職事件の渦中にいた男の死体が見つかる。隣には女性の死体が。捜査の手を逃れられないと知った、覚悟を決めての心中ということで決着がつくのだが、どうしても信じることのできない男の妻と妹は、警察に知らせることなく独自に調査をはじめる。が、容疑をかけた何人かの人物には、全員に鉄壁のアリバイがあった。
鬼貫警部の「アリバイくずし」ものです。前半は、心中した男の妻・妹の立場から、愛情・憎しみ・嫉妬などの女性の心理が描かれ、サスペンスにあふれていて物語を盛り上げます。鬼貫警部登場は半ばすぎ、一気に推理を組み立て犯人を捕まえる、とはならず、相変わらずに小さなことを丹念に着実に調べあげていく。「アリバイくずし」が苦手、キライだという人は、このヘンがまだるっこしく感じるのかもしれませんが、実はここが一番の読みどころ、犯人の完璧に近い嘘が少しずつ少しずつあばかれていく、一度ハマると病みつきになる快感です。
投稿元:
レビューを見る
社会的なテーマを、「本格作家」として上手く料理してある。被害者たちの思いと心理描写が巧みに表現してあるため、その裏に隠された犯人の意図は全く見えず、読者を完璧にミスリードしている。鮎川作品は、タイトルの巧さにも感服するが、この作品にもそれがよく現れている。
投稿元:
レビューを見る
心中の背景にあるのは汚職事件。
でも犯人と思われる人のアリバイは完璧。
調べていくうちに次々に事実が判明し、意外な方向にすすんでいく。
スピード感があって面白いです。
投稿元:
レビューを見る
社会派全盛期の本格推理。心中と見せかけた殺人事件や事件の発端などは他の作家さんの作品と共通した部分がありますが、一番の見所は「逆転の発想」ですね。被害者の男性の親族の視点から始まっていくのに、実は・・・といった展開。ここで犯人が照子や由美に過剰な反応を見せず、手紙の中でも自分の苦しさを語ったりしないあたりが当時のダンディズムでしょうか。せっかくなら「意外などんでん返し」という紹介がされていない方が楽しめたように思います。
投稿元:
レビューを見る
こういう作品を読んでると本当に自分が何故昭和30〜40年頃をメインに生まれてこれなかったのだろうと悔やみたくなります(笑)。
それほどこの時代の雰囲気が好きです。
などと余計なこともほざきつつ以下ネタばれ感想です。
円満な家庭に舞い降りた汚職事件の捜査の手、そして真面目実直だったはずの夫がある日突然失踪、後にとある女性と心中をして…という話ですが、前半は汚職事件絡みの捜査メインの記述、後半は一転して心中した女性の側の事情を追求していったらそこには…という展開です。この反転のところがうまいな〜と思います。
こういう眼からウロコ的な展開が大好きです。
あと文庫解説にも書かれてましたがラストの描写が美しい。
追い込まれた人間の弱さ儚さと一縷の強さというものが自然な筆致で描かれていると思います。いいなあ鮎哲。
トリック的にはやはり「2月5日」の二重トリックが印象的です。
証言者の誰もが嘘を言っていないのに、実はそこにズレがあるという発想が面白い。実際にやろうと思ったら結構難しそうですが(笑)、やはりミステリはこうでなければね! と思うのです。
そして情死した(ことにさせられた)遼吉さんの妹御の由美さんが素晴らしく頭の切れる素敵な探偵役です。
でも鮎哲作品て(まだ三作品しか読んでませんが)登場人物の誰もが探偵役になれる可能性を秘めているというか、場面場面によって探偵役が移り変わるので一概にこの人が秀でてるとかないのが面白いと思います。鬼貫警部も快刀乱麻を断つよりもまとめ役ぽいもんなあ。由美さんの嫂(あによめ、つまりは遼吉さんの奥さん)の照子さんも素敵な女性でした。
しかし最後に出てきた粋な姐さんはてっきりまた警察官のおとりかと思ってたんですが、本当に単なる恐喝者だったのですね…。ああびっくりした。
そういえば最初の頃に久子さんの葬式の場面で出てくる大学生のことなんてすっかり忘れ去っていたんですが、実はかなり重要な人物だったんですねえ。
すべての伏線が絡まり合ってさっと解ける瞬間ていうのはやっぱり心地いいです。ミステリ万歳。
投稿元:
レビューを見る
鬼貫警部シリーズ
汚職事件に絡んだ男の心中事件と思われた事件に疑問を持った男の妹と女の義弟の調査。本当に殺したかったのは誰か?殺害された男女の関係は?
2009年9月19日再読
投稿元:
レビューを見る
人は皆、警察までもが、河辺遼吉は浮気の果てに心中したと断定した。……しかし、ある点に注目した妻と妹だけは、偽装心中との疑念を抱いたのだった! 貝沼産業の販売部長だった遼吉は、A省の汚職事件に関与していたという。彼は口を封じられたのではないか? そして、彼が死んでほくそ笑んだ人物ならば二人いる。――調べるほどに強固さを増すアリバイ。驚嘆のドンデン返し。美しい余韻を残す長編。
投稿元:
レビューを見る
汚職事件を絡めたプロットは社会派を意識していますが、アリバイ崩しに二転三転する展開と、素晴らしい本格推理小説でもあります。
情死とみられる男女の遺体発見からはじまり、哀切漂うラストシーンまで読んで、「人それを情死と呼ぶ」というタイトルが大変胸に沁みます。
投稿元:
レビューを見る
松本清張『点と線』を頂点とし、長らく隆盛を極めた日本特有の社会派ミステリに対して、孤高の本格ミステリ作家:鮎川哲也が放った鬼貫警部ものの代表作。<アリバイ崩し>という、ある意味で大技のない地味な印象を与えるプロットながら、読者の予想を次々と覆す展開がビンテージの貫禄に相応しい一編だ。情景描写・心理描写・説明描写の練り方がすばらしく、折り目正しい文章を読むだけでも心地好い。名探偵役による快刀乱麻の推理・解決を楽しむのではなく、謎を秘めた事件そのものの構造が丹念に開示されていく過程を楽しむ。主役はあくまで事件なのだ。タイトルに込められた意味が重層的な余韻を残し、読後の印象を哀しいセンチメンタリズムで包み込む。まだ戦争の傷跡が癒えきらないミッドセンチュリーの日本への慕情を感じながら、こうしたオールド・ミステリに酔うのもまた良いものである。
投稿元:
レビューを見る
箱根の山中で発見された一組の男女の死体。警察は汚職事件の果ての心中と断定したのだが……。
鮎哲お得意のアリバイ崩しものにして鬼貫シリーズの代表作。精緻に作りこまれているため、トリックそのものものよりも、捜査により謎が徐々に解きほぐされてゆく様がとにかく愉しい作品。特に中盤、ある事実が発覚し事件の様相が一変してからの展開は圧巻の一言。
タイトルに込められた意味が明らかとなるラストの描写の美しさも素晴らしい。
投稿元:
レビューを見る
フーダニットとして読んでいった場合、他の犯人候補たちのアリバイはもうちょいゆるい方が好みだけれど、物語としてはこちらの方が良いのか。
最後の章が肝、として、他の犯人候補のアリバイが強固であれば、追い詰められる絶望も深い。
しかしながら、最近のアピールが派手な物語に触れている身としては、感情の起伏がもっと大きく、大味な方が自分には良いのかも。
あと、なぜか食べ物に関する描写が妙におかしく感じるものが(笑)
「人の世に移りかわりはあるけれども、今川焼の味はつねにおなじである」
投稿元:
レビューを見る
鬼貫警部の「アリバイ崩し」モノです。
犯人のアリバイトリックはリスクが大きのにも係わらず実行出来たのは首を傾げたくなりますが、それでも完璧に作り上げたアリバイを小さな嘘から少しずつ着実に暴かれていく展開は秀逸です。何気ない伏線が次々と真相に繋がる構成も素晴らしいです。
お話自体はかなり地味ですが、印象的なラストと、二重の意味が込められたタイトルが深い余韻を残してくれます。あまり知られていないようですが、間違いなく代表作の一つに数えられると思います。
投稿元:
レビューを見る
良い意味の昭和の小説。
文章も重厚であるけれど、古臭くない。
アリバイ工作に無理があると思うけど、どう崩すのかワクワクした。
投稿元:
レビューを見る
お話としてはおもしろかったけど、ほんとなんでそんなことで殺した!って感じ。
あと、このころの女の人ってほんとにこんなしゃべり方をしてたんだろうか。
投稿元:
レビューを見る
鮎川哲也の長篇ミステリ小説『人それを情死と呼ぶ~鬼貫警部事件簿~』を読みました。
アンソロジー作品『線路上の殺意 鉄道ミステリ傑作選〈昭和国鉄編〉』に収録されていた『早春に死す』を読んで、鮎川哲也の作品を読みたくなったんですよね。
-----story-------------
人は皆、警察までもが、河辺遼吉は浮気の果てに心中したと断定した。
…しかし、ある点に注目した妻と妹だけは、偽装心中との疑念を抱いたのだった! 貝沼産業の販売部長だった遼吉は、A省の汚職事件に関与していたという。
彼は口を封じられたのではないか? そして、彼が死んでほくそ笑んだ人物ならば二人いる。
―調べるほどに強固さを増すアリバイ。
驚嘆のドンデン返し。
美しい余韻を残す長編。
-----------------------
『週刊文春』の1961年(昭和36年)1月23日号から3月6日号に連載された中篇を長篇化したもので鬼貫警部シリーズの作品です。
■一 見知らぬ女
■二 山の宿
■三 失踪のはて
■四 論理の軌跡
■五 意外な発見
■六 庫裡(くり)の灯
■七 海の宿
■八 狩猟家は語る
■九 夜くる客
■十 疑惑の否定
■十一 夢をみた男
■十二 鏡の説話
■付録1●あとがき 鮎川哲也
■付録2●人それを情死と呼ぶ 鮎川哲也
■エッセイ●街角のイリュージョン―鮎川哲也小論 芦辺拓(作家)
■解説●鮎川哲也とセンチメンタリズム 山前譲(推理小説研究家)
失踪したサラリーマンが箱根の山中で白骨死体で発見され、浮気相手との情死と思われたが、妻と妹は現場での違和感から偽装工作を疑い、夫が関与していた汚職事件を調べ始める… 読みながらどんどん物語に惹き込まれていき、ページを捲る手がとまりませんでした、、、
面白かった! 二転三転する痛快なストーリ―展開やアリバイ崩しの面白さ、汚職事案とは無関係の意外な動機、そして結末の美しい余韻とタイトルが印象に残る素晴らしい作品。
昭和30年代のノスタルジックたっぷりな雰囲気も大好きです… 犯人の告白による事件の全貌が描かれる哀愁感溢れる最終章が泣けますね。