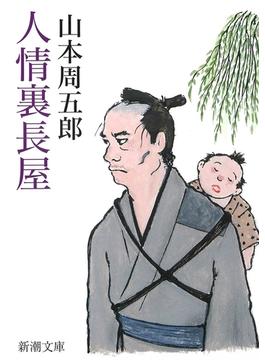人の情を面白く切なく暖かく怪しく描いた11編
2010/01/27 19:03
4人中、4人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:toku - この投稿者のレビュー一覧を見る
時代小説9編ほか、『豹』『麦藁帽子』の現代小説2編を含む全11編。
どれも人の情を多彩に繊細に描き、人それぞれの情の働きが流れ込んでくる作品ばかりである。
特に印象に残っている作品をピックアップ。
『おもかげ抄』
長屋の住人に甘田甘次郎と陰口を叩かれるほど、女房に甘い鎌田孫次郎。
実は、妻は三年前に死去し、幸せにしてやれなかった妻を思い、生きている時のように語りかけているのだった。
そんな孫次郎に心打たれた沖田源左衛門は、仕官の話を持ちかけ、娘の小房を孫次郎に紹介する。
亡き妻への哀惜と誠を尽くす孫次郎の思いが、切なく暖かく、そして源左衛門の孫次郎を見る強く暖かい眼差しを描いている。
茶の席で出された菓子を見て孫次郎が目を潤ませた、その悔恨と尽きない愛慕に胸を熱くさせられる。
本書中いちばん気に入っている作品。
『風流化物屋敷』
化物屋敷と言われている屋敷に御座(みくら)平之助という若侍が引っ越してきた。
隣家に棲むとみは、不思議や不可解な事が大好きで、隣の化物屋敷にも興味津々。そこに突然人が引っ越してくるというので、とみは子どものように興奮している。
やがて平之助は化物屋敷に現れる化物たちに遭遇し、とみは平之助の話す遭遇話しが楽しくて仕方がない。
ややとぼけた平之助と化物たちのやり取りが面白く、とみのやや妄想気味のキャラクターもこの物語の味になっている。
この作品を読んで真っ先に気づくのが改行のほとんどない事。
全九章ある中で一つの章すべて改行なしがほとんどで、長々と連なる文章が独特の連続したリズムを作り出して、読者をたたみかける。
話が面白いので、改行がなくても苦しまずに読むことができる。
『人情裏長屋』
飲んだくれの浪人松村信兵衛は、仕官をする気はまったくなく、金が無くなると剣の腕を活かし、道場破りすれすれの事をして金を巻き上げているが、人情は人一倍あり、長屋のみんなから慕われている。
ある時、長屋に越してきた子持ちの浪人が、将来子どもを育てるための仕官を目指すので子どもの養育を頼むと、子どもを残し去っていった。
憤慨しながらも、長屋の娘おぶんの助けを借りながら、子どもを育てる信兵衛。
やがて仕官を果たした浪人が、子どもを引き取りに来たと長屋に現れた。
仕官をする気がまったくない信兵衛が、おぶんの助けを借りながら子どもを育てる様子と、信兵衛に生まれてくる父性が微笑ましい。
浪人と子どもに影響されて、ある決心をするラストがよい。
『泥棒と若殿』
成信は、家中の政争により廃屋に軟禁されている。
そこに伝九郎が泥棒に入るが、廃屋の酷さや、訳あって何日も飯を食べていない成信の人柄に惹かれ、伝九郎が成信を養っていくという奇妙な生活が始まる。
やがて成信は、自分を政争の道具にしかしない家を捨て、伝九郎と暮らしたいと思い始めた。
家のごたごたに嫌気がさしている成信が、人間の生活に満ちている伝九郎との生活を夢見るようになっていく様子が見所。
伝九郎との生活を夢見た若殿に、家臣たちの生活を背負っているという現実が迫るラストは切ない。
『雪の上の霜』
常に人の事を優先し、人の幸せのためなら自分は損をしてもかまわないという性格の伊兵衛と、そんな夫が好きな妻おたよの物語。
最後はやっぱり良い事をして損をするが、おたよはそんな夫がやっぱり好きなのだ。
鶴田真由快演で好評のNHK「ゆうれい貸します」の原作者が、山本周五郎と知って驚いた人、原作「ゆうれい貸屋」を収めた本書を手にとってもう一度驚こう。
2003/06/24 10:36
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:拾得 - この投稿者のレビュー一覧を見る
コミカルでテンポの良い人情ものの時代劇「ゆうれい貸します」を、「鶴田真由さんってきれいなんだなぁ」と見ていたら驚いた。「原作、山本周五郎」とクレジットが流れるではないか。山本周五郎=『さぶ』の印象が強すぎた評者にとって意外だったからだ。早速、原作「ゆうれい貸屋」を収めた『人情裏長屋』を探し出して手に取った。
「もちろん」と言うべきだろう、番組と原作とはかなり違う。共通しているのは、弥六とお染とが「ゆうれい貸屋」を開業することと、世の中には成仏できなくてゆうれいになる者が少なくないこと、彼らが成仏するには身内の者に供養される必要があること、の三点くらいである。
しかし、そこが脚色の妙というべきか、それとも原作者の腕なのだろうか、それが気にならない。むしろ、「滑稽もの」と呼ばれる作品群を収めた本作品集からは、番組が作り出しているのと同じ雰囲気が湧き上がってくる。人情を扱ってお涙頂戴が自己目的にならず、生きていくことの滑稽さを描いて軽くなりすぎはしない。「生きてるって素晴らしい」などと言う気はないけれど、「生きているのもそう悪くはないことだよ」とは言ってみたくなる。
1950年に発表された本作が、21世紀の現代に活き活きと蘇ったことを素直に楽しみたい。
投稿元:
レビューを見る
滝田さんが長屋に住む浪人・松村信兵衛役で出演したTVドラマ「柳橋慕情」の原作本。しっとりとした良いドラマでした。
投稿元:
レビューを見る
居酒屋でいつも黙って一升桝で飲んでいる浪人、松村信兵衛の胸のすく活躍と人情味あふれる子育ての物語『人情裏長屋』。天一坊事件に影響されて家系図狂いになった大家に、出自を尋ねられて閉口した店子たちが一計を案ずる滑稽譚『長屋天一坊』。ほかに『おもかげ抄』『風流化物屋敷』『泥棒と若殿』『ゆうれい貸屋』など周五郎文学の独擅場ともいうべき"長屋もの"を中心に11編を収録。
【感想】
http://plaza.rakuten.co.jp/tarotadasuke/diary/200505100000/
投稿元:
レビューを見る
昨日眠たい帰り道 KIOSKで本を買った
なぜか目に飛びついた 人情裏長屋 山本周五郎である
何年か周期で 時代小説や落語ブームが私の中に去来するのですが。今年がそうらしい
帰ってひと寝りして こんな時間に本を読んでるわけだが
いいね 下町
「あんた」 「おまえさん」 「飴ん棒う」
「―ってー始末だ」「ちょいと旦那」 「粋だねー」
なんて言葉が溢れてる。 なんか幸せになるな。
投稿元:
レビューを見る
2007年5月に歌舞伎座昼の部で坂東三津五郎の若殿と尾上松緑の泥棒で上演された「泥棒と若殿」の原作が読みたくて探した本。お家騒動の内紛で幽閉されてその日の食料にも事欠き餓死するかもしれないと武士の世界に絶望しかけた若殿と、お人好しにもつい彼に食料を運んでくるようになってしまう泥棒との話で、非常に原作に忠実に舞台化されていることがわかる。山本周五郎はいい話ばかり書いているわけではないけれど、これは表題作を含めて大半が結末の温かい話を集めていて読後感がいい。講談調の語り口の楽しい「風流化け物屋敷」などもなかなかいいですよ。
投稿元:
レビューを見る
笑わせる話、熱くなる話、スッとする話、怖い話…
いっぱい作品が詰め込まれているけれど、
この話のほとんどが、立場的に庶民(もしくはそれに満たない人々)
と言える人たちによって織り成されるのが良いです。
まさに大衆のための小説。
「泥棒と若殿」「雪の上の霜」あたりが個人的には好きだったかな。
笑ったのは「風流化物屋敷」と「長屋天一坊」。
投稿元:
レビューを見る
11の短編集。
その中で一番良かった作品は、「ゆうれい貸屋」。ゆうれいを使って一儲けしようとする男の話。笑えた。
投稿元:
レビューを見る
私にとって一昨年11月以来久しぶりの山本周五郎氏の小説。読み始めからもう山本氏の世界引き込まれてしまいます。11編の短編どれをとってみても珠玉いえる。男同士の友情を描く『三年目』や『秋の駕籠』などは『さぶ』を髣髴させる話だ。
驚いたのは表題作『人情裏長屋』だ。めっぽう腕のたつ浪人・松村信兵衛は裏長屋住まい。金の入り用があると「取手呉兵衛」と名乗って道場破りをして金を稼ぐ。あっ、これは今から三十数年前、私がまだ中学生か高校生の頃にテレビでやっていた時代劇『ぶらり信兵衛道場破り』ではないか。高橋英樹が主演、信兵衛役でした。普段は贅沢をせずこつこつと仕事をしてつましい生活をしている信兵衛が、困っている他人を助けるためにまとまった金が入り用になると道場破りに出かける。信兵衛はめっぽう剣が立つので道場の門弟をつぎつぎ薙ぎ倒してしまう。いよいよ道場主との手合わせという段になって、最初は力の差を見せつけ道場主を追い詰めるのだが、そこで勝ってしまわず道場主がいまにも「参った!」という寸前になって逆に信兵衛が「参った!!」と言ってわざと負けてやり、あとで袖の下を頂戴するという筋書きであった。そうか、山本周五郎氏の小説がベースになっていたのか。三十数年たって初めて知りました。そういえばそんな浪人・信兵衛に岡惚れするおぶんちゃん役の武原英子の可愛かったこと。なんとも微笑ましく味わい深い時代劇でした。YouTubeで検索すれば少し視ることが出来るようだが、DVDは無いのかな。是非もう一度視たいものです。
投稿元:
レビューを見る
タイトル通り、長屋の短編小説。
高校生の頃、付き合ってすぐに別れた男の子が何故か貸してくれた本。
メッセージは、読み取れなかった。すまん。
しかし、面白かった。
たぶん時代小説、好き。
投稿元:
レビューを見る
短編集でしたが、どの話も面白かったです。ゆうれいとの掛け合いがおかしくって大笑いしました。面白さというのはいつの時代も変わらないのだな、と心が和みました。
投稿元:
レビューを見る
今月の図書館での出会いから…この表紙ではなく、古い版で灘本唯人さんのイラストレーションの表紙でした。好きなイラストレータのひとりです。この絵は、どうかな?この大きさでは、わからないなぁ…本の中身ですが、つまみ食いのような感じで、短編を読んだだけなのです。時代小説の名手という印象がありますが、現代小説も2編ほど収録されていて、そっちのほうを先に読んでしまいました。解説を読むと、山本周五郎さんは戦前に直木賞を辞退されたそうです。現代では、欲しくて欲しくてたまらないヒトたちが多いようですが、時代が違うのでしょう。短編をポツリポツリと読んでいきたいものです。
投稿元:
レビューを見る
11篇からなる短編集。
「おもかげ抄」
周囲から甘次郎と呼ばれるほどに女房に甘い鎌田孫次郎は、腕も確かで武士を助けたことで仕官の道が開ける。しかし孫次郎の妻は、本当は既に亡くなっていて…。
「三年目」
大工の友吉は博打から足を洗うために、許婚のお菊を信頼できる友、角太郎に預けて上方に旅立った。しかし戻ってみるとふたりは夫婦となっており、怒りに駆られた友吉はふたりの住処を捜し当て…。誤解が解けてよかった!
「風流化物屋敷」
おおらかな性格の武士、御座平之助が化物屋敷と名高い屋敷に越してくる。日々、物音がしたり化物が脅かしてくるが平之助は平気の平左、ちっとも動じない。賭場として使いたいがために博打打ちたちが化物屋敷として広めていたというのがオチ。
「人情裏長屋」
松村信兵衛は優れた剣客であり、弱きに優しい武士である。長屋の住人とも親しくしていたが、ある日ひとりの浪人に親切にしてやると、浪人は信兵衛に赤子を押し付けて消えてしまう。酒を断ち、赤子を育てるが…。
「泥棒と若殿」
藩の後継ぎ争いに巻き込まれた末に孤独に貧しく暮らしていた武士の屋敷に伝九郎という名の泥棒が押し入る。あまりの窮乏に見かねた伝九郎は武士の世話を焼いてやり、ふたりは楽しく暮らしていた。そこへ藩からの迎えがきて…。「信さん、行ってしまうのか」の台詞が切ない。
「長屋天一坊」
長屋の家主である吾助は業突く張りの嫌われ者。女房と娘もそれに張る強烈な性格の持ち主。吾助が家系図に興味を持ったことから起きる騒動。
「ゆうれい貸屋」
職人の弥六は芸妓の幽霊お染と意気投合し、幽霊を貸す商売を始める。しかし思うように働いてもらえなかったり、人間に負けて返ってくる幽霊も。すったもんだの末に実家に帰っていた女房とやり直すことになる。
「雪の上の霜」
「雨あがる」の続編。伊兵衛は武芸には優れているが、優しすぎる性格が災いして仕官の道を見出せない。病気の妻おたよを養うために街道で荷物運びをして日銭を稼ぐが、人足達から縄張り荒らしだと責められ…。己の立身出世よりも他人が虐げられることに我慢がならない伊兵衛を支える妻の姿が微笑ましい。
「秋の駕籠」
駕籠屋の相棒である六助と中次は、普段は一緒に暮らすほどに仲がいいが、時折つまらないことで喧嘩をする。ある日、払いのいい客を乗せて箱根まで行くが、途中でその客を追ってきた男にそいつは詐欺師なのだと教えられる。タダ働きかと意気消沈するふたりだったが…。
「豹」
正三は兄が死んでから、義姉と甥が暮らす家に寄宿していた。ニュースで近くの動物園から豹が脱走したと知り…。女の生々しさと情。
「麦藁帽子」
偶然であった老人から昔話を聞く。いったいどこまでが真実だったのか、それとも全てが老人の紡ぐ物語だったのか。
投稿元:
レビューを見る
長屋にて生活する人々の正直であるがままの呼吸を感じる事ができる短編作品集。共通のテーマは"他人への思いやり"か。裏長屋に込めた筆者の思いは、ギリギリの生活の中に灯すわずかな希望がつまった場。そして地道に稼ぐ人間が汗のする銭でつつましく生きる場かな。特にお勧めの作品は「おもかげ抄」と表題作の「人情裏長屋」。ふか~い愛情にふれ感涙に咽んだ~ 。秋の夜長に読む本としてうってつけ。
投稿元:
レビューを見る
山本周五郎はいつか読まねばと思いつつ手を出せていなかったのだが、
読書会の課題図書になったので読む機会を得た。
推薦してくれたかっきーさんが言うように、
「どのページを開いても泣ける」というところまではいかなかったが
(僕の人生経験がまだ浅いのかもしれない)、
いつくかの短編はとてもよかった。
表題作の『人情裏長屋』は、読書会でいろんな感想を聞けて面白かったが、
僕の感想は、
●その場所のいい・悪いではなく、その人の居るべき場所、居るべき世界というのがあるのかもしれない。本来、下にいるべき人間が上に行っても不幸だし、松村信兵衛のような人間が下にいるのも、いいようでやっぱり不自然なのかもしれない。
●「おぶん」は若いのに、賢くて情のあるいい女。惚れる。
の2点。
他には『風流化物屋敷』に出てくる「おとみ」がとてもかわいくて惚れる。
『泥棒と若殿』は号泣。
『豹』の正三はなんて意気地なしなんだ!と思い、『麦藁帽子』は美しいいい話だなぁと思った。