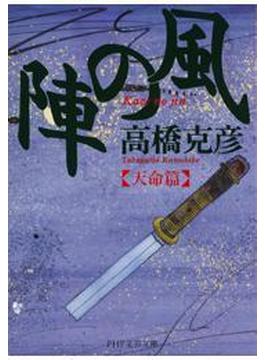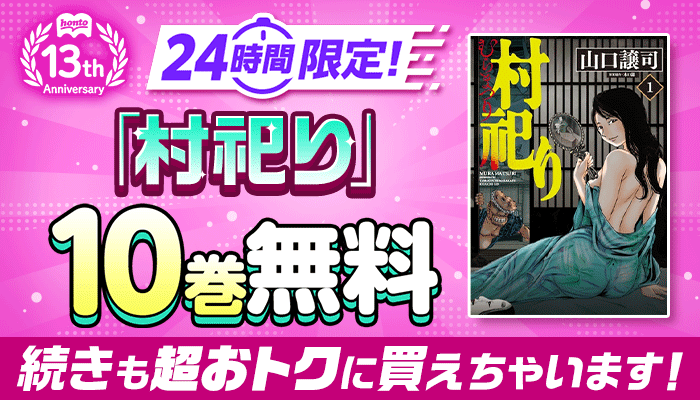風の陣【天命篇】
著者 高橋克彦
恵美押勝が討伐されてから一年近くが過ぎた天平神護元年(七六五)――。淳仁天皇を廃した孝謙上皇が帝位に返り咲き、再び内裏に訪れたかに見える平穏。その裏には、女帝を誑かし、陰...
風の陣【天命篇】
商品説明
恵美押勝が討伐されてから一年近くが過ぎた天平神護元年(七六五)――。淳仁天皇を廃した孝謙上皇が帝位に返り咲き、再び内裏に訪れたかに見える平穏。その裏には、女帝を誑かし、陰で政治を操る怪僧・弓削道鏡の存在があった。異分子を巧妙な罠に嵌め、次々に排除していく道鏡。その毒牙が嶋足の最愛の婚約者・益女にも迫る! 道鏡の専横に危機感を募らせた嶋足と天鈴は、密かに「打倒道鏡」を誓い合うのだが……。彼らの目論見とは裏腹に、道鏡と女帝の蜜月関係は続き、その権勢は揺ぎないものになっていく。黄金眠る陸奥に食指を伸ばし、帝位さえ脅かし始める飽くなき道鏡の欲望、その阻止を図る嶋足、天鈴らの奇計妙策の数々……。朝廷への憧憬と疑心暗鬼の念に揺れる蝦夷たちは一枚岩となることができるのか? 暗雲漂う平城の都と陸奥を舞台に、蝦夷の存亡と誇りを懸けた新たなる戦いの火蓋が切って落とされた。シリーズ第三弾、待望の文庫化!
関連キーワード
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
小分け商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
この商品の他ラインナップ
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
歴史上の人物が生き生きと描かれている奈良時代の大河小説
2007/08/05 21:26
5人中、5人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ドン・キホーテ - この投稿者のレビュー一覧を見る
高橋克彦による、奈良時代の蝦夷と都にいる貴族の物語第3弾である。これまでの2巻は面白く、一気に読んでしまった。歴史に登場する人物がまるでこの世に生きているように大活躍する。今までは教科書などに閉じ込められ、名前だけしか縁のなかった人物に命が吹き込まれたかのように生き生きと呼吸をしている。
第3作目の本書は、前2作に続いており、奈良時代の後半の歴史物語である。時は孝謙女帝の御世である。孝謙女帝といえば、弓削の道鏡という怪僧が付き物である。主人公は蝦夷のホープ、牡鹿嶋足である。この人物は実在していたらしい。その取巻きの蝦夷が多彩である。この筆頭が物部天鈴であるが、これらは架空のようだ。
嶋足とその取巻きの蝦夷等は、これまでの立志編、大望編で多彩な戦略を練って、今までに恵美押勝や橘奈良麻呂などを退けてきた。押勝を一掃したまではよかったのだが、それまで助成してきた道鏡が当初考えていたように、自分たちのいうことは聞かなくなってきた。
蝦夷の本拠地では砦の建設が始まり、朝廷の勢力誇示が実地に行われようとしている。本拠地では各部族の取りまとめをしなければならない。嶋足と物部天鈴は多忙である。和気清麻呂が宇佐八幡へ使いに出て、託宣を伺いに行ったところで本編は終わっている。
当然、流れは歴史のとおりである。登場人物も坂上苅田麻呂や道鏡など歴史上の人物が登場するので、読者をして奈良時代日本史の細部を伺わせるような面白みがある。
ただし、今回は前2編のように、大きな乱があったわけでもなく、謀反がおきたわけでもないので、やや盛り上がりには欠けている。一方で、蝦夷の本拠地でこれからの動きを予測させるような伏線が張られているので、以降の続編が楽しみとなった。
本編では貴族の階位が如何に重みがあるかを描いている。事あるごとに階位の説明がなされている。ちなみに主人公の嶋足は、蝦夷出身ながら従四位下であり、陸奥守の適正階位をとうに上回っている。これらの階位は千年以上を経て未だに公務員に叙位されている。
私はこれでてっきり完結だと思っていたが、続編があるとのことである。どこまで続くのか興味深い大河小説である。
「天命篇」の主役は弓削道鏡である。道鏡といえば巨根伝説を知っている程度であった私はこの栄達プロセスを興味深く読むことはできた。
2010/11/28 18:22
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:よっちゃん - この投稿者のレビュー一覧を見る
恵美押勝討伐の功で破格の昇進を遂げ、勲2等まで授けられた牡鹿嶋足は、しかし実際には閑職に追いやられた。嶋足を陸奥守にして蝦夷の平穏を確保しようとする物部天鈴らの企ては実現しそうもない。朝廷内で高位の官位をえた嶋足は奥州の安定よりも官人としてむしろ中央政権に国家安泰の政治を期待しているのだが、権力抗争に明け暮れる朝廷には天皇皇族にも有力豪族内にも彼が忠節を尽くすべき中心人物が不在である。この悩み多きインテリの嶋足に対して、物部天鈴は奥州支配へのパワーを分散させるためにさらに中央の混乱を激化させようとする。
「天命篇」の主役は弓削道鏡である。天鈴の機略によりに孝謙上皇に接近した道鏡は恵美押勝討伐の役割を果たすが、それだけにとどまらず女帝の寵愛をえてその怪物振りを発揮する。もはや彼らの手に負える相手ではない。法王という未曾有の官位を得て天皇と同じ所得を与えられる。人臣最高の地位まで上り詰めた道鏡の専横と野心はとどまるところを知らない。
道鏡といえば巨根伝説を知っている程度であった私はこの栄達プロセスを興味深く読むことはできた。ただ、孝謙女帝の人間がまったく描かれていない。快癒祈願によって命を救われただけで、ここまで人を信用し政治を任せることができるとは暗愚としか言いようがない。このため文献にある史実をなぞっただけで、肝心な緊張感ある人間ドラマになっていないことに不満をもった。
道鏡攻略作戦では「奈良麻呂の変」、「恵美押勝の乱」のように天鈴得意の複雑な奇手、奇略が展開される。道鏡は天皇の位を承継するため神のお告げをでっち上げようとする。それを欺瞞と暴き、道鏡の失墜を決定的にしたのが「宇佐八幡宮神託事件」であるが、これは天鈴の仕掛けた罠であった。この事件を知らない私としては騙し騙されのスリリングな展開に引き込まれた。
ただし三巻まで読むと、一篇ごとに登場する巨悪に罠を仕掛けるという同工異曲の繰り返しはどこか攻略ゲームに似て、全編通じてあるはずの朝廷対蝦夷の対立ドラマが平板にしか流れていないことが気になり始めた。
奥州藤原氏の時代を描いた『炎立つ』はまだ読んでいないが、『風の陣』『火怨』『炎立つ』この三部作の中で作者の蝦夷に対する思いの熱さが一番に表現されているのは『火怨』だと思われる。
『風の陣』を三巻まで読んで、いささか退屈してきているのは『風の陣』は『火怨』のための前史であり、前座の役割でしかないのではないかと思えてきたためである。