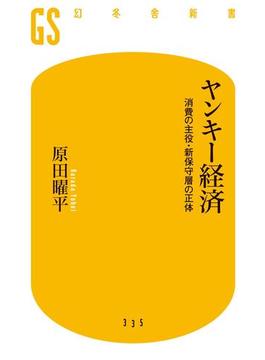新時代のヤンキー論の定番となるかも
2019/03/03 22:33
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:もちお - この投稿者のレビュー一覧を見る
2014年の刊行時点から5年が経過した今でもこの本で描写された新たなヤンキー層の生態は変わっていない。彼ら/彼女らは地元から出ず、半径5キロしか視野に入れていない近くの友人知人を大事にし、その維持ツールとしてスマホを使う。有名なブランドが好きで、自動車への関心は高い。これらの特徴から、現代のヤンキーをマイルドヤンキーと評し、世間一般にも定着している。どうしてこういう現象となっているかの原因分析やマイルドヤンキーの生態を統計学的裏付けで証明できれているかは疑問が残るが、若者論の中では一読に値する本であり、00年代に育った若者論の定番になるかもしれない一作。
ヤンキーという言葉の移り変わり
2015/03/29 14:53
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:オオトリさま - この投稿者のレビュー一覧を見る
「マイルドヤンキー」という言葉をこの本で初めてしりました。
80年代大ブームを起こした「ホットロード」が映画化されると金髪はソフトな茶髪になり、何だか全体に「マイルド」になったが、あれが現代版「ヤンキー」なのだろうか?
地元を愛し、外に出たがらない若者たち。
日本が高度成長時代から成熟社会になり、「大きすぎる夢」を持たない事が成熟社会を生き延びるすべだと若者は本能的に悟っているのだろうか?
マイルドヤンキー向けの商品の提案
格安のレンタルームは空き家対策としてもこれから発展的に可能性を探すのはいいと思いました。
ディズニーランドの家族パックも面白いかもしれません。
投稿元:
レビューを見る
かつての不良「ヤンキー1.0」→いわゆるヤンキー・チーマー「ヤンキー2.0」→残存ヤンキー+地元族「ヤンキー3.0」の変遷を軸に分析。
仲間を大事にして地元から離れたがらないヤンキーの消費論理。閉じた仲間たちとのうちわの交流、手軽な非日常の追求、現状維持のための消費。
社会的な階層上昇の可能性が縮小する時代に、特に地方の消費経済を考える上で外せないヤンキーの消費行動。「新保守層」云々の議論は薄いが、現状維持の姿勢からくるものと読めば積極的な保守主義というよりも、情報もない中でのとりあえずの保守・守旧とも読める。
投稿元:
レビューを見る
マイルドヤンキー…不良・暴走族(70-80年代)~ヤンキー・チーマー(90-00年代)に引き続き登場した、第三世代の若者たちの生態を綴った本。
地元志向、保守的な消費性向、等身大な見栄など、あまりメディア等には登場しない低成長時代における新・保守層の実態を理解するには面白い。さらに、著者は広告代理店の人なので、それをいかに企業のビジネスと結びつけるかについても言及しており、ビジネス書としても参考になる。
地元志向、と言ってもマイルドヤンキーたちにとっての地元とは、半径5km以内の中学校区程度のエリアを指す。東京都心に電車で数十分で出られるようなエリアに住んでいても、めったに電車には乗ろうとせずにまったりといつメン(いつものメンバー)と宅飲みや近所のモールなどで遊ぶのだ。
そんな彼らにとって私的なゾーンの延長であるクルマは必需品であるが、かといって昔のヤンキーのようにスポーツカーを改造したりしない。むしろ、仲間たちがたくさん乗れるように、ワンボックスカーをホスピタリティ溢れる形で気持よくしていくことに心血を注ぐ。
TwitterやLINEといったソーシャルメディアの使い方も、広く新しいことを知り、様々な人たちと出会い交流するためといった好奇心ではなく、仲間内で日常的な内輪ネタをやり取りする掲示板のようなものとして認識しており、ITリテラシーが低いために身内向けのネタが時々流出して炎上してしまう“バカッター”に繋がっている。
このような新・保守層とも言える若者たちは、東京都下から地方の中核都市に至るまで、広く存在している。もはや彼らにとっては、東京で次から次へと新しいコンセプトを生み出し、クリエイティブに情報発信していくといった仕事はまったく魅力を感じておらず、むしろ地元で気心の知れた家族や仲間たちと日常の思い出を重ねていくことに関心を見出している。
恐らく、今後の日本の消費を引っ張っていくであろうこの層に対して、いかに有効なアプローチを仕掛けていくのか。大量生産大量消費のモノカルチャーの先に位置づけられる企業間競争は、すでに始まっている。
投稿元:
レビューを見る
現代のヤンキー像とその消費行動について。今のヤンキーは、地元思考が強く、隣町に行くことも嫌がると。確かにそんな感じがする。今のヤンキーの人達に知り合いがいる訳ではないが、仲間意識が強いこと、ファッションが昔の様子と違うことなどは、よくわかる。エグザイルが典型的な今のヤンキーということらしい。
投稿元:
レビューを見る
タイトルはアレだけど、地元とその仲間の繋がりを大事にする“マイルドヤンキー” のインサイト。面白く納得感あった。 …沖縄の出張タイミングに読んだからとか、そんなのカンケーねー! はずだ。
投稿元:
レビューを見る
話題のマイルドヤンキー本。とてもおもしろく読めたが、ちょっとおもしろく書きすぎだと思う。あとマイルドヤンキーがこれからの消費のキーってのはわかるんですが、その割合って人口の何%くらいなんでしょうか?
投稿元:
レビューを見る
遅ればせながら読了。「マイルドヤンキー」という言葉だけが一人歩きしてしまっている感がありますが、なかなかの良書でした
失われた20年をへて、日本でも階級社会化が相当なレベルで進んできているのではないか、という肌感覚を見事に裏付けてくれる内容でした。成り上がる事が既に難しく、維持する事が目的になった世代。さらに20年後は維持する事すら難しくなっているのかもしれない。否応なくこの現実に立ち向かうしかないのですが
投稿元:
レビューを見る
同じ世代といえど、色々な角度から消費者を考える必要がある。
その考えを教えてくれる一冊。
よく20代前半はデジタルネイティブなんて言われるけど、それも20代前半の一部を切り取っただけかもしれない。
それを知っているのと知らないのとでは、視野の広さが変わってしまう。
地方出身の僕としては、納得する部分も多く、地元帰るとそうだよねとうなずくことも多かった本書。
※僕は「成り上がり」読みカテゴリですけど。
・メモ
-閉じた関係をそのままオープンにすることで起こったバカッター騒動
-マイルドヤンキーは知っている範囲でモノゴトを決める。
※知ってもらうことが大切。
-LINEが受け入れられたのは、そのハードルの低さも大きな要因
インタビューから把握出来た調査のアプトプット過ぎたのが個人的には微妙に感じる点ですが、定点観察としては知りたい情報であった。
投稿元:
レビューを見る
現代のヤンキークラスタを研究した経済(?)書。
いわゆるヤンキーと呼ばれる人たちは昔からいるが、本書では現代のヤンキーを「マイルドヤンキー」と定義している。その主な特徴としては、向上心は弱く地元への執着心は強い、地元友人との付き合いが生活の中心、娯楽はパチンコで喫煙率が高い、スマホ普及率は高いがITは苦手、車はセダンよりミニバン、などなど…
昔ながらのヤンキーと比べると少し小粒で、いかにもゆとり世代の不良、草食系ワルといった風情だが、同年代の他のクラスタと比較すると購買意識が高いという、このご時世に何とも心強い特徴があるようだ。実際に彼らをターゲットとした、悪羅悪羅系(笑)の雑誌やファッションは売れているらしい。
一見すると非常に特異に見える研究だが、もしかしたらマーケティング目的だけではなく、若年層の自殺や老人の孤独死、また首都圏一極集中など、いま日本が抱える様々な社会問題に対しても、解決の糸口と成り得るのではと、少し真剣に考えた。
上昇志向は無いけれど、いつも気の合う仲間同士で集まり、たまにショッピングモールでささやかな贅沢をする。
考えてみると、人生の幸せって意外とそんな些細な事なのかもしれない。自分が若い頃、仕事を理由に友人の結婚式を欠席してしまい、あとから猛烈に後悔した事を、不意に思い出してしまった。
マイルドヤンキー的なライフスタイル、決して悪くないと自分は思う。
投稿元:
レビューを見る
読む前から「マイルドヤンキー」というキーワードで、「ああ、分かった、そういう切り口は確かにある!彼らのことね!」と思って読んでみた。期待に違わず非常に良くまとめられていた。
要するにこういうカテゴリの人たち向けのマーケティング用ペルソナ分析的な本なんだけど、
・暴力的なヤンキー、族ではない(そもそもその層は残滓しかない)
・男子はEXILE、悪羅悪羅系
・地元大好き、半径5km以上行動したがらない
・地元の友だち関係が何より大事
・新しい人間関係を築くのがおっくう
・東京郊外〜地方都市部在住
・都心部まで電車で20分であっても出ようとしない
・学歴は「高くない」が、中卒〜私立大ぐらいまでバラつく
・「湘南乃風」と「西野カナ」の世界観
・イオンとラウンドワンですべてが完結する
・クルマで移動したがる、電車嫌い
・ワンボックスカーに友達と乗るのが好き
・「既知のものしかほしいと思わない」現在知っているものだけから選択する
・観光にはあまり興味が無い。行っても本当に有名なところに仲間と行ったことが大事
・PC・スマホ苦手、検索したがらない
・選択肢が多いことは苦痛でしかない
・知的好奇心はそれほどない
なんかね、そーそー、って感じで。
2点すごく釈然としないものがあって、一点はそもそもこのクラスタに対する釈然としなさなんだけど、
もう一点は、切り口の問題。
まず切り口の問題なんだけど、このクラスタ(というには巨大なんだけど)、「EXILE、悪羅悪羅系」という属性を外しちゃえばもっと広くターゲット層が存在するだろうこと。ユニクロ/しまむら/イオンファッションと通販で買うEXILE/悪羅悪羅系は、同じカードの表裏でしかないだろうから。ファッションとか車のデコレーションみたいな、デティールが意味がある者はちょっと違うかもしれないし、そこは限定的にカテゴライズしていった方がエッジが立つのはわかるけど、もう少し広いゾーンの特性を、限定したペルソナで説明しているように思えるのが気になる。
「ショッピングモールから考える」あたりの切り口を交えた再整理が欲しい感じはするんだよな。
もう一点はやっぱこのクラスタに対する釈然としなさだよね。「地元の友達」概念ほど私が個人的に理解しにくいものはないし、知的好奇心の薄さと、「既知のものしか求めない」感じ、慣れてきたような気もするけどやっぱりこうして文章にされると、本当にそれはそう言い切って終わりにしてしまっていいんですかと、どーしてもモニョモニョしたものを感じてしまう。
まあ、2014年現在、興味深い本では合った。
投稿元:
レビューを見る
またHONZに釣られた。
消費の主役、新保守層の正体という副題も気になった。
低成長下でそういう生き方もありと思う。幸せの形は色々。
ただ、カモにされるのはバカバカしいな。
投稿元:
レビューを見る
知らない世界。地元思考の昔ほどバリバリなヤンキーじゃない人を「マイルドヤンキー」として、その消費傾向を記載していた。
投稿元:
レビューを見る
マイルドヤンキーという、さとり世代とはまた違った若者層の実態をよく表せていると思う。
だっているもん!周りにこういう友人!笑
マイルドヤンキーの特性、今ある幸せが続くことを望む、にマッチしたビジネスを何か考えたいなぁ
投稿元:
レビューを見る
ネットや在京メディアに拾われにくいクラスターの若者たちの生活や価値観を調査してまとめています。その「クラスター」の存在に気は付いていたが言語化できていない、というフェーズで本書を手に取りました。着眼のタイミングがよく、内容的にもなかなか整理されていると思いました。
統計的な調査とするにはサンプル数は少ないですが、対象の特質的に大規模調査がしにくそうなので現時点では仕方ありません。代わりに、インタビューなどの取材調査をして目立つ特徴を拾っていっており、初期段階としては妥当かと。
ただ…、このクラスターの若者たちを「優良消費者」と著者が表現するのですが、それが「いいカモ」に脳内変換されてしょうがありませんでした。私が意地悪いのでしょうか笑。マーケティングは、「商売の鴨を探す商売」だと分かっちゃいるのですが、この本はなんだか露骨ですよね。