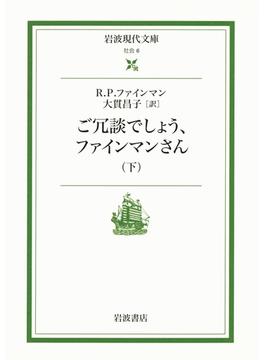20世紀を代表するリチャード・ファインマン氏の様々なエピソードが面白、おかしく語られます。
2020/05/04 10:50
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ちこ - この投稿者のレビュー一覧を見る
本書は、20世紀を代表するアメリカの物理学者リチャード・ファインマン氏が語る非常にユニークなエピソードを集めた一冊です。彼は、人生の中で様々な経験をするが、常に自分自身が物理学者としての誠実さを忘れなかったと言われています。同書の中では、ブラジルの国立研究所滞在時に、同国の大学教育が暗記中心であることを見つけたことや、アメリカの学校教科書の選定委員となった際、教科書記述が科学的誠実さを欠いていることを見つけたことなどが語られ、また、カジノでプロの博打うちに弟子入りしたり、ボンゴドラムでバレエの国際コンクールの伴奏をしたり、また幻覚に強い興味を持ち、旺盛な好奇心から感覚遮断装置にまで入ってしまうというエピソードも伝えられます。物理学者として、また一人の人間として味わい深いファインマン氏の素顔に触れられる一冊です!
投稿元:
レビューを見る
著者:R.P.ファインマン
今日読み終えました。
最近ファインマンものばっかり読んでます。
大学からコーネル大学で教鞭を握っている時期のことが
書かれている。
ほんと物理学者という以前に
面白い人だ。
何事も楽しんでしまう。
ちょっといたずらすぎる面もあるけど。
しかし、物理の研究に対して
やや身が入らない時期もあったようだ。
意外だったけど、やっぱりファインマンらしく
スランプをすり抜けている。
人間、動物、自然現象、あらゆる面に関して
鋭い観察力をもっており、
さらに実験上手。
中でもナイトクラブでの経験など
一回は是非とも試してみたい。
投稿元:
レビューを見る
この人は当然、すばらしい学者でもあるので教科書も書いてます。
「ファインマン物理学」って言います。大学1,2年生には難しいそうです。持ってないから分かんないんですけど、お金に余裕ができたら買いたいです。
投稿元:
レビューを見る
妥協という言葉から程遠い、ファインマン教授の人生が垣間見える。この本は面白い! 2007/10/06
投稿元:
レビューを見る
後編。
日本好き!というのがまたとても嬉しいですし
実際あってみたいなーと思ってしまうほどです。
おすすめ
Aug, 2008
投稿元:
レビューを見る
21/9/16 95 好奇心!!
こうして僕は実際の世の中では、刷新ということがいかに難しいかを学んだのだった。>叔母のホテルでのアルバイトで
聾唖の人々のダンスパーティーで>この場に気持ちよくとけこめるかどうかは、ことら次第だ。こういう経験は得がたいものだと僕は思う。
催眠術をかけられるというのはなかなか面白いものだ。僕たちは「できるけどやらないだけのことさ」といつも自分にいいきかせているわけだが、これは「できない」というのを別な言葉で言っているだけのことなのだ。
成果をうみにはただ単にその仕事の意味を教えてやるだけでよかったのだ。
積極的無責任さ>社会的無責任感
投稿元:
レビューを見る
2009年09月19日読了
p27
それ以来僕は酒を一滴も飲んでいない。そんなに簡単に止められるぐらいだから、アル中になる危険などなかったのだろうが、とにかく自分で理解できないような、あの強い衝動がおそろしかったのだ。僕は考えるということが愉快でたまらないよいう人間である。だからこんなにまで人生を楽しませてくれるすばらしい機械である僕の脳を、こわしてしまいたくないのだ。
p206
本の優劣をきめるのにこれをよく研究するのがいいか、あるいは多くの人がいい加減にしか読まずに書いた報告を見て評定するのがいいかという問題は、例の有名な古い話に似ている。昔中国では、国民が皇帝の顔を見ることはいっさい禁じられていた。ところが、その皇帝の鼻の長さはどれだけあるか、ということが問題になった。そしてこの答えを出すため、役人が国中をかけずり回っていろいろな人から皇帝の鼻の長さがどれだけあると思うかを聞いて歩き、これを平均して答えを出した。という話である。あれだけ大人数から聞いた長さを平均したのだから、さぞかし「正確な」答えが出ただろうと思うと、それはとんでもない話だ。どんなに広範囲の人間の意見であろうが、正確にそのものを見ていない人の意見などいくら平均してみたところで、正確な知識を得るには何の役にも立ちはしないのだ。
投稿元:
レビューを見る
09/10/27読了
ご冗談でしょう、ファインマンさん(上)と同じく、ファインマンの逸話を軽快な語り口で紹介している。深く考えさせるエピソードは上巻よりも少なく感じたが、それでもファインマンの魅力を十分に感じる。ただ、最終章のカーゴ・カルト・サイエンスは必読。本章では、科学者としての行動誠意を尽くすことの重要性についてといているが、これは、一般社会できるものすべてに通じるものであると考える。企業に属している以上、われわれは何かの専門性をもっており、それに関してはプロである。よって、「科学者といての行動」を「自らの仕事」に換言すれば、自らの仕事をに対して誠意を尽くした行動をすること、知識を持っていないものを相手にする際にも嘘を言わず、不利なこともふべて打ち明ける精神が大切である。ということになる。言うはやすしだが実行は非常に難しい。しかし、このように行動することが、結局一番自分の人生を有意義にさせるような気もする。 あとがきにも書かれていることだが、本書を読んで感銘を受けた価値観は
・好奇心を失わず、いい加減な答えでは満足せず、納得がいくまで追求する
・自分の仕事に対して誠意を尽くすこと
の2点である。この価値観が失われないよう、思い出したときに読み直そうと思う。
僕はここで気がついたのだが、彼は数というものの内容を理解はしていないのである。そろばんではいろいろな算術上の組合せを覚える必要は全然なく、あのそろばん玉を押し上げたり下ろしたりすることを学びさえすればいいのだ。
僕は考えるということが愉快でたまらないという人間である。だからこんなにまで人生を楽しませてくれる素晴らしい機械である僕の脳を、壊してしまいたくないのだ。
理論は何もかも丸暗記したものの、それを意味のある言葉におきかえることは全然していなかったのだ。
「いったいなぜ我々は他の国に遅れをとってはならないなどと思わなくてはならないのだろうか?他の国もやっているからなんぞというようなそんな下らない理由ではなく、もっとよい理由、もっと筋の通った理由で科学教育を行なうべきなのです」と言った。そして科学の実用的価値、人間の生きる条件の改善に対する科学の貢献などを挙げた。
男が方程式をよくよく見ると、なるほど間違いが見つかる。そうすると「はじめは何もわかっていなかった相手が、こんなにごちゃごちゃたくさんの方程式がある中で、どうして間違いを見つけることなどできたんだろう?」とふしぎがることになる。彼は僕が問題を一段階ずつ数学的に追っているのだと思っているらしいが、僕は実はそんなことをやってはしないのだ。彼が分析しているものの物理的な例を一つ頭の中に入れておいて、直感と経験からそのものの性質が、ちゃんと分かるだけのことだ。
このカーゴ・カルト・サイエンスで必ずぬけているものが一つあります。それは諸君が学校で科学を学んでいるうちに、きっと体得してくれただろうとわれわれが皆望んでいる「あるもの」なのです。その場でそれが何であるかは取り立てて説明しないけれども、とにかくたくさんの科学研究の例を���て、暗黙のうちに理解してくれるだろうと我々が心から願っている「そのもの」です。ですから今これをはっきり明るみに出して、具体的にお話するのは有意義なことだと思います。「そのもの」とはいったい何かと言えば、其れは一種の科学的良心(または潔癖さ)、すなはち徹底的な正直さとも言うべき科学的な考え方の根本原理、いうなれば何ものもいとわず「誠意を尽くす」姿勢です。たとえばもし諸君が実験をする場合、その実験の結果を無効にしてしまうかもしれないことまでも、一つ残らず報告すべきなのです。
もう一つ、これは科学にとってさほど重大なことではないが、私が信じていることを申し上げたい。それは諸君が科学者として話をしているとき、たとえ相手が素人であっっても決してでたらめを言ってはならないということです。(中略)私が言わんとしているのは、嘘を言う言わないではなく、科学者として行動しているときは、あくまでも誠実に、何ものもいとわず誠意を尽くして、諸君の説に誤りがあるかもしれないことを示すべきだと言うことです。
ファインマンが皆にいちばん心にとめていてほしいと願っておられたのは、ノーベル賞を取ったことでもなければ、論理物理学者であったことでもなく、ボンゴドラムでもマンハッタン計画でもない。僕が好奇心でいっぱいの男だったということ、それだけだ。
とにかく何かにあっと驚き、なぜだろう?と考える心を失わないこと。そしていい加減な答えでは満足せず、納得がいくまで追求する。わからなければわからないと、正直に認めること。これがファインマン先生の信条であり、そっくりそのままの生涯を浮き彫りにしていると思う。
(ケインズがニュートンに対して、)「彼の得意な天分は、頭の中の問題をすっきり解ききるまで休みなく考えつづける能力にあった。彼の直感の力は他の誰のものよりも強く、長く持続した、其れが彼を偉大にしたのだと思う」
彼が多くの語りの中で本当に言いたかったことは、とらわれない発想の価値だと思う。そして、追求の執念の力。読者は彼の語りの行間を読まなくてはならない。
投稿元:
レビューを見る
【読む目的】ファインマンさんの人柄に触れたい。
【感想】好奇心、独特なくだけた口調、体制に屈しない姿勢、
読んでいて目が回るほどおもしろかった。
彼は常にテーマをもうけて学び徹底して体得している。
投稿元:
レビューを見る
上を読んで、下は読むか迷っていたけど、結局読んでしまった。
読むにつれて引き込まれていく。
特に最後の章「カーゴ・カルト・サイエンス」はすごくいいことがたくさん書かれているので線をたくさん引いた。
P.50
そのギリシャ人の学者が、ここで発見したことは、この国の学生はギリシャ語を学ぶのに、まず字の発音から始め、単語、分、段落というふうに進んでいくのだということだった。彼らはソクラテスの言ったことを一言一句間違えずに全部暗証することはできたが、そのギリシャ語の言葉が実際に何か意味を持っているのだ、ということには気がついていなかったのだ。学生にとってそれは、ただの人工的な音に過ぎなかった。学生が本当にわかるような言葉で、それを解説してくれる者は誰もいなかったのだ。
P.254
亭主というものは、いつも女房が間違っていることを証明したがるものだ。そして彼は世の中の亭主の常ながら、やっぱり女房が正しかったのだということを発見したわけだ。
P.294
つまりこのえせ科学は研究の一応の法則と形式に完全に従ってはいるが、・・・何か一番大切な本質がぽかっとぬけているのです。
ただ私の見るところでは、このカーゴ・カルト・サイエンスで必ず抜けているものがひとつあります。それは・・・暗黙のうちに理解してくれるだろうとわれわれが心から願っている「そのもの」です。・・・「そのもの」とはいったい何かといえば、それは一種の科学的良心(または潔癖さ)、すなわち徹底的な正直さともいうべき科学的な考え方の根本原理、いうなれば何をもいとわず「誠意を尽くす」姿勢です。たとえばもし諸君が実験をする場合、その実験の結果を無効にしてしまうかもしれない問いことまでも、ひとつ残らず報告すべきなのです。・・・
諸君に第一に気をつけてほしいのは、決して自分で自分を欺かぬということです。己というものは一番だましやすいものですから、くれぐれも気をつけていただきたい。自分さえだまさなければ、ほかの科学者たちをだまさずにいることは割りにやさしいことです。その後はただ普通に正直にしてればいいのです。・・・
もうひとつ、・・・うそを言う言わないではなく、科学者として行動しているときは、あくまでも誠実に、何ものもいとわず誠意を尽くして諸君の説に誤りがあるかもしれないことを示すべきだということです。
投稿元:
レビューを見る
カーゴ カルト サイエンスの章だけでも良いから読んで欲しい。YouTubeにあるジョブズのスピーチが良いと思うなら是非。
投稿元:
レビューを見る
科学的な考え方の根本原理、「何ものもいとわず誠意を尽くす」姿勢。「自分で満足のできる仕事」を。
他の人々が諸君の仕事の価値を判断するにあたり、その評価を特定の方向に向けるような事実だけを述べるのではなく、本当に公正な評価ができるように、その仕事に関する情報を洗いざらい提供すべきである。
決して自分で自分を欺かぬことです。
投稿元:
レビューを見る
20100425
この忙しいというのに上巻を読んだがために下巻まで手に取るはめになった不幸な読者を裏切らない内容。
投稿元:
レビューを見る
ネタが絶えない物理学者、R・P・ファインマンさんの自伝です。
リオのカーニバルで太鼓を叩いたり、オーフェイという画家として絵を最高200万ドルで買われたり、色々なことをするもやっぱり物理を拠り所とするお茶目な彼の話は読んでいて飽きません。
投稿元:
レビューを見る
上巻に続いて大人げない大人のファインマン教授の話。
日常生活で当たり前のように受け止めていることをおかしいと感じる力だったり、それを素直に伝える力だったり、非常に興味深かったです。
最後のカルテックでの卒業講演の話はファインマン教授の思想が詰まったものだと思うので、この部分だけでも読んでみてください。