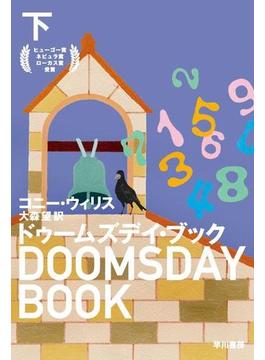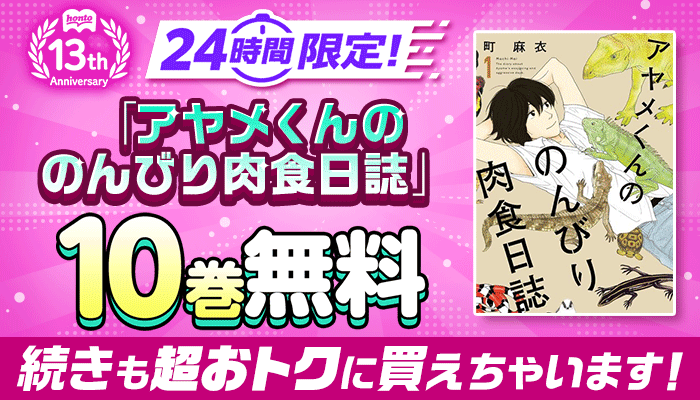ドゥームズデイ・ブック(下)
著者 コニー・ウィリス (著) , 大森望 (訳)
〈ヒューゴー賞・ネビュラ賞・ローカス賞受賞〉中世にタイムトラベルした史学生キヴリンの身を案じるダンワージー教授は、未来で奮闘をつづけるが…… 21世紀のオックスフォードか...
ドゥームズデイ・ブック(下)
商品説明
〈ヒューゴー賞・ネビュラ賞・ローカス賞受賞〉中世にタイムトラベルした史学生キヴリンの身を案じるダンワージー教授は、未来で奮闘をつづけるが……
21世紀のオックスフォードから14世紀へと時をさかのぼっていった史学生のキヴリン。だが、彼女が無事に目的地にたどりついたかどうか確認する前に、時間遡行を担当した技術者が正体不明のウイルスに感染し、人事不省の重体に陥ってしまった。彼女の非公式の指導教授ジェイムズ・ダンワージーは、キヴリンの無事を確かめるために、新たな技術者を探そうと東奔西走するが!? ヒューゴー賞・ネビュラ賞・ローカス賞を受賞したウィリスの感動の大作。 /掲出の書影は底本のものです
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
小分け商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
この商品の他ラインナップ
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
面白くて面白くて・・・
2013/10/14 20:08
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:あんず86 - この投稿者のレビュー一覧を見る
人がばたばた死んでいくかなり悲惨な話?読むには覚悟がいる本…と思いましたが
結果をいうと全くそんなことはありませんでした。
反対に、これほど読むのをやめるのがつらい本はついぞなかった。
時間さえ許せば、ずーっと没頭していたかった。
事実、読んでいるあいだ家のなかのことはあとまわし状態^^;
なぜ私はあの時あの場所にいて、なぜあのように行動したか——その意味は時間がつけてくれる、きっと。死んでみて初めて、悲しむ人の数で人の真価がはっきりするように。
2003/08/06 19:22
1人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:中村びわ(JPIC読書アドバイザー) - この投稿者のレビュー一覧を見る
SFの話ができないものだから、アリソン・アトリーを出してきたり、ページを繰る手を止めさせない手腕は、かのJ・オースティンばりかな…などと、他ジャンルの少ない持ち駒のなかからの発想になってしまう。
けれども、この本はあの本より面白いとか優れているといったランクづけは苦手である。もちろんどうしようもない本に行き合うこともあろうが、こと作家のもつ個性が感じ取られる場合には、身をしばしその人の揺籃に預けて夢見るより他にない。気持ちよければ、いずれにも価値(その時々の私が好ましいと感じるもの)があると思うから、順位というのはどうでもいい気がする。
それでも比較対照は、読み手として積極的に本を堪能するためには有効だ。互いの特徴を分析することで見えにくいものが見えてきたり、言いにくいことを言い得たりする場合がある。
作家ウィリスが本書で進行するドラマを2つのままにしたことにも、その比較対照の効果である。女子大生ギヴリンが行き着いた14世紀のドラマに力点を置いて壮大な仕掛けにすれば、ももちろん読みごたえある小説に仕立て上げることが可能だ。だが、作家はギヴリンを『時の旅人』のような時間旅行者にはしなかった。そこには二重の意味が読み取れると私は思う。
ひとつは、14世紀を代表する王とか貴婦人、領主など名の通った人びととは接触させず、オックスフォードの町近郊の小さな村にヒロインを派遣するという設定。そこには、「○○年の戦争では、死者が数十万人に達した」という1行で言い表さざるを得ない「歴史的記述」への物言いがあると思う。
歴史というものは大きなうねりを中心に書き表され、うねりの象徴となる英雄たち一握りのものであるかのように伝承されてきた。英雄主義的なものから庶民へ、それも抑圧された下層民や女性への視点の転移は、網野史学を想起させる。
庶民一人ひとりがどのような宗教心で教会の教義を支えていたか、そこから来るモラルで社会をどのように成立せしめていたか。また、生活のどのような不便が技術への需要となっていったか。エリザベス女王の王冠に意匠された真珠の数よりも、生活の変遷を知りたいと私たちは時に思う。ウィリスはそれに応えている。
いまひとつ、ギヴリンに村の人びとの介護者としての役割を与え、彼女の存在する21世紀の半ばと旅先の14世紀に広がる病災に対し、人間の成し得ることを問うた点である。ペストほかの伝染病による危険度が高い中世を旅するに当たり、ギヴリンは予防接種を受ける。しかし、薬品や注射器などは持ち込まない。歴史に影響を与えてはいけないという時の旅人のルールに従い…。わずかに、記録のための小さなレコーダーを骨に埋め込んではいるものの。
そして、ごく短い期間ではあるがお世話になった人、心を通わせた人たちのために、いかな科学の助けもなく、素手で病災害に立ち向かう。このとき、彼女がやってきた世界ではあっけないほどに人が死んでいくのに、彼女が手をかけた人たちは
意外にもしぶとく生きながらえる。科学的ではない良薬を彼女の魂の中に託した作家の思いは、現代の様々な技術や社会現象へとつづいているかのようだ。
「萌え」を感じた登場人物たちの魅力を書く余裕がない。テーマか、技術の卓抜さか、人物像の織り成すドラマか、ここには私自身の比較対照が働いてしまった。