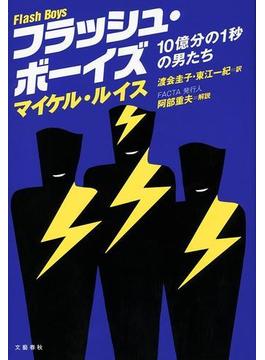一気読み必至の傑作!
2015/08/25 12:43
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:A - この投稿者のレビュー一覧を見る
電子化された証券取引の陰で、高速回線等を利用した、高頻度取引業者と呼ばれる業者が暗躍していることを暴いた男達に焦点を当てたノンフィクション。
あまりに信じがたい内容で、しばらく読み進めた所で、マイケル・ルイスがフィクション作家に転向したかと思って著者略歴を確認してしまった。
同作者の「世紀の空売り」と比べると、高頻度取引業者=悪という図式がやや単純すぎるきらいはあるが、その分リーダビリティは図抜けている。
徹夜覚悟で読むこと。
翻訳がしっくりこない
2016/01/30 04:13
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:エトワール - この投稿者のレビュー一覧を見る
翻訳が昔の小説みたいな感じで読んでいて少し違和感を感じるところがありました。また、途中で翻訳者が変わっているようで、その点でも統一感がないように感じました。そういう点を除けば全体的には面白い内容だったと思います。ただし途中理解しにくいところが多々ありましたけど。
表紙デザインがダサい
2018/07/14 22:41
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ぴょん - この投稿者のレビュー一覧を見る
株の超高速取引をテーマとしたノンフィクション。
出版されてから年月も経過したので、更に手口は進化していることでしょう。
FXの店頭取引など、業者側からの告発本の出版があれば面白そうです。
投稿元:
レビューを見る
証券取引所のシステムまでの距離の差で出てくる、ミリ秒やマイクロ秒の遅延を利用して注文を先回りすることで無リスクの儲けを出す超高速取引業者。一般投資家は知らないうちに利幅を掠め取られていた。そのからくりを白日の下に晒そうと挑む弱小投資銀行のカナダ人を主役にしたノンフィクション。文句なく面白かった。サイドストーリーのロシア人プログラマーの話も良い。
投稿元:
レビューを見る
【電子化された市場は巨大な詐欺の現場になっていた】なぜか株を買おうとすると値段が逃げ水のようにあがってしまう。その陰にはナノセカンドの差で先回りするフラッシュボーイズがいた。
投稿元:
レビューを見る
ドキュメンタリータッチ。ストーリーは面白い。
半分くらいに端折れると思う。
今まで知らなかったことを知れたという意味では良かった。
投稿元:
レビューを見る
本書はシカゴーNY間の光ケーブルを敷設しようとするダン・スパイヴィの話から始まる。
本来であれば、シカゴーNY間の信号は12mSで伝わるはずなのだが、実際は14.7−17mSかかっている。これは光ケーブルがまっすぐ引かれていない(山脈を迂回したりする)ことによる。2008年終わりにこのことに気づいたダン・スパイヴィはスプレッド・ネットワークス社を設立し、2010.3にまっすぐなケーブルを引き、月30万ドルで募集をかける。五年間のリース契約で1400万ドル,これを200のトレーダーに売ったが、あっという間に売り切れた。数ミリ秒速くマーケット情報を入手することにどういう意味があるのか?
実際、我々がNYSEやナスダックと呼んでいる市場はあちこちのサーバーが集まったものである。売買の注文のほとんどはダークプールと呼ばれるローカルな板でマッチングされ、残りは各サーバー間に振り分けられる。
超高速トレーダーは、サーバー毎に微妙に呼値に差がある(と、いっても0.01ドル)ことを利用してさやを抜いたり、フロントラニング(大口の買いが出たことを察知すると、先回りして他のサーバーの売り板を自分で食い、少し高めの売値で出す)したりする。
こうした行為により、年金基金など機関投資家は、本来買えるべき価格よりも高い価格で買わされており、3−4%ほどの損になっているんだとか。
個人的にはこれはルールにのっとった行為であり、責められるべきとは思わないのだけど、こうした「不正行為」をゆるさないためにIEXという新興市場が作られた経緯が後半で語られる。
しかし、マイクロ波を使ってシカゴーNY間のより高速な通信網を構築しようとする動きもあり、超高速トレーダーとの戦いはまだまだ終わらないのであった。。。
*クオンツ、というとインド人のイメージだったのだが、最近はロシア人ばかりらしい
投稿元:
レビューを見る
日本の高速取引も非常に恐ろしい。取引所や金融監督所轄が天下り先として、高速ブローカーを利用しているのではないか、また東証の意味不明な小数点以下の取引は、そのための高速ブローカーに対する便宜供与なのだろうと、例によって推測される。マイケルルイスの傑作!
私も以前は取引担当者だったので、フロントランニングの立場や誘惑がよくわかるつもりである。技術や取引方法がわかれば、非常に恐ろしい、取引の公正さが脅かされる由々しき問題である。ダークプールも問題だが、取引所がこのような不正に手を染めるとは。信じられないし、モラルの無さにびっくりしてしまう。
投稿元:
レビューを見る
『マネーボール』や『世紀の空売り』などのノンフィクションの名作を世に出してきたマイケル・ルイスの新著。既作と同様、関係者への丁寧な取材によって得た情報に基づき、当事者の目線にて出来事と心の動きを時系列に沿って進める手法は健在。どうすれば、次にどうなるのか気にさせて読者をひきつけることができるのかを知っている。
物語は、シカゴとニューヨークをできるだけ最短距離の光ファイバーで結んでしまおうとするプロジェクトの描写から入る。工事をしている人は何のためにこんなことをしているのかわからない。このプロジェクトを進めるものだって、なぜ早く通信できることで超高速取引業者が金儲けができるのかわからない。この物語の底にある異常さを示す象徴的なエピソードだ。
主役はウォール街では二流の銀行であるRBC(カナダロイヤル銀行)のトレーダーのブラッド・カツヤマ。超高速取引業者が市場からノーリスクで投資家から皮を剥ぐように利益を得ている仕組みを明らかにし、公平な取引環境を市場に取り戻すべく、クセのある仲間とともに新しい取引所であるIEXを開設する。
彼らが、分析やIEXの運用を通して明らかにしたことは、超高速取引業者だけでなく投資銀行や取引所もその分け前を預かることになる複雑な取引システムだ。簡単に言うと複数の取引所の間で、最も早い取引所から情報を得て、その取引がまだ届いていない取引所に先回りをして(フロントランニング)、有利な取引をしてさや取りをするというものだ。もちろん、その仕組みは実際にはもっと複雑だが。
数年前、ロシアの大陸を経由して日本と欧州をつなぐケーブルが、今までの南回りの海底ケーブルを通るルートよりも速いので金融系の会社での需要があると言っていたのが、数msの違いでなぜ?と疑問だったのだが、そういうことだったのかと腑に落ちた。
ブラッドの立ち上げた取引所は、ゴールドマンサックスが味方に付いたことで成功を収める。ゴールドマンサックスは、彼らが超高速取引業者に対してこの分野で優位に立つことができないという事実と、複雑なアルゴリズムによる超高速の自動取引による市場のクラッシュのリスクを合理的に判断したがゆえにブラッドの側に付いた。超高速取引業者を捕食者(プレデター)と呼んだが、その食物連鎖の頂点に立つのはいつも彼らなのかもしれない。
光ファイバーの敷設で始まった物語は、光ファイバーよりも速く通信できる可能性がある無線通信を行うための鉄塔の話で締め括られる。鉄塔建設の申請がなされたのは2012年7月、IEXが運用を開始したのは2013年10月だ。新たないたちごっこがが始まるのか、それとも公平な市場が築かれつつあるのか、この世界はそれほどシンプルではないよ、というメッセージなのかもしれない。
金融の世界がわからなくても(自分も分かってない一人)、人間模様の物語として面白く読める。さすがマイケル・ルイスの安定感あり。
投稿元:
レビューを見る
僕からしてみればウォール街なんて何が起こっているか全く想像つかなかったけれども、こんなイカサマが行われていたなんて!という驚きと共に、ウォール街の取引システムに関わる技術者がどんな人たちか知ることができる。
(一応)ITに関わる者としては、第8章「セルゲイはなぜコードを持ち出したか?」は特に興味深い。
投稿元:
レビューを見る
専門家が現在可能な最高の仕事を自ら見つけたことから、そのあとの仕事が激変した。
人間には理解できないスピードの話しだ。
全人類から1円でも集めれば、10億円近くなるのと同じ原理だ。損してるようには感じないが、気づいてしまうと腹が立つ。新たな市場の始まりというのは、最初の人間が得をするのだから、健全といえば健全だけど、だれにもコントロールできなくなるのは、許せない。
投稿元:
レビューを見る
LIBOR・TIBOR問題に引き続き、「やはり」という業界の倫理問題。シリアスな内容だけに、メディアでの取り上げも国内ではあまり目立ってないようだ。出版が金融系ではなく、文芸春秋からというのもやはり・・・というか。
そもそもこういう膿を、金融各社のリスク管理部門は見つけていないのだろうか?大手投資銀行・証券会社の内部監査・法務・コンプライアンス部門では高級取りを大勢抱えているはずだが、こういう大きなネタには手を付けないのか、本当に知らずにいるのか?監督庁から業界への天下りは問題が大きいことの証も描かれている。
投稿元:
レビューを見る
株式市場で横行する超高速取引(HFT)に対し、公正な市場を作るためにIEXを立ち上げたブラッド・カツヤマ氏が主人公のノンフィクション小説。著者はこれまでも金融関連のノンフィクション小説を書いてきた方。「超高速取引」について知りたかったので読みました。
市場を先回りして利益をさらっていく高速トレーダー、取引内容が外部から見えないダークプールを作る投資銀行、データセンターのすぐ傍のスペースをHFT業者に売る証券取引所と、システムの隙を見つけてお金を稼ぐ能力に驚くばかりです。
それに異を唱え、仲間たちと一緒に立ち向かっていくブラッドのドラマもかっこよく、途中でフィクションなのかノンフィクションなのかわからなくなるほどでした。
投稿元:
レビューを見る
久しぶりに途中から飽きてしまい流し読みになってしまいました。内容的にはコンマ数ミリ秒の速さで株取引の覇権を争う成金たちの戦いを描いた作品で、アメリカには金を稼ぎたい(儲けたい)一部のクレイジーな人間がこういう世界に集まるのだなぁと驚きでもありました。株取引システムの仕組みを制する者が株取引の世界を制するという図式なのですね!
投稿元:
レビューを見る
タイトルの名前から連想するのは戦隊モノのヒーローかと思うがそうではなかった。あの金がうごめくウオール街が舞台になっている。著者は、「マネー・ボール」などで有名なマイケル・ルイス。
ニューヨークの証券取引所で人がいろいろやり取りしている姿をニュースで見ることがあるが、今の時代に重要なのは機械、しかも素早く売買できるシステムを持っていることだ。個人投資家には到底勝ち目はない。
この本を読んで初めて「超高速取引業者」という存在を知った。1秒でも早く売買できるシステムを構築して他の奴らを出し抜いて一儲けしてやるぜとなかなか鼻息の荒い人たちだ。
取り締まるはずの機関や証券取引所も取り締まりに精を出すどころか、おいしい御馳走を食べる側に回ってしまっている始末。「証券ムラ」か。この本が発表された今年の3月末には、業者やナスダックは知らぬ存ぜぬの対応をしたとある。
今日も1秒を争って我先にアクセスして儲けてやるぞと、戦っている人たちがいるのかな。自分たちだけおいしい思いをするなんて、そんなの「だめよ、だめだめ!」と言いたい。