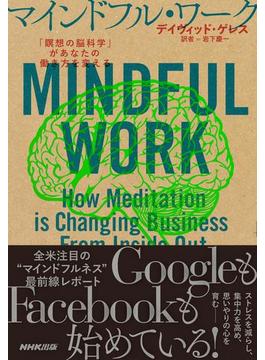( ^-^)ノ∠※。.:*:・'°☆
2017/03/15 20:50
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:はるにゃん - この投稿者のレビュー一覧を見る
はじめは、期間限定価格だったので読んだのですが、読み始めたら、結構役に立てそうなことがたくさん書いてあって満足です!(^_^)
マインドフルネスへの称賛。そしてアメリカでの現象の取材。
2016/01/24 18:34
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:たまがわ - この投稿者のレビュー一覧を見る
圧倒された。
アメリカの主にテクノロジー企業などで、近年マインドフルネスが急速に広がっていく現象について、取材した本。
著者自身がそもそも、大学時代から瞑想に親しんでおり、フィナンシャルタイムズとニューヨークタイムズの経済記者として活動していた。
そのため、著者は基本的にマインドフルネスに対しほぼ全面的に肯定・称賛の思いを持っているようだ。
『マインドフルネスの実践により、私たちは集中力を鍛え、意識を安定させ、
ずっと長く穏やかなままでいるようにトレーニングできるのだ。
ジムでバーベルを持ち上げて筋肉を鍛えるように、瞑想は私たちの心を鍛え、安定させ、
一つに集中できるようにしてくれる。(中略)
この安定した集中力は、計り知れないほど価値のある能力となる。』
『一五年間マインドフルネスを見続けてきて、例外はあるにせよ、瞑想が人を悪い方向に導くことは
ほとんどないとも断言できる。マインドフルになった人は、より幸福に、健康に、そして優しくなる。』とも言っている。
だが私は、瞑想の効能については本書の見解におおよそ賛同するが、基本的に瞑想は非常に危険の伴う難しいものであると思っているし、
また、瞑想を行う場所についてもとても気を使う必要があると考えているので、そのような点で、
著者の認識とアメリカでの流行現象は、楽観的・短絡的な面が過ぎると感じた。
本書では、マインドフルネスを取り入れた企業や人が、いかに良い方向に変化したかの実例が、数多く紹介されている。
著者自身も、妻と実家で、とあるイースターの週末を過ごしていたとき、二つの大手製薬会社のM&A話、それに絡む他紙のスクープ記事情報などで
振り回されたが、マインドフルネスを実践していたおかげで、その間、仕事のことで無駄に悩んだりせずにやるべきことをやり、
家族との時間に集中して、リラックスしながら楽しんで過ごすことができたという。
また、オハイオ州のライアン下院議員は三〇代後半に、働き過ぎから慢性的な疲れに悩まされるようになり、体重も増えた。
支持者が知る陽気な彼は影を潜め、同僚や友人に対する刺々しい態度が目立つようになった。
だが二〇〇九年、瞑想を日常的に始めると、ライアンは角が取れて穏やかになった。
数か月のうちに、自分の行動に思慮深くなり、スタッフにさえ気遣いある行動をするようになっていた。
マインドフルネスが自分に思いやりの心をもたらしていたことに気づいたのは、しばらく経ってからのことだった。
そして彼は、数年間のマインドフルネス実践のあと、これまでの発見を『マインドフルな国家(A Mindful Nation)』というタイトルで、
本にするまでになった。引きずり落とす格好の材料にされることを覚悟の上で。
著者も、
『思いやりの心は、マインドフルネスになるに従って無意識のうちに湧いてくる。
真面目に瞑想を続けていれば自然に生まれる副産物だ。』と言う。
仏教的瞑想がアメリカで取り入れられ、今日に至るまでの歴史の話なども読み応えがあり、面白かった。
マインドフルネスが脳に与える好影響の科学的な解説などは、少々物足りないと感じた。
また、近年の現象について様々な方面からの批判的な見解についても、紹介されている。
それにしても、キリスト教国のアメリカで、更に合理的・実用的風潮が強いであろうテクノロジー企業群で、
これほど急速に、仏教の瞑想法から宗教色を排除したマインドフルネスが広がっていく様は、アメリカ文化の、
進歩と変化に対する貪欲な姿勢が見られるようで、衝撃を受けた。
投稿元:
レビューを見る
GoogleやFacebookといったよく知るテック企業の名前が帯にあることが、本書の敷居をいくらか低くしているものの、読み始めるまで、あるいは読み終えるまで「マインドフル」「瞑想」といった怪しげな言葉からくる不信感はなかなか払拭できないのではないでしょうか。もちろん私もそうでした。(読み終えて分かりますが、裏帯にあるGoogle,LinkedIn,Huffington Postのエグゼクティブ達のコメントはどれも正確です)
著者は瞑想の実践者ですが、NYタイムズのビジネス・ファイナンス分野を専門とする記者であり、スピリチュアルな要素や宗教性がいくらか緩和されているかと期待して読み進めましたが、実際その点は期待どおりでした。
宗教的なルーツを否定はしないものの、科学的な根拠を提示しながら、手法や効果について紹介されています。
マインドフルネス瞑想の効果は、種々の研究で明らかになっているようですが、まだ自分で実感したわけではないのでまだ分かりませんが、少なくとも「やってみよう」という気持ちが湧いてくる内容です。
「ストレスに対して反応的になるのではなく、ある事象に対してそれをどう扱うか、どう捉え選択をするか?」みたいなことは、アドラーやコヴィーなども同じようなことを書いていたような気がします。
仏教的思想に基づくトレーニングの実践者になるには、シリコンバレーの皆さんよりも、日本人の私の方がいくらか精神的に近いところにいて、少し有利なのではないかと思います。マインドフルネス瞑想やヨガ(こっちはダイエット的なものも意識して……)を身につけて働き方、人との接し方、自分との向き合い方を少しずつ変えていきたいです。
<目次>
イントロダクション
第1章 マインドフルな瞬間
第2章 白鳥は舞い降りた
第3章 瞑想の科学
第4章 ストレスを軽減する
第5章 集中力を取り戻す
第6章 思いやりの心
第7章 企業の社会的責任
第8章 リーダーシップに活かす
第9章 マクマインドフルネス
第10章 マインドフルネスの未来
付録 マインドフルネス瞑想のやり方
投稿元:
レビューを見る
「瞑想」というと、どうしても宗教的な”胡散臭さ”を感じて、一部の著名な経営者やスポーツ選手など、激烈なストレス環境下にある人だけが行う「特別な世界」のものだと思っていた…本書を読むまでは。
瞑想によって得られる「マインドフルネス」とは、過去の呪縛や未来への不安から自己を解放し、思考を保留して「今、ここにいる自己」をありのままに許容することによる「心の気づき」である。マインドフルネスは様々な研究機関によって、ストレス低減や集中力向上、さらには他者への慈悲の心を育むことが科学的に実証されており、Googleやパタゴニア、フォードといった名だたる企業が社内研修として組織的に瞑想を取り入れ、生産性向上だけでなく社会的責任にも役立てているという。
一方で、マインドフルネスをお手軽な自己研鑽商品として売り込んだり、単なる「従順な社員」の育成を目的に導入する動きへの批判もあり、著者は、急速に拡大する需要に対して、供給サイドに一定の質的・量的な安定をもたらす必要性を説く。ジャーナリストの立場から極めて中立的に書かれていて納得感が高く、誰でもすぐに実践できる解説つきで実用性も高い一冊。
投稿元:
レビューを見る
近年、瞑想は、「マインドフルネス」という呼び名で、世界中に広まっています。グーグルなどの世界的企業のエグゼクティブたちが瞑想を習慣とし、職場にも取り入れています。
本書は、経済記者である著者が、中立的立場から、瞑想がいかに働く人々や組織に影響を与えるのかをまとめた一冊です。
詳細なレビューはこちらです↓
http://maemuki-blog.com/?p=6555
投稿元:
レビューを見る
最近つとに増えてきたマインドフルネス本。「born to run」とか「脳を鍛えるには運動しかない」の本を推してた人からの次はコレ的な感じなんで、試しに読んでみた。自分も一時期、ヨガから瞑想をかじっていたが、結婚してから全くご無沙汰。この本にある通り宗教色を抜いた脳と心の静寂のための瞑想の心地よさは多くの人に知ってもらうのはとても良いことだと思う。一時のブームに終わらないことを願う。
投稿元:
レビューを見る
こういったムーブメントがあること自体を知らなかったので、まずこんな大きな動きであるということが驚きであった。
感覚的には個人的に考えた場合、自分の考えをまとめる、感情を鎮める、その瞬間に集中する。自分他者を思いやるというのは非常に重要なスキルだし、たしかにいまの情報過多の状況で目のまえのことに集中するということの重要性はつねに感じる。
ランニングやホットスパなどで少なからずこういった時間を持っていたが、もう少し意識して自己に集中する時間を持とうと思う。
欧米人に比べれば、日本人としては非常に受け入れやすい考え方だと思う。
投稿元:
レビューを見る
マインドフルネスの効用と米国での受け取られ方を知るための本である。宗教ではなく科学に基づくツールとしてのマインドフルネスとそれを支える慈愛のココロの大事さについて米国の企業での導入の例を通してレポートしたのが本書である。
仏教と切り離されて広まる事で様々な解釈が生まれているヴィパサナー冥想とマインドフルネスであるが、本書の定義はキリスト教をベースとした人々から見た見方であることには注意が必要である。サンガというものの存在自体に全く触れていない。無宗教と言う名前の神道と形ばかりの葬式仏教からの視点に比べれば分かりやすいとも言えるのだが。
第三次産業のさらに上を行く第四次産業とも言えそうな、クリエイティブ産業では、より深いコミニュケーションがその成功の鍵である。第三次産業では、ブラックボックス化してコミニュケーションを減らす方向で対処していたのとは全く逆のアプローチである。その効率化のためにマインドフルネスに目をつけるというのは発想としては正しい。
一点気を付けなければならないのは、この取り組みには終わりはないということである。常に学ぶ姿勢が必須である。良くなったからもういいというスタンスではより悪くなる可能性すらある。釈尊もこの点には言及しており、間違い易い点でもあり、私もこの間違いをしたので書き記す。
ビジネス書としても今までにはないアプローチなので面白いはず。
投稿元:
レビューを見る
瞑想の本。
Googleなど、今世界に代表する様々な企業に、生産性向上のために瞑想が取り入れられているという事実と、瞑想の科学的メカニズムの説明が記載の99.9%。
最後の数ページに実際の瞑想のやり方が書いてある。
99.9%を読破すると、瞑想、やってみようか、と思うようになる。
投稿元:
レビューを見る
仕事はどんどんマインドフルになって行くのかなという気がします。概要と研究結果はよくわかる。
もう少しマインドフルネスの実践例があると良かったが…
投稿元:
レビューを見る
マインドフルネスの効能を全編にわたって書き連ねてある。自分の中ではマインドフルネス=瞑想と思って読み進んでいたが最後にマインドフルネスは瞑想じゃありません、と書いてあってちょっと肩透かしを食らった感じ。日本で言えば禅、中国で言えば気功のような位置づけ、かな。マインドフルネスでは「過去」でも「未来」でもなく「今」を味わい尽くすことが大切。非常に共感出来るし、世の中がその方向にシフトしつつあるのならとても興味深い。ただ個人的には「身体」へのアプローチが少し物足りない気がしました。
投稿元:
レビューを見る
[図書館]
読了:2016/1/1
思いやり、共感、愛…こんなものがあふれているビジネス本なんてないよなぁ…と、これを読み終わった後にかつて買った「2000人調査から分かった!いる社員、捨てられる社員」という本を手にとってパラパラめくりながら思った。
p. 183 ダン・ハリスが「怒り」について「毒素が血管を駆け巡るあの感じ」と表現しているのにとても共感した。
3章、fMRIの開発によって脳の動きがリアルタイムに把握できるようになり、ダライ・ラマのような宗教指導者と脳神経科学者たちの知識と経験が融合していく様が面白かった。
この本でも「扁桃体によるハイジャック」の話が出てきた。
投稿元:
レビューを見る
瞑想や禅は人間の脳の筋トレになる。フィジカルを運動で、メンタルを瞑想で、スキルを仕事を通じて心技体バランスよく整えることが、成果を出すためで重要。自己流の瞑想をやってきたけどあらためて理論的背景がわかる。
投稿元:
レビューを見る
瞑想が持つ、宗教的・スピリチュアル的要素をどこまで削いで、科学的効用を引き出すかというトライアルの現場がわかる一冊。
投稿元:
レビューを見る
マインドフルネスの研究本と言っても良い。マインドフルネスの歴史、現在で活かされている手法、活用例、そしてこれからのマインドフルネスについて書かれてあります。マインドフルネス入門本として、雑学も含めて知りたい人にオススメ。