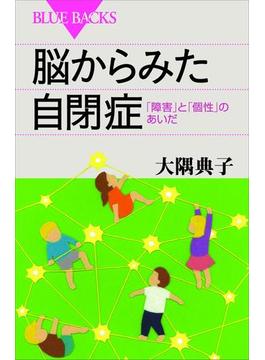まだまだ原因が特定されていない「自閉症」について解説した画期的な書です!
2020/01/29 09:58
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ちこ - この投稿者のレビュー一覧を見る
本書は、学問的な知識がわかりやすく理解できると好評の講談社「ブルーバックス」シリーズの一冊で、同巻は「自閉症」について考察した書です。現在、メディアなどで盛んに言われるようになってきた「自閉症」という症状ですすが、現在の医学では、まだ、なぜそれが起こるかが完全には分かっていません。ただ、脳ができあがるまでのほんのちょっとした「バグ」で起きるということは推測されています。では、どんな「バグ」が自閉症を引き起こすのでしょうか。同書は、第一線の研究者が最新の研究成果をもとに、「自閉症」について、やさしく解き明かしてくれる画期的な書です!
投稿元:
レビューを見る
内容紹介
自閉症と診断される人の割合は、40年前には5000人に1人でしたが、2014年には68人に1人と、約70倍に増えています。
「アスペルガー」「大人の発達障害」という言葉もよく話題にのぼるようになり、いまや自閉症はごく身近な障害といえます。
しかし、自閉症にはいまだに多くの誤解や偏見がつきまとっています。
「親の育て方が悪いと自閉症になる」「親が自閉症だと子も自閉症になる」「三種混合ワクチンを接種すると自閉症になる」……これらは明らかな間違いであり、誤りの原因は、
自閉症という障害がなぜ起こるかが知られていないことにあります。
自閉症は、脳ができあがるまでのほんのちょっとした「バグ」で起きます。
脳ができあがるプロセスは複雑をきわめていて、無数の「罠」に満ちています。実は誰の脳にもバグがあり、
「完璧な脳」など、どこにも存在しないのです。では、どんなバグが自閉症になるのか?
第一線の研究者が最新の研究成果をもとに、やさしく解き明かします。
目次
第1章 自閉症とは何か
第2章 脳はどのように発生発達するのか
第3章 ここまでわかった脳と自閉症の関係
第4章 自閉症を解き明かすための動物実験
第5章 自閉症を起こす遺伝子はあるのか
第6章 増加する自閉症にいかに対処するか
著者について
大隅 典子
神奈川県出身。1985年東京医科歯科大学歯学部卒業。1989年同大学大学院歯学研究科修了。東京医科歯科大学歯学部助手を経て1996年国立精神・神経センター神経研究所室長、1998年東北大学大学院医学系研究科教授。2006年東北大学総長特別補佐(男女共同参画担当)。2008年から2010年、東北大学ディスティングイッシュトプロフェッサー。
日本分子生物学会理事長。専門は神経生物学(神経発生学・発生発達神経科学)。脳の発生・発達の観点から人間の心のなりたちを理解しようとする研究を展開し、特に精神疾患にまつわる問題への関心が高い。
投稿元:
レビューを見る
多くの偏見の中にある(私にもありました)自閉症について、生物研究の先端の動向を織り交ぜて解説されており、私の古い遺伝研究のイメージが大きく刷新され、膝を打つ部分がたくさんありました。ちょっとセンチメンタルですが、中高生の頃、ブルーバックスをたくさん読んでいた時の感触がよみがえるような感じをもちました。
投稿元:
レビューを見る
副題は「「障害」と「個性」のあいだ」となっている。自閉症のあとにはスペクトラムということばがついて、とらえ方の幅が広くなっている。どこまでが「個性」で、どこからが「障害」と言えるのか、その境目もあいまいである。診る人によって判断が異なってしまうのだろう。ただ「うちの子は自閉症なんかじゃない」とかたくなになるより、「まあ自閉症みたいやし、なんとかして」というくらいに思って、援助を受けた方がうまくいく可能性が高い。そういう点は学習障害だったり、ADHDだったりも同じようなことが言えるだろう。自分が見ている子どもたちのなかにも、何とかしてあげられないものかと思う子が複数いる。(どうも小学生の方がそう思わせられるケースが多い。これは年齢が上になると見えにくくなるということなのだろうか。学力の格差はより広がっていくはずなのだけれど。塾に来る範囲の子しか見ていないからか。)より良い方法で接してあげればもっと成長を促すことができるかもしれないのに、と思うことがある。そして、本や新聞で見た実践例を参考にするわけだけれど、もちろん誰にでも効く処方箋があるわけでもなく、日々試行錯誤するよりほかない。本書は自閉症の一般的な話から、脳科学・遺伝子などの基礎事項の確認、そして最先端の話題にまで、非常に分かりやすく話がすすめられている。途中で少し「おいていかれた感」はあったけれど、おおむねついて行くことができた。自閉症の原因は決して一つではない。したがって対処法も多岐にわたる。ひとりひとりをしっかり見つめて対処していかないといけないのだろう。自閉症は増えている。定義の仕方が変わってきたことを考慮した上でやはり増えているという判断だ。その理由も一つではない。その中に、高齢者の精子があげられるようだ。精子をつくる際に遺伝子のコピーミスが起こりやすくなるのだそうだ。結婚年齢の上昇が原因となって来る。いろいろな社会のあり方もつながってくるということが興味深い。
投稿元:
レビューを見る
発達障害=神経発生発達障害 自閉症は、この発達障害に分類される精神疾患。現在は「自閉症スペクトラム(連続体)障害」と呼ぶ。症状=「社会性の異常」「コミュニケーションの障害」「常同行動」「社会性の異常」とは「親とも目を合わさない」「人が指をさした方向を見ようとしない」「まるで耳が聞こえないかのように名前を呼んでも反応がない」他者の心の状態を推測する機能(心の理論)が損なわれると他人の立場で物事を考えることができない。何となくずれたコミュニケーションをとってしまう。人間の脳には、顔や目を優先的に見る性質がある(他の動物も同じ)人間の集団生活に必要な、近くに他人がいることを察知できないと社会生活がうまく営まれない。これらに適応する方向に脳が進化しているので、顔の存在に敏感。自閉症の視線の動きは、人の顔を見る動きより物などに視線が向く。脳の発生発達に関係があるのでは。常同行動には、単なる機械的反復ではなく、「興味の限定」という意味合いもある。一つのことを突き詰めてやり続ける、極端な集中力の表れともいえる。感覚の敏感さと運動のぎこちなさ。「サヴァン症候群」=感覚の過剰さ。ADHD(注意欠陥多動性障害)=落ち着かなく歩き回る、貧乏ゆすり、睡眠障害を合併。脳の障害には「器質的」正常な脳の状態との外形的な違いが具体的にわかるもの「機能的」脳の働きに異常がるの二種類。「器質的」は神経内科(パーキンソン病、アルツハイマー病)「機能的」は精神内科「心療内科」心理社会的な原因による身体的な症状を統合的によくする。脳は左右対称ではない。前頭葉は右側がやや大きい、後頭葉は左側がやや大きく、ねじれた感じになっている。男女差もあり、男性のほうが左右の非対称性が大きい。さらに自閉症は健常者よりも大きい。「自閉症の脳は男性化している」女性のほうがコミュニケーションが得意。物を収集するのは圧倒的に男性が多い等。・オキストシン欠損=攻撃性の増加、母子関係の異常、固体認識機能の異常
・自閉症は親から子への遺伝によって生じたものがすべてではない。
ドゥノボ変異=父母どちらかの生殖細胞、つまり精子か卵子が作られるときに、コピーミスによって起きると考えられる変異。この変異による自閉症は3分の1から2分の1を占めている。
・「バックス6」神経発生因子、ここから作られるタンパク質は転写制御因子です。転写のスイッチをタイミングよく押している因子。また、親分遺伝子と呼んでもいい。実行部隊である子分の遺伝子が大勢いて、彼らに号令を出して働かせるのが仕事だから。このバッツクス6遺伝子がまったく働かないと、大脳皮質の厚みが非常に薄くなる。そして、視床から大脳皮質への神経回路が形成されず、小脳も小さくなる。マウス実験で、バッツクス6変異のラットには、自閉症の症状がみられる。
・脳の発生発達における遺伝子の働き方は、まだ多くの謎に包まれている。「自閉症をおこす遺伝子はこれだ!」などという言い方をできる段階に到底ない。
・わずか40年ほどで自閉症が急増。70倍以上。遺伝子の変異だけではない可能性。※遺伝子変異が広まるには数十年では短すぎる。
・「母体環境は脳に影響を与える」母体の栄養が不足していると、子の発生にダメージを与える。とくに胎児の脳が育つ時期の栄養不足は影響が大きい。
・周産期の母体感染。母体からのウイルスで胎児や新生児が感染症を発症。妊娠・分娩を通じて感染する「垂直感染」母乳を通じて感染する「水平感染」など。なかでも、妊娠時に風疹やサイトメガロウイルス感染症に罹ると自閉症や発達障害のリスクが高くなる。
・薬剤:予防接種自体が原因になることない。バルプロ酸(坑てんかん薬)は脳の発生プログラムが書き換えられる可能性がある。
・父親の加齢:15~29歳の時に生まれた子のリスクを1とすると、30歳代は1.7、40歳代では5以上、50歳過ぎは9にまで高まる。
・精子が精子幹細胞からつくられるときに生じるコピーミスは、年齢とともに増える傾向。ドゥノボ変異の原因になる。
・次世代への影響を与えるメカニズム「エピジェネティクス」という現象で、DNAの塩基配列の変化を伴わずに、遺伝子発現や細胞の表現型が変化する現象。父親の加齢によって子供に自閉症が発生した場合、精子にこの現象が起きていることが考えられる。
・「早期発見」を。学習支援による社会適応力を高める。診断は3歳ぐらいの時点でなされる。脳の配線や髄鞘化の多くはこの時期までに完了するが、海馬などでの脳の神経新生は生涯にわたって続くので、学習支援によりニューロンの配線をよりよくつなぐことは可能。・自閉症も「塩基ひとつ」という遺伝子レベルの違いによって発症しうることは、つまり、「個性」のひとつ。
投稿元:
レビューを見る
自閉症は「発達障害」の1つであり、近年、増加傾向があるという。
精神疾患はとかく「わかりにくい」イメージがあるが、その「わかりにくさ」にはおそらく、いくつかの原因がある。
1つは、症状が目に見えず、また数値でも表しにくい点。癌や脳卒中であれば、腫瘍や病変部分がある。高血圧や糖尿病などには、血圧や血糖値など、設定された基準値を外れていれば治療が必要とされる目安となる、測定値がある。心の病の場合、チェック項目があるが、診断者(医師)の主観はどうしても入ってくる。
それから、前の項目とも関わってくるが、「正常」と「異常」、「健康」と「疾患」の間に明確な線が引きにくい点。何となく困難を抱えているが、しかしはっきり精神疾患と言えるほどでもない、精神疾患的な「気質」「傾向」がある。いわゆるグレーゾーンである。極端なことを言えば、誰もがどこかしらに傷を抱える。完璧に異常がない精神は存在しない。身体でももちろんそうではあるのだが、精神の方がより「見えにくい」「線を引きにくい」感がある。
そしてまた、多くの場合、精神疾患は複数のものが重なる。自閉症とてんかん、鬱病と統合失調症、あるいは、自閉症に不安障害に強迫性障害といったように、複数の精神疾患を抱える人は決して少なくない。
こうして考えてみると、精神疾患の「わかりにくさ」は、見えてくるのが主に「症状」の部分で、「原因」の部分が見えにくいことによるのではないかと思えてくる。
足をすりむいたからその傷が痛い、血栓ができたから血流が滞った、というようにはっきり目に見える部分が少ないのだ。
では精神疾患の「原因」はどこか、といえば、もちろん、脳である。
脳で何が起きているのか、疾患(本書の場合は自閉症)が起こるのは、脳のどのような現象が原因なのか、発症の根底に何があるのか。現時点でどこまでわかっていて、どこからわかっていないのかを、脳発生の見地から解説するのが本書の目的である。
著者は、歯学部から、顔面発生学を通じて神経発生を専攻とするようになったそうである。本題に加えて、このあたりの研究遍歴も興味深い。
全体として、ブルーバックスらしく、非常にわかりやすい1冊である。
発達障害に関わるリスク要因は、脳の発生に合わせて、いくつか挙げられる。
神経の単位であるニューロンの産生。その配線。ニューロンとニューロンの連絡部分に当たるシナプスの形成。神経形成の際に補助や調整を司るグリア細胞。過剰なまたは不要なシナプスを刈り取る工程など。
脳の発達に関する基礎研究が進むにつれ、こうした各段階の詳細が判明してくる。
それとともに、自閉症などの発達障害は、それぞれの段階の不具合や不備から生じている場合があることがわかってきている。複数の段階で不備がある場合もあり、不備の程度もさまざまである。
単純にここに不備があるとわかったからといって、薬物等で対処して直ちに改善されるというものではないが、解きほぐす手がかりが掴めるようになってきたのは大きい。
神経細胞同士の連絡は、興奮と抑制によって制御されるが、自閉症でよく見られる「常同行動」(同じ行動をずっと続ける)は、抑制部分が働いていないことを示唆する症状と考えられる。細胞レベルで何が起こっているかがわかってくると、薬剤開発などの糸口になる可能性もある。
脳発生を知る上で役立つ遺伝学の基礎知識も平易に説き起こされている。
「冷たい母親」に育てられると自閉症となる、ワクチンで自閉症になる、といった、自閉症に関する「誤った神話」が明確に否定されている点も、有益な情報だろう。
著者の拠点は東北である。大震災の後、本書が上梓されるまでの経緯を述べたあとがきも読み応えがある。
自閉症に関する一般向けの書籍は数多いと思われるが、基礎生物学寄りの最先端の研究も盛り込んだ本はおそらくそう多くはない。
研究の前線に触れつつ、自閉症への理解を深める点で、格好の入門書である。
投稿元:
レビューを見る
自閉症をはじめとする発達障害は「親の育て方」が原因ではない。基本的には、脳の発生や発達に関するトラブルから起こる生物学的な障害である。ただし、器質的には同じ程度の自閉症であっても、家庭でネグレクトなどの虐待を受けた子供は、そうでない子供に比べて症状が重篤になる可能性がある。
脳の発生や発達に関するトラブルが、なぜ発生するのか。まだ100%解明された訳ではないが、
①異常な遺伝子を受け継いでしまった
②遺伝子のコピーミスが起こってしまった
③胎児の時代の母親の栄養が不足していた
④父親の高齢化による精子の遺伝子のコピーミスが起こった
など、遺伝子の異常がその発生原因と思われるが、特定の遺伝子ではなく、複数の遺伝子の異常の組み合わせが、その原因である可能性が高い
投稿元:
レビューを見る
自分の子供に軽い発達障害が有るので、興味を感じて読んでみた。
肝心の脳を直接、細密に検査する機会が中々得られない為に、医学・医療機器の進歩程には進んでいない現状は有るものの、素人から見れば様々な知見が得られていることを知る機会となる本。
自分は男だが、男性の晩婚化による自閉症発生リスクが高い(理論的にも理解・納得できる説明がある)という点は、"ああ、そうなのかー!"と思わされた。
難解な生化学の説明部分も多いが、要点だけ読もうと割り切れば読める。
いろいろと考えさせられる、ある意味では"重い"本だが、読んで良かった。
投稿元:
レビューを見る
なんとなく、よくわからない自閉症を、
「器質的な原因」で
「機能的な疾患」が出ていることを
わかりやすく、説明した一冊。
遺伝的要因、遺伝子の劣化による原因、発生時の原因など、各ステージに合わせた原因追及をしている。
正しい理解をすることができた。
投稿元:
レビューを見る
専門用語が多いため難しく感じたが、DNAの複製から生命の発生、脳の発生に至るまでとても複雑なプロセスを経て私たちができていることを理解することができた。
その中での沢山のポイントでミスは起きるのだ。起きない方がおかしい。一つのミスが、人の形成に影響を与えている。
発達障害はそうした違い=個性のひとつであって、けして誰かのせいでそうなっているというものではないのだ。
つまるところタンパク質のやりとりの不具合な部分もあるため、薬で症状軽減の可能性もあることを初めて理解できた。今後研究が進み、症状を緩和する薬が増えてきたらいいなと思います。
また、こういった知識が広まり、誤った偏見がなくなり、多様な人が生きやすい世の中になればいいなと思いました、
投稿元:
レビューを見る
タイトルには「脳」と謳ってあるけれど、実際はその中の「遺伝子」が本書の中軸。つまり自閉症における遺伝子の影響は如何なるものかと言うことなのだけれど…。なにせ、著者が「かなり長くなりましたが、これでやっと自閉症と遺伝子の関係を見ていくための準備運動は完了です。」と記すのは245ページ中の193ページ目なのだ。で、本編はほんの数小節、しかもサビの部分である自閉症が増えている理由として挙げられているのは、遺伝子というより、母体環境だの父親の加齢だのといったあまり「遺伝」とはカンケーない要因(しかもほんの数ページ)なんだかなぁ…下手くそな前座の小咄を延々聞かされて、肝心の真打は風邪を理由にすぐに引っ込んじゃった、って感じ。ガマンして聞いてたのに足が痺れただけだった…。
投稿元:
レビューを見る
大隅典子氏は、東京医科歯科大学大学院歯学研究科修了(1989年)、東北大学大学院医学系研究科教授、東北大学副学長を務める神経科学者(神経発生学・発生発達神経科学)。
本書は、自閉症(正式には「自閉症スペクトラム障害」)について、脳科学の立場から、自閉症とは何か、どのような原因で生じるのか、今どのような研究が進んでいるのかを、一般読者にもわかりやすく解説したものである。
私は、古くはダスティン・ホフマンとトム・クルーズが共演した『レインマン』を見、その後、神経学者オリバー・サックスの『妻を帽子とまちがえた男』等の著作、サヴァン症候群といわれるダニエル・タメットの自著『ぼくには数字が風景に見える』、1998年生まれで、アインシュタインよりIQが高く、早くもノーベル賞のホープと言われる、自閉症のジェイコブ・バーネットの成長を母クリスティンが綴った『ぼくは数式で宇宙の美しさを伝えたい』などを読む機会もあったのだが、今般、医学・生理学的見地から「自閉症」について詳しく知りたいと思い、本書を手に取った。
読了してまず感じたのは、まだまだ分からないことばかりの領域なのだということであった。確かに、画像診断や動物実験により、自閉症患者の脳と健常者の脳では、各部位のサイズ、ニューロンやシナプスの形状などに、微小ながらも明らかな違いがある可能性が見えてきており、その原因についても、一部には遺伝的なものがあることも分かってきたというが、専門外の人間から見ると、解明途上の難しい分野という印象が強かった。
一方で、米国のデータによれば、1975年には5,000人に一人の割合だった患者が、2001年には250人に一人、2014年には68人に一人と、40年間で患者数が70倍以上に増加しているといい、その背景には、診断基準・診断方法の変化(自閉症の疾患概念の拡大)や、疾患が広く認知されるようになったことだけではなく、生まれるときの母体環境(女性のスリム願望、低体重出生児の増加、周産期の母体感染など)や、父親の加齢があるという分析は、大いに気になるところであった。
本書を読むまでもなく、自閉症はあくまで個性の一部である。とすれば、自閉症患者の出生割合が高まることを懸念するのも妙な話ではあるのだが、いずれにしても、社会は自閉症患者の個性を、自然に受け入れられなくてはならない。そのためには、本書にあるような情報を、少しでも多くの人びとが共有していくことが大事なのではないかと思う。
(2020年5月了)
投稿元:
レビューを見る
自閉症の正式名称は自閉症スペクトラム障害であり、発達障害(正式には主に胎児期における"神経発生発達障害")の一種である。自閉症の発案者である精神科医ブロイラーは、"自閉"の意味として「自分以外の他者・外界の一切を排除しているかのような患者の状態」とし、ギリシャ語の自己(Autos)を引用して名付けた。
自閉症のコア症状は、①社会性の異常(人への認識・興味が薄い、他者の心の状態を推測しにくい)、②常同行動(興味の限定)、③感覚・運動の異常(音に敏感など)である。患者本人にとっては③が最も苦痛とされ、外界の正常な認識や積極的な接触を妨げる原因となっている。
(神経発生)発達障害の一種である自閉症は、胎児期の神経発達プロセスのエラーが原因であり、通常、ご両親は我が子が3~5歳頃に気が付つ先天的なものである。つまり、自閉症は親の"育て方"により生じるものではない。著者は脳科学者であり、脳の発生学的知見(器質的なデータ)から自閉症等の原因究明にアプローチする。余談であるが、健常者が罹患する鬱病や統合失調症などは後天的な精神疾患であるが、器質的原因については自閉症とも共通する部分もあるかと思われる。自閉症は、先天的原因(遺伝子変異や脳発生プロセスのエラー)の観点では急激に増える障害ではないが、実際、自閉症認定される患者数は増加傾向にある。1975年の自閉症患者は5000人に一人だったのが、2014年には68人に一人にまで増加している。この背景として社会環境の変化が挙げられ、具体例として①診断基準の変化(自閉症の疾患概念が拡大)、②自閉症が社会に認知され受診者増加に寄与、③対人関係が重視される第3次産業の割合が上昇、④発達障害に対する社会支援の拡充(2004年の発達障害支援法の制定)などが考えられる。
著者によれば、胎児期の神経発生プロセスは複雑であり、健常者だからといって全くエラーがないわけではない。問題は、エラーの程度と本人周囲の受け取り方による。それを個性と呼ぶか障害と呼ぶかは、本人(や周囲の人)が苦痛を感じるか否かで決まる。第一に本人が、症状に対して苦痛ではなくむしろ満足を感じるならば"個性"と言えよう。
著者の専門である脳の発達メカニズム(と遺伝子の話)には多くの紙面が割かれている。哺乳類の脳が他の脊椎動物と比較して大型化する理由として、インサイドアウト型のニューロジェネシスであることを挙げており、同時に神経発達の複雑化も伺い知れる。一般に医学的な障害の分類方法は、顕微鏡等の観察により得られる客観的な原因、つまり、健常者との身体的(細胞レベル)な違いが明白な"器質的な障害"と、器質的には健常者と大差ない"機能的な障害"に分けられる。ただし、この分け方はその時代の解析能力に依存する。先端分析技術であるfMRIやPETなどにより、従来は機能的な障害とされた精神疾患に対して脳における器質的な障害として捉えられるデータが蓄積しつつある。例えば、統合失調症患者では、ニューロンの電気信号の漏電を防いで通信速度を飛躍的に高めるミエリン鞘と呼ばれる、絶縁体(電線を覆うゴム膜のような)構造が減っていることが指摘される。ミエリン鞘が減るとは、パソコンの基盤に水がかかったような���態で計算させるようなもので、思考スピードが遅くなり、時系列の整理や思考の統合もままらない。もちろんドーパミンなど神経伝達物質の過剰分泌などミエリン鞘の減少のみを原因とするわけではないが、器質的に調べられるとそれを正常化させる薬の開発につなげられる。
脳科学者である著者は、自閉症の解決策として最終的には器質的な原因、つまり、脳の発生プロセスのエラーを引き起こす遺伝子の特定とその機能の解明がひとまずの目標となる。本書でも、パックス6と呼ばれる神経発生制御遺伝子と自閉症の関係性について言及されている。最近の研究では、ゲノム情報は同じであっても、実際に保有する遺伝子が適切に働くかどうかによって現れる状態が変化する…というエピジェネティクスの考え方に注目が集まっている。つまり、何か特別な身体的特徴やスキルを手に入れるためには遺伝子自体の変異は必ずしも必要とせず、もともと持っている遺伝子を単に長く働かせたり、全く働かせないようにすれば環境適応できる個体が生じうるということだ。キリンの首は長いが、遺伝子自体が変化したのか、遺伝子は変化せずに働かせる方法が変化しただけなのか。いずれにせよ環境変化はストレスの負荷が大きく、そうしたストレスが遺伝子のオンオフに関与したのでは…と想像する。このオンオフ切り替えのほうが世代交代を必要とする遺伝子変異よりも環境適応の即時性は高い。遺伝子のスイッチのオンオフはDNAのメチル化やヒストン化学修飾によって引き起こされる。これを人工的に行うことでキリンの首を成長させず短いままにする遺伝子があれば、キリンの進化において遺伝子自体の変化は必要なかった(実際はどうかわからないが)…と言えるのではなかろうか。
投稿元:
レビューを見る
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057402