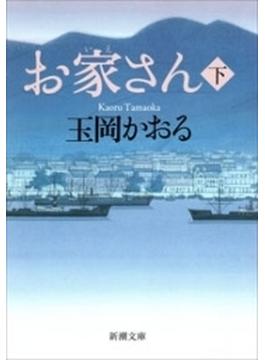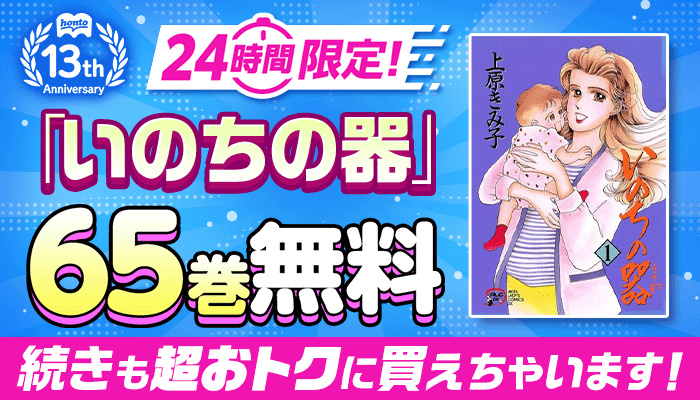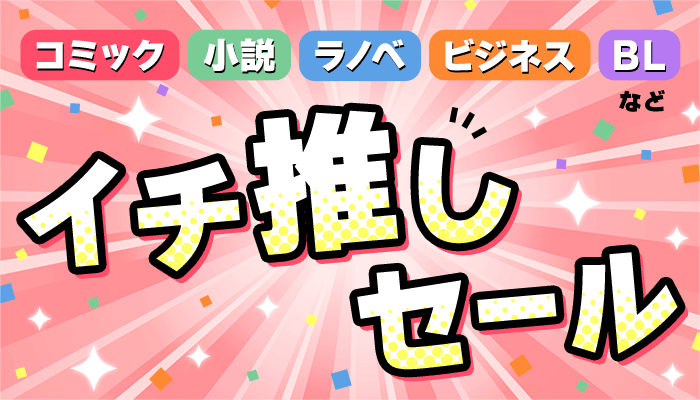0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ガンダム - この投稿者のレビュー一覧を見る
後半はそれこそジェットコースターの展開で涙あり、笑いあり、はらはらドキドキ感
が満載で、一気読みです。ノンフィクションもので何だかすごく考え合させられます。
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:あおい - この投稿者のレビュー一覧を見る
転勤で神戸に住むようになって、神戸が舞台の小説を探して読みました。神戸の華やかな活気溢れる時代が描かれています。今もその残り香を探すことはできますが、この時代の神戸に住んでみたかったと思います。最近テレビドラマ化もされました。同じ題材で、城山三郎「鼠」もどうぞ
日本人たるべき…
2014/01/14 10:08
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:笑う門ふう - この投稿者のレビュー一覧を見る
「日本人」であること、正しく生きることをじんわりと考えさせて下さる本ですね。
しっかりと着実に生きねば・・・一歩、一歩。
鈴木イズムを今ある会社に是非、引き継いで頂きたいですね。
活気のある神戸を自分の目でこの時代に見てみたかったです。
投稿元:
レビューを見る
神戸の地で偉大な人が、
会社は番頭の存在が重要。
ワンマン社長も良いが一人では何ほどにも。
でも時代の流れも読まないと!
投稿元:
レビューを見る
読み応えがある作品。上巻から引き続き鈴木商店が一気に上りつめ、さまざまな苦境に立たされ、必死に抗おうとする姿が胸をうつ。
さらによねと強いつながりのある一人の女性の人生が物語をさらに深みを持たせる。
日本の経済が大きな転換期にさしかかった時代を体感できる絶対お勧めの一冊。
投稿元:
レビューを見る
大正~昭和と日本一の売上を誇った鈴木商店。神戸を舞台に、一砂糖商を、未亡人となったよねが女社長として、大番頭とともに一大商社に築きあげていく波乱万丈の大河ロマン。
鈴木商店自体は米騒動の焼き打ち、更に関東大震災により倒産の憂き目にあうが、育てた子会社関・連会社は今でも続き、連綿と商店の伝統を守っている。
地の文と、「お家さん」の一人称とが交互に登場し、大正昭和の政治・経済を背景に巨大化していく商店と、一代商社の女社長にのぼりつめながらも、本人は一商店のおかみさんとして店の「オク」を取り仕切るだけ、というギャップがうまく、おんな太閤記的な女の目線の歴史を振り返ることができ、非常に読みやすい。
しかし山崎豊子や有吉佐和子を読みつぶした人間からすると、一抹の物足りなさが残るのは否めない。
もっと深く知りたくなり、城山三郎著「鼠~鈴木商店焼き打ち事件」という
ノンフィクションを購入。楽しみだ。
投稿元:
レビューを見る
米騒動における、鈴木商店焼き討ちのシーンは圧巻。
日本人が暴徒化するなんて、いまではありえないだろうけど、
実際に集団で過激になるというのは、とても恐ろしいし、
そういったところに、敗戦する萌芽があったように思う。
それにしても、朝日新聞はしようもない。
あくまでも、鈴木商店は「商店」という通り、
昔ながらの商店であったと思う。よくもわるくも。
投稿元:
レビューを見る
鈴木商店の興亡だけでなく、明治から大正、昭和と駆け抜けた熱い商売人達の思いが伝わる。そして、いつの時代も新聞には真実がなく、かといって新聞がなければ情報が伝わらない。お家さんの物語でありながら、この時代の流れがよくわかる小説だ。
投稿元:
レビューを見る
明治、大正、昭和を太くも短く駆けぬけた商社を通して、歴史と文化と日本人というものをしっかりと伝えてくれる、そんな本です。
また、商売を行っていく中で、それぞれの人生にどのような意味を見つけ出していくのか、登場人物たちが力強く邁進していく様が熱く胸に突き刺さります。国益に一途のもの、会社を守るもの、家族を背負うもの・・・それぞれの生き様に心を動かされます。
投稿元:
レビューを見る
文庫本で上下巻だったのですが、先週末に途中でやめられなくなり一気に読んでしまい、寝不足に陥った本です。
主人公の鈴木よねは明治、大正、そして昭和初期の日本において世界を股にかけた貿易で、当時の日本で一番の年商をほこった鈴木商店のオーナーです。三井、三菱・・などの財閥の名前は有名ですが、それに勝るとも劣らないすごい”商社”が他にあったとは!まずそれが驚きで読み進めていきました。
神戸において夫が営んだ店を夫亡き後、未成年だった息子たちが成人するまでと優れた働きをする大番頭を中心に店を続けていく覚悟をした"よね"でした。
日清日露戦争で勝利して世界の列強に仲間入りをしようとする日本の躍進に合わせて店は大きくなっていき、個人商店から合名会社へとなり彼女の呼び名もおかみさんではなく大勢の使用人のいる「家」を構えた商家の女主人に与えられる「お家さん」となります。
よねは最初の結婚に失敗しているのですが、その頃兄と一緒に見てもらった占いで出た絵柄が船。神戸の港から出る船を掌中に収めるとの正気とは思えない予言が鈴木商店に嫁いだことで実現していくのです。
登場人物は店が大きくなるごとに増え、歴史上の人物も登場していく大河小説ですから、筋書きは波乱に富んでいます。
時々登場する関西弁のよねの独白がその時々の彼女の心情を生々しく伝えます。個人を超えた大きな店になり、とうに彼女の思惑を超えた取引に印を押すだけの役割になっても、彼女はこの「家」を守るお家さん。この家で起こる様々な出来事のひとつひとつに心を揺さぶられながらも、地道に慎ましくひたすら進んでゆくのです。
最初は凄腕の女主人、実業家を想像していたのですが、よねさんは多分どこにでもいる働きものできっぷの良く面倒見のよいおかみさん。それが、周りの人たちや時代に左右され、それこそ波乱万丈の一生を送ることになるのですから、その不思議な運命の綾を思わずにはいられませんでした。しかし、もしかすると彼女ほど振幅は大きくなくとも誰もが”波乱”を経験して一生を送っているのでしょう。
投稿元:
レビューを見る
人は、自分を一つの使命にかりたてる時、果たそうとする責任を過大評価するものだ。
2012.2.1 完読
投稿元:
レビューを見る
鈴木商店とは---。現代にその痕跡を探すとすれば、神戸製鋼所や日商岩井などに認められる。この鈴木商店は明治7年から昭和2年の約半世紀の間、まだ「総合商社」という呼称がなかった時代に、世界をまたにかけて大活躍したビッグ・ビジネスである。当主は鈴木よねという女主人で、その番頭を務めたのが、金子直吉だった。より正確に言うなら、鈴木商店とは金子直吉が育て、世界のビッグ・ビジネスとして活躍した企業だ。鈴木商店は昭和2年の金融恐慌で、市場から退場した。しかし、金子が育て残した総合商社、製鉄業、化学、繊維など各種事業は姿を変えながらも今に生きている。つまり金子直吉は工業化のもっとも優れたオルグナイザーであると同時に、ベンチャーキャピタルでもあった。もう一つ金子直吉の事績を上げておくならば、彼が残した人材のことである。紙数に限りがあるので詳述は避けるが、代表的な人物を上げておくなら、戦後の産業復興公団総裁を務めた長崎英造、帝人の大屋晋三、神戸製鋼所の田宮嘉右衛門、日商の高畑誠一などがいる。
さて、金子直吉のことである。読者の中には城山三郎の小説『鼠』を読み、ご存じの方も多いかもしれない。けれども、これほど評価の別れる人物も珍しいことだ。神戸の小さな個人商店林兼を、世界的な大商社に発展させた、その経営手腕に着目し、天才的で非凡な事業家と評価される一方で、組織を無視したワンマン経営を敷き、結局は鈴木商店を破産させた張本人と断罪する向きもある。他方では数多くの企業を創業し、育成したという旺盛な事業家としての評価だ。さらにもう一方では比類なき主家に対する忠誠心や、私生活における無欲恬淡な態度を評価する向きもある。つまり金子直吉は見る人の立場で評価が大きく別れる人物なのだ。
投稿元:
レビューを見る
大正から、第一次世界大戦後の不況が鈴木商店を直撃する。下巻は義娘珠喜、田川、拓海の三人の運命のすれ違いがメインとなる。近代国家に加わった日本のように、時代の流れに乗り突き進む「鈴木商店」だったが、、、
投稿元:
レビューを見る
鈴木商店という一つの企業の勃興から全盛そして解体まで、「金子直吉はんに、うちはええ夢を見せてもろた」という鈴木よねの言葉が象徴するように長大なドラマは、ローマ帝国衰亡史などを読んだのみも比すべき充実感がありました。特に珠喜の悲劇と喜びの交錯が鈴木商店そのものの衰亡と絢を成すような素晴らしさを演出していると思います。珠喜と拓海の台湾での出会いの場面は涙なしに読めないような情景です。しかし、著者の筆は少し早過ぎるように思ったのは、米騒動の焼き討ち事件から、関東大震災、金融恐慌などがあっという間であり、ここの記載が少し乏しいように思えることです。それにしても、一時は三井・三菱を遥かに凌駕しながら沈んでいった鈴木商店を巡る歴史は劇的です。昔、日本史で学んだ知識で解り得なかった裏の物語は当時の世相との関係での奥の深さを感じました。どこまでが史実で、どこからがフィクションなのかはよく分かりませんでしたが。
投稿元:
レビューを見る
日本最強商社であった鈴木商店が倒産するまでの後半部。世代交代や危機管理についての教科書のような一冊。