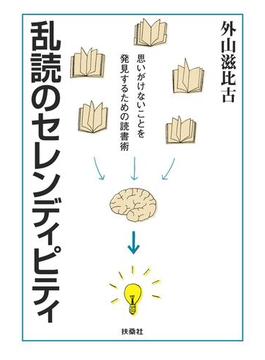外山さんらしい発想
2016/11/19 19:26
6人中、5人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:mistta - この投稿者のレビュー一覧を見る
言葉に関する考え方や勉強というものについての読み物は
個人的には外山さんがベスト。
セレンディピティという言葉は外山さんお気にいりの言葉であり、
私も好きな言葉だ。
この本はひたすら読めということを勧めるものではない。
本の読み方というものを考えさせられる内容。
読書は単なる知識集めではなく、よりよく生きるため、新しいものを
生みだす力をつけるため。外山さんの主張に大いにうなずく。
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:risa - この投稿者のレビュー一覧を見る
思考の整理学とセットでおいておきたい本です。読むという行為について考察しつくした本。ある意味、潔くて正しいと思います。
本が読みたくなる
2017/03/21 06:48
2人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:s.k. - この投稿者のレビュー一覧を見る
読書をすることの意義が再確認でき、やる気に繋がりました。これからも、どんどんたくさんの本を読みたいと思いました。
読書時間がとれず
2021/01/05 13:58
1人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:KEY坊 - この投稿者のレビュー一覧を見る
最近読書時間があまり取れずにいた所、コロナ禍で時間がたくさんできたのでどんなジャンルの本を読もうか迷い、まずはこの本のタイトルに惹かれ購入してみました。
投稿元:
レビューを見る
○乱読にも「意味」を持てば明るい知的ライフ!その意味を教えてくれる
セレンディピティとは、
思いがけないことを発見する能力。とくに科学分野で失敗が思わぬ大発見につながったときに使われる。(p92)とある。
タイトルにある「乱読のセレンディピティ」とは、乱読することによる思わぬ大発見があること、を指すのだろう。
・本は身銭を切って買うべし
・何回も読めばなんとなくその本のことが理解できる
・ただ本を追随するのではなく、生きる力に結びつくように読むべし
・・・などと、読書の仕方を懇切丁寧に、教えてくれている。
p82では、乱読の意義を語っている。
そもそも文章を読むうえで「アルファ読み」と「ベーター読み」という種類があり、「アルファ読み」は読む側がある程度知識を持って読んでいる状態。いたって基本的な読み方ではあるが、新たな知識を入れるとすると「ベーター読み」のように知らない言葉でも推測したり読み飛ばしたりする読み方をやらないといけない。
義務教育などの学校では「アルファ読み」しかやらない。「ベーター読み」をやればいろんな分野の本に好奇心を持って立ち向かうことができるはずだ。
また、乱読をするうえで最もうってつけなのは新聞だ、とも勇気づけてくれる。
自分の読書のはじまりは実は新聞だったし、進学校であった高校のときに「わからない単語は類推して読んでみよ」と現代文や古典の授業で言われていたことも、影響しているのかもしれない。
その点では、高校までに聞きかじりで得ていたことが著されているという点で心強い一冊。読書を人に薦めるときの理論的支柱にしたいと思う。
ちなみに、思考の整理学と表紙が似せてあるのも面白いポイントである。
投稿元:
レビューを見る
セレンディピティ。serendipity。思いがけないことを発見する能力。
それはまさに乱読から生まれる。
乱読者の私としては、そうそうと頷きながら読む本だった。
有名な外山滋比古さんだが、履歴を見ると私過去に著書を読んだことなかったみたい。思考の整理学とか有名だよなぁ。
『ガリバー旅行記』読んでみないとと思ったよね。
「忘却が活発であれば、知識過多になる心配は少ない。忘却がうまく働かないと、それほど摂取知識が多くなくても、余剰知識がたまって頭の活動を阻害するおそれがある。よく忘れるということは、頭のはたらきを支える大切な作用であると考えるようになった。」
一時間ほどでさくっと読んだ。
投稿元:
レビューを見る
【本は風のごとく、映画のフィルムのごとく読むのが良い。】
「思考の整理学」で東大・京大の若者から絶大な支持を受ける英文学者、外山滋比古氏による、“乱読スタイルでアイデアを生み出す読書のススメ”です。本棚に置く価値のある良書。
【1.著者はどんな人?】
外山氏は日本の英文学者・言語学者で、お茶の水女子大名誉教授です。「ことば」による子供や若者への情操教育に取り組み、思考法に関する本やエッセイなどもたくさん書いています。
【2.本書のテーマは?】
本が大量に多種多様に出版され、いつでもだれでも手に取れる現代では、“乱読”(色々なジャンルの本を、ある程度速いスピードで、大量に読む)こそが一番おもしろく、自身の思考の役に立つ読書の仕方だ、という主張です。
「本は風のごとく読むのが良い。(p.67)」
「ことばの流れは、映画のフィルムのようなもの・・・バラバラだったフィルムの一コマ一コマが結びつき動きが出る。読むのも、これに近いと考えて良い。(p.65)」
【3.細部はどんな内容?】
・本は一つのジャンルにとらわれず、文学、科学、哲学、宗教、ビジネスなど、自分の土俵ではない分野もふくめて読むことを勧めています。なぜなら、自分が理解しやすい分野の本ばかり読んでいると、「正確に理解するだけの読書(物理的読書)」に偏るためです。一方、「理解しにくいが好奇心をそそり、無意識に残る読書」を続けることで、頭の中で化学反応が起き、思いがけないことを発見する能力(=セレンディピティ)が鍛えられる、と述べています。
p.75「ベーター読み(内容・意味がわかりにくい文章を読むこと)の能力を身につければ、科学的な本も、哲学も、宗教的書物も、・・・好奇心を刺激する点ではおもしろい読みができるはずである。」「とにかく小さな分野の中にこもらないことだ。広く知の世界を、好奇心にみちびかれて放浪する。」
・“知識”と“思考”は相反する関係であるとし、知識が過剰になると借り物のアタマになり、自分で考えることを妨げるため、過剰な“知識・教養信仰”に対して警告しています。そこで、インプットとともに“忘却・忘れる”ことを勧め、溜まり過ぎた余計な知識を排出して整理することで、思考の整理によりアイデアが生まれやすくなる、と述べています。
p.52「本当にものを考える人は、いずれ、知識と思考が二者択一の関係になることを知る。・・・問題はどう見ても、生きる力とは結びつかない、知識のための知識を不当に喜ぶ勘違いである。」
p.168「知識をとり込み過ぎ、それを使うこともなく、頭にためておくと、知的メタボリックシンドロームになるのではないか。」
【4.ココがオススメ!】
本の後半では実際に著者が乱読から得たセレンディピティによるアイデアを紹介しており、その内容が非常に面白いです。編集者時代に雑誌が売れずもがいていた時、トイレの中で「編集とは料理に似た加工である」ことに気づいて売り上げV字回復へ導く話。日本語がハイコンテキスト(回りくどい言語)なのは、日本が島国なので人同士の関係が密接であり、あうんの呼吸で伝わるために相手に理解を促すようになったから、とひらめいた話など。乱読が実際に著者の人生でさまざまなアイデアに結びついている様子がわかります。
私自身、仕事の合間の休憩や散歩中、またはお風呂の時によく「ひらめいた!」状態になります。脳が無意識下で情報をせっせと統合しており、頭が切り替わった時にアウトプットされやすい、というのはその通りだと頷けます。あのスティーブ・ジョブズも、散歩しながらミーティングしていたと言われます。なお、色々な考えを頭のフラスコに入れて寝かせると化学反応が起きる、という視点は、ジェームス・W・ヤングの「アイデアのつくり方」にも通じます。
【5.こんな方にオススメ!】
・読書から生きた教養・思考力を身に付けたい社会人。
・本を読んだほうが良いと思いつつ活字が苦手な大学生、就活生。
・色々な本を読むことで、どんな良いことがあるかを知りたい中高生。など
【6.買う前に知っておくと良いこと】
この本はノウハウ本ではなく知的なエッセイです。乱読・速読の具体的な方法論や本の選び方、おすすめ本などの紹介はほとんどありません。あくまで「考え方」を紹介するものですのでご注意を。
【7.目次】
ほんはやらない/悪書が良書を駆逐する/読書百遍神話/読むべし、読まれるべからず/風のごとく/乱読の意義/セレンディピティ/修辞的残像まで/読者の存在/エディターシップ/母国語発見/古典の誕生/乱談の活力/忘却の美学/散歩開眼/朝の思想
以上、これから購入をご検討の方の一助になれば幸いです。どうぞ楽しい読書Lifeをお過ごしください!
投稿元:
レビューを見る
本を選んで読むのではなくて、乱読、本を選ばずに山のように読み切ることで予想外の幸運な偶然に出会うことがある。という趣旨の本。
α読書(本の最初から最後まで順番に読み進める一般的な読書)ではなく、β読書(わからないところは飛ばしつつも、一定のスピードで最後まで読み切る)というのは、確かに「本を読む人と読めない人の最大の差」ではあると思う。本を読めない人は、きちんと読まなければならないという思い込みにとらわれている。
最初は「えー?」と思っていたのだけれども、読み進むうちに「ああ!」ってなり、最後は「乱読しなければ」ってなる。
ただ、これ、乱読って年に100冊読む基礎が無いと、実行できないんじゃなかろうか。そして、β読書ができない読者層は、この構成だと、1章か2章で脱落するんじゃなかろうかって思わないこともない。
読書家が、さらなる高みへ進化したいときにどうぞ。
投稿元:
レビューを見る
セレンデイピテイとは思いがけないこと発見する能力である。さがすものは出てこなくて、思いもかけぬものが飛び出してくる不思議。例としてペニシリンを発見したフレミングの例が書いてあった。失敗が思わぬものを発見するキッカケになる例だ。著者は思いがけないことを発見するためには乱読をすればいいと主張している。ぼくが実践していることと同じだ。嬉しい。
投稿元:
レビューを見る
珍しいが「乱読」を推奨する本。
日本の教育では普通「古典」や夏目漱石などの「」名作本を読むことを勧めるが、この本は手あたり次第(というわけでもなかろうが、だいたいそんな感じ)に開いて読んで、心に留まらない場合は途中で投げ出してまた違うものを読むと良いと宣う。
なんて斬新な読書法!と思うのだが、著者の思惑はそのような読み方を繰り返すことで何かに気付くときがある。それが「セレンディピティ」だというわけ。
何かの「あるある」みたいだけど確かにそういうことってある、ある。
対して期待したわけでもなく、時間つぶし程度に思って買った本に「おぉ!」と感銘を覚えたり。そういう時は「これが読書の醍醐味!」なんて偉そうに思ったりするけれど。そういう感覚を「乱読」で手に入れようなんて思ったこともなかったよ。
「本は好き嫌いせず心のままに読んで楽しもう!」と肩から力が抜ける読後感でした。
投稿元:
レビューを見る
至言の宝庫。肩肘張らずに、素直に、気ままに読書を楽しもうという気持ちにさせてくれる。「思考の整理学」の復習的要素も。
投稿元:
レビューを見る
乱読、まさに自分にぴったり。「溢れるほどの本の中から自分に合う本を見つけることがそもそも知的労働である」「根を詰めて読むのではなく、風のように読み流せば良い。役に立つ知識はあとからでも必ず蘇る」「メモを取る必要はない。心に刻まれないことは文字に書いても無駄である」「乱読すると駄作を読む失敗を避けられないが、失敗を恐れては良い本に出会えない」
投稿元:
レビューを見る
生きることは 考えること
生きることは 読むこと
生きることは 発見すること
生きることは 散歩すること
生きることは とらわれないこと
生きることは 好奇心そのもの
「思考の整理学」も
何遍読み返しても面白い
本が好きな人は
輪をかけて面白く
読めるでしょう
乱読読みの人は
とてつもなく面白く
読みきってしまうことでしょう
投稿元:
レビューを見る
話が二転三転する
想像とは違った内容だった
本は買うべき
書店で買うのと図書館で借りて読むのとは違う
書店で買うのは自分の意思で選んでる
図書館は人が選んだ本だからダメ
みたいな内容で
書店から選ぶのも図書館から選ぶのも
数ある中から自分が読みたい本を
選んで読むのだから同じだと私は思う
投稿元:
レビューを見る
外山先生の本はいつ読んでも面白い。
読むこと以上に話すことの重要性、さらに記憶以上に忘却していくことでストレス回避に繋がるという話が興味深かった。