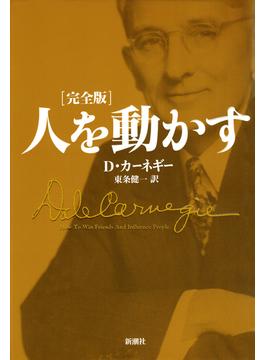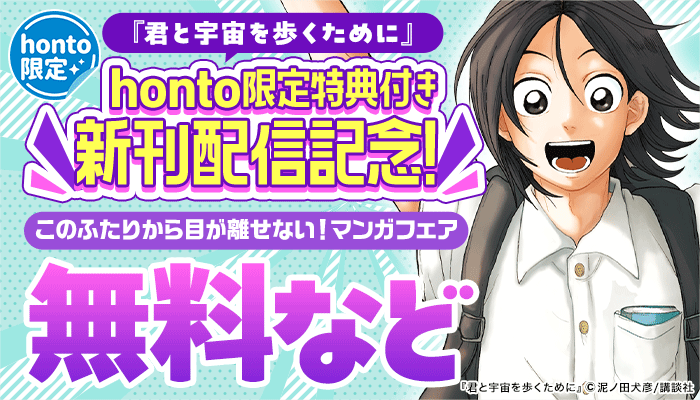以前の版とは別物
2018/12/29 16:39
4人中、4人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:obiwan0623 - この投稿者のレビュー一覧を見る
本の冒頭に説明されているが、カーネギー本人の記述を忠実に訳したということで、これまで存在していた「人を動かす」とは、全く別物という印象を持った。
以前の版は、正直、何とも言えない取っ付きづらさを感じていたのだが、この版は、理由を上手く言えないが、とても読みやすく、腹に落ちやすい。単に表現が口語調だからなのだろうか?
しかしながら、書かれている事を実践するには、何度も読み返して、日々状況に合わせて試行していくしかないのは、以前と一緒。
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:なつめ - この投稿者のレビュー一覧を見る
新訳になって、より読みやすくわかりやすくなって、よかったです。人との関わり方、社会とのつながり方の参考にしたいです。
投稿元:
レビューを見る
社長から薦められて購読。
対人関係の教科書みたいな本。すっごく勉強になった。
これからは人との接し方に悩んだら、
この本を読むようにしよう。
もう少し早く読んでいれば、、、と、口惜しくなる一冊。
投稿元:
レビューを見る
ビジネスマンの中では言わずと知れた有名な本。
著者は本書を書いた動機として「人間関係についての実用的な教科書を書くことにした」と述べる。
キーフレーズはこの本の中に数えきれないほどあるが、その一つ。人を動かす原理原則として「自己有用感への渇望」を満たすことを説いている。言い換えれば相手の欲求を満たすこと。よく「相手を褒めなさい」と言われるが、それも褒める行為自体を指すのではなくて、褒めて相手の承認欲求を満たすことに意味が出てくる。
ビジネス書として有名だか6章のうち1つの章は、円満な家庭生活の実現についても割いていることにも注目。子供に対する懺悔を書く『お父さんは忘れていました』の紹介は胸に響く。
色褪せない名著です。
投稿元:
レビューを見る
「原則7 実際以上の評価を与える」
「原則8 励ます。改善点をわかりやすくする。簡単にできると思わせる。」
確かに、期待されるのは嬉しい。期待を裏切らないよう、幻滅されないように、張り切って取り組もうと思う。
ただし、それは「本当はそうあるべきだ」「そうしなければならない」「きっと自分もそうできるはずだ」等、謂わば元々、本心ではどこかで自分で自分に期待していたことであったことに限られるのではないかと思う。自分自身への期待に、他人が共感してくれたからその効果が現れる。しかし、本人の期待と、動かしたい方向とを、どのように擦り合わせるかというのが本当の「技術」であるように思う。
投稿元:
レビューを見る
自己啓発書の元祖と呼ばれる本。
批判は不快、褒められればやる気を出すなど、言われてみれば確かに、と思うことしかないのだが、これを読むまで分かっていなかったように思う。
何度か読み返したい、出会えてよかった本だった。
投稿元:
レビューを見る
「人を動かす」というと、相手の上に立つとか強い言葉を掛けるなどのイメージがありましたが、それらを大きく覆してくれました。
◆感謝する、褒める、評価する
◆相手の視点に立つ
◆人に深い関心を持つ
◆笑顔を見せる
◆聞き上手になる(自分のことばかり話さない)
◆相手の興味の対象を見つけ、それを話す
◆個人攻撃をしない、批判・非難をしない
◆命令でなく質問を投げかけ、相手に考えてもらう
◆小さな頼みごとをする
投稿元:
レビューを見る
人の話を聴くなんて当たり前のことだけど、自分は自分のことしか考えてなくてそれが出来てなかったって思った。
投稿元:
レビューを見る
言わずと知れたマネジメントの世界的名著。紹介されている”原則”は至極当たり前に見えますが、多数の具体的な事例と一緒に読むことで理解が深まるのです。定期的な読み直し推奨。
続きはこちら↓
https://flying-bookjunkie.blogspot.com/2019/05/blog-post_8.html
Amazon↓
https://amzn.to/2vuw2u8
投稿元:
レビューを見る
自己啓発本として紹介されているので読んでみました。
表紙を見ると、はじめは宗教っぽい感じかした。
しかし、読んでみると事例が多く、勉強になることが書かれており目からウロコでした。
「心から評価し、惜しみなく称賛する」という一節が心に響きました。
また、本のカバー裏に「次の章に進む前に、同じ章を2度読みましょう」とあり、実践してみました。
毎月読み返して、自分事にしていきたい。
投稿元:
レビューを見る
完全版はカーネギー本人が書いたオリジナル版を翻訳したもの。これまで読まれてきたものは、カーネギーの死後に夫人が改訂したものになる。
カーネギーが本署を書いたきっかけは、人間関係をうまくやることができる技術を語った本がなかったから。この本は史上初の人間関係の技術書と説明している。
ある調査で、収入増加の要因は15%が技術的知識の向上、残りの85%は対人技術と個性、そして人を動かす能力に起因しており、人のやる気を喚起する能力がある人は、昇進しやすいことがわかった。つまり、社会では人間関係をうまくやれることがとても大事だということ。
本書は目的別に、実践のための一言で表された原則が示されている。本のほとんどの内容は、過去にあった具体的な事例を紹介している。「こうしたかったら、こういう話があるよ。大事なのは○○(原則)です」という流れで話が進んでいく。
人に動いてもらうには?
最大のポイントは、自分の振る舞いを考えること。これはつまり、相手を変えようとするより、まず自分を変えることが大事。そうすることで、人を動かせるようになる。相手の「自己肯定感」をうまく保ち、そして引出すコミュニケーションを取るスキルを磨くこと。
注意するポイント
・相手を批判しない(自分も完ぺきではないと認める)
・相手を評価し「有用感」を満たす(相手の人格を大事に扱う)
・相手の望むものを提案する(相手の視点も考える)
実践するには、まず相手を褒め自分が下手に出る。頼みごとした時、相手の事情を聞き理解を示す。これをすることは相手の利益にもなることを伝える。そして、相手の小さな努力も評価する。これができれば人になにかやってもらいたいとき、うまく話しをすることができるかも?
この本からの気づきは、相手を変えるより自分を変えることが大事ということ。この意識があれば最初から批判するような言葉は出ないと思う。しかっり意識していきたい。
投稿元:
レビューを見る
説明不要の良書。
洋書特有の言い回しの不可解な部分や、長い例文を飛ばし読みすれば、疲れずに読めます。
投稿元:
レビューを見る
対人関係のバイブルとも言うべき不朽の名作。
人を動かすというタイトルですが、自分が変わることが重要であり、更に相手に有用感を持ってもらうことが大事。
そのためにやるべき事が具体例を添えて書かれています。当たり前のことばかり書いてあると言う方もいらっしゃると思いますが、80年も前に書かれたとは思えない、現代にこそ大事な一冊で全ての大人の必読書だと思います。
投稿元:
レビューを見る
文句なしの自己啓発書。
どんな人でも「誰かの役に立ちたい」「認めてもらいたい」という意識が根底にあるもの。人を動かすということは相手の心情を理解して発言、行動すること、、
投稿元:
レビューを見る
『自己啓発に興味がある方は必読』
●相手が完全に間違っていても相手はそう思っていません
少し前のネットスラング?で「はい、論破~ww」
というのが流行りましたが、
これは「人を動かせる人」は絶対にやらないということです。
完全に間違っていて完全に論破されても相手にはそのことに対する悔しさ、怒りみたいなのが残ってしまい動いてくれないということです。
論破されたことがある方なら、うなずけるのではないでしょうか?
本書によると、人を批判するのは誰でもできるが、
間違いを直接指摘せず、本人に間違いを気付かせられるのが人を動かせる人つまり、賢い人、知恵のある人のやり方ということです。
では、どのように話を展開していけばよいかということが実例で紹介されています。
●本書は確かに古いけど人間の本質は同じ
1936年に出版。1936年といえば2.26事件の年。太平洋戦争前です。でも、紹介されるエピソードに古臭さは感じられず、「こういう人いるな~/こういうことやっちゃうなぁ」という共感と発見がたくさん見つかります。
●読んだきっかけ
図書館で借りました。
でも、何度も読み返したいので
『道は開ける』同様購入するつもりです。