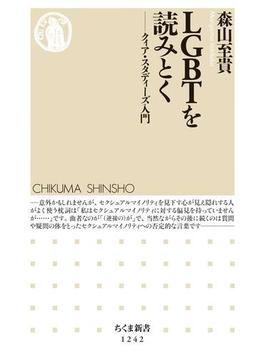広まりつつあるLGBTという概念。しかし、それだけでは多様な性は取りこぼされ、マイノリティに対する差別もなくならない。正確な知識を得るための一冊。
2017/08/29 20:04
3人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ぴんさん - この投稿者のレビュー一覧を見る
クィア・スタディーズの専門家は日本にもたくさんいて、英語圏も入れると文献は本当にたくさんある。ただ、そもそもクィア・スタディーズの内容以前に、セクシュアルマイノリティについて全然知らない人が多い。まずはセクシュアルマイノリティについて、続いてクィア・スタディーズについても基本的なことが押さえられる本が欲しいと思っていた。この本はまさにその二枚の看板を掲げ、前半は準備編としてセクシュアルマイノリティについて、さらにクィア・スタディーズの基本的な発想や用語について後半で書くという構造。
LGBTはセクシュアルマイノリティの全てではないのに、そのことが忘れられて使われているし、LGBTそれぞれの間の差異についてもあまり考えられていない。たとえば、マーケティングやビジネスの分野ではLGBTの間の格差などを考えずにいろいろな人をひとまとめに指す用語になってしまっているところがある。そういうわけで、LGBTは取り扱い要注意の単語であることを読者の方にわかってほしい。
この『LGBTを読みとく』というタイトルは二種類に解釈でき、しかもその2つの解釈がこの本を読むことで読者の方にやってほしいことをそのまま表している。ひとつは、セクシュアルマイノリティについて何も知らない人に対して、LとかGとかBとかTが何を指していて、それぞれがどういう社会的な枠組みのもとに成り立ってきたのかとか、それぞれの人たちがどういう社会的な戦いをしてきたかとかについてしっかり理解する=「読みとく」ということ。それぞれがどういうものなのか、そしてLGBTがセクシュアルマイノリティの全てではない。もうひとつの意味は、今の「LGBT」現象を批判的に解釈する=「読みとく」ということ。とりあえずLGBTって言っておけばいいとか、この言葉を使うと何かものが売れるとか、そういう現象そのものに対する批判的視点を獲得してほしい。
つまり、『LGBTを読みとく』は、LGBTと言われているものの中身と、またみんながLGBTと言っている現象双方を理解し解釈するというダブルミーニングになっている。
さよなら知ったかぶり
2018/10/11 14:31
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:きり - この投稿者のレビュー一覧を見る
副題『クィア・スタディーズ入門』の文字をもっとでかくした方がいい。クィアは調べてみるも全然ピンとこなかったけど、この本の解説でだいぶ分かりやすく頭が整理された気がするし、知れば知るほど社会のあらゆるものごとに関わってくるからすごく面白い分野だと思う。
主題『LGBTを読みとく』も、これだけパッと見るとうーん今更〜と思っちゃいそうになったけど全然今更なことはなく、むしろ知らなかったことや勘違いしてたことも多くて知ったかぶり大変失礼いたしました!!!(土下座)な本だった。
そんな歴史的、分類的あれこれを見据えてクィアという学問なのだな。
個人的には、文脈違うかもしれんけど「カップルでいることで得をする社会ってどうなのか?」て問題提起がされてることにすごく勇気付けられた…(独身アラサーの悲しき焦りを開き直らせているだけかもしれないけど)でも考えたうえでひとりの方がいいわ〜ていう結論になる人も絶対一定数はいるはずでしょ?!?!
そういう、LGBTだけの問題にとどまらず、かなり直接的にわたしの問題として立ち上がってくる事柄もあって、ここに順応できないのはわたしの落ち度かなと思ってしまっていたことも実はそういうことでもないのでは?と思わせてくれたというのがとてもいい読書をしたなという感じでした。
投稿元:
レビューを見る
1〜2章、余裕あれば4章までは基礎理解の文章として、事始め的に広く読みやすい内容。5章からはクィア・スタディーズという今の”LGBT理解”のさらに一歩先にあるような視点なので、少し小難しいかもしれないけど、「なんでもあり、十人十色、みんな違ってみんないい」的な収められ方に対抗する論考として、あえてここから始めるというのもありか。いずれにしても学部生・教養的な新書として読みやすく。蔵書入り。
投稿元:
レビューを見る
「良い新書は大学1セメスター分の講義である」
最近の口癖。講義をベースに書かれている新書もあるのだから当たり前といえば当たり前である。
読みやすいのに重要な点がちゃんと抑えられていて、復習を提供してくれると同時に、いつでも戻って参照できる基本が詰まっていた。巻末読書ガイドも丁寧でありがたい。こういう本に出会えるかが学びでは重要なのかもしれない。
投稿元:
レビューを見る
マイノリティの味方だと明言し、様々な論拠、意味を声高に叫んで来たが、本書を読んで、そこにどれほどの落とし穴があったか気付かされた。
・ローレティスはジェンダーとセクシュアリティの問題を区別すべきだと主張した。
・クィア・スタディーズの5つの基本概念。パフォーマティヴ、ホモソーシャル、ヘテロノーマティヴィティ、新しいホモノーマティヴィティ、ホモナショナリズム
・クィアスタディーズの基本的な視座。差異に基づく連帯の志向、否定的な価値付けの積極的な引き受けによる価値転倒、アイデンティティの両義性や流動性に対する着目。
投稿元:
レビューを見る
2017/05/19
差異を認識した上での連帯、価値観の内側からの転倒、
「差異に基づく連帯の志向」
「否定的な価値づけの積極的な引き受けによる価値転倒」
「アイデンティティの両義性や流動性に対する着目」
投稿元:
レビューを見る
この分野多少の興味はあるのだが詳しくなく、そして読んだら、ここ10年20年でもすごい変化しているもよう。多少整理できた気がして良かった〜
・LGBTと言う言葉はもはや差別隠蔽の指標として重要になっている
あー…分かる…(^_^;)かく言う私もこのタイトルだから気軽に電車の中でも広げて読んでたけど、ゲイとか同性愛とかって単語だとちょっとためらうところある…
・ホモソーシャルな絆はホモフォビア(嫌悪)を伴っている
そうそう、これ気になってたやつ。男の人たちがキャッキャたわむれているのを好む人の中に、ホモなんかじゃないから!!みたいに同性愛を見下す発言する人多いよな〜ての…
不快感感じるのは分かるのだが、差別意識表明しなくても良くない?て思っちゃう…ビミョーなところで私自身覚えがあるのでな…
そして時々「やおい」と言う単語が使われてたのに違和感なんですがw 私の感覚ではその単語は高河ゆんデビューあたりで盛んに使われてた印象…そしてその後すたれた気がしてたんだけど。
現役大学生がチェックしたそうだから、今も一般的に使われてんのかな…?
投稿元:
レビューを見る
副題『クィア・スタディーズ入門』の文字をもっとでかくした方がいい。クィアは調べてみるも全然ピンとこなかったけど、この本の解説でだいぶ分かりやすく頭が整理された気がするし、知れば知るほど社会のあらゆるものごとに関わってくるからすごく面白い分野だと思う。
主題『LGBTを読みとく』も、これだけパッと見るとうーん今更〜と思っちゃいそうになったけど全然今更なことはなく、むしろ知らなかったことや勘違いしてたことも多くて知ったかぶり大変失礼いたしました!!!(土下座)な本だった。
そんな歴史的、分類的あれこれを見据えてクィアという学問なのだな。
個人的には、文脈違うかもしれんけど「カップルでいることで得をする社会ってどうなのか?」て問題提起がされてることにすごく勇気付けられた…(独身アラサーの悲しき焦りを開き直らせているだけかもしれないけど)でも考えたうえでひとりの方がいいわ〜ていう結論になる人も絶対一定数はいるはずでしょ?!?!
そういう、LGBTだけの問題にとどまらず、かなり直接的にわたしの問題として立ち上がってくる事柄もあって、ここに順応できないのはわたしの落ち度かなと思ってしまっていたことも実はそういうことでもないのでは?と思わせてくれたというのがとてもいい読書をしたなという感じでした。
投稿元:
レビューを見る
第1章 良心ではなく知識が必要な理由
第2章 「LGBT」とは何を、誰を指しているのか
第3章 レズビアン/ゲイの歴史
第4章 トランスジェンダーの誤解をとく
第5章 クィア・スタディーズの誕生
第6章 五つの基本概念
第7章 日本社会をクィアに読みとく
第8章 「入門編」の先へ
著者:森山至貴(1982-、神奈川県、社会学)
投稿元:
レビューを見る
LGBTについて、理解したいからこそ、この本を手にしました。
たしかに、LGBTの歴史や知らない用語の意味は知れました。
しかし、理解したように思い込む危険性をこの本から教わりました。
私はこの本を読み、他人のことはわからない。わからないからこそ、わかろうと努力し続けることが大切だと感じました。
投稿元:
レビューを見る
分かりやすくキャッチーな図説ではなく、一定の読み応えのある(けど初心者向けな)書籍を探していたところ、当事者の知人に勧められて手に取った一冊。(求めていた粒度どんぴしゃりだった!知人に感謝……!)
少し砕けた印象の語り口で、多少難解な記述(六章とか……)も大学の講義を聴く感覚でスルスルと流し読みできます。
ところどころ、「おおっ!」っと唸ってしまうような、心にズバンと響いてくるような、絶妙な記述があるので、そういったものを探しつつ、読み物として、知的好奇心をくすぐる本として、気楽に読むにも向いている本だと思います。
投稿元:
レビューを見る
入門書として、こぶりでいい。読書案内も便利。歴史だいじ。でもぜんぶに首肯しにくい。ま、それもまた、いいことだなあ、と。
投稿元:
レビューを見る
「LGBTの入門書」というよりも「LGBTを読み解くツールとしてのクィアスタディの入門書」。
LGBT、という名前そのものが、4つの言葉の頭文字を取ったものであることからもわかるように、LGBT(やそれらを含むセクシャルマイノリティ)を語るとき、いろんな言葉が出てくる。
そんな言葉そのものについての説明だけでなく、その言葉がどういう背景があってできた言葉なのか、またその背景がどう変わってきたのか含めて説明してくれる一冊。
入門書なので、そこまで難しいことは書いてない。でも、それが理解できたのか、と言われると正直疑問な本でもある。
ただ、LGBTというよりも性差やそれにまつわる社会問題を考えるとき、なんとなくモヤモヤしていただけのものを、うまく説明できるかもしれない言葉と考え方がすでにあるのかもしれない、ということは理解できた。
少なくとも、ネットでそういう言葉が出てきたとき「ほんとにそういう理解でいいのかな?」と思ったら、この本を読み返せばいいかも、というくらいには。
複数の性の人間が同じ生活圏で生きることが当たり前になった以上、性差についてまがりなりにちゃんと考えないとトラブルになるのは当たり前のこと。
それを考えるための一助となる一冊でした。
投稿元:
レビューを見る
LGBTについて理解を深めたいと思い、購入。
1章で日本における状況について書かれており、歌舞伎の女方のことなど挙げられたのを見て、はっとした。
皆がカミングアウトを望んでないなど、言われればそうだよなと思っても、まだまだ自覚が足りないと気付かされた。
またマーケティングに関する視点、事例も個人的には新鮮な話しと感じた。
投稿元:
レビューを見る
性的マイノリティについての様々な歴史を学べるとともに、それだけに限らず差別を改善していくためには学問が必要であるということが理解出来た。