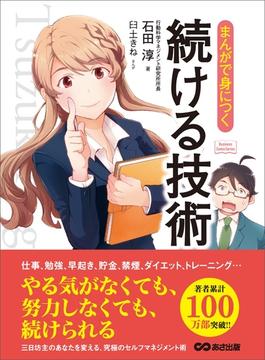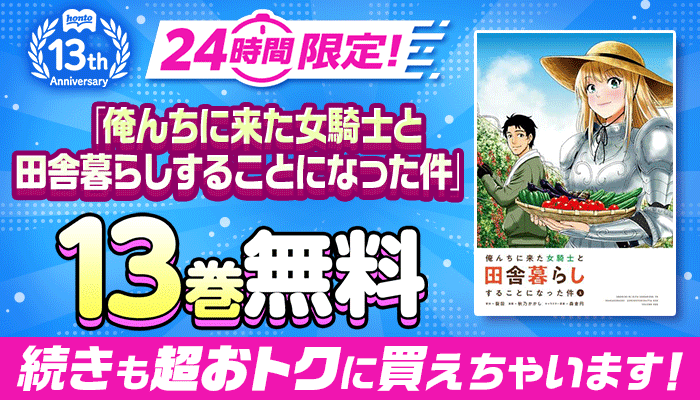続けるための準備について分かりやすいです!
2021/02/24 19:50
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:なのはな - この投稿者のレビュー一覧を見る
続けることは誰にとっても難しいことです。意欲があっても日常生活の中で障害となるものがたくさん。本書はそんな状況でも続けていくためのノウハウを教示しています。「続けるためには、続けられるようにしていくこと」当たり前のことなんですが、それが大切だとあらためて思いました。努力して続けても長続きしないし楽しくない。目的、動機、目標などをしっかり定め、色んな準備をしてから始まるのがいいのだな、と感じました。ご丁寧に見本シートまで乗っていて、コピーしてすぐに実践出来るようになっているのは良かったです。
投稿元:
レビューを見る
続けるために努力は不要???
誰もがなりたい自分をつくるための行動を続けられる行動科学の本。
行動にはその前後に条件が存在する。
行動を起こす前に起きる先行条件とその行動によって現れる結果条件だ。
それぞれ自分がターゲット行動を起こすためにどのような条件が揃っていればその行動を起こすのか、その結果を見据えてその行動を引き起こすための分析ができる。
不足行動と過剰行動を見極め、自分がなすべき行動をするための分析に「続ける技術」は存在する。
実際に数値として見れるように工夫したり、環境を整えてみたり。
自分が本当になりたい自分になるために行動しよう!
投稿元:
レビューを見る
行動科学マネジメント
行動の3つの要素
A:先行条件
B:行動
C:結果条件
ターゲット行動
・過剰行動 例 タバコ、ダイエット
→行動の発生を抑える先行条件
・不足行動 例 フィットネス、英会話
→行動の発生を促す先行条件
ライバル行動 睡魔、動画
・行動のヘルプ
睡眠アプリ、朝の日光浴、PCを開かない
・動機付け条件
達成インセンティブ
メジャーメント
・設定した先行条件が正しいかチェック
行動契約
・行動内容 定量目標、期間
・達成インセンティブ
・違反ペナルティ
以上
投稿元:
レビューを見る
当たり前だけど、大事なこと。
達成したいこと(行動)があって、それを続けるためにはどうすればよいのか。
どういう時にやりたくなるのか、どういう時にやりたくなくなるのか。
行動とは管理するもので、やる気とか、モチベーションとか関係ない。
「英語を勉強する」と決めて、その日の気分で英語の勉強をしたりしなかったり、そんなことをしていたら結局身につかない。
であるならば、どういう時に英語の勉強をしたくないのかを振り返ってみたり(お酒を飲んだとき、家にいてテレビを見ているとき、など)、どういう時に英語の勉強をしたくなるのかを振り返る(外国人と話したとき、洋画を見たとき)
その結果から、家ではなくカフェにいく、家にいるときは洋画や英語のドラマをみるようにするとか、行動を変えると、自然と英語を勉強するようになるのではないかってこと。
行動は、管理するもの。
投稿元:
レビューを見る
好きすぎるよハウツー本…と思いつつ読んでしまうわけですが、続けるには習慣化すればいいっていうのはわかっていてもなかなか実践しないんだなあ。
具体的で面白かったですけど。
投稿元:
レビューを見る
漫画を読むだけでも概要がスッと入ってきてとっつきやすかったです。
文章による説明セクションも小難しいことはかなり省いて「難しそう」「やっぱり面倒くさそう」といったネガティブイメージを読み手が抱かないように工夫されてる気がします。
「根気や努力は必要ない」はいささか煽りすぎというか、机上の空論といった感が否めないなーと感じました。
ですが「この理論に沿って行動してみたら続けられそう!」というモチベーション維持には有益でした。
読み終わった今、さっそく自身の達成したい事を整理しながらリサーチシートに落とし込んで行動してみたいと思っています。
(リサーチシートや行動計画書のファイルがダウンロードできたらちょっと嬉しかったかも…)
投稿元:
レビューを見る
http://www.asa21.com/book/b226409.html ,
http://www.will-pm.jp/
投稿元:
レビューを見る
一度決めた目標を挫折せず、日々続けるためのコツとは何か。
それは「やる気の問題」といったように、精神論で片付けないことである。
ダイエットやランニング、読書等は、そもそもが辛くてやりたくないものである。
それを意志の力でやり続けようとしても、やはりどこかで無理が出て挫折してしまう。
必要なのは精神論ではなく、科学的なアプローチで行動を分析し、コントールすること。
本人の意志や才能に関わらず、やり方さえ知っていれば、誰でもやり続けられる方法。
すなわち、「続ける技術」が大切なのである。
具体的には、まずターゲット行動(目標にしている行動)が、不足行動か過剰行動か判別する。
不足行動とは、それが足りてない、つまり増やしたい行動のこと。(読書、ダイエット等)
過剰行動は、それが多い、つまり減らしたい行動のことである。(ギャンブル、ゲーム等)
そしてその行動について、フロント行動(その行動が発生した時の状況)とアフター行動(その行動が発生した後の状況)を分析する。
不足行動ならそれが発生しやすいように、過剰行動ならそれが発生しづらいように前提条件を整えれば、行動を変えることができる。
行動すれば、成果は後からついてくる。
大切なのは、成果そのものではなく、行動をコントロールするという考え方である。
不足行動を増やすための具体的なポイントは、以下の3点。
ここでは、「毎週英会話レッスンに通う」という目標を例に考えてみる。
一つ目は、行動の回数を増やすような補助を作ること。
例えば、毎日英会話の横を通って通勤するようにすれば、帰りにふらっと寄ってみるようになるかもしれない。
二つ目は、行動のメリットを増やすこと。
例えば英会話に通うメリットが「周囲に褒められて嬉しい」であるなら、通った後にSNS等で拡散してみる。そうすればもっと褒めてもらえて、やる気が継続するようになる。
最後は、行動のハードルを下げること。
例えば、近くの英会話に通う、雰囲気の明るい教室に行く、などが挙げられる。
また不足行動には、それを阻害する「ライバル行動」が存在する。
このライバル行動が何であるかを分析し、それを減らしていくことも重要である。
また、過剰行動を減らすためのポイントは、不足行動の逆になる。
つまり、行動を起きづらくし、メリットを減らし、ハードルを上げる、ということになる。
なお過剰行動の場合は、メリットを他で置き換える「チェンジ行動」といった考え方もポイントになる。
例えばパチンコがやめられないなら、無料のゲームアプリで遊んで満足しておく、といった方法が考えられるだろう。
自分は三日坊主とまでは行かないまでも、土日の時間をゲームなどでダラダラ潰してしまうことが多く、日々の努力をもう少し継続できるようになりたいと思い、本書を手にとってみた。
手短にまとめられているが、要点は押さえられており、非常にためになった。
これらのノウハウを日々続けることができれば、本書にもある通り、人生は変わるだろう。
それくらい大きな力を持っている一冊。
投稿元:
レビューを見る
課長がけっこう可愛い。このジャンルじゃなかったら二人の関係は進展していたんじゃないかと。自分で表を埋めるページもあって実践的。
投稿元:
レビューを見る
続けたい行動を「不足行動」と「過剰行動」に分け、行動をするため又はしないための環境や条件を整える。行動を数値化する、など、当たり前と言えばそうだけど、分かりやすくまとまっている。まず自分が実践したい。
投稿元:
レビューを見る
行動が起きやすい(起きにくい)環境を整えて、実践する。その環境が本当に行動を変えているかどうか、メジャーメントする。
「メジャーメント」とは、行動がどれだけ増えたかどうか、減ったかどうかを「計測・測定」すること。
投稿元:
レビューを見る
「まんがで身につく 続ける技術」は継続するための技術的手法がよくわかる本でした。勉強やダイエットなど、何かを継続することに挫折したことがある人にぜひとも手に取っていただきたい1冊です。
随所にマンガで継続するための方法の実例が記載されています。なので、継続する技術の実践例がイメージしやすく、実際に自分自身で試してみやすいです。
また、継続するための技術を使うためには自分の行動を分析する必要があるのですが、行動分析のための記入シートが記入例と一緒に記載されているので実践しやすくなっています。
継続したいことがあるけれど、挫折したことがある人にはぜひともこの本をよんでみてほしいです!
投稿元:
レビューを見る
行動科学マネジメント手法
目標達成のため不足行動と過剰行動をコントロールして習慣化を図る方法が分かりやすい
具体例があるので早速やってみたい
投稿元:
レビューを見る
過剰行動と不足行動と言う言葉も初めて知りました。行動するには、いかにして過剰行動を減らすかが重要で、そのための方法が分かりやすく載せられていました。
これから参考にします。
投稿元:
レビューを見る
継続の為の技術を学ぶ視点からの感想と個人的な学び
・続けるには仕組みが必要(気合いだけは無理)
・続けるモチベーションを保つものを理解する
・良い万年筆などを買うのはあり
・ターゲットとする行動が起きやすい、起きにくい環境を理解する
・ターゲット行動が起きやすい環境を作り、そこに身を置く
・ターゲット行動が起きにくい環境を避ける、作らない
・ターゲット行動が起きやすい環境、起きにくい環境をそれぞれ分析し対処方法を決める