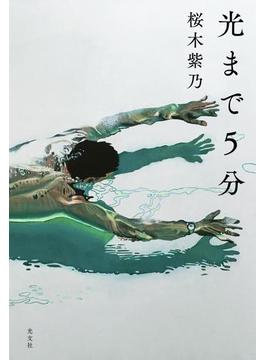どんな人生だとしても
2018/12/28 05:53
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:リンドウ - この投稿者のレビュー一覧を見る
北海道の釧路で生まれ育ったツキヨは小学校教員だった義父から性的な悪戯を日常的にされていた。義父が他界した後、流れ流れて、沖縄の那覇の路地裏の売春宿「竜宮城」で身体を売って生活していた。気づけばもう38歳になっているが、「竜宮城」では「25歳」から歳はとらない。
タトゥー彫師兼闇歯医者の万次郎とその同居人ヒロキに、彼らがねぐらにしている「暗い日曜日」という元バーで出会い、ツキヨの人生が動き出す。
沖縄が舞台なのに全体的に暗く湿気のある雰囲気のある作品。他の桜木作品と同じように、性描写が多い作品だが、表社会では生きていけない男女の人生を考えさせられる大人の小説。
沖縄の光は眩しすぎた
2019/01/18 07:17
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:夏の雨 - この投稿者のレビュー一覧を見る
毎回決定のつどニュースとなる芥川賞直木賞であるが、あれは新人賞であるはずで、大相撲でいえばせいぜい十両優勝というところではないか。
脚光をあびて幕内にあがって、そこからどこまで精進し、小結関脇と進めるか。あの賞の選考委員の人たちは引退をしたわけではないので親方衆ではないから、大関横綱級になるのかしら。
『ホテルローヤル』で第149回直木賞を受賞した桜木紫乃の場合、番付でいえばどのあたりだろうか。
受賞後もいい作品を書いているし、筆力の巧さは受賞の際にも際立っていてその後も健在だ。
小結ぐらいか。
ところが、この作品はどうだろう。
今まで多くの作品の舞台となっていた北海道を離れ、沖縄を舞台にしたのはどういう心境の変化であったのか。
主人公のツキヨは桜木が得意とする北海道の出身ながら、流れながれて那覇の街で自身の身体で食べている女性に設定されているが、義父との肉体関係をほのめかせられても、その義父が自刃しても、それが沖縄まで流れていく訳ではあるまい。
那覇の街でツキヨが出会う、桜木ワールドでしばしば登場するような影のある男万次郎にしても、元歯科医で女性関係からこの街に隠れているといわれても、それさえしっくりこない。
あるいは万次郎と生活を共にするヒロキという青年、彼に暴力で君臨する南原という男にしても、実体がいずれもおぼろである。
巧さだけで勝負しようとしても、勝てるわけではない。
桜木紫乃には沖縄の光は眩しすぎたかもしれない。
投稿元:
レビューを見る
北海道から流れ流れて沖縄にやってきたツキヨは、那覇の路地裏で身体を売っている。客に教えてもらったもぐりの歯医者を訪ねたツキヨは、元歯科医の万次郎、同居人のヒロキと出会った。ヒロキと気が合ったツキヨは、万次郎たちと暮らすことにするが――。
投稿元:
レビューを見る
2018/12/19 M リクエスト
楽しみにしていたのですが、いつもの作品ほど、染み込んでこなかった。残念。
投稿元:
レビューを見る
初出 2016〜17年「小説宝石」
北海道から流れ流れて沖縄の「竜宮城」という売春宿に居着いたツキヨは、歯の治療をしてもらうために、女性関係のもつれから逃げて匿われている元歯科医万次郎のもとを訪れ、その同居人で万次郎からモナリザの刺青を施されていたヒロキと、3人の奇妙な共同生活が始まる。
ヒロキが拾って来た子猫が死んで、ヒロキのおばあが居る奥武島に橋を渡って行く。おばあによると、ヒロキは死にかけた子猫ばかり拾って来る「看取りの天使」なのだという。暗い前半からうって変わって明るい後半だが、生活感のないふわふわした物語が続く。
竜宮城は短期のアルバイト感覚で女の子が入れ替わる海の底なのだが、ツキヨはそこへ戻ってママ(遣り手)の後釜に座り、万次郎は海で本当に行方不明になる。
ツキヨが少女期に義父から受けた性的行為がトラウマになっていることが、物語の端々に伺えるのだが、ずっと読み手の心に刺さっている棘ような気持ちになる。
タイトルの「光まで5分」は歯の治療後にツキヨに吸わせたタバコ(たぶんマリファナ)が効くまでの時間、象徴的だが分かりにくい。
投稿元:
レビューを見る
姫野カオルコの「ツ、イ、ラ、ク」があまりにも面白くスイスイと進んでしまうので、途中に別のを挟もうと手に取った。
ツキヨは北海道から沖縄に流れ、風俗の仕事をしている。虫歯を治してくれたタトゥーの彫り師とその友人と親しくなり、一緒に暮らすようになる・・・
正直、まったく面白くなかった。桜木紫乃には高いレベルを求めてしまうのもあるのかも知れないけれど、読了した彼女の作品の中ではワーストの駄作と言って差し支えないと思う。
流されていく女、男の悲哀のようなものが描かれているけれど、ただでさえ薄い本に、あまり意味のない叙情的な表現が多いのと、ストーリーそのものに読ませる感がない。
大好きな桜木紫乃だから、たまたま今回は、と思いたい。
投稿元:
レビューを見る
桜木さんの作品はほとんど読んでいて、沖縄が舞台!どんなテイストになるの?どんな女性が描かれるの?と楽しみで、図書館の予約待ちにしびれを切らして購入した。
残念ながら、桜木さんで初めて、自分の心に全く響くものが無かった。好き嫌いの問題かもしれないが。
ツキヨ、この人本当に流れていくしかないのか?ただの薄っぺらい意志のない女にしか感じない。
幼少期からの義父との関係が…と言うなら彼女の思い出が(母親はともかく)辛いものという訳でもなさそう。
万次郎の過去も今ひとつ不明だし、ヒロキもフワフワした半透明な感じで、魅力的なキャラクターが誰も居ない。
文章表現はやはり好き。沖縄の風景や空気感を描くとこうなるんだーと素敵だった。
でもいかんせんストーリーに入り込めない。
「みんな痛くて泣きたい」なら何とかしようよ、しようとしてないじゃない!と思ってしまった話。
星を一つにしたいのだが、自分の読みが甘いだけかも、という桜木さんびいきで二つにしました。
投稿元:
レビューを見る
北海道から流れて沖縄までたどり着いたツキヨ。「竜宮城」で体を売って暮らしている。奥歯が痛く、闇の歯医者に行くことになる。そこには、元歯医者の万次郎、万次郎に刺青を入れてもらっているヒロキがいた。二人が同居しているところに、ツキヨも加わることになる。はきだめメルヘン。
登場人物みんな幸福から縁遠い人たちばかりだし(「おばあ」がまともか)、終始暗いムードが漂う。そういうジメジメを描きたかったのかしらね。性と金と暴力。そして、いつもの女の強さ。私の中では桜木史上一のどんより感いっぱい。
投稿元:
レビューを見る
北海道の東の果ての町から沖縄に流れてきたツキヨは、奥歯の痛みに耐えかね訪ねた闇の歯医者の元に居つくことになる。そこにいたのは、訳あって死んだことになっている男・万次郎と、なぜか近づく者の命を看取る運命にある少年・ヒロキだった。
人生のどん詰まりで希望を持たない3人の生活は穏やかな日々だったが、それも長くは続かなかった・・・
桜木さんには珍しい沖縄を舞台にした作品。
桜木さんが描く女性は相変わらず強くて、どんな悲惨な境遇にあっても淡々と、どこかあっけらかんとしている。
不幸のどん底にあるような3人だけど、舞台が沖縄というだけでいつもの身も凍るような寒さ(←当たり前か)と救いようのなさが緩和されて、それがいいような物足りないような・・・。やっぱり、極寒の北海道を舞台に不幸な女の切なさ、やるせなさを描いて欲しいわ~。
帯にある「はきだめのメルヘン」の言葉に「何じゃそりゃ!」と思ったけれど、読み終わってみるとあながち的を外していないような気がするのは、登場人物たちが吸っていた葉っぱ(多分マリファナ)の煙と、それが見せる幻覚のせいか・・・。
でもメルヘンだとやっぱり、物足りないのよね~。
投稿元:
レビューを見る
桜木さんの作品は、どんどんよくなる。
最近は、どんよりグレーな感じはあまりなくて、薄いブルーグレーって感じw
同年代の作家さんの書く作品を読むのは、格別の感があって、楽しみ。
投稿元:
レビューを見る
正直、つまらなかった~
魅力的なキャラもいないし、好感持ったり共感できるような人が一人もでてこない。
何をしたいのだ?というか、何を書きたかったのか?分からなかった。
投稿元:
レビューを見る
沖縄のうらぶれた店で体を売って生きている女性が、同様に社会からつまはじきにされた人たちとともに生きていくさまを描いた長編。
幼児期から義父に性的暴行を加えられていた記憶がときには甘美な思い出と感じるほど、幸せとはほど遠い日々を送る主人公。登場する人たちはみな、一般社会の基準から大きく外れ、はきだめのような世界に生きている。
無力ゆえにそこから脱出することも叶わず、虐げられ、踏みにじられるばかりなのだが、当人たちはあきらめから無気力、無感動になり、さほど苦に思わないところがまた恐ろしい。
痛々しすぎて、胸の悪くなるような思いを引きずる読書だった。
投稿元:
レビューを見る
前回の「ふたり暮らし」が心温まる作品で、きっと同時進行で書いてらした「緋の河」が大河小説で、その間にふっと書きたくなった、青春がひりひりする小説なのかな、と感じました。
舞台は南国の島。北海道とは違って明るくカラッとした空気があります。とはいっても、もやもやせつなくて、なにひとつ解決しない感じは相変わらずです。
ただ、私が感じたのは「死」と「生」をわけるものはたった「5分」。
ヒロキに選ばれるかどうか、その線は紙一重。
ツキヨが選ばれなかったこと、それがこの小説の一つの柱なんでしょうね。
投稿元:
レビューを見る
桜木ワールド全開です!!!
【本文より】
闇に浮いた母の肌の白さと、左右に揺れた瞳の余白が忘れられない。
南原の口ぶりは義父がよくツキヨを遊びに誘ったときのそれに似ていた。こちらの指の間を砂そっくりに通り抜けてゆく話し方をする。あのころと同じ感触の言葉を耳に入れながら、ツキヨはまた誰かを失う予感に漂った。
「旨い飯も音楽も、生活の上の棚に置いておくのは難しいんだ」
パンを焼いた万次郎も食べたツキヨも、買ってきたヒロキもなにも食べられなくなったランコさんも、世の中からこぼれたところに在った。
投稿元:
レビューを見る
淡々としている感じ。どの人物の気持ちも一方通行で成り立ってる関係って珍しいなと思う。
桜木紫乃さんが北海道以外の作品を題材にしてるって珍しいというか始めてなのかな?でも沖縄の雰囲気がよく出てると思う。