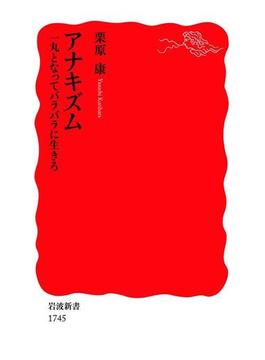言葉の宝石箱だ 今から一緒に殴りにいこうか YAH YAH YAH!!!
2019/08/24 10:04
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:せきた - この投稿者のレビュー一覧を見る
ムダなことしかやりたくないけどやりたいことにも縛られない。
自らの奴隷根性を自覚して抗え。自由な生を掴みとれ。
弱者は死ぬんだよぉぉ~。だから闘うんだろうがぁぁぁー!!!
一つひとつの言葉が勇気と元気をくれる本。
読むのに頭をつかう本。
今の日本に忍び寄る危機への警鐘かも。
オチは「あなたがされたいと思った善いことを他人にするのです」??
投稿元:
レビューを見る
アナキズム関連で最近多くの著作のある栗原康さんの最新作です。岩波新書から出たってのと、装丁が真っ黒ってところがとりあえずスゴイですね。
最近の栗原さんの著作って叫び声というか、擬音がいっぱいで「取りあえず叫びのエネルギー!」という印象。理論的な部分は著名アナキストの著作からの引用が多いようです。アナキストの著作って、妙に言い回しが回りくどかったり、逆に詩的だったりするんですが、シンプルってところは読みやすかったですね。巻末の参考文献も役に立ちそうです。
投稿元:
レビューを見る
完全に自分が悪いのだが、全く分からなかった。
まず文体については、ラノベ的というより、予備校の出す講義系の参考書の感じに近い(より下品だが、それが面白みでもある)言文一致という感じで、読みやすい、と思いきや、そうとはいかない箇所もある。
アナキズムについては、千坂恭二的なものを想像していたので、違うのに驚いた。が、人類の積み上げてきた倫理的思索やそれにまつわる秩序を根本から否定してしまいうる思想については、よく配慮する必要があるんだろうと思った。このロジック(というか、「非論理」というロジック?)は確かに敵に回すと厄介。
投稿元:
レビューを見る
アナキズムとは何かを、まさにアナーキーな文体と
随所に挿入されるアナキズム文献からの引用、そして筆者の実体験をベースに伝えてくれる。
繰り返される破綻寸前の文章は自分には合わない、というのが正直なところだが
反復から浮かび上がってくるものがおそらくアナキズムの本質なのだろう。
序列を、階層を、作らない。
コンセンサスを是としながらも、コンセンサスに従うかは結局のところ本人次第。
読めば読むほど混乱してくるが、
近年良しとされるボトムアップ型・自律型組織とアナキズムの類似点などアナロジーを駆使してこの本と相対すると中々に楽しい。
投稿元:
レビューを見る
2018年12月読了。
この著者の著作を読むのは2冊目(1冊目は『村に火をつけ、白痴になれ』)。
今回の『アナキズム 』、なにか非常に飛んでいる。
文体が飛んでいる、というよりも文体以前の問題でイッテしまっている。
「真面目な岩波新書でございます」てな調子で読み始めたら痛い目に遭う。
アルケー(arche)がないのがアナーキー(anarchy)、アルケーは「統治」や「支配」という程度の意味で、それがan、つまり「〜がない」のでアナーキーは「無政府主義」と訳されるが、アルケーは哲学用語では「万物の始原」、あるいは「根源的原理」という意味のものであって、アナーキー=無政府主義だけでは足りない。根拠のないことをやる
という意味も抑えておく必要がある(9ページ)。
とかく意味や根拠、社会的な評価の尺度に合わせて生きなければならない、もしくはそう生きなければならないかのように思わされている人々にとっては、アナーキズムはそういった発想から解放される手段になる。
邪推するに、この手の本が新書として出版されるということは、今の世の中に不自由や理不尽に憤っている人が多く、あるいは慣習、因習その他諸々の人の思考や行動を制限する何かによって窮屈な思いをしている人が多いのではないか、と思う。
もっと群れずに自由に生きる、過去にもそんな人がいて、度々痛い目に遭いながら=時の権力に押さえ付けられたりしながら、どうにかやってきたということを知ることで、より自由な発想で生きるための縁としたい。
投稿元:
レビューを見る
いろいろな考えの人がいる。無責任な人がいる。自由を謳歌しつつ、結局は他の人に頼って生きている。なんとなくあこがれるが、絶対にそれで良しとはいかない。
投稿元:
レビューを見る
序章 アナキズムってなんですか?
第1章 自然とは暴動である―エコ・アナキズムの巻
第2章 ファック・ザ・ワールド―アナルコ・キャピタリズムの巻
第3章 やられなくてもやりかえせ―アナルコ・サンディカリズムの巻
第4章 われわれは圧倒的にまちがえる―アナルコ・フェミニズムの巻
第5章 あらゆる相互扶助は犯罪である―アナルコ・コミュニズムの巻
著者:栗原康(1979-、埼玉県、政治学)
投稿元:
レビューを見る
岩波新書にしては思い切った装丁に惹かれて手に取る。政治思想は元来不勉強分野だが、「アナキズム」についてまとまった形で読むのは本書が初めて。登場する思想家・活動家中、辛うじて名を知っていたのは大杉栄くらい、あとは和洋問わずほとんど聞いたことのない名前の連続でやや戸惑ったが、内容は新書らしくシンプルでわかりやすく、著者の思いがストレートに伝わってくる良書だと思った。
本書を一読して我が身を振り返れば、自分の信条を体現しているわけでもない国家や組織の価値観をいつの間にやら内面化し、当初は確かにあった衝動を忘れてしまったことに無自覚な自分に思い至り、冷や汗が出る。この「他人の自我」に従属する奴隷状態から「棄脱」するには、衝動に基づく行動や共鳴に基づく無償の「相互扶助」を通じて、自分にも制御できない自分の力を取り戻すしかないというのが著者の主張。
研究者として書きたいことを書く地位を得るため、その自分の書きたいことの代わりに周りから評価されることを書かねばならないことの矛盾を良しとせず、伝統的な研究者としての地位に甘んじることなく非常勤講師の道を選ぶという実践を、著者自身が踏んでいるだけに一定の説得力がある。しかも、ここには「アナキズム」という言葉から連想されるようなストイックな堅苦しさや偏狭さは感じられない。それは賛否あろうが「個人に開かれたアナキズム」ともいうべき著者の信条をわかりやすく体現する文体に依るところが大きいのだと思う(やや紋切り型な一人称「おいら」や意外にバリエーションに乏しい間投詞は少々気になったが)。
本書の内容を実践に移すのは簡単ではあるまいが、「ユートピアを志向し続ける意志の力だけはどのような立場に置かれている人間であっても忘れてはならない」という著者のメッセージはクリアーに伝わってきた。今年から高校に行く息子に読んで欲しい。ま、無理に読ませて本当に読むような人間であれば、そもそも本書でいう奴隷根性へ一直線、ということになるのだろうが。
投稿元:
レビューを見る
長渕剛の歌詞がところどころに出てくる。実際ファンだとちゃんと公言してた。
砕けた文体でアナキズムとは何かを語っている。アナルコキャピタリズム、アナルコサンディカリズム、アナルコフェミニズム、アナルココミュニズム等々について、大杉栄、エマゴールドマン、伊藤野枝といった人々を紹介しつつ説明。
ちょっと自分には理解が難しいんだけど、対価交換が当たり前だとか役に立つ立たないだとかって既存の資本主義の秩序を当たり前と思っている自分に気付かされた。
投稿元:
レビューを見る
色々毀誉褒貶のかまびすしい著者の文体ですが、それほど読みにくいわけではないので、これはこれでいいのではないか、としておく。
内容は、正しいことを教えてもらう本ではないので、刺激をもらい参考になる事柄や本を紹介してもらえば良いので、私には参考になった。
著者の重視する身体性?のようなもの、誰にも支配されないで生きるということ、などを手掛かりに一人一人の読者が考えていけば良いのではないか。
一つ気になるのは、著者が取り上げているのは欧米と日本の話ばかりで、それ以外の社会においても同様な主張で通すつもりなのか、ちょっと聞いてみたい気がする。
投稿元:
レビューを見る
2019年1月15日図書館から借り出し。アナーキーなのもいいが、この本は度が過ぎている。ジョイス気取り?買わずに図書館で済ませて良かった。買っていたら頭にくるところ。当然ながら途中で投げ出し。ウッドコックの古い本を読み直して、口直しをしたい気分。
投稿元:
レビューを見る
「大往生」永六輔さんの一冊が
岩波新書に入った時にも
「おっ こんな一冊が 入ってくるのだ、
岩波さんもオツだねぇ」
と 思った。
そして、
まさかの栗原康さんの「アナキズム」
いつもの調子の
いつもの文体
「おっ こんな一冊も 入ってくるのだ
岩波さんも懐が深いね」
と 思った。
私は、好きなのですがね…
投稿元:
レビューを見る
最低の読後感、いや、読み出しから最低だった。分かりやすい言葉で伝えることと、悪乗りの言葉を連ねるのは違うと思う。岩波新書の安心感からネットで購入したが……
投稿元:
レビューを見る
うーん。悪い意味で、文才というものに思いを致さざるをえない。つらい。ただし、アナルコ・フェミニズムのところは抜群に面白い。伊藤野枝、すごいなあ (206-7頁)。
投稿元:
レビューを見る
体型的なアナーキズムが説明されていると思ったけど、そうではなかった。
実践的アナーキズム、帰納法的にアナーキズムを知りたい方にオススメ。