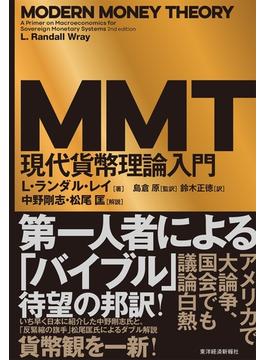紙の本
マクロ経済の教科書
2019/10/20 01:31
2人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:へもへものへじ - この投稿者のレビュー一覧を見る
自国通貨建て国債のみを発行している国の政府は、債務不履行には陥らない。
政府の赤字は民間の黒字、政府の黒字は民間の赤字である。
貨幣とは債権であり、債権はただ通帳に記帳したりお札を刷るだけで、発行する事が可能である。
などなど、言われてみれば当たり前なのだが、言われてみないと気付けない事実を丁寧に説明したマクロ経済の入門書である。
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:イ! - この投稿者のレビュー一覧を見る
現代貨幣理論について,非常に長いページを割いて解説されている.MMTに関してはまだ理解できていないが非常に面白いと感じた.
紙の本
書いてあることはわかりやすい。でも内容は難しい?
2019/10/15 21:47
2人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:一読者 - この投稿者のレビュー一覧を見る
アメリカはじめ、話題になっている経済・財務理論だったので、興味があり、読んでみました。
日本語自体は読みやすいです。読む前段階として、簿記3級ぐらいの下地があると、負荷が少なく読めると思います。
書いてある内容は、なるほどと思える内容で、素人である自分では間違っているとかおかしいと感じる説明はありません。完全雇用実施のため、公的セクターが労働者を募ることも、最低賃金を上げていくことも、自身が夢想したことがあったので、イメージしやすかったです。
ただ、なぜ租税を徴収するための道具としての貨幣、ということをこれだけ強調するのか、そして、それだけ強調されても自身が腹落ちしないのはなぜなのか。モヤモヤが残っています。単純に、国にはその貨幣を使うことを強制させる力があるから、公共の決済は計算貨幣を使うことが半ば強制されているから、公的セクター以外でも計算貨幣が使われることが疑いないことが個々人疑いない状況を形成できているから、という説明ではダメなのでしょうか。
所得税の累進課税は、貧富の不均衡を是正するのに良い、しかし法人税はよくない、というところも、それだと頭が良い人は法人に純利益を作って、それを無配当で法人にため込んで、その代表者が費用として私用するのではとか思いました。
今の日本だと、公共事業として国土整備や国内サービスセクターに支出するのが良い? 今の量的緩和政策とは仲良く出来ない理論? もう少し勉強が必要だと実感しました。
紙の本
これは本当に経済理論なのだろうか。
2021/03/20 21:42
4人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:FA - この投稿者のレビュー一覧を見る
主流派経済学の貨幣論はいわゆる「商品貨幣論」である。私も大学生として勉強してきたし、今も当然だと思っている。
この理論は、人々がお札という単なる紙切れに通貨として価値を見出すのは、その紙切れで税金が払えるからだというのである。MMTは、租税制度の主な目的は通貨を「動かす」ことであると主張する。
本気で言ってのかな。租税をきちんと徴収できている国家が少ないと言われているぐらいなのに。通貨を動いているけど、租税徴収なんて一部だけを表しているだけだと思う。
数学的な理論がない。これは本当に経済理論なのだろうか。
投稿元:
レビューを見る
主流の理論が間違っている
キーストロークだから大丈夫
...の2点しか頭に残らない。
ところどこと面白い議論もあるので、無駄だったというわけではないが、知りたいところに手が届かないモヤモヤが残る本でした。
理論の骨格とかロジックを知りたかったのだが、主流派批判に邪魔されてピントがぼけてしまっている印象を受けました。
既存の理論との違いはを知りたいのですが、何が争点なのかよくわからない。(もちろん結論はちがっているのですがそこに至る何処に違いがあるのか)
最初はすごく丁寧に説明しているくせに、後半、もっと丁寧に説明がいるのでは、というところが、主流派批判の勢い優先でかかれていて論理展開についていけなくなるところが多々ありました。
まとめると
・理論の全体像がつかめない
・主流派経済学との相違点と共通点が不明確、争点がどこか分からない(どこの解釈の違いで結論が違ってくるのか)
・MMTの方が現実をよく説明している、というデータの不足
金利と為替で制限がかかるのでメディアが騒ぐほど自由に財政赤字にできるわけではない、と言うのはわかりました。
投稿元:
レビューを見る
MMTとは「主権を有し、不換通貨を発行する政府は、その通貨において支払い不能になることはない」と『説明』してるのであって、「無尽蔵に支出してもよい」とは主張していません。本書を通じ、マクロ会計の仕組みと実際のオペレーションがよく分かりました。
よってMMTのことを「ハイパーインフレを発生させる」「財政の不健全化をまねく」と主張する人は、年金を「払ったって貰えない」と言ってる人と同じレベルだということです。
何事もよく学び・理解してから主張する大切さを実感しました
投稿元:
レビューを見る
MMTが主張するところによると、「通貨発行権のある政府にデフォルトリスクはまったくない」。通貨が作れる以上、財源の制約はなく、インフレが悪化しすぎないようにしさえすれば、財政赤字を気にする必要はないという。
さてここで気をつけたいのは、本書にも指摘があるように、政府がデフォルトを選択することはありうるということだ。特に対外債務に頼っている場合は、自らデフォルトすることで借金をチャラにするという誘いが常に存在し、実際にそのような事例は歴史上たくさんある(『国家は破綻する』参照)。したがって、国債所有者から見たデフォルトリスクは存在するわけで、そのリスクを踏まえた金利設定がされるはずだ。政府はこの金利負担に耐えられるのだろうか。
MMTの主張を読んでいると、政府への無限の信頼(これは行き着くところ警察権力や軍事力といった国の強制力の話になると思う)が前提になっているように思える。しかし、今の時代、その気になれば国外逃亡できるし、資金も簡単に移動できる。この前提がどこまで現実的か、という話のような気がする。
投稿元:
レビューを見る
主権と中央銀行を持つ国の政府は、まず貨幣を創造し、次にその貨幣で納税義務を課す。均衡不要で予算制約なしに支出できる。課税プロセスで、公共・民間に有益な活動を促進する。政府は最低給での就業保証プログラムを実施することで、再分配に代わる不平等是正を行える。
残り物のオマケ程度の位置づけだった税が、まず最初に来るとは。税制の在り方が、社会の活動の方向性を決めるとは。不換・電子情報時代の理論とのことですが、いつまで有効なのだろう。
投稿元:
レビューを見る
中野剛志さんの本で概要を聞いていたので、かなり長く感じたが、いろんな批判に対して丁寧に説明しようとしている内容。
このレベルで基本書と言われると、専門書はどのレベル??と困ってしまう。
最後の解説がシンプルにまとまってるので、先に読んでから読んでみても良いかもしれない。
投稿元:
レビューを見る
誰でも自分の家計が赤字では苦しいでしょう。
政府の家計を他人事と考えれば、政府の家計がどれほど赤字でも苦になりません。
国民個々人の家計と政府の家計を比較考量して、たとえば新型コロナ感染拡大の今の時期は政府の家計を赤字にしても個々人の家計を補填するという政策は一つの考えと思います。
それは政府の家計を犠牲にして個人の家計を潤すというゼロサムの考え方があります。
しかし、MMTは、そのゼロサムを無視して、打ち出の小槌があるような説明になっていることが欺瞞です。
投稿元:
レビューを見る
たしかに今までの金融・財政理論とは異質だが、否定する内容ではないと思った。トリクルダウンが上手くいかなくなった時、就業保証プログラムで需要側を刺激するのは、まさにイマ使う手なのかもしれない。
投稿元:
レビューを見る
理論として現実味を除けば、就業保証プログラムなど、画期的であり面白いと感じた。
しかし、あまり現実味はないような気もする。また、キーストロークの部分であったり、恒等式に関しては、わざわざMMTという学派を打ち立ててまで取り上げるものでもないような気がする。ただ、やはり画期的であるという点で評価できる。
あと、文体が非常に読みづらい。カギカッコが多すぎる。そこをどうにかして欲しかった。
投稿元:
レビューを見る
貨幣の本質=債務証書と、GDPの恒等式をシステム思考的に突き詰めた、みたいな感じ?
そんな簡単なことでいいの?とも思うし複雑だなとも思う。
本質的な役割で見たら、貨幣は債務証書。政府が発行する通貨は、まず政府が負債として支出し、後に税金や罰金などで受け取って償還される。政府は、中央銀行の負債に数字を追加する…「キーストローク」で支出する。
なるほど。
政府の赤字は民間の黒字。貿易の黒字は政府か民間どちらかが赤字。
ゼロ金利は投資を刺激しない。
政府は完全雇用を目的に赤字支出せよ、失業者を直接に雇用せよ、そこまでがMMTだ、と。
純粋に、経済の仕組みに関わるところと、熱く語る思想的主張が混ざってて繰り返しも多い…かも。
巻末の松尾匡先生の解説がわかりやすい。
投稿元:
レビューを見る
「自国通貨を発行できる国は、財政赤字を膨らませても問題ない」という衝撃的な主張をしている現代貨幣理論(MMT)の入門書。アメリカの経済学者による著作であるが、日本では中野剛志氏などが同様の主張をしている。財務諸表については勉強したばかりであるので、ある程度は理解できたが、難解で理解できない部分もある。お金はいくら刷っても問題ないとはいえ、インフレへの警戒も強調しており、要は程度の問題なのかもしれない。確かに巨額の財政赤字を抱えながら更なる国債発行を行っている日本も、一向にインフレに向かう気配はなく、MMTは正しいようにも思える。貨幣についての考え方も納税の所要からその価値を説いているが、ビットコインなどを否定している点では、多くの研究者と考えは一致しているようだ。正しいか否かは定かではないが、概要は理解できた。
「政府と民間という2つの部門から成る経済においては、民間部門によって保有される純金融資産は政府によって発行される純金融負債にぴったり一致する。もし政府が支出と租税収入を常に一致させ、均衡財政を保つならば、民間部門の純金融資産はゼロになる」p54
「(国内民間収支)+(政府収支)+(海外収支)=0」p59
「(ケインズの倹約のパラドクス)総消費を減らして貯蓄を増やそうとすると、貯蓄は増えず、所得が減ってしまう」p75
「GDP=消費+投資+政府購入+純輸出(これは国民総所得に等しい)」p103
「(貯蓄—投資)+(租税—政府購入)+(輸入—輸出)=0」p105
「租税の不払いに対して課される罰を避けるために、納税者は政府の通貨を手に入れる必要がある」p120
「金利(γ)がGDP成長率(g)を上回っている場合に限って、債務比率は上昇する(ガルブレイズ)」p145
「非政府部門の純貯蓄は、所得と貯蓄を創造する政府の赤字支出の結果だと考えるのが最もよい」p228
「貨幣が租税などの強制的な義務を履行するために必要とされる限り、そうした義務が貨幣に対する需要を創造する。つまり、納税者が貨幣を必要とするので、政府は貨幣を発行してモノを買うことができる」p272
「租税が貨幣を動かす。主権を有する政府は、支出をするために自国通貨での歳入を必要としない」p272
「米国(あるいは、英国や日本、いずれも巨大な赤字国である)の現在の、あるいは将来見込まれる条件の中に、ハイパーインフレはもちろん、高インフレを予想させるものは何一つない」p456
「重要なのは、政府は物価安定とともに完全雇用を促進すべき」p484
「「モノとしての貨幣」の制度としての本質は何か?最も明白な共通の特徴は「負債の証拠」だということである」p496
「(金利を下げても企業は簡単に投資はしない)企業をだまして投資させるためには、妖精の粉を大量に撒く必要がある」p505
「(金利と投資と需要)投資を増やすことは需要不足の解決策にはなりえない。つまり、投資を増やすと総需要が増える以上に総供給が増える」p506
「(MMTは、債務や赤字の持続性に関する議論に負けている)政府がキーストローク(お金を刷る)によって支出することは「不道徳」だからだ」p520
「(まとめ)
・通貨発行権のある政府にデフォルトリスクはまったくない。通貨が作れる以上、政府支出に財源の制約はない。インフレが悪化しすぎないようにすることだけが制約である。
・租税は民間に納税のための通貨へのニーズを作って通貨価値を維持するためにある。総需要を総供給能力の範囲内に抑制してインフレを抑えるのが課税することの機能である。だから財政支出の帳尻をつけることに意味はない。
・不完全雇用の間は通貨発行で政府支出をするばかりでもインフレは悪化しない。
・財政赤字は民間の資産増であり、民間への資金供給となっている。逆に、財政黒字は民間の借入れ超過を意味し、失業存在下ではその借入れ超過(貯蓄不足)は民間人の所得が減ることによる貯蓄減でもたらされる」p528
投稿元:
レビューを見る
ケインズからラーナーへの流れを60年代で時間を止めた理論。当時の標準的ケインズ経済学とそれほど違うところはないのになぜか新しい理論なんだそうだ。ケルトンのクルグマンに対する回答の需要の金利弾力性の話はまさしくその頃のマクロ経済学の教科書に書いてあることと同じ。馬は水飲み場まで連れて行くことはできるが無理矢理飲ませることはできない、とか紐は引っ張れるけど押せない、とかそういう比喩で教えてたらしいけど。