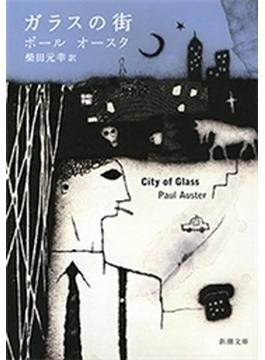2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:RUE - この投稿者のレビュー一覧を見る
『ガラスの街」はポール・オースターのニューヨーク三部作の第一弾であり、NYという現実に存在する巨大な街が、出口のない迷路となり、作者の手の中で弄ばれているような作品である。私立探偵が探偵小説の枠組みを使っているため、当初は探偵小説として扱われたようだけども、本筋とは少し離れる自然言語、小説内の人物が書いた「楽園と塔」という作品、等の詳細な描写が面白く、これらが伏線となり、最後に謎が解けるというカタルシスを味わえると思っていたのだけども、探偵小説とは異なり謎は謎のままである。ただし、違和感はあるものの、読者の中には何らかの解答ができたようにも感じる。私の場合はその解答が伏線となり、ポール・オースターの他の作品を読み続けることになった。
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:雄ヤギ - この投稿者のレビュー一覧を見る
主人公が探偵ということで、ミステリーという扱いを受けることが多かったが、結末に至っても謎が解けることはない。
人間の存在に関わる物語ということは、何となくわかるのだが、論理的に説明しづらい。でも読後感は悪くなく、面白かった。
『シティ・オヴ・グラス』と『ガラスの街』
2016/03/31 02:58
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:イッパイアッテナ - この投稿者のレビュー一覧を見る
角川文庫から『シティ・オヴ・グラス』として出版済みでしたが、柴田元幸氏の翻訳で読みたいとの要望が多かったのでしょうか? 私としては角川文庫版に特に不満はありませんでしたが、本作自体が好きなので、ポール・オースターのほとんどの本を翻訳している柴田元幸氏のバージョンが読めるのは、それはそれで良かったと思います。すでに『Coyote』で発表済みで購入もしていましたが、文庫化してくれたのは素直に嬉しいです。普通の探偵小説とは違う不思議な読後感が魅力です。
投稿元:
レビューを見る
角川文庫から出ていた『シティ・オブ・グラス』の新訳版。翻訳は柴田元幸。
1本の間違い電話から始まるミステリアスな物語だが、ミステリではない。『訳者あとがき』にあるように謎は解決されないし、合理的なオチも無い。
当初はミステリとして紹介されたようだが、柴田訳で読んでみると確かに『何でこれをミステリとして紹介しようと思ったんだろう?』。
角川文庫版も家の何処かにあった筈だが、あんまり印象に残っていないのはそのせいだったのだろうか……。
投稿元:
レビューを見る
ニューヨーク三部作の第一作目。バベルの最後の二文字EとLや第二のスティルマンなどの伏線がどうなるのかも知りたかった。第三作『鍵のかかった部屋』も読みたい。
投稿元:
レビューを見る
ニューヨーク三部作「ガラスの街」の柴田さんによる新訳。
ニューヨークという大都会で一本の電話から始まる物語。
ラストの文章の美しさはため息がでました。
表紙もクール!!
オースターファン、柴田ファンは必読です。
投稿元:
レビューを見る
NY3部作「シティ オブ グラス」の新訳。いくつもの謎がなんにも解決されてないけど、昔よんだときより少しは理解できた気がする。(NYのストリートネームも大体イメージつくし)
ピーター・スティルマンの語り、スティルマンの著書による新世界・神の言葉・バベルの塔、ラストのドン・キホーテ論からこの本自体の著者とポール・オースター、主人公クイン(ウィリアム・ウィルソン、マックス・ワーク)の複雑な文章の構成、ラストの圧倒的な孤独への昇華。
荒々しいんだけど、なにかスムーズに物語が進む不思議な感じ。
投稿元:
レビューを見る
「そもそものはじまりは間違い電話だった」という、いかにもミステリーという書き出し。主人公ダニエル・クインは三十五歳。詩や評論を書いていたが、妻子を亡くしてからというもの文学的野心を見失い、今は匿名でミステリーを書いて暮らしている。世間と隔絶し、仕事をしない時間はニュー・ヨークの街を散歩する毎日だ。それが五月のある真夜中、電話で起こされる。用件は、ポール・オースターという私立探偵への仕事の依頼だった。間違いを指摘して切るが、電話はその後も続く。興味をそそられた作家は探偵に成りすまし、依頼者に会うことにする。
出迎えた依頼者の妻ヴァージニアは魅力的な女性だった。しかし、その夫はすべての点において奇妙な若者で、その話たるや常軌を逸していた。カスパー・ハウザーの話を読んだことがあるだろうか。光と音の刺激を一切遮断した部屋で幼少期を過ごすことを強制され、物心ついてから外の世界に直面するという経験の持ち主だ。ピーター・スティルマンは二歳の頃、同名の父によって九年間暗闇に閉じ込められた後救出された。精神病院に入院していた父が解放され、自分を殺しに来るので見張ってくれというのだ。
スティルマン・シニアはボストンの名家出身の秀才で元は大学教授。宗教学の著述もあり、将来を嘱望されたが、妻の死を契機に息子の養育という名目で退職、隠遁生活に入る。その著書『楽園と塔 初期の新世界像』には、新大陸は発見当初から第二のエデンと考えられていたことや、バベルの塔が崩壊した原因である言語の混乱は、アダムの堕落に重ねられること、つまり、真正の言語を復活させることができたら、新大陸は新たな楽園と化すだろうという、ヘンリー・ ダークなる著者による『新バベル 』という書物が紹介されていた。息子ピーターの幽閉は、人間が堕落する以前の神の言葉を発見することを意図しての実験だったのだ。
小説の前半は、いささかエキセントリックではあるもののちょっと毛色の変わったミステリーとして読めなくもない。しかし、ニュー・ヨークの街 中を行方定めず歩き回る元教授の後を毎日尾行し続けるうちに作家は少しずつ変調をきたしてゆく。携行する赤いノートに教授の歩く道筋を記録し、図示してみると一日の道筋がアルファベットの文字のように見えてくる。連日の行程を順にたどると、“WEROFBAB”となる。“OWER OF BAB ” 文頭にT、末尾にELを添えれば、「バベルの塔」だ。
ミステリーの読者は、探偵の眼を通して世界を見ている。当然のことながら探偵はどこまでも客観的であるよう求められている。でないと、読者は 犯人を推理するための正確なデータが得られないからだ。つまり、探偵はあくまでも視点人物であって、対象人物ではない。ところが、ある時点から主人公は視 点人物であることを放棄し、思い姫であるヴァージニアのため自分の命を賭して依頼者を守る騎士道物語の騎士のように振舞いはじめる。ドン・キホーテが騎士道物語の愛読者だったように、クインもまたミステリーの世界に耽溺する男だったのだ。
この小説が、セルバンテスの『ドン・キホーテ』のパロディ或はパスティーシュであることは、作中に登場する『ドン・キホーテ』論を執筆中の���家 ポール・オースタ-が、「あの本は結局のところ、作り話の危険性に対する批判」であるとばらしているところからも分かる。そこで作家は、ドン・キホーテの真の作者について論じている。セルバンテスは、この本はシーデ・ハメーテ・ベネンヘーリによってアラビア語で書かれたもので、トレドの市場で偶然見つけたその原稿をスペイン語に翻訳させ、自分は編集しただけだと語っている。では、そのシーデ・ハメーテ・ベネンヘーリとは何者か。このあたりの『ドン・キホー テ』論は秀逸で、E・A・ポオやメルヴィル、果てはマルコ・ポーロの『東方見聞録』への度々の言及からも、ポール・オースターという作家が非常にブッキッ シュな作家であることを物語っている。
つまり、いかにもミステリーめいた意匠を凝らしたこの小説は所謂メタ小説で、玉ねぎの皮をむくように、どこまで皮を剥いていっても、作家が書 くことの中には真実などない、ということを意を尽くして言おうとしているのだ。小説の語り手は最後になって登場する作中の作家オースターの友人で、オースターからこの話を聞かされ、クインの居所を探し、部屋に残された赤いノートを発見する。それに基づいて執筆されたのが、この小説であり、事実以外は書かれていないというのだが、はたして誰がその言を信用することができるだろうか。登場人物である作家オースターは、『ドン・キホーテ』について以下のように語っている。
「いずれにせよ、本に書いてあることは現実だという建前ですから、物語を書いたのはそのなかで起きる出来事の目撃者でなくてはいけません。ところが、著者と称されているシーデ・ハメーテはまったく登場しません。一度たりとも、出来事が起きた場に居合わせたと主張したりもしません。」
作中にも登場する妻、シリと出会えなかったら自分はどうなっていたか、という設定で著者は、この小説を書いたという。つまり、妻子を亡くした主人公クインは、著者の「可能態」であった。ポオの「群衆の人」にはじまる、都会の雑踏に紛れ、自分自身を滅してしまいたいという願望は、都市に住まう孤独な人間の心に宿る最後の願望なのかもしれない。クインの孤独は他人事ではない。愛する対象を亡くした、或ははじめからそんなものを持たない人間の孤独を都市は許容する。誰も自分を知らない街の中で、人はどこまでも堕ちてゆくことができる。ニュー・ヨークという都市の非情さと、それゆえにそこでしか生き られない人間存在の孤独を突き詰めた傑作。ポール・オースターの訳者として定評のある柴田元幸氏の新訳によるオースターの小説デビュー作の文庫化。
投稿元:
レビューを見る
なんて表現したら良いんでしょうね…という小説
文章も話の流れも綺麗だしぐいぐい引き込まれて
でも最後に私の疑問には何も答えてくれない
すっきりはしないんだけどそれはそれでいいような…
ミステリーや探偵小説を装った『ひとりの孤独な男の物語』と思えばいいのかな
ちょっと不思議な世界観
またこの人の小説が読みたいと思った
投稿元:
レビューを見る
「そもそものはじまりは間違い電話だった。」という文句に惹かれて手にとった。解決を楽しみに最後まで粘って読んでいくも結果は期待とはずいぶん違う。
登場人物は少ないのに、人格として様々な人物を迎える。
わけがわからないようで、最終的には不快感のない不思議な読後感。
投稿元:
レビューを見る
誰でもなくなる、アイデンティティーがなくなるというと不安になりそうだがさらに突き抜けると不安さえ感じないのか。禅のさとりにも似ている。
一面では、繁栄するニューヨークで誰でもなくなったように扱われる弱者のことに作者は、心を痛めている。
投稿元:
レビューを見る
オースターのニューヨーク3部作の1つ。「幽霊たち」と同じく、冒頭の文章から非常に力があり、引き込まれる。後半、物語の進行とともに思索的、哲学的な文章が多くなり、読むほうも主人公と同じ思考を強いられる。
主人公が、亡くした妻と息子のことを回想する箇所は、本当につらい。訳者による解説を読み、本書が生まれた意図を知って、深く納得。
(2014.1)
投稿元:
レビューを見る
探偵小説と思いきや、そうではなかった。
はじめの書き出しの文章から引き込まれた。
雑踏に埋もれる自分に安心感を覚える、あの感覚。
物語もだけど、文章力が凄くて、どんどん読み進めてしまうのだった。
あの夫妻は結局、何者だったのか、太った女は偶然なのか、とか、謎なところも多くて気になるのだけど、主人公は自分とは何か、という問いを突き詰めた究極形に思えてならなかった。誰にでも主人公のようになる可能性はある訳で、ちょっとぞっとした。
投稿元:
レビューを見る
最初はぐいぐいと読み進めることができて、はてさてどうなるのかと思っていたけれど、だんだんと読んでいるこちらも不安になり、うつろな気分になった。
孤独だけれど一人でも平気と思っていて、自信がなくて、でも認められたくて、そしてやっぱり寂しくてって感じがどんどん重なって押し潰されてしまったような。
語り手が意外で、ああそうなのとびっくりした。
初めて読んだポール・オースターだったので他の作品も読んでみたいと思う。
投稿元:
レビューを見る
文庫版は出たばかりということで図書館の新着コーナーにあったので借りて読んだ。
ポール・オースターの文章も、柴田元幸さんの翻訳も素敵で満足。
話も、独自の探偵の仕事が始まってからはどんどん引き込まれた。
最後もすごいオチ。
今でこそ有名な作品だけれど、自分で出版社をまわって13社も断られたのもわかる気がする。