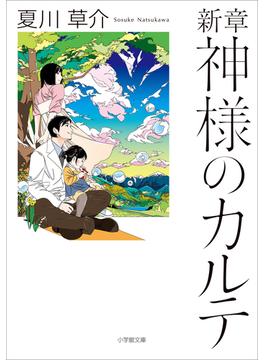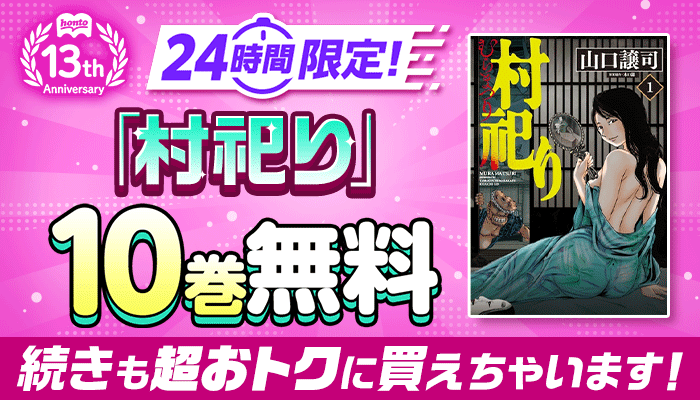部下を持ち成長する一止
2022/08/27 05:59
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:lucky077 - この投稿者のレビュー一覧を見る
大学病院に移り、自分の子供が生まれた一止。副班長的な立場になり、後輩を指導する立場にもなる。患者を大切にし、肩入れする故、医局と対立することもしばしば。
また、時間の経過とともに生活環境も変化、多忙になるが、その中で一本芯が通った人間に成長していく。読み終わったあと、気持ちが良かったです。
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:nap - この投稿者のレビュー一覧を見る
このシリーズ、何度も読みたくなります。
ずっと手元においておきたい本ですね。
大学の医局って、こんな感じなんでしょうかね?
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:エムチャン - この投稿者のレビュー一覧を見る
わずか29歳の若さで末期のすい臓がん患者との向き合い。キツイです。内科医栗原一止は、信州・松本平で「24時間、365日対応」を掲げる本庄病院から信濃大学医学部に入局し、二年。消火器内科医が向き合う死……。
投稿元:
レビューを見る
大学病院の複雑怪奇さ、終末医療の在り方。
最終盤では、静かな感動に包まれました。
栗原一止の一貫した患者ファーストの姿勢に、
とても共感を覚えます。
周りを囲む人たちも、粋な感じがしました。
御嶽荘の行く末も気になります。
投稿元:
レビューを見る
「私は、現代に蔓延る病気を全て治せる医者ではない。奇跡を起こせる医者でもない。ただ良心に恥じぬ、懸命に命と向き合う一人の内科医である」
投稿元:
レビューを見る
昨年末に読み切れると思いきや年越ししてしまいましたが、今年最初の読了となりました!
神様のカルテシリーズの続編ですが、相変わらずの登場人物とストーリーに魅了されました!
主人公医師の栗原一止を中心にした展開ですが、大学病院の医師となった主人公が、大学病院のルールやしがらみに対峙しながら、難病の患者と向き合う姿が爽快でした!
またこれからの続編が楽しみですね!
投稿元:
レビューを見る
理想論だけでは片付けられない医療の世界にユートピアを構築しようとした過去作とは異なり,医局に立ち位置を移すことで現実との融和を図る.白い巨塔の教授が果たして人格者足りうるのか,半信半疑ながら,それが先進医療のあるべき姿だというメッセージと受け取る.
投稿元:
レビューを見る
今回はもっぱら一止が大活躍。大学院生ながら4内科の班の中堅として活躍。学内で揉め事起こしながらも最後はそれが認められて班長に昇進。これに対して利休は気の毒だが、今後戻ってきて再び一止とともに活躍することを期待。それにしても今回は一止がモテすぎのような気がするが。。。
投稿元:
レビューを見る
文庫版に収録の特別編狙い。
新たな登場人物もあり、今後の物語の展開が楽しくなりそうなエピソードです。
単行本を読んだ人もぜひ。
投稿元:
レビューを見る
「24時間、365日対応」の本庄病院を辞め、大学病院に移ってからの一止の活躍が描かれる新章。
本庄病院の話で、このシリーズは終わりかと勝手に思っていて、単行本が出た時も番外編だと思って、スルーしていたが、ドラマが始まることを受け、内容をよく確認したら、新しい物語と言うことで、発売から随分経ってから読むことに。
大学病院を舞台に、「引きの栗原」の存在は継続しつつも、大学病院でありがちな縦割り制度や、理不尽な取り決めにも、真っ向から立ち向かう一止の姿が描かれる。
いろいろな患者さんとの交流が描かれるが、ベースにあるのは、29歳の膵癌の女性患者さんの話。
彼女の病気の進行の速さに、医療の限界を感じつつも、最期まで患者さんの想いに寄り添おうとする一止を始め、四内のメンバーの熱く、優しい思いにとめどなく涙が溢れる。
実際に身近な人を膵癌で亡くしているから、その病気の進行の速さは手に取るように分かるし、まだ幼い子供を残して、死にゆく運命を必死に受け止めようとする患者の二木さんの姿にも、ただただ涙するのみ。
しばらく離れていたので、一止のキャラクターがこんなに面倒臭かっただろうか?と疑問に思いつつも、ラストの人事の内定シーンでも、さらに涙。
もともと一止以外も魅力的なキャラクターが多い、今作。舞台が大学に変わって、さらに興味深いキャラクターも増え、今後も楽しみ。
ドラマの第1話には間に合わなかったけど、ドラマも見てみたくなる。
投稿元:
レビューを見る
再読しました。またもや魂が痺れました。私の大好きな信州の美しい情景を文章であれだけ再現できる夏川さんって、凄いです。
投稿元:
レビューを見る
----小学館 <書籍の内容より>----
信州にある「24時間365日対応」の本庄病院に勤務していた内科医の栗原一止は、より良い医師となるため信濃大学医学部に入局する。消化器内科医として勤務する傍ら、大学院生としての研究も進めなければならない日々も、早二年が過ぎた。矛盾だらけの大学病院という組織にもそれなりに順応しているつもりであったが、29歳の膵癌患者の治療方法をめぐり、局内の実権を掌握している准教授と激しく衝突してしまう。
舞台は、地域医療支援病院から大学病院へ。
シリーズ320万部のベストセラー4年ぶりの最新作にして、10周年を飾る最高傑作!
----小学館 <書籍の内容より>----
久しぶりの読書で思わずレビューを書かずにいられなかったくらい、
心を動かされた作品。
医療現場の葛藤や、若い母親の癌とその家族の姿など、
読んでいる途中は胸が苦しかったけれど、
悩みのなかにいる主人公の姿に、自分だったらどうすると思考力を試されるような成長物語。
ガイドラインやルールに縛られて、
でも現実はそのルールがあるから、物事がゆるぎなく進んでいくなかで
自分ができることは何だろうという部分は、
まったく違う職種でも、今の自分の仕事について考えさせられる部分がある。
「ルールや規則ばかりが押し出されていて、本来の目的を忘れている」
「私は、患者の話をしているんだ」
現実世界であれば、きっと理想通りには行かず、
理不尽な異動になっているだろうラストシーンで、
最後は主人公の理想論を持った姿を受け入れてくれる上司がいて、
自分の信じる道を進んでいけるハッピーエンドでよかった。
物語はこうでないと。
主人公も、細君も、その他医師たちも、魅力的な人物ばかりだった。
投稿元:
レビューを見る
「3」の続編である。栗原一止が信濃大学病院に移って2年が経っている。その間、娘の小春も生まれ、病院のチーム医療のリーダーらしくにもなっている。それは慣れたということではない。娘の股関節に異常が見つかる。患者が居るのに大学病院のベッド使用を上司が許可してくれない‥‥。
特に、第四内科の御家老、宇佐美准教授はパン屋と呼ばれ、「一個のパンがあり、10人の飢えた子どもがいる。さて君はどうするか」という譬え話が十八番である。第一話は大した問題にはならなかった。でも、これはその後キツイ選択を一止に求めるだろう。小説内の話ではない、これは優れてコロナ禍のもと現代の問題でもある。つまり「トリアージ」の話であり、この1月日本の何処かでも行われたかも知れず、昨年の欧米では頻繁に実施されただろう。
その予測は、変化球ながら当たらずと言えども遠からず、一止はパン屋と正面衝突する。あの有名な台詞の変化球が生まれる。
「私はパンの話をしているのではないのです。私は患者の話をしているのです」
さて、結果はどうなったか?黙してご覧じろ。
それはともかく、15年前、私は10時間もかけた膵癌手術に立ち会ったあとに、麻酔の副作用でたくさんの幽霊が見える父親に付き添い、大学病院の病室に1週間泊まったことがある。
その難しい手術を担当した若い医師は、今考えると栗原一止と同じ大学院生だったかもしれない。夜の8時に回診に来て、次の日の朝にちょっと見に来たこともある。ボサボサの髪をしていた。「いつ寝ているんだろか」と不思議に思ったことがある。こんな長時間のブラック労働、大変だけど高給取りなんだろうな、と思ったことがある。まさか、大学院生の給与が手取り16万円とは想像だにしていなかった。さらに言えば、病状が少し安定すると、30キロ離れた実家近くの病院に転院せよと言われた。救急車を使ってくれるかと思いきや、自分で行けという。その非常さに当時は恨みを感じたが、本書を読んでこれも大学病院の「ルール」だと悟った。せめて一止のような「患者に寄り添う丁寧な説明をしてくれる医師」だったらよかったのだが、一止がかなり「特別」或いは「変人」なのである。
膵癌は絶望的な癌である。本書の二木さんのように、ステージ4ともなれば尚更である。それなのに、ステージ4の前半だった我が父親は、その後3年も生きた。北条先生は言う。「言ったろ。大学ってのはすごい場所なんだって」今ではあの医師に感謝している。
投稿元:
レビューを見る
生死が隣り合わせの過酷な内容の物語を、目に見えるような自然の描写とユーモアを散りばめたテンポ良い会話で柔らかく包んでいる。単なる時間の変化を、[東から差し込んでいた日差しが、茜色の西日にかわった]という素敵な表現力が、至る所で感じることができるのも魅力のひとつ。
投稿元:
レビューを見る
理不尽や苦労が絶えないが、目の前の患者のために日々真面目に全力を尽くす主人公が好きで毎回(文庫が)出たら買っている。
仕事に対する矜持が伝わり心が熱くなる。「真面目とは真剣勝負のことです」という夏目漱石からの引用が熱い。真面目に生きることって大切だ。自分もがんばろうと思った。