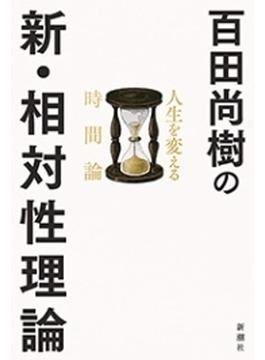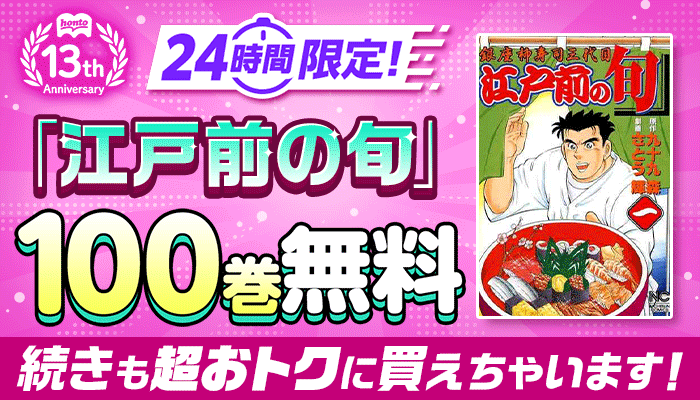百田目線の理論炸裂
2022/05/09 00:15
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ぶっちゃん - この投稿者のレビュー一覧を見る
新の意味がよーく分かった。
なるほど、新しい相対性理論である。
しかし、そこは百田さん。乱暴ではあるが、なかぬか納得できる理論。
投稿元:
レビューを見る
時計で測ると時間はどんな状況でもいつも一定の感覚で進んでいくのは分かっていますが、その時に置かれた気分・感情によって、時間の進み具合が違って感じるのは昔から感じてきたことです。
時間とは何かを考えてきた私は、先日近くの本屋さんでこの本のタイトルを見て、そして著者が百田氏であったこともあり中身も見ないで購入しました。本屋さんを歩いていると、このような出会いがあるので嬉しいですね。
本の帯に「時間の本質を知れば、人生が一変する」とありますが、この本で時間とは何か、という私がずっと探してきた答えに近づいたような気がしました。
以下は気になったポイントです。
・充実した時間が少なければ寿命が短い(時間が減る)ということは、充実した時間が多ければ寿命が長い(時間が増える)、つまり物理的な時間は同じでも「長生き」できる。これが、百田氏のいうところの「新・相対性理論」である(p14)生きるために行う作業は苦行に要する時間を短縮して、その短縮した時間を楽しみの時間に換えれば、その分、長生きしたことになると考える(p17)
・私たち現代人はこうした発明(槍、斧、モリ、釣り針、網、袋、籠など)は「便利」のため、あるいは「エネルギーの効率化」のためと思い込んでいたが、実は全て「死」から逃れることのできない人類の潜在的な恐怖心によって生み出されたものであった(p23)私たちは一世代前の人達に比べて比較にならないくらい自由な時間を得ている。つまり、平均寿命が延びた以上に「長生き」していることになる(p27)
・夏と冬では日照時間が違うため、同じように等分した時間も長さが違った。ちなみに江戸時代の日本は、夜明けが「明け六つ」日暮れが「暮れ六つ」で、その間を6つに当分していて、夏と冬とでは同じ「一刻」でも時間の長さに違いがあった。(p35)
・嫌な仕事や作業は長く感じ、楽しい時間はあっという間に過ぎる。私たちは時計を持っているので自分が感じる時間が心理的なものだと知っているので、心理的時間は一種の錯覚と看做しているが、それは大きな間違いである。人理的な時間こそが真に重要な「時計」である(p35)
・アインシュタインの相対性理論によれば、全ての基準は光であり、時間さえも伸びたり縮んだりする。例えば動く物体は止まっている物体よりも時間がゆっくりと進む。仮に、高速に近いロケットに乗って地球を出発して何年かして地球に戻ってくると、ロケットに乗っていた人は地球にいた人よりも歳を取っていない。この時間の差は、ロケットの速度と航行時間から正確に求められる。これは100年前に理論上で証明されていたが、スペースシャトルに載せた原子時計で実証された。しかし人類は時間というものは伸び縮みするということを知っていた。物理的に同じ時間であっても、長く感じたり逆に一瞬に感じたりすることを経験していた(p37)
・過去の時間の体感は、感動と記憶にあるのではないか。人生を振り返った時、そうした出来事が多かった時代は「長い時間」に感じるのではないか、少ない場合には「短い時間」に感じるのではないか。つまり「時間の濃淡」に差が出る(p39)中年になって転職したり、起業したり、再婚すると、途端に「時間」が濃密になる。後で振り返った時に、その辺りの人生は非常に長く感じる、それは記憶に強く残るイベントが多いから(p41)
・人間の潜在意識の中にある最も大きな欲望は「長生きしたい」というものと「楽しいことをしたい」である。ところが楽しいことをすると時間が早く過ぎてしまうことは大いなる矛盾である。長生きの感覚を味わうには、つまらない時間を多く過ごせば良いということになる。これは矛盾でなはい、楽しい時間は過ぎ去ってしまうと、その人の人生の中に大きな時間として残る、心の中に感動や驚き、喜びをたくさん残すからである。素敵な思い出を回想する時、これらの経験は長い時間の感覚として蘇る、つまらない時間は、感動や驚きは少なく、あれほど長く感じたのに、振り返ると記憶にも残らず、逆に短い時間となっている(p43)
・何を楽しい時間と思うかは、人それぞれであり「楽しい時間の長さが人生の長さ」である。これを現代に生きる私たちはそのことに気づかない、物理的時間に支配されているから。だから心理的に「長い」と思っても、それは一種の錯覚と見做してしまう(p49)好きなことを仕事にするのではなく、仕事を好きになると、その時間は「楽しい時間」になる(p52)人生において「達成感」というものは「過去の記憶」も塗り替えてしまうほど大きなものである(p55)
・仕事とは「時間の売買」であるが、サラリーマンが一方的に時間を売っている側ではない、そんなことになれば世の中の時間のバランスが大きく崩れる。人々は自分の時間を売って得たお金で、今度は楽しい時間を買っている。私たちの楽しみは、実は他人の時間を買うことで成り立っていることが多い(p60)私たちは経済活動の中で「金」と「モノ」を交換していると思っているが、それは錯覚であり、実は「時間」である。そのものを生み出すのにかかる時間こそが商品の価値である。ダイヤやゴールドが高価なのは、希少性ゆえではなく、それを見つけ、掘り出す時間が莫大だから。工芸品、食品もそれを作るのにかけた時間が多いほど高価になる。逆に短時間で作れるものは安価である(p68)
・新相対性理論によれば、才能とは、同じことをするのに、他人よりも短い時間でやれる能力と定義できる(p83)一方で、努力する人というのは「時間を投入することに優れた人」と言える。人が業績を残した場合、それが才能なのか努力によってなされたのかは実はほとんど区別されない。結果というのは、その人物の「時間」の使い方にあるわけである(p86)
・人類は地球上に誕生した時から、2つの大きな敵と対峙してきた。一つは、寿命を制限する「時間」、もう一つが行動を制限する「重力」である(p92)
・金は豊かな生活を送るための手段であって、けして目的ではない。有限である時間を他人に売って「金」に換えながら、それをほとんど使わなかったというのは、時間を金に交換するためだけに使った人生と言える(p104)使われない品(死蔵品)=ただ所有しているという実感、を持つ目的のためだけに、有限である貴重な時間をせっせと「私蔵品」と交換している人生は、どこか空しさを覚える、コレクターがそれを眺める時、実は自分が使った「時間」を眺めているのかもしれない(p112)
・古代人から見れば夢のような暮らしができるのは、言葉による知識の伝達と保存があったから、言葉は人類が時間を超えるために作られた(p115,121)
・若い頃の時間というのは大きな砂時計をスタートさせた状態に似ている、砂が減っていくスピードを自覚できるようになるのは、砂が半分以上、いや残りの四分の一くらいになった時でしょうか。最初から砂の落ちていくスピードは変わっていないのに、その速度は加速しているように思える(p160)
・時間を共有することで「楽しみ」が増加していく、これが時間の不思議なところで同じ時間を、複数の人々が楽しいと感じると、その時間は濃くなる(p178)
・空気の振動とリズムを記号におきかえる記譜法というのは、画期的な発明であり、ある意味、文字以上の発想かもしれない。これにより私たちは何百年も前の作曲家が作った音楽を聴くことができるようになった(p197)
・ニュートン力学である、エネルギー保存の法則は難しく言えば、孤立系のエネルギーの総量は変化しない、というものである。これが説明できないのは、原子核分裂により質量がエネルギーに変化するというケースである、さらにあるのは、芸術作品が持つエネルギーである。作品の中に投入されたエネルギーは、その作品を干渉する人の心に感動という形で作用する=蘇る(p199)
・将来の調子は、現在の食生活と生活習慣でかなり正確に予測できる、最近はそこに遺伝子情報を加えることができる。私たちの未来は物理学同様に、現在の条件と、それに加わっている力を見れば、ほぼ予測ができる。つまり未来の人生は現時点で決まっていると言える(p203)
・仕事の量は、完成のために与えられた時間いっぱいに膨張するという法則がある、なぜなら、私たちが時間を支配していなくて、時間に支配されているから。基準になっているのが、自分の能力ではなく時間だからである、そしてその時間は第三者が設定したものだから。私たちは誰かが決めた時間に合わせて生きている、しかし偉大な業績を残す人物たちは、そんな時間に縛られず、自分の能力をいっぱいに使って仕事に取り組む、言い換えるとやることの優先順位を間違えないということ(p204,205)
2021年2月6日作成
投稿元:
レビューを見る
【まとめ】
・時間の概念を変える≒相対性理論
・物理的な時間は同じであるが充実した時間を長く生きることで「長生き」と捉える
・経済活動は金とモノのやりとりではなく、実は金と時間の交換で成り立っている。(時間が基準の考え方)
・使わない金などただの石ころと同じだ
・金は使えば減る、使わなければ減らない。時間は使っても使わなくても絶対に減る。
・他人の時間を買うことは出来るが自分の時間は何百億円出しても買えない。そんな貴重な時間を退屈凌ぎ使ってしまうのは勿体ない
・他人が時間を浪費している間に自分は進め
【Todo】
・生きる時間に対する考え方や概念を変える。ダラダラと無駄な時間の浪費をやめ、しっかりとしたビジョンに則って行動する。
・意味や目的もなくスマホを眺めるのを禁止にする
・金を使う(浪費するという意味ではない)
投稿元:
レビューを見る
時間の大切さを再認識する機会となった。何か真新しい知識が得られるというよりは、誰もがいつも頭の中で考えていることを言語化したという内容。
投稿元:
レビューを見る
本書のタイトルは、「新・相対性理論」だが、物理学の本ではない。
時間論、いや哲学とも言える内容である。
人間の営みはすべて時間が基準になっているという。様々な物事や行為を時間という観点から論じているが、なるほどの連続であった。
ほとんどの人は、長生きをしたいと思っているが、
物理的な時間の長さではなく楽しく濃密な時間を生きたいということだ。
例えば、牢獄の100年と自由な生活の50年のどちらか選べと言われたら後者を選ぶだろう。
つまり、充実した時間を長く過ごすことが長生きするということだ。
自分の過去を振り返ると、若くて素晴らしい時間をどれだけ無駄に過ごしてきたのかと思う。
どんなにお金を払っても、過ぎた時間を取り戻すことはできない。
だからこそ、これから先の人生は充実した時間を過ごす努力をしよう。
挑戦する心を持とう。時間に支配されるのではなく、時間を上手く使うように意識しよう。
貴重な時間を退屈しのぎに使うのはもったいない。
今まで、時間の大事さを漠然と分かっているつもりになっていたが、全然分かっていなかった。
この本に書かれているように時間を俯瞰できれば、もっと【長生き】できるようになるだろう。
投稿元:
レビューを見る
時間というテーマでの切り口は、とても面白かったです。流石は百田先生でした。時間には限りがあるという意識を持つだけで、日々の過ごし方が変わってきますね。
投稿元:
レビューを見る
百田尚樹さんの考えた時間論を、アインシュタインの相対性理論をもじって「新・相対性理論」と名付け、時間の本質について語られた一冊(私たちの社会、道具、才能、恋愛から年齢まで、さまざまな側面から解説される)。あまり計画を立てずになんとなく日常を過ごしている人にとっては、読むと時間の大切さが分かり、時間の使い方について今一度再考したいと思わせる作品だと思う。百田さんの小説と同じで読みやすいのも◎。
投稿元:
レビューを見る
社会の基準は時間だと言い切ります。
お金も物も、時間を換算したものにすぎません。
娯楽や労働による時間の奪い合いが現代です。
まさにその通りです。
社会は、「時間の売買」によって成り立っているとは、至言です。
ところで、読者の中には「才能」には「努力」で対抗できるんじゃないか、と思われる人もいるかもしれません。
たしかにそれは間違いではありません。普通の人の半分の時間でやれる「才能」ある人に対しては、倍の時間をかければ並ぶことができます。三倍の時間をかければ追い抜くことができます。けれどもそうやって努力できるのも、実は「才能」なのです。 ー 85ページ
投稿元:
レビューを見る
百田氏の主張はいちいち納得ができるし、彼の小説も好きである。しかし、この本はあまりに冗長であり、途中で読むのをやめようかと思ってしまった。多作な方は全て良作とは限らないかもしれない。
投稿元:
レビューを見る
時間の大切さに改めて気付かされた一冊。
お金=時間であり、時間は金に換えられるがその逆はできない。
人生は一度きりであり、今この瞬間は2度と戻らない。自分の時間を大切にして、無駄にすることなく生きていきたいと感じた。
投稿元:
レビューを見る
タイトルは大袈裟だが、「時間をすべての軸としてその捉え方・考え方を今一度よく精査してみましょう、そうすれば人生が変わりますよ」といった啓発本に近い内容。ただそこら辺の啓発本のように生臭さはなく、辻褄あわせもあるが、至って的確な内容。
投稿元:
レビューを見る
人生の時間の長さは心理的なものであるという、事だが、その場その場を楽しむのか、苦しむのかは自分の捉え方次第。
そらなら、絶対前者がいい。
全体的に、イメージでモノを語っているように見受けられるが、一個人の意見としてはとても面白く、納得させられる見解だ。
豊かな生活とは、他人の時間を買えるゆとりある生活のこと。また、その時間も有限であり、お金は無限。
極端な考えではないかと?頭を捻る点が多々あるが、
捉え方を変えれば確かに、合理的な考えである事は間違いない。今後の過ごし方を考える上で、参考にさせられる。
※各所、アンチを意識した記述があり、個人的にはもっと堂々としてほしいなっと感じた。。。
投稿元:
レビューを見る
時間について、縄文時代などの歴史に照らし合わせ解説してくれているので、とにかく分かりやすかったです。時間を長く使える方法は早速実践したいし、仕事を納期軸で考えるのは、もう止めようと思います。
そして、最後のこの言葉は、やっぱり良い....座右の銘にしたいぐらいです。
「お前がいつの日か出会う禍は、お前がおろそかにしたある時間の報いである」
投稿元:
レビューを見る
老後のために貯蓄をしなくちゃとよく言うが、老後に金があっても体の自由がないから楽しめない。
老後に金を残すより、有益な金の使い方をして、今を楽しく生きた方が幸せだ。
投稿元:
レビューを見る
人間は「濃い時間をすごす」ことで長生きをできる。
時間は長さではない、濃さが大切である。
一方で、人間は退屈を嫌う。
いかに世の中が「時間つぶし」のためのビジネスが多いか。
副業あっせん、YOU TUBER、メルカリ…こうしたことも「時間つぶし」をさせ、更に達成感も味わせようとするビジネスではないか?と思った。
時は金なり。それを伝えたいのだと思った。