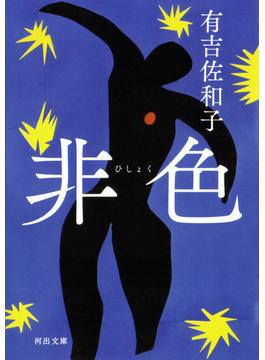紙の本
現代人必読
2023/04/25 19:41
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:アカイ - この投稿者のレビュー一覧を見る
女の生きづらさ、多様性、格差などなど、最近よく聞くようになったキーワードに世界が無自覚だった時代の物語。こうしたワードを知らない主人公がその全てに正面から向き合う姿勢は、教科書的な知識では得られない苦しみの「感触」を読者に与えます。現代の私たちこそ読むべき一冊です。
電子書籍
「ワーブライド」という美しい言葉の陰に隠された
2023/01/01 14:14
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:Todoslo - この投稿者のレビュー一覧を見る
残酷な現実が描かれています。たどり着いた異国の地で謂れのない偏見に晒される姿に胸が苦しくなりますが、笑子の力強さに救われました。
投稿元:
レビューを見る
1964年に発表された、いわゆる戦争花嫁である笑子を主人公とした小説。
笑子は特段器量良しでもない自分に真剣にアプローチしてきた黒人軍人のトムに気をよくし、家族の反対を押し切って結婚する。
やがて生まれた娘を偏見から守るため、トムを追ってニューヨークに渡るが、そこで待っていたのは想像もしていなかった生活だった‥。
アメリカには、日本では知り得なかったさらなる人種差別があった。ことに、同じ船でニューヨークに渡った女たちが、それぞれ被差別人種の妻だったこと、そのことを当の本人たちも知らずに渡米しただろうこと、それゆえに辿ったその後の数奇な人生には悲壮なものがあった。
ただ、笑子自身の逞しさと行動力が読み物として読者を惹きつけて、ほかの有吉作品同様夢中になった。
投稿元:
レビューを見る
敗戦後の絶望的な状況下、占領軍関係施設で働き、そこで出会った軍人と結婚し、夫の母国アメリカに渡った女性がいた。彼女らは当時、「戦争花嫁(ウォーブライド)」と呼ばれた。この物語は、日本で米軍伍長と結婚し、1児をもうけた戦争花嫁が渡米、夫が黒人であったことから人種差別や偏見にあいながらも、逞しく生き抜いていくというストーリーになっている。
日本で生まれた娘に、親からも偏見の目を向けられ、いたたまれなくなった主人公・笑子は夫の待つニューヨークに渡るが、待っていたのは、貧民街ハアレムでの半地下生活だった。夫のトムは夜間、病院で看護夫として働いていたが薄給、しかも、日本にいた時のような覇気がなかった。そんな二人の間に次々と子どもが生まれ、笑子は生活のため、レストランやメイドとして働く。黒人の妻ということで、蔑みを受けながら持ち前の反発心で気持ちを切り替えながら強く生きていく笑子の姿が全編を通じてよく描かれている。
そして、何より強く提起されているのが黒人差別に代表される人種差別の実態。笑子は日本から渡米する際の船中で知り合った竹子、志満子、麗子とニューヨークで再会するが、彼女らの夫は黒人、イタリア人、プエルトリコ人と異なり、それぞれ苦悩を抱えていた。アフリカ黒人とアメリカ黒人がお互いに相手を蔑む実態も描かれている。いまだ解決されていない奥深い問題の内面がひしひしと伝わってくる秀逸な長編作品だ。
著者の文体は堅苦しさがなく、自分には親しみやすく感じられた。また、大阪出身の竹子の言葉の中に、「なんでまっと遊ばなんだんよ」と明らかな和歌山なまりが混じっていたことで、親近感が増した。
投稿元:
レビューを見る
ブレイディみかこさんの帯が気になってジャケ買い。
終戦直後、黒人兵と結婚し、戦争花嫁(ワーブライド)としてニューヨークに渡った主人公、笑子。
ニューヨークの貧民街で「ニグロ」の夫と暮らす半地下生活。どんどん「殖える」子どもたち。肌の色はいろいろ。同じくニグロの夫を持つ竹子、「イタ公」の夫を持つ志満子、プエルトリコ人の夫を持つ麗子。
人種差別とはあからさまに虐げたりするものでなく、息をするように自然に、違う人種だと見下すこと。「私は差別なんかしていません」という人がいちばん怖いという話。
1967年にこの本が出版されてから50年ちかく。今、読みたい本。
「プエルトリコをかばうのはええ気持やろ?黒より下の亭主持ってる女やと思えば、単純な私らは嗤いものにするけど、あんたはもう一つ手ェこんでいるだけや。同じことなら嗤うたり悪口言うたりする方が私は好きやな、正直で」
投稿元:
レビューを見る
手に取った時にすぐに想起したのはやはりBlackLivesMatterの問題だった。読了した今、自分のレイシズムに対する観念のなんと狭く薄っぺらであったことか。なんと無知だったことか。打ちのめされた。差別といっても様々に階層があり、憎悪も入れ子になっている。いくら過酷な時代だからといっても、主人公の人生を逞しいの一言でまとめることは私にはできない。主人公自身の差別感情が理解できてしまうからだ。テニス選手が「いつまで(こんな差別が)続くんだ?」と嘆いたことは広く知られているが、私も解決できない問題じゃないかと悲観してしまう。1967年に刊行され、この文庫は2020年に復刊されたもの。実にタイムリーだがこんな差別って本当にあったの?と言われる世界は遠い気がする。
投稿元:
レビューを見る
状況的には絶望すぎるな。
笑子は離婚するんじゃないかと、勝手にイメージしてたけど、異国の地で逞しく生きる笑子の姿にページをめくる手が止まらず。
有吉佐和子さんの書く文章、テーマはほんと魅力的。
投稿元:
レビューを見る
色に非ず。誰かを下に見る心は、ここにあるのだ。
黒人兵トムと結婚し、子どもを連れてニューヨークに渡った笑子。思った以上の苦しい生活でも、彼女は戦い続ける。そのエネルギーとなったのは、何への反骨芯か。日本人、黒人、イタリア系、プエルトリコ、ユダヤ。複雑に絡み合う差別の視線の中で、笑子が最終的に掴んだものは。
アメリカの人種差別は、階級闘争なのではないか。この言葉が印象的であった。この小説が書かれたのは1964年だという。東京オリンピックの年で、アメリカでは公民権運動がピークになっていた頃、そしてアフリカの国が次々と独立していた頃。アメリカの黒人に対する、アフリカの黒人たちの冷ややかな目や、アメリカの黒人のプエルトリコ人への強烈な差別意識、そして南部からニューヨークに憧れて出てきた黒人の語る南部の暴動の激しさ。つい「アメリカ人」とまとめて言ってしまいがちで、しかしその時のイメージはいわゆる白人である。作品内でも何度か言及されていたように、イタリア系だとかプエルトリコ人だとか、アイルランド系だとかの「アメリカ人」の中の違いは、日本に生まれ育ってきた人にとって、意識するものではなかった。
「差別はいけない」「どんな人も等しく扱われるべき」美しいことを言うのは簡単で、笑子の行動のいくつかを糾弾したくなることもあるだろう。しかし、人種や国籍、性別に限らず、誰でも「私はあの人たちより上だ」とか「あの人たちと私は違う」と思ったことがあるはずだ。決して、肌の色ではないのである。確かに肌の色や髪の毛、目の色などはわかりやすい差で、生まれ持ったものだから標的にしやすい。けれど、そこではない。氏より育ちという言葉があるように、言葉や動作を学び、強く生きようとする人間は、変化するエネルギーに満ち溢れている。最後に笑子がエンパイア・ステイト・ビルに上ってみよう、というのは、そういうことではないだろうか。上に行こう、というエネルギー。この作品の書かれた1964年は、上に行こう、という行動指標が最も肯定される生き方だったのではないか。
どうしても「下にいるあの人たちとは違う」という意識がある。この意識からは逃れられない。しかし「あの人たち」は、固定化されてもおらず、生まれつきのものでもないことを、必ず心に止めておきたい。そうすれば、一緒にエンパイア・ステイト・ビルに上ろう、大陸で変わった桜は素晴らしい、と思った笑子のように、共にいる彼らと一緒に生きていこう、という気持ちになれるだろう。
投稿元:
レビューを見る
#英語 "Not Because of Color" by Sawako Ariyoshi
“Without Color” という訳もみつけました。
一気に読みました。
米国の人種差別を扱ったすばらしい小説が、日本の作家によって1964年に書かれていたとは…
有吉佐和子さんの視点が素晴らしい
"金持は貧乏人を軽んじ、頭のいいものは悪い人間を馬鹿にし…インテリは学歴のないものを軽蔑する。人間は誰でも自分よりなんらかの形で以下のものを設定し、それによって自分をより優れていると思いたいのではないか。それでなければ落着かない…生きて行けないのではないか" 『非色』有吉佐和子
自信ないけど私訳してみた。"The rich despise the poor, the smart make fun of the bad...the intellectuals scorn the uneducated. I think we all want to set ourselves up by putting others down, and thereby think of ourselves as superior. If not, we cannot settle or we cannot live."
投稿元:
レビューを見る
年末にベストオブザイヤーな本に出会った! 戦後の冒険譚としても読み応え抜群、そして米国の人種問題の刳り方がパワフル。無意識の差別など差別の根源に気付かされた。人間の底浅さが醜くて怖い。ユーモラスな筆致で暗くなり過ぎないところもよかった。 この本が50年以上前に書かれながら、現在もBLM運動が行われてることで根深さがより一層浮かび上がる。 もっと有吉佐和子の本を読みたい。
投稿元:
レビューを見る
1番驚くのはこの本が1960年代に書かれたということ。今読んでもまったく色褪せないのは、本質が何も変わっていないから。ここ数年、読むのがこんなにつらかった本はなかった。多くの人に読んで欲しいと思う。
投稿元:
レビューを見る
「打ちのめされる本」とかいうのがあった気がするけど,まさにそれ。先が気になりすぎて日曜つぶして読んだ。『華岡青洲の妻』でも打ちのめされた記憶が蘇ってきた。有吉佐和子すごい。どうしようもなく絶望してしまう話な気がするけど最後上を向くところが良い。すごく好き。
BLMのこと何も分かっていなかったよ,と思う(これを読んだことで理解できたとも思わないけれど)。そりゃ根深いわと思う。ウェストサイドストーリーも全然別の話に思えてくる。
「阿川佐和子さんがラジオで勧めてた」という情報から読みたいリストに入れてた記憶。阿川さんにも感謝。
投稿元:
レビューを見る
黒人が生まれた瞬間から直面する人種差別や偏見を真っ向から書いていて、陰惨なだけの話になってしまってもおかしくないのに、ぐいぐい読ませるのはさすが有吉佐和子さん。主人公の笑子を貫く闘争心が、全編にエネルギーを与えている。
「人間は誰でも自分よりなんらかの形で以下のものを設定し、それによって自分をより優れていると思いたいのではないか。それでなければ落ち着かない、それでなけば生きていけないのではないか。」と笑子がたどり着く一つの結論は、いくら平等が謳われる世界になったところで、厳然とした事実のように思われる。
その上でどうするか、というのがこれからの社会の課題なのかもしれない。
投稿元:
レビューを見る
久しぶりに、寝る時間も惜しんで読みたいと思えた本でした。
これが60年も前に書かれたとは思えない、今の現状…
投稿元:
レビューを見る
アメリカに一年ほど留学した作家が、差別の構造について深く考え書き上げた小説なのだろう。黒人と白人。プエルトリコ人。イタリア系。ユダヤ系。アフリカ人。アジア人についての記述は少ないが、戦争花嫁として生きるということ。考えさせられることが本当に多く、物語としても面白く読めた。